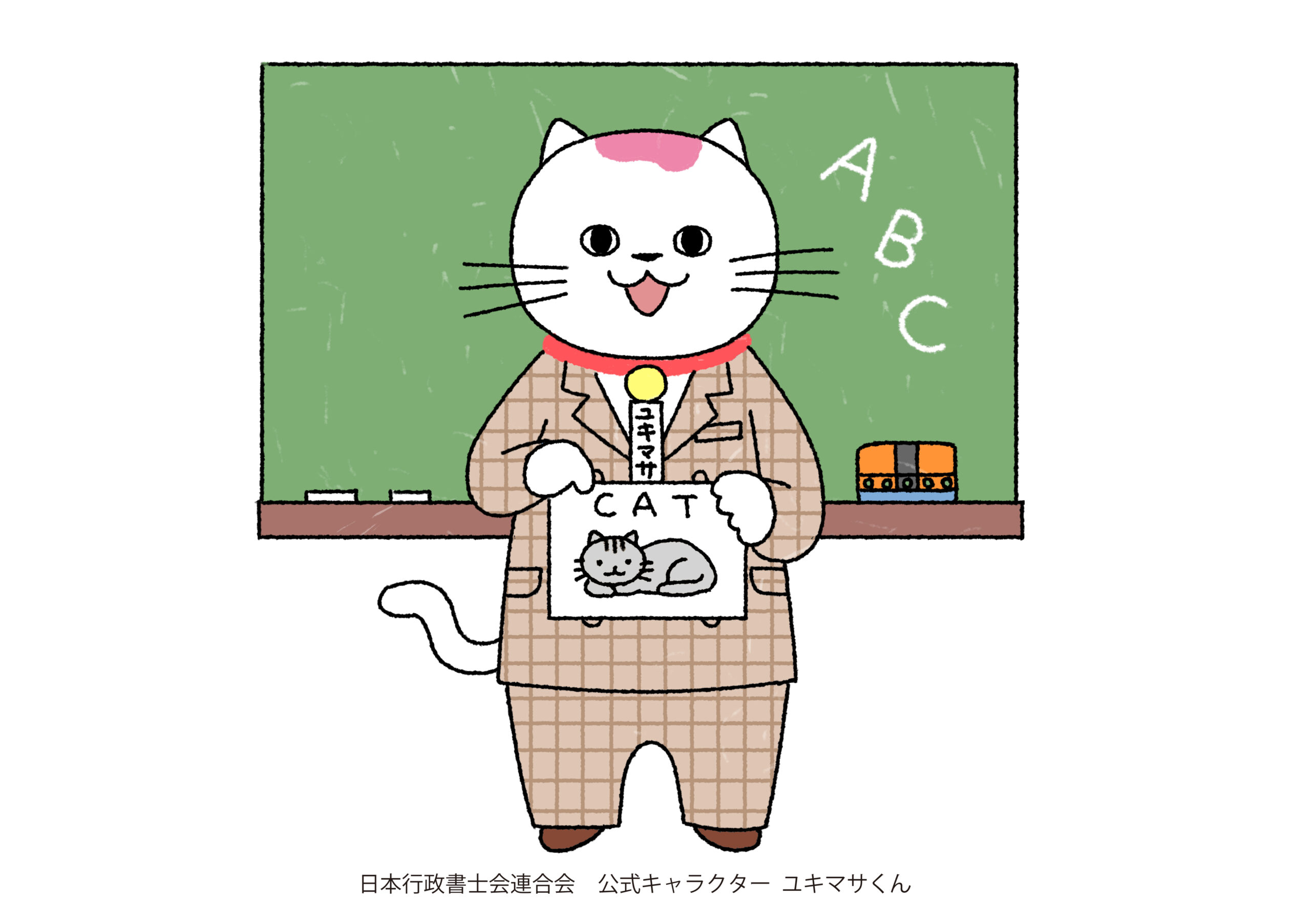
特定技能1号と特定技能2号の徹底比較:7つの重要な違いを行政書士が詳しく解説
執筆者:行政書士法人塩永事務所
はじめに
2019年4月に新設された在留資格「特定技能」は、日本の深刻な人手不足を背景として創設された重要な制度です。特に2023年には特定技能2号の対象分野が大幅に拡大され、外国人材の長期定着に向けた制度設計が整いました。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、特定技能1号と2号の違いについて、実務経験に基づき詳細に解説いたします。企業の人事担当者様や外国人材の雇用をご検討中の事業者様にとって、実践的な情報をお届けします。
特定技能制度の基本概要
特定技能制度の創設背景と目的
特定技能制度は、我が国の生産年齢人口の減少と深刻化する人手不足に対応するため、特定産業分野における外国人材の受入れを目的として創設されました。従来の技能実習制度が「人材育成を通じた国際協力」を目的としていたのに対し、特定技能制度は明確に「労働力確保」を目的としている点で大きく異なります。
他の就労系在留資格との違い
特定技能の特徴は、就労可能な業務範囲の広さにあります。従来の就労系在留資格では単純労働に従事することができませんでしたが、特定技能では「単純労働をメインとしない」という条件のもと、単純労働を含む幅広い業務に従事することが可能です。
対象分野の詳細比較
特定技能1号の対象分野(12分野)
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(工業製品製造業)
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
特定技能2号の対象分野(11分野)
特定技能2号は、上記1号の分野から介護分野を除く11分野が対象となります。
介護分野が除外される理由: 介護分野については、在留資格「介護」という専門的・技術的分野の在留資格への移行ルートが既に確立されているため、特定技能2号の対象外とされています。
特定技能1号と2号の7つの重要な違い
以下の比較表をご参照ください。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 1年・6カ月・4カ月ごとの更新<br>(通算5年まで) | 3年・1年・6カ月ごとの更新<br>(更新の上限なし) |
| 永住権取得 | 永住権取得要件の在留歴に算入されない | 永住権取得要件の在留歴に算入される |
| 技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能<br>(管理・指導レベル) |
| 外国人支援 | 支援計画の策定・実施が義務 | 支援計画の策定・実施は不要 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子について条件付きで可能 |
| 日本語能力試験 | 技能試験と併せて受験必須 | 原則不要(分野により例外あり) |
| 試験実施状況 | 国内外で定期実施 | 2023年より順次開始<br>(国内中心) |
1. 在留期間の上限について
特定技能1号の制限:
- 在留期間は通算で最大5年間
- 期間満了後は原則として帰国が必要
- 他の在留資格への変更は可能(要件を満たす場合)
特定技能2号の優位性:
- 在留期間の更新に上限がない
- 就労を継続する限り、理論上は永続的な在留が可能
- より安定した在留基盤を提供
2. 永住権取得への道筋
これは最も重要な違いの一つです。出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」によると:
永住権申請の基本要件:
「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」
実務上の重要なポイント:
- 特定技能1号での在留期間は永住権申請のための在留歴にカウントされない
- 特定技能2号での在留期間は永住権申請のための在留歴にカウントされる
- 特定技能2号取得後10年経過すれば、永住権申請が可能となる
3. 求められる技能水準の具体的違い
建設分野での事例比較:
特定技能1号(配管作業):
- 指導者の指示・監督を受けながら配管加工・組立て等の作業に従事
- 基本的な技能の習得と実践が中心
特定技能2号(配管作業):
- 複数の建設技能者を指導しながら、配管加工・組立て等の作業に従事
- 工程管理や品質管理の責任を負う
- チームリーダーとしての役割を担う
4. 外国人支援制度の詳細
特定技能1号における支援義務:
受入れ機関は以下の支援を実施する義務があります:
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続等への同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(離職時)
- 定期的な面談・行政機関への通報
支援実施の要件:
- 過去2年間に外国人の受入れ実績がない場合は、登録支援機関への委託が義務
- 自社で支援を実施する場合も、適切な支援体制の構築が必要
特定技能2号の支援免除: 特定技能2号については、より高度な技能を有し、日本社会への適応能力も高いと判断されるため、支援計画の策定・実施は不要とされています。
5. 家族帯同に関する詳細規定
特定技能2号における家族帯同の条件:
帯同可能な家族:
- 配偶者(法律婚に限る)
- 未成年かつ未婚の実子
帯同家族の在留資格:
- 配偶者:「特定活動」
- 子:「特定活動」
帯同の要件:
- 本人の経済的能力(家族を扶養できる収入)
- 適切な住居の確保
- 帯同家族の素行が良好であること
6. 日本語能力要件の詳細
特定技能1号の日本語能力要件:
- 日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格、または
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上合格
- 技能実習2号を良好に修了した場合は免除
特定技能2号の日本語能力要件:
- 原則として日本語試験は不要
- ただし、一部の分野では独自の日本語能力要件を設定する可能性
7. 試験実施状況と今後の動向
特定技能1号試験:
- 国内外での定期実施(コロナ禍による一時中断あり)
- 海外実施国は二国間協力覚書締結国
- オンライン試験の導入も進行中
特定技能2号試験:
- 2023年から順次実施開始
- 多くの分野で国内実施が中心
- 企業による申込みが必要な分野も存在
取得方法の詳細解説
特定技能1号の取得ルート
ルート1:試験合格による取得
- 技能測定試験の合格
- 各分野別に実施される実技・学科試験
- 業界団体等が実施主体
- 日本語能力試験の合格
- JFT-Basic または JLPT N4以上
- 国内外で定期実施
ルート2:技能実習からの移行
- 基本要件
- 技能実習2号の良好な修了
- 移行する職種・作業との関連性
- 試験免除の条件
- 同一職種・作業:技能試験・日本語試験ともに免除
- 異なる職種・作業:日本語試験のみ免除
特定技能2号の取得要件
必要な要件:
- 特定技能2号技能測定試験の合格
- 各分野で実施される高度な技能試験
- 管理・指導能力を測定
- 実務経験の証明
- 分野により年数・内容が異なる
- 管理・指導経験を含む場合が多い
- 企業による証明書類の提出が必要
- その他の要件
- 一部分野では日本語能力(JLPT N3以上等)
- 分野固有の追加要件
実務経験の具体例:
- 建設分野: 班長としての実務経験2年以上
- 製造業分野: 日本国内での当該分野実務経験3年以上
- 農業分野: 農業経営体での管理業務経験
企業が押さえるべき重要なポイント
特定技能2号取得支援の重要性
人材確保における競争優位性: 今後、特定技能2号の取得を目指す外国人材が増加することが予想されます。企業としては、以下の観点から2号取得支援を検討することが重要です:
- 優秀な人材の長期確保
- 採用競争力の向上
- 人材投資の回収期間延長
- 組織の多様性と国際化の推進
実務経験証明の準備
特定技能2号の取得には企業による実務経験の証明が不可欠です。以下の点について事前準備が必要です:
- 業務記録の整備
- 日常業務の記録化
- 管理・指導業務の明確化
- 人事評価制度の整備
- 客観的な能力評価基準
- 昇進・昇格制度の明文化
- 証明書類の準備
- 業務経歴書
- 人事評価記録
- 管理職任命辞令等
今後の制度動向と企業対応
制度改正の動向
想定される制度変更:
- 対象分野のさらなる拡大
- 試験制度の改善・標準化
- 手続きのデジタル化推進
- 二国間協力の拡充
企業が取るべき戦略
短期的対応:
- 現行制度下での特定技能1号採用の推進
- 社内支援体制の整備
- 登録支援機関との連携強化
中長期的対応:
- 特定技能2号取得を見据えた人材育成プログラムの構築
- 外国人材のキャリアパスの明確化
- 多文化共生の職場環境整備
まとめ
特定技能1号と2号の違いは、単なる技能レベルの差異にとどまらず、外国人材の将来設計や企業の人材戦略に大きな影響を与える重要な要素です。
重要なポイントの再確認:
- 在留期間: 1号は最大5年、2号は更新制限なし
- 永住権: 2号のみ永住権申請の在留歴にカウント
- 家族帯同: 2号では配偶者・子の帯同が可能
- 支援義務: 2号では支援計画不要
- 技能水準: 2号では管理・指導レベルの技能が必要
企業の皆様におかれましては、特定技能外国人の採用にあたり、1号から2号への移行を見据えた長期的な人材育成戦略を検討されることをお勧めいたします。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、特定技能に関する以下のサポートを提供しております:
- 在留資格申請手続き代行
- 支援計画書の作成支援
- 雇用契約書等の書類作成
- 登録支援機関設立サポート
- 特定技能2号移行支援
- 永住権申請サポート
特定技能制度に関するご相談は、豊富な実務経験を持つ行政書士法人塩永事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
本記事に関するお問い合わせ 行政書士法人塩永事務所 〒[熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6 TEL:[096-385-9002] Email:[info@shionagaoffice.jp]
