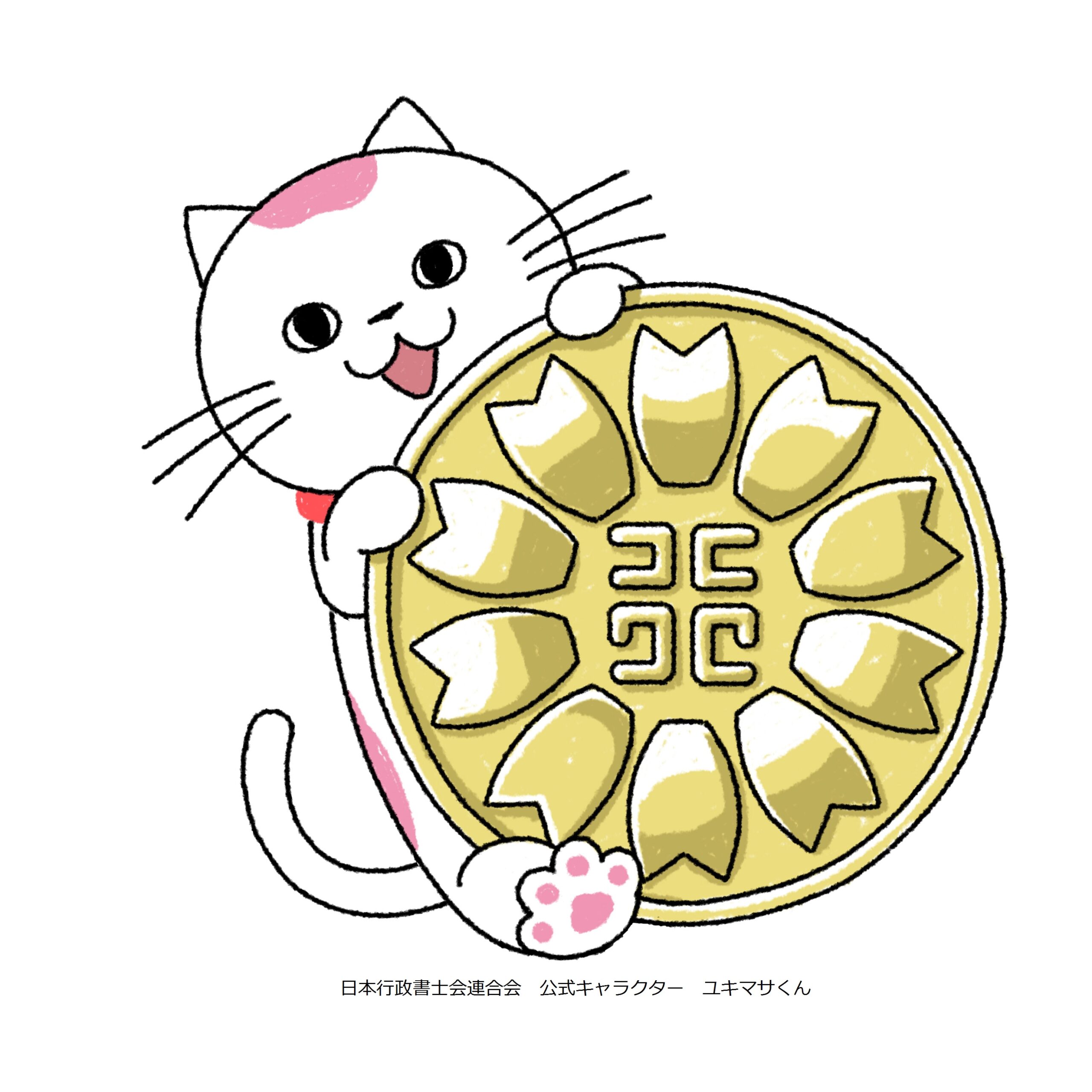
お酒の輸出に必要な【輸出酒類卸売業免許】の完全ガイド
概要
輸出酒類卸売業免許とは、日本国内で製造された酒類を、事業者自身が直接、海外の消費者や現地の酒類取扱業者に輸出するために必須の免許です。
ポイントは「自己が直接」輸出を行う場合に適用される点です。国内の輸出業者に卸す場合は別の免許が必要になるため注意してください。
認可される販売方法と品目
-
販売方法は海外(国外)への輸出に限られます。
-
原則として、販売できる酒類の品目に制限はありません。
-
ただし、申請時の「取引承諾書」に記載された取扱品目(例:清酒のみ等)に基づき、個別に限定される場合があります。
-
幅広い品目で申請したい場合は、複数種を扱う仕入先から承諾書を得るのがおすすめです。
-
よくある誤解
-
通信販売酒類小売業免許(オンライン販売など)では、海外の消費者向けの販売はできません。
→ 海外向けの酒類販売は、名称に「卸売」とあっても、輸出先消費者への販売(小売)にもこの免許が必要です。
取得に必要な主な要件
1. 人的要件
-
申請者・主要役員等に、税金滞納/未納や酒税法違反・重大な法律違反がないこと。
2. 場所的要件
-
事務所など、受注や事務手続きが実際に行える拠点が必要です。
-
不適切と認められる場所に販売場を設けることはできません。
3. 経営基礎要件
-
経営内容が健全であること(直近の決算で資本等の額を超える繰越損失がないことなど)。
-
直近3年間で、3期連続の大きな赤字(資本等の額の20%超)は不可。
4. 能力・知識
-
酒類販売の長期間の経験は不要。
-
「酒類販売管理研修」を受講することで知識面の要件は満たせます。
-
貿易実務や輸出業務の経験・知識が求められるため、未経験の場合は計画等で補う必要があります。
申請時に確認すべきポイント
-
何を売るか
(日本酒、焼酎、ウィスキーなど具体的な種類を決定) -
誰に売るか
(輸出先企業・消費者を特定し、承諾書等の証拠を添付) -
どのように売るか
(仕入れ元との取引可能性の立証が必要。蔵元・ブルワリーなど、実際の仕入先との交渉・取引承諾書取得が必須)
申請から取得までの流れ
-
初回無料相談(電話・LINEなど)
-
具体的なヒアリングとご提案、お見積り
-
ご契約・着手金お支払い
-
必要書類の準備・収集(承諾書・証明書類等)
-
税務署へ申請
-
追加対応(必要な場合)
-
許可結果通知・登録免許税のお支払い
-
標準処理期間は約2カ月ですが、書類準備の期間も加味し、実務的には3~4カ月程度かかることが一般的です。
費用の目安
| 取得する免許 | 合計費用 | 内訳 |
|---|---|---|
| 輸出酒類卸売業免許(主に輸出用) | 222,000円(税込) | 基本報酬:132,000円・登録免許税:90,000円 |
| 証明書等取得代行(オプション) | 取得手数料1,100円/通 + 諸費用 | 履歴事項全部証明書、住民票等 |
-
詳細な費用やオプションは各行政書士事務所で異なります。初回相談時に見積りが提示されます。
まとめ
-
販売方法:海外への輸出に限る
-
酒類の品目:原則制限なし(取引先次第で限定される場合も)
-
経営状態・人的信頼性・取引計画が必要
-
経験がなくても申請は可能だが、貿易実務に精通した体制・計画が求められる
日本国内で製造されたお酒の輸出拡大は、国税庁も後押ししており、年々注目度がアップしています。免許取得のハードルはあるものの、ポイントを押さえて準備すれば必ず取得が可能です。プロの行政書士と連携し、事業計画をしっかり立てることが成功のコツです。
