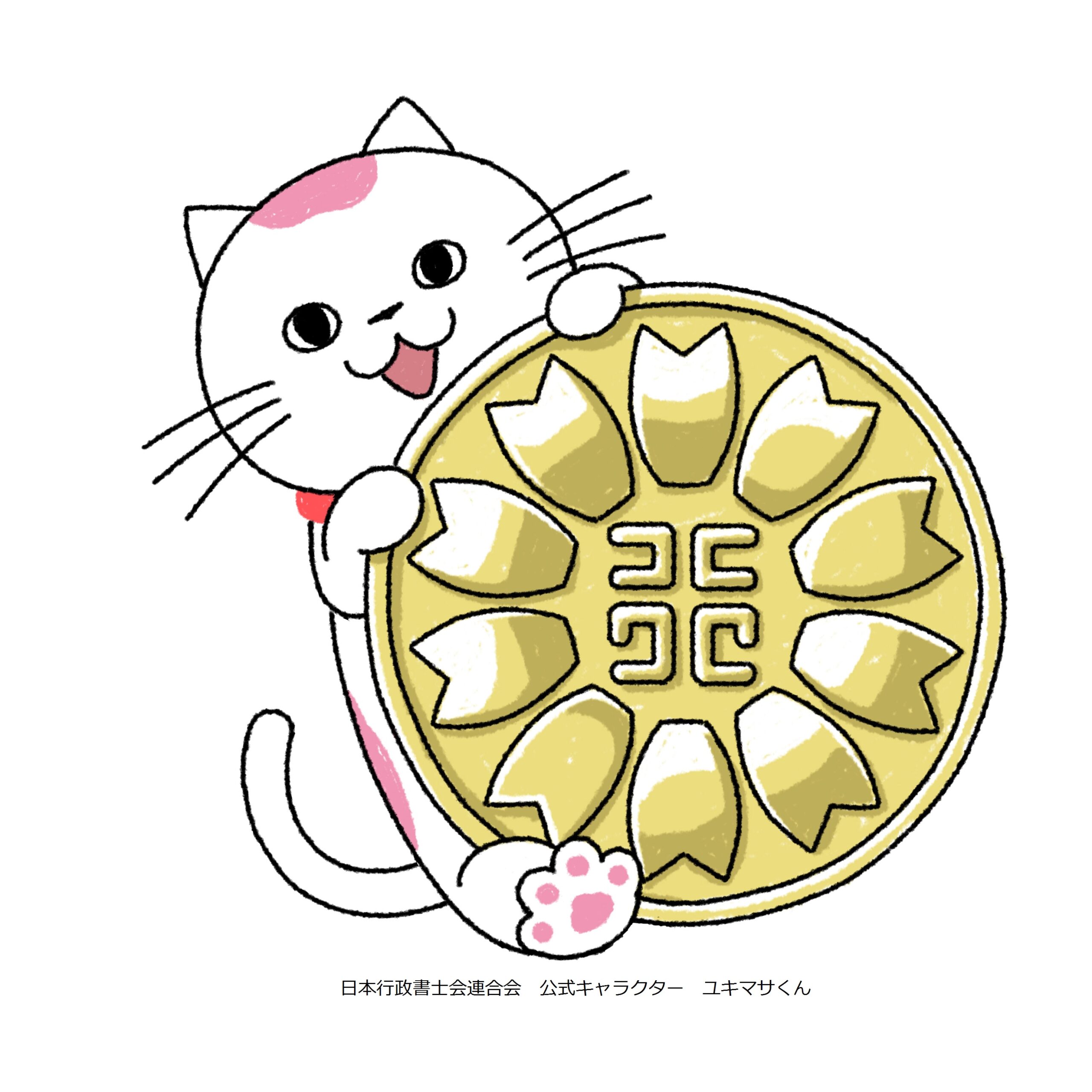
【2024年最新版】お酒の輸出・輸入に必要な免許について詳しく解説
通信販売酒類小売業免許の限界と、輸出入ビジネスへの関心の高まり
通信販売酒類小売業免許は、販売可能な酒類の種類や販売方法に多数の制限があるため、国内における酒類のオンライン販売を大規模なビジネスに発展させるのは難しいのが現状です。
そのため、現在では 海外から酒類を輸入するビジネス や、日本産の酒類を海外に輸出するビジネス に関心が集まっています。
たとえば、すでに食品や日用品など他の商材で海外との取引を行っている企業が、新たに酒類の取り扱いを検討するケースや、外国人経営者が母国との間で日本酒や焼酎などの輸出入を希望されるケースも多く見受けられます。
弊所では、酒類販売業免許の取得サポートを専門的に行っており、実に多様な相談を日々お受けしております。
輸出入酒類卸売業免許とは
酒類販売業免許は大きく分けて以下の2種類に分類されます:
-
酒類小売業免許
-
酒類卸売業免許
※その他、「酒類販売媒介業免許」という種類も存在しますが、該当ケースが稀であるため本稿では割愛します。
この「卸売業免許」の中に、**「輸出入酒類卸売業免許」**という形態があり、さらに以下のように分類されます:
-
輸入酒類卸売業免許:海外の製造業者・業者等から酒類を仕入れ、国内の酒販業者に販売するための免許。
-
輸出酒類卸売業免許:日本国内の酒類(例:日本酒、焼酎など)を海外に販売・輸出するための免許。
輸出入酒類卸売業免許の取得時の注意点
1. 貿易業務経験の有無
基本的な申請要件は他の卸売業免許と共通していますが、審査時には「貿易実務の経験」があるかどうかが確認される傾向にあります。
-
すでに他の製品で輸出入ビジネスを行っている場合、実績として評価されやすいです。
-
一方で、まったく貿易経験がない場合でも申請は可能ですが、その場合は具体的なビジネススキーム(流通ルート、販売計画など)の提示が必要になります。
2. 取引承諾書の準備
輸出入を問わず、卸売免許申請時には「取引承諾書」が必要になります。
-
輸入の場合:海外メーカー等を仕入先、国内の酒販業者を販売先として、各1社以上から承諾書を入手する必要があります。
-
輸出の場合:国内の酒造会社等を仕入先、海外の輸入業者などを販売先として、同様に承諾書が求められます。
>ポイント
取引が確定していない、あるいは「将来的に取引したい」といった曖昧な状態では申請できません。あらかじめ、仕入先・販売先との関係構築が不可欠です。
3. 販売場(事務所・拠点)に関する要件
免許は「販売場」(=酒販業務を実際に行う拠点)に対して発行されるため、所在地に注意が必要です。
例えば:
-
法人の本店が東京都港区にあっても、酒類販売業務を北海道の支店で行う場合、北海道の販売場を管轄する税務署に申請することになります。
また、店舗販売を行わず事務所のみの運用であっても、業務に必要な環境(電話、通信機器、帳簿管理の設備など)が整っていることが必要条件となります。
>多くの方が誤解されがちですが、「会社で免許を取得すれば全国どこでも販売できる」というわけではありません。販売場の所在地は非常に重要な審査ポイントです。
まとめ:酒類輸出入ビジネスの可能性と免許取得の難易度
お酒の輸出入ビジネスは、世界的な日本酒・焼酎ブームも後押しし、大きな可能性を秘めた市場です。
一方で、酒類販売業免許の申請は非常に専門的かつ複雑なプロセスを伴います。提出書類の内容や事前準備の精度が、審査通過の成否を大きく左右します。
全国対応可能な専門行政書士がサポートします
お近くに酒類販売業免許の申請に詳しい行政書士が見つからない場合でも、どうぞご安心ください。
弊所では、電話・メール・郵送のみで全国どこからでもご依頼をお受けしており、非対面で手続きが完結します。
どのような小さなご相談でも、お気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門家が丁寧に対応いたします。
