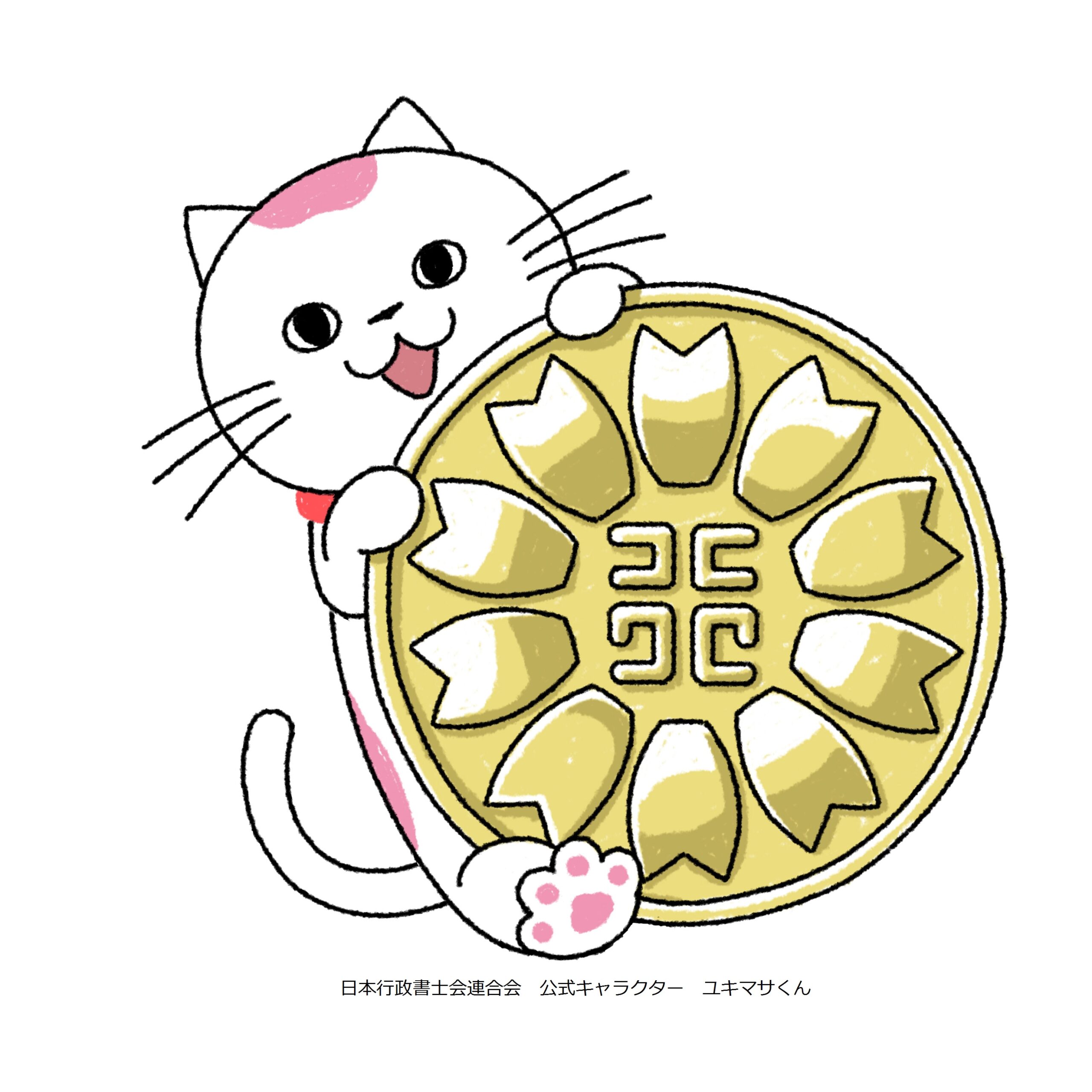
JAPHICマーク認証の詳細について
はじめに
近年、個人情報の漏洩・流出事件が増加の一途を辿っており、企業にとって個人情報保護は経営上の重要課題となっています。2023年度の個人情報漏洩件数は1万3,279件に上り、この問題は決して他人事ではありません。個人情報漏洩は、ハッキングやウイルスによるものだけでなく、PCやUSBメモリの紛失・盗難、メール誤送信、設定ミスなどの人為的な問題でも発生します。
こうした状況を受け、企業の個人情報保護体制の確立と第三者認証の重要性が高まっています。本記事では、行政書士法人塩永事務所の専門的な視点から、中小企業でも取得しやすい新しい認証制度である「JAPHICマーク認証」について詳しく解説いたします。
JAPHICマーク認証とは
JAPHICマーク認証は、個人情報保護委員会に認められた認定個人情報保護団体であるJAPHICマーク認証機構が運営する第三者認証制度です。2021年7月28日付けで個人情報保護委員会より正式に認定を受けており、個人情報保護法第37条の規定に基づく認定個人情報保護団体として、事業者の個人情報の適正な取り扱いの確保を目的とした業務を行っています。
この認証制度は、個人情報保護法を基準とする「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」(個人情報保護委員会)に準拠している事業者を認定する第三者認証であり、従来のプライバシーマーク(Pマーク)に代わる新しい選択肢として位置づけられています。
個人情報漏洩によるリスクと損害
個人情報漏洩のリスク
- 信頼性の低下:顧客やパートナーの信頼を損ない、ビジネスの評判が傷つきます
- 法的責任:個人情報保護法違反により罰金や訴訟などの法的な責任を負う可能性があります
- 経済的損失:漏洩に伴う調査費用や被害賠償、顧客離れによる売上減少など、経済的損失が発生します
- 競争力の低下:漏洩が頻発する企業は競争力が低下し、他社に取って代わられる可能性があります
損害賠償の相場
個人情報漏洩による損害賠償の相場は、1人あたり数千円から数万円程度です。
- 一般的な連絡先情報で二次被害がない場合:1人あたり3,000円~5,000円程度
- 1,000人分の流出の場合:約3,000万円程度
- 10,000人分の流出の場合:約3億円程度
- センシティブな情報で二次被害がある場合:1人あたり35,000円の損害賠償が認められた判例もあります
JAPHICマークの種類
1. JAPHICマーク
一般的な事業者が取得する基本的なマークで、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」(個人情報保護委員会)に準拠しています。
2. JAPHICマークメディカル
医療・介護関係事業者を対象とした専用のマークで、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(厚生労働省)に準拠しています。
JAPHICマーク認証の特徴
1. 低コスト
従来のプライバシーマークと比較して、約半分から1/4の費用で取得可能です。
2. 短期間での取得
取得期間は約3ヶ月と短く、迅速な認証取得が可能です。
3. 個人事業主も対象
個人事業主から中小企業、大企業まで幅広い事業者が対象となります。
4. 現実的な審査基準
個人情報保護法ガイドラインを基準とし、日常業務に即した無理のない運用を重視した現実的で明確な審査基準により、あらゆる法人が第三者認証を取得することができます。
取得をお勧めする業種
個人情報をより多く取り扱う以下のような業種が特に取得されています:
- 不動産業:開発、建設、土木、測量、ハウスメーカー、不動産仲介など
- 生活関連サービス:ハウスクリーニング、エアコンクリーニング、警備など
- 医療・福祉:病院、クリニック、薬局、介護事業、健康管理サービスなど
- Eコマース:オンラインショップやマーケットプレイス
- 教育機関:塾、オンライン学習プラットフォーム、スポーツ教室など
- 人事・採用:人材紹介会社、人材派遣会社など
- IT業界:ソフト・アプリ(マッチングアプリなど)開発など
- マーケティング・広告:データ解析やターゲット広告を行う企業など
- イベント業:イベント・セミナー運営、アンケート収集など
- その他:オーダースーツ業、印刷業(名刺やDM発送)など
申請資格
対象となる事業者
- 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」の対象となる事業者
- JAPHICマークメディカルの対象となる事業者は除外
欠格事項
次に示す欠格事項のいずれにも該当しない事業者であること:
- 申請の日前2年以内にJAPHICマーク認証の取り消しを受けた事業者
- 申請の日前2年以内に個人情報の取り扱いにおいて個人情報及び特定個人情報の外部への重大な漏えい、その他本人の利益の重大な侵害を行った事業者
認証取得のメリット
対外的メリット
- コンプライアンス(法令順守)の徹底
- 公共事業入札・大手企業との取引条件に適合
- 認証マークを表示して自社をPR
- 委託先の管理 – 委託先からの漏洩は委託元の責任となるため、委託先の認証取得は重要
社内的メリット
- 法令順守(個人情報保護法)の徹底
- 個人情報保護システムレベルの向上
- 情報漏洩リスクの低減
- 関係者による悪意ある犯罪を抑止
入札参加資格としての採用事例
熊本県での採用事例
熊本県庁では、委託先選定において「プライバシーマークやJAPHICマーク等の個人情報保護に関する認証制度による認証を得ていることを条件とすることを検討する」としています。
全国の自治体・外郭団体等での採用事例
- 大阪府総務部契約局(新行政文書管理システム開発・運用保守業務)
- 東京都北区役所(窓口業務案内、申請書類等記入案内、庶務事務補助)
- 東京都中野区役所(区立図書館システム構築及び保守運用業務委託)
- 大阪府堺市(特定健康診査及びがん検診受診率向上対策業務)
- 京都市保健福祉局(特定健康検診受診勧奨業務)
- 防衛省(職員の勤務実態及び意識に関する調査)
- 横浜市SDGs認証「Y-SDGs」加点ポイント
大企業での採用事例
- 某大手電機メーカー:ソーラーパネル販売代理店・設置業者に対し取得を条件
- 某大手インターネット検索企業:マッチングアプリ運営企業がバナー広告を掲載する際の条件
JAPHICマークとプライバシーマークの比較
| 項目 | プライバシーマーク | JAPHICマーク |
|---|---|---|
| 審査基準 | JIS Q 15001(より厳格な基準) | 個人情報保護法ガイドライン(実態重視) |
| 審査・運用負荷 | 高い(運用負担・人的負担が大きい) | 低い(運用負担が小さく、少人数でも可) |
| 費用 | 高め(コンサル料・申請料・更新料が高い) | 安価(費用はPマークの約半分~1/4) |
| 取得期間 | 約10ヶ月 | 約3ヶ月 |
| 有効期間 | 2年 | 1年 |
| 認知度 | 高い | 近年上昇中だが、Pマークほどではない |
| 対象 | 大規模事業者が多い | 小規模・中小企業向けにも適している |
| 入札要件 | 官公庁・大企業で広く認められている | 一部官公庁等でPマーク同等に扱われる |
JAPHICマーク認証の費用
新規申請(有効期間:1年)
| 従業者数 | 申請審査料 | 認証料 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 5名まで | 105,000円 | 52,500円 | 157,500円 |
| 6~50名まで | 157,500円 | 73,500円 | 231,000円 |
| 51名以上 | 210,000円 | 105,000円 | 315,000円 |
更新申請(有効期間:1年)
| 従業者数 | 申請審査料 | 認証料 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 5名まで | 42,000円 | 52,500円 | 94,500円 |
| 6~50名まで | 84,000円 | 73,500円 | 157,500円 |
| 51名以上 | 126,000円 | 105,000円 | 231,000円 |
※現地審査に係る交通費・宿泊費実費が別途必要です。
認証取得までの流れ
1. 申請前の準備
現在の個人情報保護体制の評価と認証要件との適合性確認を行います。
2. 申請手続き
JAPHICマーク認証機構の専用フォームから申請を行います。
3. 審査
審査機関による書面審査及び必要に応じた現地調査が実施されます。
4. 判定
判定会議により合否が決定されます。
5. 認証
合格の場合、年会費の支払いにより認証書が発行され、マークの使用が認められます。
6. 認証日
認証日は毎月1日となっており、審査を完了した月の翌月1日が認証日となります。
継続的な運用について
JAPHICマーク認証は1年ごとに更新審査を受ける必要があります。認証取得後も、個人情報保護体制の維持・運用と継続的な改善が求められます。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、JAPHICマーク認証の取得をお考えの事業者様に対して、以下の包括的なサポートを提供しています:
1. 認証取得の可否判断
- 現在の個人情報保護体制の詳細な評価
- 認証要件との適合性確認
- 取得に向けた課題の洗い出し
2. 必要書類の作成支援
- 個人情報保護方針の策定
- 社内規程・マニュアルの整備
- 申請書類の作成支援
3. 体制整備のコンサルティング
- 個人情報保護管理体制の構築
- 従業員教育の実施方法の策定
- 安全管理措置の整備
4. 審査対応サポート
- 審査員との面談対応
- 指摘事項への対応支援
- 必要に応じた是正措置の実施
5. 継続的な運用支援
- 年次更新審査への対応
- 社内監査の実施支援
- 法改正への対応
- 運用状況の定期的な見直し
まとめ
JAPHICマーク認証は、個人情報保護法に準拠した新しい第三者認証制度として、従来のプライバシーマークと比較して低コストで短期間での取得が可能な制度です。コストや運用負荷を抑えたい小規模・中小企業に特に適しており、現実的な審査基準により多くの企業が認証を取得できる仕組みとなっています。
個人情報漏洩による損害は、企業の存続にも関わる重大な問題となり得ます。JAPHICマーク認証の取得は、企業の個人情報保護体制の確立と信頼性向上、そして取引機会の拡大に大きく寄与します。
特に、熊本県をはじめとする地方自治体でも入札参加資格として採用される例が増えており、地域の中小企業にとっても重要な競争力向上策となっています。
当事務所では、JAPHICマーク認証の取得を検討されている事業者様に対して、専門的な知識と豊富な経験を活かした包括的なサポートを提供しております。個人情報保護体制の確立から認証取得、継続的な運用まで、お客様のビジネスに最適なソリューションをご提案いたします。
認証取得に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
個人情報保護・第三者認証に関するご相談は、豊富な実績を持つ当事務所にお任せください。お客様の事業規模や業種に応じた最適な個人情報保護体制の構築をサポートいたします。
