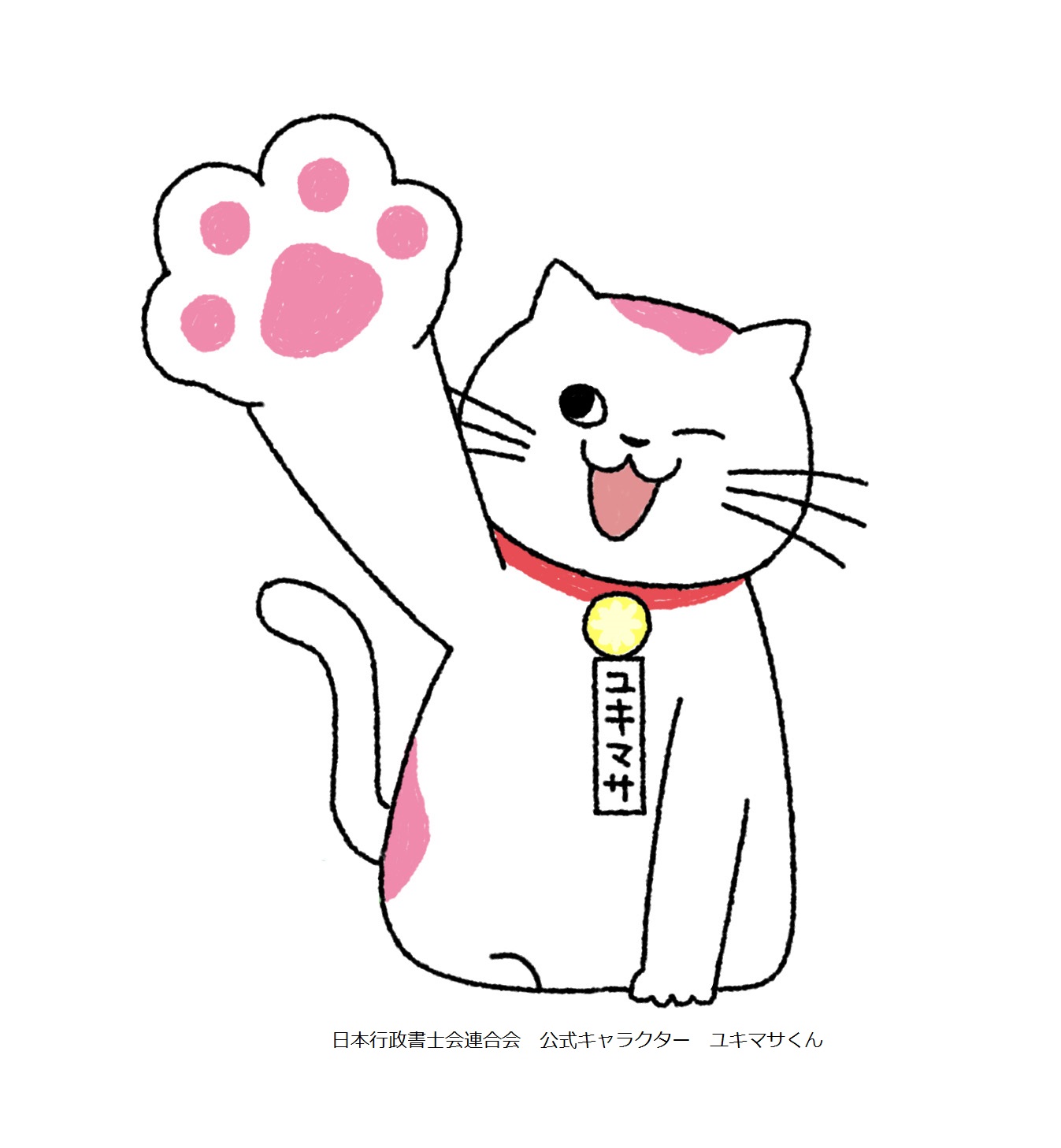
【2024年最新情報】酒類輸出のための「輸出酒類卸売業免許」を徹底解説
近年、日本酒やウイスキー、焼酎など、日本産の酒類は海外で高い評価を受け、輸出市場が拡大しています。国税庁も輸出促進に力を入れており、この成長分野への参入を検討されている方も多いのではないでしょうか。
日本から酒類を輸出する際には、**「輸出酒類卸売業免許」**の取得が必須となります。ここでは、この免許の概要から取得のポイント、そして必要となる手続きについて詳しく解説します。
輸出酒類卸売業免許とは
酒類販売業免許は、大きく分けて**「卸売業免許」と「小売業免許」の2種類があります。このうち、「輸出酒類卸売業免許」は卸売業免許の一つ**に位置づけられます。
「卸売」と「小売」の定義の違い
一般的に使われる「卸売」や「小売」とは異なり、酒税法における両者の定義は以下の通りです。
- 卸売: 酒類販売業者や酒類製造者など、酒類免許を持つ事業者に対して酒類を販売すること。
- 小売: 消費者や飲食店、菓子製造業者など、酒類免許を持たない人に対して酒類を販売すること。
つまり、販売先が酒類に関する免許を持っているかどうかが、卸売と小売の区別の基準となります。
輸出酒類卸売業免許の定義と必要性
輸出酒類卸売業免許とは、「自己が輸出する酒類を卸売できる酒類卸売業免許」を指します。「自己が輸出」とされているため、輸出申告を行うのは免許取得者(または通関業者による代理申告)となります。
海外の消費者や酒類取扱業者へ酒類を輸出販売する際に、この免許が必要になります。
過去には、海外の消費者への通販販売において「通信販売小売業免許」でも可能と判断されるケースもありましたが、現在は税務署や国税局の判断が統一され、輸出販売には原則として「輸出酒類卸売業免許」の取得が必要とされています。これは、輸出に関する手続きを円滑に進めるための措置と考えられます。
輸出に必要な2つの手続き
酒類を海外へ輸出するには、大きく分けて以下の2つの役所手続きが必要となります。
- 輸出酒類卸売業免許の申請手続き: 輸出契約を締結する前に取得が必要な免許です。
- 輸出先で必要な公的証明書類の入手手続き: 輸出先の国のルールに基づき、商品が到着し、輸入通関手続きを行う際に必要となる書類です。
これらの書類は、商品が現地でスムーズに輸入通関されるために、輸出国を出る前に準備し、 timely に送付する必要があります。
輸出酒類卸売業免許取得の主要なポイント
輸出酒類卸売業免許の取得には、いくつかの重要な要件があります。
- 取引先の確保:
- 販売先: 「免許を取得したら酒類を購入する」という旨の契約書または同意書を、輸出先の顧客(海外のインポーターなど)から事前に取得している必要があります。漠然とした輸出計画では申請できません。
- 仕入先: 商社などの場合、国内の酒造メーカーや卸売業者から「免許を取得したら酒類を販売する」という旨の契約書または同意書を事前に取得している必要があります。
- 貿易業務の経験: 申請者(法人または個人事業主)やその役員、従業員に**海外への輸出に関する知識や経験(貿易実務の知識や経験)**が審査されます。輸出経験者がいない場合は、輸出経験のある商社などを仲介に入れることも検討が必要です。
- 人的要件・経営基礎要件・場所的要件: 他の酒類販売業免許と同様に、以下の要件が問われます。
- 人的要件: 会社、経営者の経験、納税義務の履行状況、酒税法違反の有無など。
- 経営基礎要件: 過去の決算内容、納税状況など、事業を継続していくための十分な経営基盤があるか。
- 場所的要件: 酒類販売業務を行う具体的な場所(事務所や店舗)があること。単に電話やスマートフォンがあれば良いというわけではなく、物理的な場所の確保が必須です。
- 具体的な事業計画: 「とりあえず免許を取得しておこう」という考えでは申請できません。何を(酒類の種類)、誰に(輸出先の顧客)、どのように(仕入先を含めた流通経路)販売するのか、具体的な事業計画を提示する必要があります。例えば、日本酒の輸出を条件に免許を取得した場合、ウイスキーの輸出には別途条件緩和の申請が必要となる場合があります。
輸出に必要な公的証明書類とは
輸出先の国では、輸入する酒類の安全性や品質を確認するため、様々な公的証明書類の提出を義務付けています。これらの書類は、原則として輸出前に取得しておく必要があります。
主な証明事項は以下の通りです。
- 製造施設の登録、製造工程の証明、メーカー登録
- 原材料、添加物、残留農薬、抗生物質に関する情報
- 産地証明
- 福島原発事故に関連する放射能数値、安全証明(規制対象地域の場合)
- 輸入ライセンス該当商品であることの証明
これらの申請先は各国の所轄官庁や、一部は商工会議所が発行しています。書類不備により、商品が到着しても輸入通関できない、最悪の場合、現地での廃棄や積戻しとなるリスクもあるため、事前の確認と準備が非常に重要です。
免許取得までの流れと費用
酒類販売業免許の申請は、多くの書類収集や要件調査が必要となり、一般的に長い道のりとなります。税務署の審査自体に約2ヶ月かかりますが、その前の書類収集や準備期間も考慮すると、全体で数ヶ月を要することが一般的です。
申請プロセス
- 相談・ヒアリング: まずはお客様の状況や事業計画を詳しく伺い、免許取得の可能性を判断します。
- 契約・資料収集: 契約締結後、必要な書類の収集や要件調査を行います。
- 申請書類作成: 経験豊富な行政書士が申請書類を作成します。
- 税務署への申請: 全ての準備が整い次第、所轄の税務署へ申請します。
- 審査・追加対応: 税務署による審査が行われ、必要に応じて追加資料の提出や質疑応答に対応します。
- 結果通知・免許取得: 審査に通ると結果通知が届き、登録免許税を納付後、免許取得となります。
信頼できる専門家への相談を
お酒の輸出ビジネスは大きな可能性を秘めていますが、酒類販売業免許の取得は非常に複雑で、専門的な知識と経験が必要です。
当事務所では、酒類販売業免許申請を専門とする行政書士が、お客様の状況に応じた丁寧なサポートを提供しています。輸出のための免許取得経験も豊富ですので、ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
