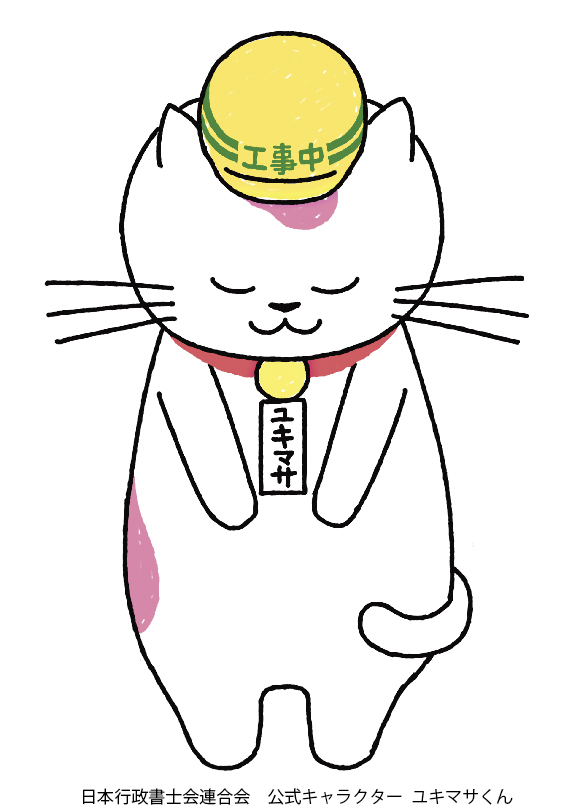
建設業許可・土木工事の申請手続き完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
はじめに
建設業許可は、建設工事を適正に施工するために国土交通大臣又は都道府県知事から与えられる許可です。特に土木工事業においては、道路、河川、上下水道など社会インフラの整備に関わる重要な業種として、厳格な許可基準が設けられています。
本記事では、建設業許可の中でも土木工事業に焦点を当て、申請手続きの詳細について解説いたします。
建設業許可の基本概要
許可が必要な工事
建設業許可が必要となるのは、以下の工事を請け負う場合です:
- 一般建設業許可:下請契約の合計額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の工事
- 特定建設業許可:下請契約の合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事
土木工事業の定義
土木工事業とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事を指します。具体的には:
- 道路工事
- 河川工事
- 上下水道工事
- 港湾工事
- 空港工事
- 鉄道工事
- その他の土木工作物の建設工事
許可要件の詳細
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者(経管)
一般建設業許可の場合:
- 許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者としての経験
特定建設業許可の場合:
- 許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者としての経験
2. 営業所ごとの専任技術者
一般建設業許可の場合:
- 大学の土木工学科等卒業後、3年以上の実務経験
- 高等学校の土木工学科等卒業後、5年以上の実務経験
- 10年以上の実務経験
- 1級土木施工管理技士等の国家資格
特定建設業許可の場合:
- 1級土木施工管理技士
- 技術士(建設部門)
- その他国土交通大臣が認定した資格
3. 誠実性
法人の場合はその法人、個人の場合はその本人及び支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
4. 財産的基礎
一般建設業許可の場合:
- 自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力
- 許可申請直前の決算期において欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
特定建設業許可の場合:
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上
- 資本金が2,000万円以上
- 自己資本が4,000万円以上
5. 適正な社会保険の加入
健康保険、厚生年金保険、雇用保険への適正な加入が必要です。
申請に必要な書類
基本書類
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 役員等の一覧表(様式第1号別紙1)
- 営業所一覧表(様式第1号別紙2)
- 収支予算書(様式第1号別紙3)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 使用人数(様式第4号)
- 誓約書(様式第6号)
- 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
- 専任技術者証明書(様式第8号)
- 実務経験証明書(様式第9号)
- 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
- 許可申請者の略歴書(様式第12号)
- 株主(出資者)調書(様式第13号)
- 財務諸表(様式第15号、第16号、第17号、第18号)
- 営業の沿革(様式第20号)
- 所属建設業者団体(様式第21号)
- 健康保険等の加入状況(様式第22号)
- 主要取引金融機関名(様式第23号)
添付書類
法人の場合:
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の住民票の写し
- 役員の身分証明書
- 役員の登記されていないことの証明書
個人の場合:
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
その他共通書類:
- 営業所の写真
- 事務所の賃貸借契約書等
- 預金残高証明書
- 納税証明書
- 社会保険の加入証明書
申請手続きの流れ
1. 事前準備・相談
申請前に、許可要件を満たしているか詳細な検討を行います。特に経営業務の管理責任者や専任技術者の要件確認は重要です。
2. 書類作成
必要書類の作成を行います。特に工事経歴書や実務経験証明書は、詳細な調査と正確な記載が求められます。
3. 申請書提出
- 国土交通大臣許可:地方整備局等
- 都道府県知事許可:都道府県庁の担当部署
4. 審査
申請書提出後、約3~4か月の審査期間があります。この間、補正指示や追加書類の提出が求められる場合があります。
5. 許可通知
審査が完了し許可が下りると、許可通知書が発行されます。
許可後の義務
1. 変更届出
- 商号、名称の変更
- 営業所の新設・廃止
- 役員の変更
- 資本金の変更
- 経営業務の管理責任者の変更
- 専任技術者の変更
2. 決算変更届
毎年、決算日から4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
3. 更新申請
建設業許可の有効期間は5年間です。継続して建設業を営む場合は、期間満了の3か月前から30日前までに更新申請を行う必要があります。
土木工事業特有の注意点
1. 工事実績の証明
土木工事業では、公共工事の実績が多いため、発注者からの工事実績証明書の取得が比較的容易です。ただし、適切な工事内容の記載が重要です。
2. 技術者の確保
土木工事業では、1級土木施工管理技士等の国家資格者の確保が重要です。特に特定建設業許可では、指導監督的実務経験を有する技術者が必要です。
3. 経営事項審査との関連
公共工事の受注を目指す場合、建設業許可取得後に経営事項審査を受審する必要があります。
申請費用
許可申請手数料
- 知事許可(一般・特定いずれか一つ):90,000円
- 知事許可(一般・特定両方):180,000円
- 大臣許可(一般・特定いずれか一つ):150,000円
- 大臣許可(一般・特定両方):300,000円
行政書士報酬
申請手続きの複雑さから、多くの事業者が行政書士に依頼されています。報酬額は申請内容により異なりますが、適正価格でのサービス提供を心がけております。
よくある質問
Q1. 個人事業主でも建設業許可は取得できますか?
A1. はい、個人事業主でも許可要件を満たせば取得可能です。ただし、法人と比べて信用面での課題がある場合があります。
Q2. 許可取得までの期間はどのくらいですか?
A2. 申請書提出から許可通知まで約3~4か月かかります。ただし、書類の準備期間も考慮する必要があります。
Q3. 他の業種の許可も同時に申請できますか?
A3. はい、要件を満たしていれば複数業種の同時申請が可能です。
最後に
建設業許可の取得は、事業の発展と社会的信用の向上に大きく寄与します。しかし、申請手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、建設業許可申請に関する豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の許可取得をサポートいたします。申請前の相談から許可取得後の各種手続きまで、総合的なサービスを提供しております。
建設業許可に関するご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
建設業許可申請の専門家として、お客様の事業発展をサポートいたします。
