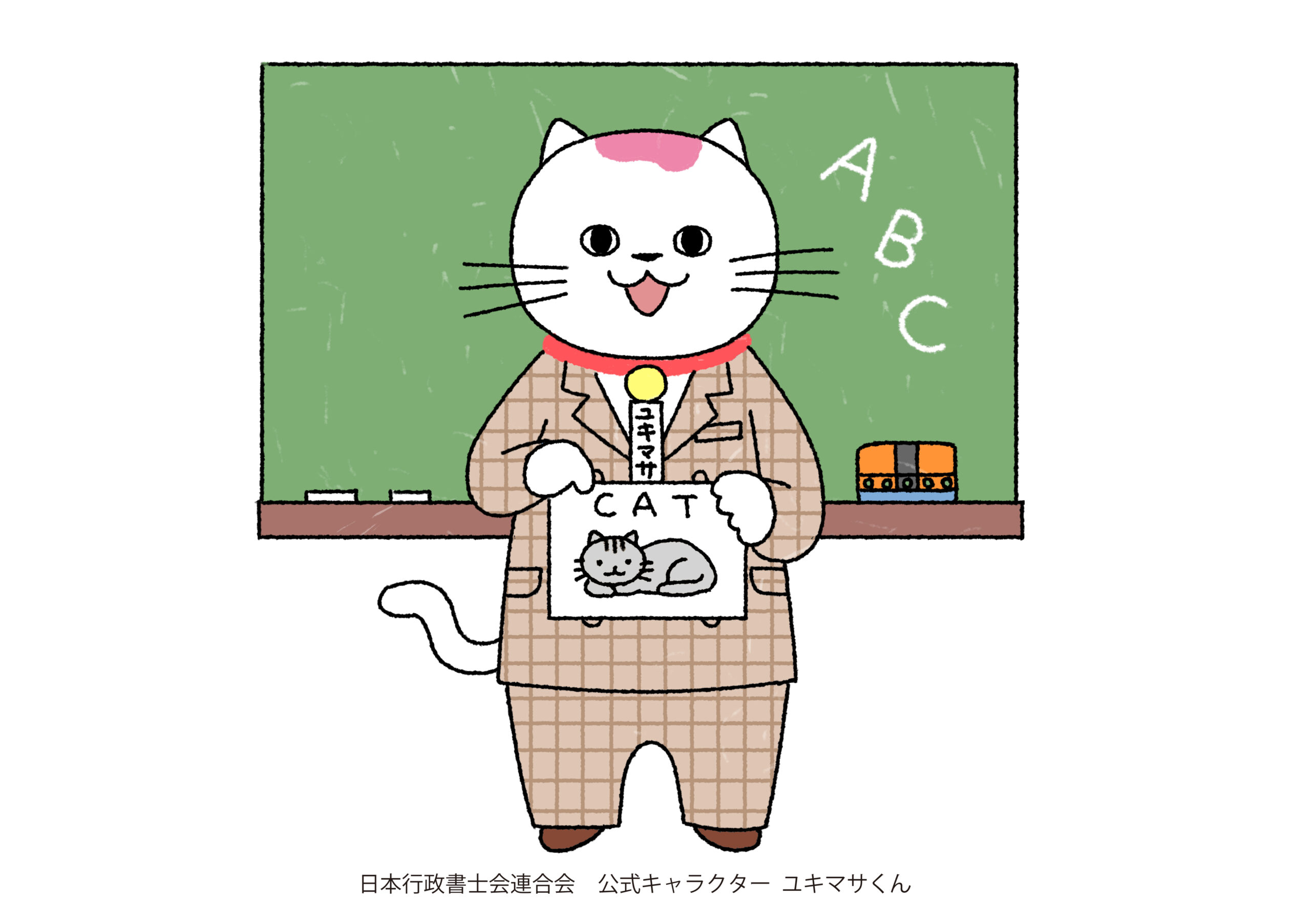
帰化申請の概要(行政書士法人塩永事務所)
外国籍の方が日本国籍を取得するための手続を「帰化」といい、法務大臣の許可により日本国籍を取得できます。根拠は国籍法4条です。帰化は権利として自動的に付与されるものではなく、申請に基づく許可制です。
帰化許可・不許可の基本枠組み
- 制度の性質: 日本は出生地主義(出生のみで国籍付与)を採用していません。日本で生まれ長く生活していても、日本国籍を有していない限り、国籍取得には帰化申請が必要です。
- 申請の方法: 申請者本人が法務局・地方法務局で出頭し、書面で申請します。審査は法務大臣の裁量で行われ、許可・不許可が決定されます。
- 審査内容: 来日(または出生)以降の在留・生活状況、現在の生計・就労状況、素行等を示す書類を添付し、将来にわたり安定して日本で生活できることを立証します。担当官による面接を経て、総合的に判断されます。
- 不許可の典型例: 税金の滞納、犯罪歴、虚偽申請、要件未達などがある場合は不許可となる可能性があります。申請後の長期出国など、審査に影響し得る行動にも注意が必要です。
- 受理と再申請: 申請時点で明らかな不許可事由があると、申請が受理されないことがあります。不許可となった場合でも、事由解消後に再申請するのが一般的で、事由によっては解消後も一定期間の経過を要することがあります。
国籍取得の他の仕組み(参考)
- 父母両系血統主義: 国籍法改正により、父が外国籍でも母が日本国籍であれば出生時に日本国籍を取得できるようになりました(両系血統主義の採用)。
- 認知による取得: 平成20年(2008年)の改正により、出生後に日本人父が認知した場合でも、所定の届出により日本国籍を取得する道が認められています(国籍法3条)。
帰化の具体的要件の例
- 通常帰化(国籍法5条):
- 居住要件: 原則として引き続き5年以上、日本に住所を有すること。
- 能力要件: 原則、成年に達していること(民法の成年年齢に従います)。
- 素行要件: 税・社会保険を含む法令順守、安定した生活、前科の有無等が総合評価されます。
- 生計要件: 自身または世帯で生計を維持できること。
- 国籍要件: 原則として重国籍を避けるため、帰化により外国籍を離脱できること(例外あり)。
- 憲法尊重要件: 日本の憲法秩序を害するおそれのある団体に属さないこと。
- 特別・簡易帰化(国籍法6–8条等): 日本人配偶者や日本出身の父母等の一定の関係がある場合には、居住年数などが緩和される類型があります。
上記は代表的な枠組みであり、実務では個々の事情に即した判断が行われます。必要書類・立証内容はケースにより異なります。
申請時の留意点
- 書類の整合性: 身分関係・在留履歴・就労・納税等の記録を正確に整え、矛盾がないようにします。
- 在留の連続性: 長期出国や在留資格の途切れは、居住要件の評価に影響することがあります。
- 生活の安定性: 雇用形態、収入の継続性、世帯の実態など、将来の安定を示す資料を準備します。
- 誠実な申告: 虚偽や不完全な申告は不許可・不受理の原因となり得ます。
帰化申請にかかる費用
- 手数料: 法務局に支払う申請手数料はありません。
- 実費: 添付書類の取得費用が必要です。日本国内の公的書類は概ね数千円程度が目安で、これに加えて本国書類の取得費用および翻訳料がかかります。金額は国・書類の種類・点数により変動します。
ご相談窓口
帰化申請は、準備書類の範囲が広く、個別事情に応じた対応が重要です。行政書士法人塩永事務所が、要件の事前確認から書類収集・作成、申請・面接対応までを丁寧にサポートします。
- お問い合わせ: 096-385-9002
