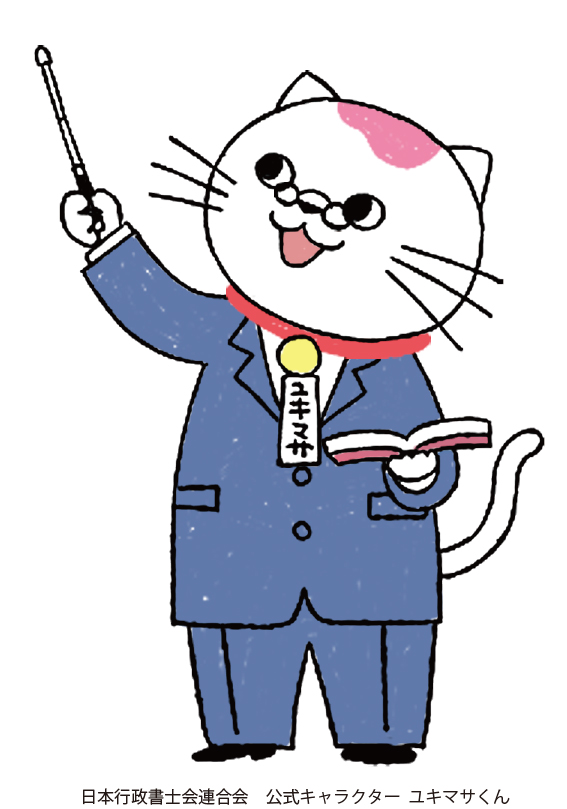
外国法人の建設業許可申請完全ガイド
はじめに
外国法人が日本国内で建設工事を請け負うためには、建設業法第3条に基づく建設業許可の取得が必要です。外国法人であっても、日本法人と同様の許可要件を満たすことで許可取得が可能ですが、海外での実務経験の証明や本国法人の資料準備など、特有の手続きが必要となります。
当事務所では、これまで数十社以上の外国法人の建設業許可取得を支援してきた豊富な実績があり、本ガイドではその知見に基づき、申請の全体像から具体的な手続きまでを詳細に解説いたします。
重要な法改正について
2025年10月16日施行の在留資格「経営・管理」に関する改正により、日本法人を新規設立する場合の資本金要件が従来の500万円から3,000万円以上へと大幅に引き上げられます。この改正は日本法人設立時に適用されますが、日本支店設置の場合は直接的な影響が限定的です。ただし、代表者の在留資格取得においては、事業の安定性・継続性を示すために十分な資本金の準備が推奨されます。
1. 日本国内における拠点形態の選択
外国法人が日本で建設業を営むためには、まず拠点形態を決定する必要があります。建設業法上の「営業所」として認められるのは、実態を伴った恒常的施設である必要があり、駐在事務所は営業活動が認められないため選択肢から除外されます。
拠点形態の比較表
| 項目 | 日本法人(株式会社等) | 日本支店 | 駐在事務所 |
|---|---|---|---|
| 営業活動 | 可能 | 可能 | 不可(情報収集・連絡業務のみ) |
| 資本金要件 | 必要(従来500万円以上、改正後3,000万円以上を推奨) | 不要(本国法人の資本で判断) | 不要 |
| 法務局登記 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 銀行口座開設 | 可能 | 可能 | 原則不可 |
| 代表者の在留資格例 | 経営・管理 | 企業内転勤 | 企業内転勤 |
| 従業員雇用 | 可能 | 可能 | 可能(営業活動を伴わない範囲) |
| 独立採算 | 独立した法人格 | 本国法人の一部門 | 本国法人の連絡拠点 |
| 税務申告 | 日本の法人税 | 支店としての法人税 | 限定的 |
各形態の特徴
日本法人(株式会社・合同会社等)
- メリット: 独立した法人格により取引先からの信用が高い、日本国内での意思決定が迅速
- デメリット: 設立手続きが複雑、資本金要件が高額(改正後)、維持コストが高い
- 適するケース: 長期的に日本市場で事業展開を計画している場合
日本支店
- メリット: 資本金不要、本国法人の信用力を活用可能、設立手続きが比較的簡便
- デメリット: 本国法人の意思決定に依存、本国法人の財務書類の翻訳・認証が必要
- 適するケース: 本国での実績を活かしながら日本市場に進出する場合
駐在事務所
- 建設業の営業活動(契約締結・見積提出等)が禁止されているため、建設業許可の取得対象外です。市場調査や情報収集のみを目的とする場合に限定されます。
拠点設置の実務ポイント
日本法人設立の場合:
- 定款作成・認証(公証役場)
- 資本金の払込(発起人名義の銀行口座)
- 設立登記申請(法務局)
- 税務署等への届出
- 社会保険加入手続き
日本支店設置の場合:
- 本国法人の登記事項証明書等の取得・翻訳・認証
- 日本における代表者の選任
- 支店設置登記申請(法務局)
- 税務署等への届出
いずれの場合も、登記完了後に銀行口座開設、社会保険加入等を進め、建設業許可申請の準備に移ります。
2. 建設業許可の要件整備
外国法人であっても、建設業法第7条に定める許可要件は日本法人と同一です。ただし、海外での経験を証明する場合、追加的な書類準備と国土交通大臣の個別認定取得が必要となります。
2-1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の配置
要件概要
建設業の経営業務について、総合的に執行した経験を有する常勤の役員等を配置する必要があります。具体的には以下のいずれかの経験が求められます。
- 経験A: 建設業の経営業務について総合的に管理した経験が5年以上
- 経験B: 経営業務の執行に関して、取締役会決議等を通じて執行役員等として関与した経験が5年以上
- 経験C: 経営業務の補佐経験が6年以上
海外経験の証明と大臣認定
海外での経験を用いる場合、国土交通大臣の個別認定を取得する必要があります。認定申請には以下の書類を準備します。
必要書類(例):
- 本国法人の登記事項証明書(会社設立証明書等)の原本および日本語翻訳文
- 申請者の在籍期間・役職を証明する書類(任命書、雇用契約書等)
- 組織図(申請者の位置づけが明確なもの、各年度ごと)
- 工事実績を証明する書類(工事契約書、注文書、請書、工事台帳等)
- 給与支払証明書または源泉徴収票(継続的な雇用関係の証明)
- その他、経営業務の実態を示す客観的資料
認定手続きの流れ:
- 国土交通省への事前相談(任意だが強く推奨)
- 認定申請書および疎明資料の提出
- 国土交通省による審査(ヒアリングが行われる場合あり)
- 認定通知書の交付(標準処理期間: 3〜6ヶ月程度)
注意点:
- すべての外国語書類には、日本語翻訳文の添付が必須
- 翻訳者の氏名・住所を明記(翻訳者の資格は不問だが、行政書士等専門家による翻訳が望ましい)
- 本国での公証・認証手続き(アポスティーユまたは領事認証)が必要な場合がある
- 認定は申請者個人に対して行われるため、担当者変更時は再度認定取得が必要
2-2. 営業所の専任技術者の配置
要件概要
建設業許可を受けようとする業種ごとに、各営業所に専任の技術者を配置する必要があります。専任技術者の要件は以下のいずれかです。
一般建設業許可の場合:
- 国家資格保有者(1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士等)
- 許可を受けようとする業種に関する10年以上の実務経験(学歴により短縮可能: 指定学科卒業者は高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上)
- その他、国土交通大臣が個別に認めた者
特定建設業許可の場合:
- 国家資格保有者(1級建築士、1級施工管理技士等の上位資格)
- 一般建設業の専任技術者要件を満たし、かつ許可を受けようとする業種について、発注者から直接請け負った建設工事で4,500万円以上のものに関し、2年以上の指導監督的実務経験を有する者
海外実務経験の証明
海外での実務経験を用いる場合も、大臣認定が必要です。
必要書類(例):
- 在籍期間・職務内容を証明する書類
- 工事実績証明書類(工事契約書、竣工図面、写真等)
- 工事内容が許可を受けようとする業種に該当することの疎明資料
- 学歴証明書(該当する場合、卒業証明書の原本および翻訳文)
営業所の実態要件
専任技術者を配置する営業所は、以下の実態要件を満たす必要があります。
- 物理的独立性: 事務所として使用できる固定的な施設(バーチャルオフィス、シェアオフィスの共有スペースは原則不可)
- 常時使用権限: 所有または賃貸借契約による使用権限
- 外部からの認識可能性: 看板・表札等による明示
- 業務実施体制: 電話・ファックス・机・椅子等の什器備品
- 専任性の確保: 専任技術者が他の営業所や他社と兼務していないこと
証明書類:
- 営業所の所在地証明(登記簿謄本、賃貸借契約書等)
- 営業所の写真(外観・内部、看板等)
- 専任技術者の常勤性を証明する書類(健康保険証、住民票等)
2-3. 財産的基礎または金銭的信用の確保
要件基準
一般建設業許可: 以下のいずれかを満たすこと
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を証明できること(金融機関の融資証明書、預金残高証明書等)
- 許可申請直前の過去5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業許可: 以下のすべてを満たすこと
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上であること
外国法人の証明方法
日本法人の場合:
- 直前決算期の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)
- 税務申告書の写し
- 資本金額を証明する書類(登記事項証明書)
日本支店の場合:
- 本国法人の財務諸表(原本および日本語翻訳文)
- 翻訳文には翻訳者の氏名・住所を記載
- 本国での公認会計士等による監査証明書(該当する場合)
- 日本支店の会計帳簿(日本での営業活動がある場合)
注意点:
- 外国法人の財務諸表が日本の会計基準と異なる場合、内容の説明が必要
- 通貨換算は申請時の為替レートを使用
- 都道府県によっては、本国法人の財務諸表に公証・認証を求める場合がある
資本金要件とビザ改正の関係
2025年10月16日以降、日本法人設立により代表者が「経営・管理」の在留資格を取得する場合、資本金3,000万円以上が実質的な要件となります。建設業許可の財産要件は500万円以上ですが、ビザ要件を満たすためには3,000万円以上の資本金準備が必要となる点に留意してください。
一方、日本支店設置の場合、代表者は「企業内転勤」の在留資格を取得するケースが多く、資本金要件の影響は限定的です。ただし、事業の安定性・継続性を示すために、本国法人の財務状況が十分であることが重要です。
2-4. 社会保険への適切な加入
加入義務のある保険
建設業許可においては、適切な社会保険への加入が義務付けられており、未加入の場合は許可を受けることができません。
法人の場合:
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険(従業員を雇用する場合)
- 労災保険(労働者を使用する場合)
個人事業主の場合:
- 国民健康保険
- 国民年金
- 雇用保険(従業員を雇用する場合)
- 労災保険(労働者を使用する場合)
加入手続きと証明
手続きの流れ:
- 年金事務所で健康保険・厚生年金保険の加入手続き
- ハローワークで雇用保険・労災保険の加入手続き
- 各機関から交付される加入証明書類の取得
許可申請時の提出書類:
- 健康保険・厚生年金保険の保険料納入証明書または領収証書
- 雇用保険の保険料納入証明書または領収証書(該当する場合)
- 各保険の加入を証明する書類(健康保険証の写し、資格取得確認通知書等)
注意点:
- 許可申請時点で加入手続きが完了していることが必要
- 従業員数がゼロの場合でも、法人は健康保険・厚生年金保険への加入義務がある
- 外国人従業員を雇用する場合も、日本の社会保険への加入が必要
2-5. 誠実性要件と欠格要件の非該当
誠実性要件
建設業法第8条第6号に定める誠実性要件では、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。
具体的な審査内容:
- 契約違反、不正行為の有無
- 建設業法違反の有無
- その他の法令違反の有無
欠格要件
建設業法第8条各号および第17条に定める欠格要件に該当しないことが必要です。
主な欠格事由:
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 建設業許可を取り消され、その日から5年を経過しない者
- 建設業許可の取消処分に係る聴聞通知前に廃業届を提出し、届出から5年を経過しない者
- 上記に該当する者が法人の役員等に含まれる場合
- 暴力団員等に該当する者、または暴力団員等と密接な関係を有する者
- 禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令で政令に定めるもの、または暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
外国法人特有の留意点
本国での違反歴の確認:
- 外国法人の場合、本国での法令違反歴も審査対象となります
- 本国での無犯罪証明書(Police Certificate / Certificate of No Criminal Record)の提出を求められる場合があります
- 本国法人が過去に営業停止処分等を受けた事実がある場合、その内容を説明する資料の提出が必要です
証明書類:
- 役員全員の身分証明書(本籍地の市区町村発行、成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明)
- 役員全員の登記されていないことの証明書(法務局発行)
- 誓約書(欠格要件に該当しない旨を誓約)
- 本国での無犯罪証明書(該当する場合、原本および日本語翻訳文)
3. 大臣認定取得と事前相談の実施
3-1. 国土交通大臣の個別認定申請
海外での経験を活用して常勤役員等または専任技術者の要件を満たす場合、建設業許可申請の前に国土交通大臣の個別認定を取得する必要があります。
認定申請の標準的な流れ
ステップ1: 事前準備(1〜2ヶ月)
- 必要書類の洗い出し
- 本国での書類収集(会社書類、工事関連書類、個人書類)
- 翻訳作業
- 公証・認証手続き(必要な場合)
ステップ2: 事前相談(任意だが推奨)
- 国土交通省土地・建設産業局建設業課への電話相談予約
- 書類案の事前確認
- 不足書類の指摘、追加疎明の必要性の確認
ステップ3: 正式申請(標準処理期間3〜6ヶ月)
- 申請書および疎明資料一式の提出
- 受付・形式審査
- 実質審査(場合によりヒアリング実施)
- 補正指示(不足書類がある場合)
- 認定・不認定の決定
- 認定通知書の交付
ステップ4: 認定後の手続き
- 認定通知書の原本を建設業許可申請に添付
- 認定内容を許可申請書に反映
認定取得のポイント
客観的証拠の重要性: 認定審査では、申請者の経験が実態として存在したことを客観的に証明できるかが最重要ポイントです。
- 工事契約書は、発注者・受注者・工事内容・金額・期間が明記されたものを準備
- 組織図は、申請者の役職・権限範囲が明確に示されたものを各年度ごとに準備
- 給与支払証明は、継続的な雇用関係を証明できる複数年度のものを準備
- 単なる在籍証明書だけでは不十分であり、実際に経営業務または実務に従事した事実を示す資料が必要
形式的書類の危険性: 認定申請において、実態を伴わない形式的な書類を提出することは厳に慎むべきです。審査の過程で虚偽が判明した場合、認定が受けられないばかりか、将来的な申請にも悪影響を及ぼす可能性があります。
翻訳の正確性: 外国語書類の日本語翻訳は、内容の正確性が求められます。専門用語(建設用語、法律用語等)については、日本の建設業法における用語との対応関係を明確にすることが重要です。
3-2. 都道府県への事前相談
建設業許可は、都道府県知事許可(一つの都道府県内のみに営業所を設置する場合)と国土交通大臣許可(二以上の都道府県に営業所を設置する場合)に区分されます。
事前相談の重要性
都道府県の建設業許可担当窓口(多くの場合、土木事務所または県庁の建設業課)では、申請前の事前相談を受け付けています。外国法人の場合、以下の点について事前相談を強く推奨します。
相談すべき事項:
- 営業所の実態認定基準(都道府県により若干の運用差異がある)
- 本国法人の財務諸表の取扱い(翻訳方法、認証の必要性等)
- 大臣認定通知書の確認
- 在留資格との関係(特に資本金要件)
- 社会保険加入の確認方法
- 申請書類の記載方法(外国法人特有の記載事項)
事前相談の進め方:
- 電話で事前相談の予約を取る
- 相談日時に必要書類案を持参
- 担当者の指摘事項をメモし、不足書類を準備
- 必要に応じて複数回の相談を実施
都道府県による運用の違い
建設業許可の審査基準は建設業法および施行令・施行規則で定められていますが、実務上の運用(証明書類の種類、翻訳方法、認証の要否等)については都道府県により若干の差異があります。そのため、管轄都道府県の窓口での確認が不可欠です。
4. 建設業許可の正式申請
4-1. 申請書類の準備
要件整備と大臣認定取得が完了した後、建設業許可申請を行います。申請書類は多岐にわたりますが、主なものは以下の通りです。
主要な申請書類一覧
会社・営業所関係:
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 役員等の一覧表(様式第11号)
- 営業所一覧表(様式第1号別紙1)
- 専任技術者一覧表(様式第11号の2)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 使用人数(様式第4号)
- 誓約書(様式第6号)
- 定款(写し)
- 登記事項証明書(原本、発行後3ヶ月以内)
- 株主調書または出資者調書
- 営業所の所在地証明書類(登記簿謄本、賃貸借契約書等)
- 営業所の写真(外観・内部、看板等)
財産関係:
- 財務諸表(直前決算期、様式第15号〜第18号)
- 納税証明書(法人税・消費税、原本、発行後3ヶ月以内)
- 資本金または出資金額を証明する書類
- 財産的基礎等を証明する書面(預金残高証明書、融資証明書等、該当する場合)
人的要件関係:
- 常勤役員等証明書(様式第7号)および常勤役員等の略歴書(様式第8号)
- 専任技術者証明書(様式第8号)および専任技術者の実務経験証明書(様式第9号、該当する場合)
- 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2別紙)
- 国家資格の合格証明書または免許証の写し
- 実務経験を証明する工事実績書類(該当する場合)
- 常勤性を証明する書類(健康保険証の写し、住民票等)
- 指導監督的実務経験証明書(特定建設業許可の場合、様式第10号)
- 国土交通大臣認定通知書の写し(該当する場合)
欠格要件・誠実性関係:
- 身分証明書(本籍地の市区町村発行、役員全員分、原本、発行後3ヶ月以内)
- 登記されていないことの証明書(法務局発行、役員全員分、原本、発行後3ヶ月以内)
- 無犯罪証明書(本国発行、該当する場合、原本および翻訳文)
社会保険関係:
- 健康保険・厚生年金保険の保険料納入証明書または領収証書
- 雇用保険の保険料納入証明書または領収証書(該当する場合)
外国法人特有の書類
日本支店の場合:
- 本国法人の登記事項証明書等(原本および日本語翻訳文)
- 本国法人の定款(原本および日本語翻訳文)
- 本国法人の財務諸表(原本および日本語翻訳文、直前3事業年度分)
- 日本における代表者の選任を証する書面
- 支店設置に関する取締役会議事録等(原本および日本語翻訳文)
翻訳文の作成要領:
- 翻訳者の氏名・住所を明記
- 原本との対応関係が明確になるよう、原本のページ番号等を記載
- 専門用語は適切な日本語訳を使用
- 金額は日本円に換算(為替レートと換算日を明記)
4-2. 申請手数料
建設業許可申請には、以下の手数料が必要です(収入証紙または現金納付)。
- 知事許可・一般建設業: 90,000円
- 知事許可・特定建設業: 90,000円
- 知事許可・一般建設業と特定建設業の併願: 180,000円
- 大臣許可・一般建設業: 150,000円
- 大臣許可・特定建設業: 150,000円
- 大臣許可・一般建設業と特定建設業の併願: 300,000円
4-3. 審査期間と許可通知
標準的な審査期間:
- 知事許可: 申請受理から約30日〜60日
- 大臣許可: 申請受理から約90日〜120日
いつでもお声掛けください。
