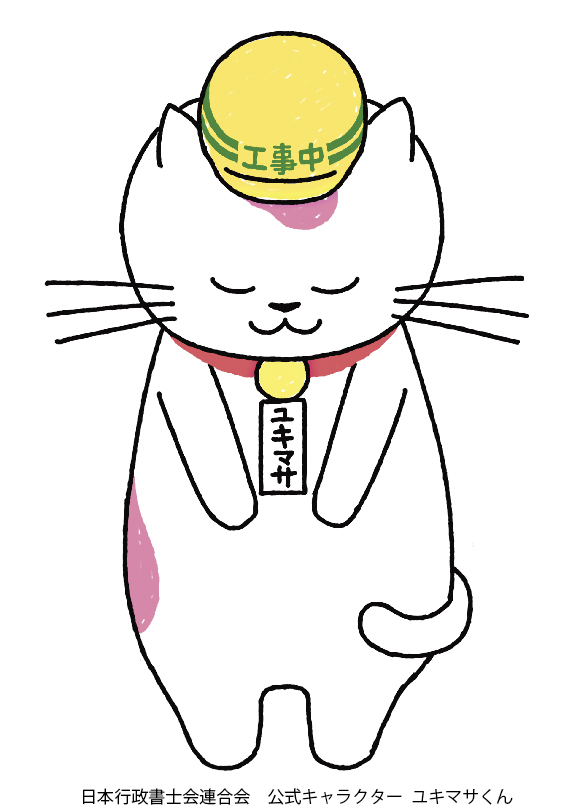
外国法人の建設業許可申請のポイント
日本国内で外国法人が建設業許可を取得することは可能です。建設業法に基づく要件は日本法人と同一で、海外実務の活用時は証拠資料の整備が鍵になります。2025年10月16日施行予定の在留資格「経営・管理」改正により、日本法人設立時の資本金要件が3,000万円以上へ引き上げられる点に留意してください(支店設置への影響は限定的)。当事務所の支援実績に基づき、選択肢・要件・手続の流れを整理します。
日本での拠点形態の選択
建設業の営業活動を行うには、駐在事務所以外の形態が必要です。用途に応じた適切な設計が、許可取得と運用の安定に直結します。
拠点形態の比較
| 拠点形態 | 建設業の営業活動 | 資本金要件 | 法務局登記 | 銀行口座開設 | 代表者の在留資格例 | 従業員雇用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本法人(株式会社等) | 可 | 必要(最低500万円、改正後は3,000万円以上推奨) | 必要 | 可能 | 経営・管理 | 可能 |
| 日本支店(外国会社の支店) | 可 | 不要 | 必要 | 可能 | 企業内転勤 | 可能 |
| 駐在事務所 | 不可(情報収集・連絡業務のみ) | 不要 | 不要 | 不可 | 企業内転勤 | 可能(非営業) |
駐在事務所は営業活動が禁止されるため、建設業許可の取得には「日本法人」または「日本支店」の設置が不可欠です。支店の場合は、本国法人の登記事項証明書等を基に日本で登記し、許可申請にも活用します。
許可取得の主な要件
外国法人でも要件は日本法人と同一です。海外の経歴・実務を用いる際は「大臣認定(個別認定)」前提で、証拠の整合性と実在性が審査の焦点になります。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)
- 配置要件: 建設業の経営業務を統括する常勤役員等の配置が必要。
- 経験要件: 原則5年以上の経営経験。海外経験の活用には国土交通大臣の個別認定が必要。
- 審査資料: 工事契約書、組織図、給与明細、在籍証明等による実態確認。
- 申請時期: 許可申請前に国土交通省(本省)へ認定申請。
営業所の専任技術者
- 配置要件: 各営業所に1名以上(国家資格保有者または原則5年以上の実務経験者)。
- 海外経験: 海外実務の充当には大臣認定が必要。
- 営業所の要件: 実在性が認められる場所(バーチャルオフィス不可)。所在地の実在証明で審査。
財産的基礎
- 一般許可: 自己資本金または資金調達能力の証明(目安500万円以上)。
- 特定許可: より高い財務基盤(目安8,000万円以上)と下請保護能力が求められる。
- 提出資料: 支店は本国法人の財務諸表の翻訳・公証、日本法人は改正後の資本金要件に適合する資本準備。
- 実務対応: 事前に管轄都道府県の相談窓口で確認を推奨。
社会保険加入
- 義務: 従業員を雇用する場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険へ加入。
- 審査: 許可申請時に加入状況の確認。未加入の場合は事前に手続きを完了。
誠実性・欠格要件
- 要件: 過去5年以内の重大な法令違反がないこと、破産手続中でないこと等。
- 外国法人の範囲: 本国での違反歴も審査対象。
海外経験の大臣認定と事前相談
- 認定の必要性: 経営経験・技術者実務を海外実績で満たす場合は国土交通大臣の個別認定が前提。
- 期間目安: 取得まで約3〜6ヶ月。許可申請前に着手が不可欠。
- 証拠の質: 形式的提出は不可。工事実績の公証書類、第三者証明、原本照合可能な証跡を整備。
- 事前相談: 管轄の都道府県土木事務所で要件・資料の適合性を確認。
許可申請の流れと必要書類
- 申請先: 原則は都道府県知事許可(一部は大臣許可)。
- 必要書類: 定款、登記事項証明書、役員経歴書、財務諸表(翻訳付)、認定通知書、営業所実在証明、社会保険加入資料 等。
- 審査期間: 申請受理から許可決定まで約1〜2ヶ月。不備がある場合は補正で延長。
- 実務上の留意: 多言語資料の翻訳適合性、公証・アポスティーユの要否、名称表記の一致、国内担当者の連絡体制を事前に整えると審査が円滑。
相談・支援体制
外国法人の建設業許可は、要件の適合判断と証拠の整合性確保、翻訳・公証の工程管理が成否を分けます。当事務所は、大臣認定から新規許可、更新、業種追加まで一貫支援。漏れのない提出と審査対応で、最短ルートを設計します。
- お問い合わせ先: 行政書士法人塩永事務所
- 電話: 096-385-9002
- メール: info@shionagaoffice.jp
必要事項が固まっていなくても構いません。現在の状況(拠点形態の検討段階、海外実績の有無、資本計画など)を教えていただければ、最適な進め方をご提案します。
