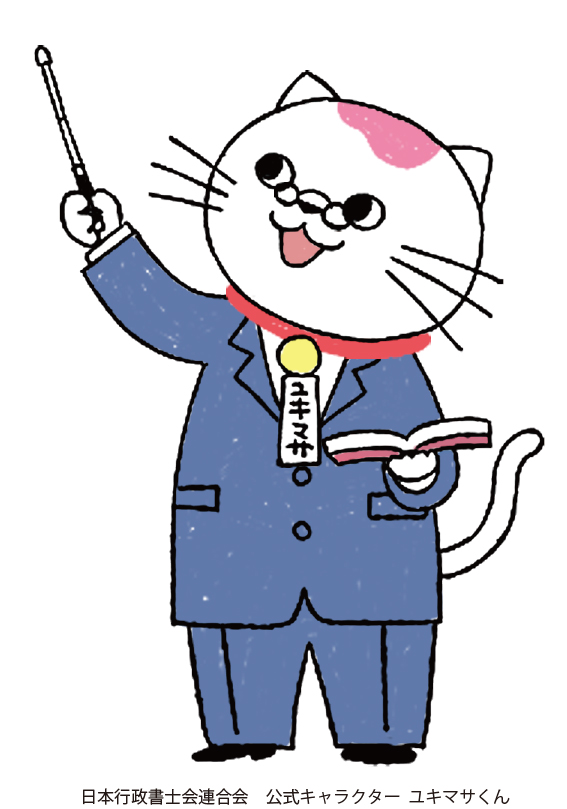
熊本県における建設業事業年度終了届完全ガイド
建設業許可を取得した事業者には、毎年の決算終了後に「事業年度終了届(決算変更届)」を提出する法的義務があります。本ガイドでは、熊本県で建設業を営む事業者様に向けて、事業年度終了届の提出方法、必要書類、注意点について詳しく解説いたします。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県における建設業許可申請および事業年度終了届の作成を専門的にサポートしており、建設業事業者様の事務負担軽減と適正な許可管理を支援しています。
事業年度終了届とは
定義と法的根拠
事業年度終了届(決算変更届)とは、建設業法第11条第2項に基づき、建設業許可業者が毎事業年度(決算期)終了後に提出を義務付けられている届出書類です。
正式名称は「事業年度終了届出書」ですが、実務上は以下のような呼び方もされます:
- 決算変更届
- 決算報告
- 事業年度報告
届出の目的
事業年度終了届は、以下の目的で提出が義務付けられています:
- 財務状況の把握
- 許可行政庁が建設業者の経営状況を把握するため
- 建設業許可の要件である「財産的基礎」の継続確認
- 工事実績の記録
- 年間の工事実績を記録・保管
- 経営事項審査(経審)の基礎資料
- 情報公開
- 建設業者の財務情報・工事実績は閲覧可能
- 発注者が建設業者を選定する際の判断材料
- 許可更新時の確認資料
- 5年ごとの許可更新時に、全ての事業年度終了届の提出を確認
提出義務者
以下の全ての建設業許可業者に提出義務があります:
- ✓ 国土交通大臣許可業者
- ✓ 都道府県知事許可業者(熊本県知事許可を含む)
- ✓ 特定建設業許可業者
- ✓ 一般建設業許可業者
- ✓ 法人・個人事業主の別を問わず全ての許可業者
重要: 工事実績がゼロの年度であっても、提出義務は免除されません。必ず提出する必要があります。
提出期限
法人の場合
決算終了後4ヶ月以内
例:
- 決算日が3月31日の場合 → 提出期限は7月31日
- 決算日が12月31日の場合 → 提出期限は4月30日
- 決算日が9月30日の場合 → 提出期限は1月31日
個人事業主の場合
毎年4月30日
個人事業主の事業年度は、開業時期に関わらず暦年(1月1日〜12月31日)と法令で定められているため、提出期限は一律4月30日となります。
期限の特例
提出期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌開庁日が期限となります。
例: 4月30日が土曜日の場合 → 5月の最初の平日が期限
実務上の注意点と作成期間
実質的な作成期間
事業年度終了届の作成には、決算報告書(税務申告書)が完成していることが前提となります。
実際のスケジュール例(3月決算法人の場合):
- 4月〜5月中旬: 税理士による決算報告書の作成
- 5月中旬〜6月: 税務署への確定申告・納税
- 6月〜7月下旬: 事業年度終了届の作成・提出
したがって、決算報告書の完成から提出期限までの実質的な作成期間は約1.5〜2ヶ月程度となります。
余裕を持った準備が重要
- 決算報告書が完成次第、速やかに作成に着手することをお勧めします
- 期限間際になると許可行政庁の窓口が混雑します
- 書類の不備があった場合の修正時間も考慮が必要です
提出しないとどうなるか
1. 許可更新ができない(最大のリスク)
建設業許可は5年ごとに更新が必要です。更新申請時には、直近5期分(5年分)の事業年度終了届が全て提出されていることが要件となります。
具体例: 令和7年3月に許可更新申請を行う場合、以下の5期分の事業年度終了届の提出が確認されます:
- 令和2年度分
- 令和3年度分
- 令和4年度分
- 令和5年度分
- 令和6年度分
1期でも未提出があれば、更新申請は受理されません。
2. 許可の取消しリスク
建設業法第29条第1項第3号により、事業年度終了届を提出しない場合、許可行政庁から指示処分を受け、従わない場合は許可の取消しとなる可能性があります。
3. 監督処分の対象
提出遅延や未提出は建設業法違反であり、以下の監督処分の対象となります:
- 指示処分
- 営業停止処分
- 許可取消処分
4. 経営事項審査(経審)が受けられない
公共工事の入札に参加するために必要な経営事項審査は、事業年度終了届を提出していることが前提条件です。未提出の場合、経審を受けることができません。
5. 社会的信用の低下
事業年度終了届の内容は閲覧可能であり、未提出は発注者や取引先から「コンプライアンス意識が低い」と判断される可能性があります。
提出先
熊本県知事許可の場合
熊本県 土木部 監理課 建設業班
- 所在地: 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
- 電話: 096-333-2536
提出方法:
- 窓口持参
- 郵送(簡易書留等、配達記録が残る方法を推奨)
国土交通大臣許可の場合
九州地方整備局 建政部 建設産業課
- 所在地: 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二合同庁舎
- 電話: 092-471-6331
提出方法:
- 窓口持参
- 郵送
必要書類一覧
事業年度終了届には、以下の書類が必要です。法人と個人事業主で一部様式が異なります。
共通書類
1. 変更届出書(表紙)
様式第22号の表紙です。以下の情報を記載します:
- 許可番号
- 商号または名称
- 代表者氏名
- 事業年度(自 令和○年○月○日 至 令和○年○月○日)
2. 工事経歴書
様式第2号。許可を受けている建設業の種類ごとに、当該事業年度に施工した主要な工事を記載します。
記載内容:
- 注文者名
- 工事名称
- 工事場所
- 請負金額
- 工期(着工・完成年月日)
- 元請・下請の別
- 配置技術者名(経営事項審査を受ける場合)
記載すべき工事の範囲:
| 区分 | 記載すべき工事 |
|---|---|
| 経営事項審査を受けない場合 | 各業種につき主要な工事10件程度 |
| 経営事項審査を受ける場合 | 各業種につき完成工事高の大きいものから順に記載(原則として全ての工事) |
注意点:
- 未成工事(継続工事)は記載しません
- 当該事業年度内に完成した工事のみ記載
- 自社施工分のみ記載(材料のみ納入した工事は除く)
3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
様式第3号。申請日より直近3年(3事業年度)分の完成工事高を、建設業の種類ごとに記載します。
記載内容:
- 元請完成工事高
- 下請完成工事高
- 兼業事業売上高
業種別の記載:
- 許可を受けている29業種ごとに分類
- 許可を受けていない建設工事は「その他の建設工事」に記載
財務諸表(建設業法様式)
重要: 税理士が作成した決算報告書をそのまま提出することはできません。建設業法で定められた様式に従い、建設業会計(建設簿記)に基づいて作成し直す必要があります。
4. 貸借対照表
様式第15号(法人用)または様式第16号(個人用)
建設業特有の勘定科目:
- 完成工事未収入金
- 未成工事支出金
- 工事未払金
- 未成工事受入金 など
5. 損益計算書
様式第15号(法人用)または様式第16号(個人用)
建設業特有の勘定科目:
- 完成工事高
- 完成工事原価
- 完成工事総利益 など
注意: 一般企業の「売上高」「売上原価」「売上総利益」とは異なる勘定科目を使用します。
6. 完成工事原価報告書(法人のみ)
様式第15号。完成工事原価を以下の科目に分類して記載します:
- 材料費
- 労務費
- 外注費
- 経費
個人事業主は提出不要です。
7. 株主資本等変動計算書(法人のみ)
様式第15号。株主資本(資本金、資本剰余金、利益剰余金)等の当期変動額を記載します。
個人事業主の場合は、様式第17号「注記表」を提出します。
8. 注記表
様式第17号(法人用)または様式第18号(個人用)
財務諸表に関する重要な会計方針や注記事項を記載します:
- 継続事業の前提に関する注記
- 重要な会計方針
- 貸借対照表等に関する注記 など
9. 事業報告書(法人のみ)
会社法で作成が義務付けられている事業報告書を提出します(株式会社の場合)。
個人事業主は提出不要です。
納税証明書
熊本県知事許可の場合
法人:
- 法人事業税の納税証明書(直近1年分)
- 発行機関:熊本県税事務所
個人事業主:
- 個人事業税の納税証明書(直近1年分)
- 発行機関:熊本県税事務所
納税証明書の注意点:
- 「滞納がないことの証明」ではなく「納税額の証明」が必要
- 事業税を納付していない場合(免税事業者等)は、「非課税証明書」または「0円の納税証明書」を取得
国土交通大臣許可の場合
法人:
- 法人税の納税証明書(その1)(直近1年分)
- 発行機関:所轄税務署
個人事業主:
- 申告所得税の納税証明書(その1)(直近1年分)
- 発行機関:所轄税務署
提出部数
- 正本:1部
- 副本:提出先により異なる
- 熊本県知事許可:1部(合計2部)
- 国土交通大臣許可:2部(合計3部)
副本は、確認印が押印されて返却されます。必ず保管してください。
建設業会計(建設簿記)への変換
一般会計と建設業会計の違い
税務申告用の決算報告書は一般会計で作成されますが、事業年度終了届の財務諸表は建設業会計で作成する必要があります。
主な相違点:
| 一般会計 | 建設業会計 |
|---|---|
| 売上高 | 完成工事高 |
| 売上原価 | 完成工事原価 |
| 売上総利益 | 完成工事総利益 |
| 売掛金 | 完成工事未収入金 |
| 買掛金 | 工事未払金 |
| 仕掛品 | 未成工事支出金 |
| 前受金 | 未成工事受入金 |
建設業特有の会計処理
1. 工事完成基準
建設業では原則として「工事完成基準」を採用します。工事が完成し、引き渡しが完了した時点で売上を計上します。
処理のポイント:
- 工事進行中の支出は「未成工事支出金」(資産)に計上
- 工事完成時に「完成工事原価」(費用)に振り替え
- 工事進行中の入金は「未成工事受入金」(負債)に計上
- 工事完成時に「完成工事高」(収益)に振り替え
2. 工事進行基準(一定の工事のみ)
請負金額が大きく、工期が長期にわたる工事については「工事進行基準」を適用できます。
3. 完成工事原価の分類
完成工事原価は以下の4つに分類します:
- 材料費: 工事に使用した材料の費用
- 労務費: 作業員に支払った賃金
- 外注費: 下請業者への外注費
- 経費: その他の経費(機械損料、現場管理費等)
変換作業の実務
決算報告書から建設業会計への変換は専門的な知識が必要です。以下のような作業が発生します:
- 勘定科目の読み替え
- 未成工事支出金・未成工事受入金の確認
- 兼業事業(建設業以外の事業)の売上・原価の区分
- 完成工事原価の材料費・労務費・外注費・経費への分類
- 注記表の作成
この作業を誤ると、財務諸表の整合性が取れず、書類不備で受理されない可能性があります。
よくある間違いと注意点
1. 提出期限の誤解
誤り: 「決算日から4ヶ月以内」 正しい: 「事業年度終了日から4ヶ月以内」
例: 決算日が3月31日の場合、事業年度終了日も3月31日であり、4ヶ月後の7月31日が期限です。
2. 工事経歴書の記載ミス
よくある間違い:
- 未成工事(継続工事)を記載してしまう
- 完成年月日ではなく着工年月日で判断してしまう
- 許可業種と異なる業種で記載してしまう
正しい記載:
- 当該事業年度内に完成した工事のみ記載
- 工事の内容に応じて正しい業種に分類
3. 財務諸表の様式間違い
よくある間違い:
- 税理士作成の決算報告書をそのまま提出
- 法人用の様式を個人事業主が使用(またはその逆)
- 建設業会計に変換せず一般会計のまま提出
4. 納税証明書の種類間違い
よくある間違い:
- 「滞納がないことの証明」を取得してしまう
- 国税と地方税を取り違える
- 有効期限(発行後3ヶ月以内)が切れている
正しい納税証明書:
- 熊本県知事許可:法人事業税(法人)・個人事業税(個人)
- 国土交通大臣許可:法人税その1(法人)・申告所得税その1(個人)
5. 副本の未保管
副本は許可更新時に全て提示する必要があります。紛失すると再度作成・提出が必要となり、更新手続きが遅れる原因となります。
対策: 確認印が押印された副本は必ず保管してください。
6. 工事実績ゼロでも提出が必要
誤解: 「工事をしていないから提出しなくてよい」
正しい: 工事実績がゼロでも提出義務があります。工事経歴書に「該当なし」と記載して提出します。
許可更新時の確認
5年分の副本提示が必要
建設業許可の有効期間は5年間です。更新申請時には、直近5期分の事業年度終了届の副本全てを提示する必要があります。
具体例(令和7年3月更新の場合): 以下の5期分の副本を提示:
- 令和2年度分(令和2年4月〜令和3年3月)
- 令和3年度分(令和3年4月〜令和4年3月)
- 令和4年度分(令和4年4月〜令和5年3月)
- 令和5年度分(令和5年4月〜令和6年3月)
- 令和6年度分(令和6年4月〜令和7年3月)
未提出があった場合
1期でも未提出がある場合:
- 更新申請は受理されません
- 速やかに未提出分を提出する必要があります
- 提出遅延として指導を受ける可能性があります
許可期間内に提出できない場合:
- 許可が失効します
- 失効後に建設工事を請け負うと無許可営業となり、罰則の対象となります
余裕を持った準備が重要
許可更新は許可有効期限の3ヶ月前から受付開始されます。更新申請前に、5期分の事業年度終了届が全て提出済みであることを確認してください。
経営事項審査(経審)を受ける場合の注意点
経審との関係
経営事項審査(経審)は、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受ける必要がある審査です。
経審を受けるための前提条件:
- 審査を受けようとする事業年度の事業年度終了届が提出済みであること
工事経歴書の記載範囲
経審を受けない場合と受ける場合で、工事経歴書の記載範囲が異なります。
| 区分 | 記載範囲 |
|---|---|
| 経審を受けない | 主要な工事10件程度 |
| 経審を受ける | 原則として全ての完成工事(完成工事高の大きい順) |
経審を受ける予定がある場合は、工事経歴書に全ての工事を記載する必要があります。
配置技術者の記載
経審を受ける場合、工事経歴書に配置技術者名を記載する必要があります(経審を受けない場合は不要)。
提出の流れ(ステップバイステップ)
ステップ1: 決算報告書の完成を待つ
税理士による決算報告書(税務申告書)の作成完了を待ちます。
ステップ2: 必要書類の収集
- 決算報告書のコピーを入手
- 納税証明書を取得(県税事務所または税務署)
- 工事台帳等から工事実績を整理
ステップ3: 財務諸表の作成
決算報告書をもとに、建設業会計に基づいた財務諸表を作成します。
作成する書類:
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 完成工事原価報告書(法人のみ)
- 株主資本等変動計算書(法人のみ)
- 注記表
ステップ4: 工事経歴書の作成
工事台帳等をもとに、業種ごとに工事経歴書を作成します。
ステップ5: 直前3年の工事施工金額の作成
直近3事業年度分の完成工事高を集計し、様式に記入します。
ステップ6: 変更届出書(表紙)の作成
必要事項を記入し、代表者印を押印します。
ステップ7: 書類の確認とセット
全ての書類が揃っているか、記載内容に誤りがないかを確認し、所定の順序でセットします。
ステップ8: 提出
熊本県土木部監理課または九州地方整備局に提出します(窓口持参または郵送)。
ステップ9: 副本の保管
確認印が押印された副本を受け取り、大切に保管します。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、熊本県における建設業許可関連の手続きを専門的にサポートしています。
事業年度終了届作成サポートサービス
1. 決算報告書の分析
税理士が作成した決算報告書を分析し、建設業会計への変換作業を行います。
2. 建設業会計に基づく財務諸表の作成
- 貸借対照表の作成
- 損益計算書の作成
- 完成工事原価報告書の作成(法人)
- 株主資本等変動計算書の作成(法人)
- 注記表の作成
建設業法で定められた様式に従い、正確な財務諸表を作成します。
3. 工事経歴書の作成
お客様から提供いただいた工事台帳等をもとに、業種ごとに工事経歴書を作成します。
4. 直前3年の工事施工金額の作成
過去3期分の完成工事高を集計し、業種ごとに分類して記載します。
5. 必要書類の取得代行
納税証明書等、必要に応じて取得代行を行います(別途実費)。
6. 提出代行
作成した書類一式を、熊本県または九州地方整備局に提出代行いたします。
7. 副本の管理サポート
提出した副本のコピーを保管し、許可更新時にスムーズに対応できるようサポートします。
サポートのメリット
1. 正確な書類作成 建設業会計の専門知識を持つ行政書士が作成するため、書類の不備や記載ミスがありません。
2. 時間の節約 複雑な財務諸表の作成作業から解放され、本業に専念できます。
3. 期限管理 提出期限を管理し、余裕を持った提出をサポートします。
4. 許可更新の安心 毎年確実に提出することで、5年後の許可更新をスムーズに迎えられます。
5. 経審対応 経営事項審査を受ける予定がある場合も、適切な形式で作成いたします。
税理士との連携
当事務所では、お客様の顧問税理士と連携しながら業務を進めることも可能です。税理士が作成した決算報告書をもとに、建設業法に適合した財務諸表を作成いたします。
建設業許可の総合サポート
事業年度終了届の作成だけでなく、以下のサポートも提供しています:
- 建設業許可新規申請
- 建設業許可更新申請
- 業種追加申請
- 各種変更届
- 経営事項審査申請サポート
- 入札参加資格申請サポート
熊本の建設業者様へのメッセージ
建設業許可を維持し、事業を継続的に発展させるためには、毎年の事業年度終了届の確実な提出が不可欠です。
当事務所の強み
1. 熊本の建設業に特化 熊本県の建設業許可申請に力を入れており、熊本県土木部監理課との手続きに精通しています。
2. 豊富な実績 多数の建設業者様の事業年度終了届作成をサポートしてきた実績があります。
3. 迅速・丁寧な対応 お客様の疑問や不安に、迅速かつ丁寧にお答えします。
4. 継続的なサポート 単年度のみならず、長期的なパートナーとして建設業者様の成長をサポートします。
ともに成長するパートナーとして
行政書士法人塩永事務所は、熊本の建設業者様とともに成長していくことを目指しています。許認可手続きのサポートを通じて、建設業者様が本業に専念し、事業を発展させられる環境づくりに貢献いたします。
