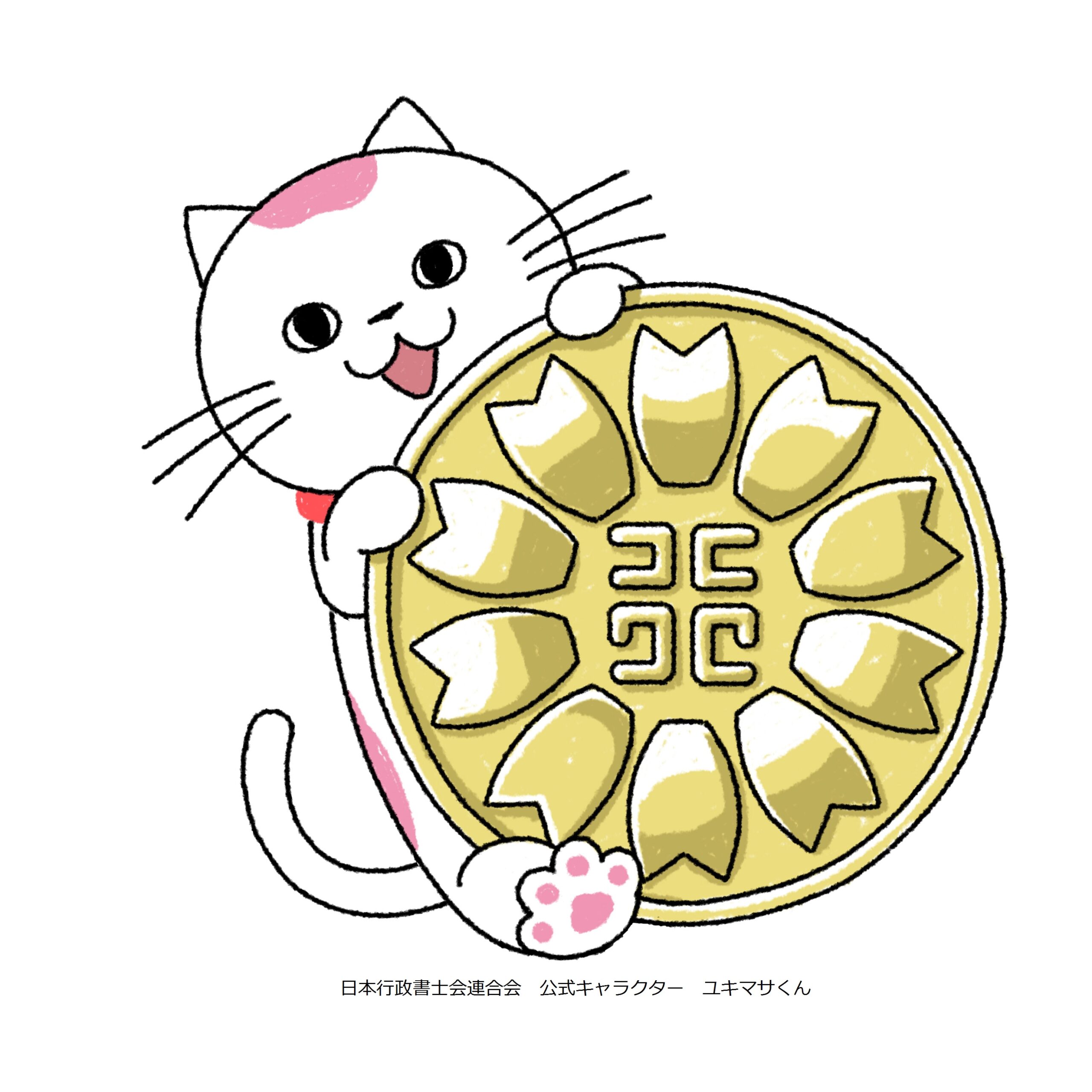
事業協同組合の設立手続きを徹底サポート!行政書士法人塩永事務所が詳しく解説
執筆:行政書士法人塩永事務所 代表行政書士 塩永
行政書士法人塩永事務所の塩永です。当事務所は、中小企業や小規模事業者の皆様が抱える法人設立や許認可申請の課題を、迅速かつ丁寧にサポートすることを使命としています。特に、事業協同組合の設立支援では、組合員の皆様がスムーズに事業をスタートできるようにお手伝いしてまいりました。近年、中小企業者が互いの強みを活かした共同事業を進める動きが活発化しています。そんな中、事業協同組合は、共同宣伝や共同販売を通じて取引条件の改善を図る有効な手段として注目されています。本記事では、事業協同組合の設立手続きを、初心者の方にもわかりやすく、ステップバイステップで詳細に解説します。設立を検討されている事業者の皆様、ぜひ参考にしてください。当事務所では、設立から登記、運営相談までワンストップで対応可能です。事業協同組合とは?基本を押さえよう事業協同組合は、中小企業等協同組合法(以下、中協法)に基づいて設立される法人です。組合員である中小企業者(個人事業主を含む)が、相互扶助の精神のもとで協同して事業を行い、経営の合理化や取引条件の改善を目指す組織です。主な特徴は以下の通りです。事業協同組合の主な特徴
|
項目
|
内容
|
|---|---|
|
根拠法
|
中小企業等協同組合法(中協法)
|
|
組合員
|
地区内の小規模事業者(中小企業者)。建設業、商業、工業、サービス業など業種を問わず、異業種組合も可能。
|
|
目的
|
共同経済事業(共同宣伝、共同販売、共同購買、共同受注など)を通じて、組合員の利益を向上させる。
|
|
非営利性
|
非営利団体ですが、事業から生じる剰余金は組合員に分配可能。
|
|
税制優遇
|
法人税の軽減措置(中小企業者等に該当する場合)や、消費税の免税事業者扱い(条件あり)。
|
事業協同組合は、単なる業務提携を超えた「法人格」を持つため、銀行融資の受皿や補助金申請の主体としても活用できます。たとえば、建設業者の場合、資材の共同購買でコストを削減したり、異業種の事業者同士で共同プロモーションを実施したりする事例が多数あります。設立のメリットは、個別事業では難しい規模の経済を実現できる点です。ただし、設立には行政庁の認可が必要で、手続きが煩雑になりがち。そこで、当事務所のような専門家に相談することを強くおすすめします。設立要件:誰が設立できるのか?事業協同組合を設立するには、以下の要件を満たす必要があります。中協法第8条~第10条に基づき、厳格に審査されます。1. 組合員の要件
- 最低人数: 発起人(設立の中心となる者)は4人以上。組合員は中小企業者(資本金3億円以下または常時使用人300人以下)でなければなりません。
- 地区内限定: 組合の事業区域(例: 都道府県内)内に本店を有する事業者。
- 業種の適合: 組合の定款で定めた事業を行う者。建設業者のみで構成する「同業組合」や、複数の業種を混在させた「異業種組合」が可能です。
2. 事業内容の要件
- 共同経済事業の必須: 少なくとも1つの共同経済事業(例: 共同販売、共同購買)を実施する計画が必要です。これにより、組合の事業収入が見込まれ、剰余金の発生が想定されます。
- 公益性: 組合員の経済的利益だけでなく、地域経済の活性化に寄与する内容であること。
3. 資本金の要件
- 最低額の目安: 業種により異なりますが、製造業で300万円、商業で100万円、サービス業で50万円以上が一般的(中協法施行規則に基づく)。ただし、厳格な最低額は定められていませんが、事業計画の現実性から審査されます。
これらの要件を満たさない場合、認可が下りない可能性が高いため、事前の相談が重要です。当事務所では、発起人様の事業内容をヒアリングし、要件適合性を無料でチェックいたします。設立手続きの流れ:ステップバイステップで解説事業協同組合の設立は、発起人による準備から行政庁の認可、登記まで約3~6ヶ月を要します。以下に、詳細な手順をまとめました。所要期間の目安も記載しています。ステップ1: 発起人の募集と準備(1~2ヶ月)
- 発起人の選定: 4人以上の事業主(個人または法人代表者)が発起人となります。共通の事業目的(例: 共同販売の推進)を共有していることが重要。
- 事業計画の策定: 組合の目的、事業内容、収支計画、組合員募集計画を作成。共同経済事業の具体例(例: 共同購買で年間売上1,000万円の見込み)を明記。
- 定款の作成: 組合の名称、本店所在地、目的、組合員資格、役員構成などを規定。行政書士がドラフトを作成し、発起人総会で承認。
注意点: この段階で、中小企業庁のガイドラインを参考に計画を練る。失敗例として、共同事業の具体性が不足すると認可否認の原因となります。ステップ2: 設立総会の開催(1週間)
- 議事録の作成: 発起人総会で定款を承認し、役員(組合長、副組合長、監事)を選任。最低5名の役員が必要です。
- 出資金の払込: 発起人が出資金を組合の仮口座に振り込み。証明書を作成。
ステップ3: 認可申請の提出(1~2ヶ月)
- 申請先: 組合員の事業を所管する行政庁(例: 商業・サービス業なら都道府県知事、建設業なら国土交通大臣経由の地方整備局)。異業種の場合、主たる事業に基づく庁へ。
- 必要書類:
- 認可申請書(様式あり)。
- 定款(2通)。
- 設立総会议事録。
- 役員就任承諾書および住民票・登記事項証明書。
- 出資金払込証明書。
- 事業計画書・収支予算書。
- 発起人・役員の誓約書(欠格事由なしの宣誓)。
- 審査内容: 法令適合性、事業の公益性、組合員の適格性。追加資料の提出を求められる場合あり。
Tips: 申請書類の作成は専門知識を要します。ステップ4: 認可の取得と登記(1ヶ月)
- 認可通知: 行政庁から認可後、遅滞なく法務局へ登記申請。
- 登記手続き:
- 登記申請書、定款、認可証明書を提出。
- 登録免許税
- 組合の成立: 登記完了で法人格取得。登記事項証明書を取得。
ステップ5: 設立後の届出(2週間以内)
- 税務署・社会保険事務所への届出: 法人設立届、青色申告承認申請。
- 組合員総会の開催: 正式な運営開始。
|
ステップ
|
所要期間
|
主な担当者
|
|---|---|---|
|
1. 準備
|
1~2ヶ月
|
発起人・行政書士
|
|
2. 総会
|
1週間
|
発起人
|
|
3. 申請
|
1~2ヶ月
|
行政書士
|
|
4. 登記
|
1ヶ月
|
司法書士連携
|
|
5. 届出
|
2週間
|
行政書士
|
よくあるQ&A:設立時の疑問を解決Q1: 個人事業主だけでも設立可能ですか?
A: はい。発起人の4人以上が個人事業主で構いません。ただし、事業の継続性が審査されます。Q3: 認可が下りなかった場合の対処法は?
A: 事業計画の修正が主。事前相談で回避可能。当事務所ではシミュレーションを実施。行政書士法人塩永事務所のサポートで安心設立事業協同組合の設立は、書類作成の正確さと計画の説得力が鍵です。組合員の皆様が早期に共同事業をスタートできるよう、全力でサポートします。お問い合わせ先:
- TEL: 096-385-9002
- Email: info@shionagaoffice.jp
今すぐ一歩を踏み出して、事業の新たな可能性を広げましょう!ご質問があれば、いつでもお待ちしています。
