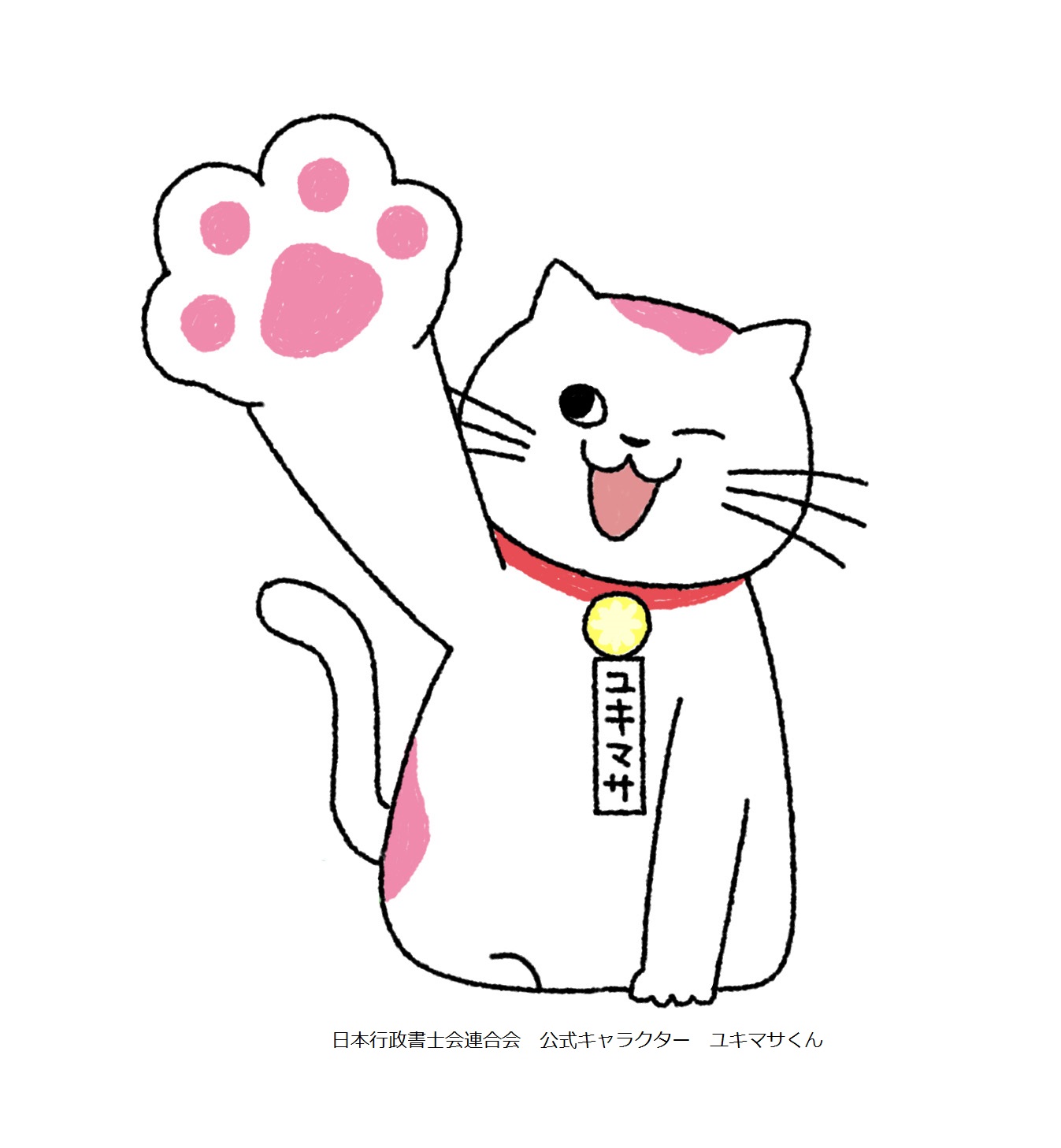
医療法人とは
医療法人は、医療法に基づいて設立される法人であり、病院・常時医師(または歯科医師)が勤務する診療所、あるいは介護老人保健施設の開設を目的として設立されます(医療法第39条)。設立後は、診療報酬の受領や施設運営を個人ではなく法人が行う形になります。
医療法人の種類(概要)
-
社団医療法人(社団法人型)
複数の「社員」(=人)が集まって設立する形式で、基本的な運営ルールは定款で定めます。かつては「持分あり」の社団医療法人もありましたが、新規設立は原則「持分なし」が標準です -
財団医療法人(財団法人型)
個人または法人が財産を寄附して設立する形式で、基本事項は寄附行為(寄付行為)で定めます。 -
一人医師医療法人(小規模医療法人)
「常勤する医師または歯科医が1人または2人」の診療所を設置する医療法人を指します。小規模な診療所でも医療法人化が可能になっており、実務上多く採用されています。
病院(診療所)を法人化するメリット
-
税務上のメリット(節税効果)
一定規模以上の所得がある場合、個人の累進課税に比べて法人税の適用により税負担が軽くなるケースがあります。また、給与化による給与所得控除、理事への退職金計上、欠損金(赤字)の繰越期間(法人の方が長期化可能)といった税務上の利点が得られることがあります。 -
事業承継・継続のしやすさ
個人開業の場合、院長が廃業すると後継は改めて開設手続きを行う必要がありますが、医療法人化すれば理事長の交代手続きのみで運営を継続でき、事業承継が円滑になります。 -
分院・多角化が可能
個人では制約のある分院展開や介護施設、研修機関等の併設が行いやすく、事業拡大・多角化に向いています。 -
対外信用の向上
法人としての会計・運営体制が整うことで金融機関からの信用が高まり、融資や人材採用で有利になることがあります。
デメリット(留意点)
-
手続き・事務作業の増加
都道府県への事業報告や会計・監査、登記手続きなど提出書類が増え、総務負担やコストが上がります -
社会保険(厚生年金等)への加入義務
法人格になると、従業員の人数にかかわらず社会保険(健康保険・厚生年金)の適用や法定福利費の負担が発生します(福利厚生コストが上がる点に注意)。 -
簡単に解散できない点
法人を安易に解散することはできず、地域医療の担い手として継続性を求められます。理事長交代・後継者問題やM&Aなどの選択肢を検討する必要があります。 -
解散時の残余財産の帰属
近年の法改正により、新規の(持分なし)医療法人は解散時の残余財産が出資者に分配されず、定款や寄附行為で特段の規定がない場合は国や地方公共団体等に帰属する仕組みになっています。解散時の資産処理については事前の方針設計が重要です。
医療法人設立の主な手続き(概略・準備期間)
医療法人の設立は書類が多く、準備から認可・登記までは概ね半年〜1年程度を見込むのが一般的です(状況によりさらに要する場合があります)。事前相談・仮申請・事前協議を丁寧に進めることがポイントです。
主な流れ(要点)
-
説明会・事前準備
都道府県や市町村が開催する設立説明会に参加し、必要書類(定款、事業計画・予算書、役員名簿等)を準備します。各自治体の様式や添付資料を事前に確認してください。 -
設立総会の開催
社員(設立参加者)による総会で定款等を承認し、理事・監事等の体制を確定します。 -
仮申請(事前審査)
仮申請を行い、本申請に必要な書類の確認・指摘を受けます。仮申請がなければ本申請に進めない自治体が多い点に注意 -
事前協議(修正・追加)
提出書類に対する審査・面接が行われ、必要に応じて補正や追加資料の提出を求められます。 -
本申請・認可(医療審議会等)
本申請後、医療審議会等で審議され、認可が下りれば設立許可書が交付されます。許可後、登記手続き(法務局)を行います。
熊本市での実務メモ(様式・窓口)
熊本市では医療法人設立に関する各種様式(設立認可申請書・定款様式・決算届等)を公表しており、提出前に熊本市保健所医療対策課へ相談することが案内されています。提出様式は市の窓口ページで確認・ダウンロードできます。
最後に(ご相談のすすめ)
医療法人設立は法令理解・定款設計・税務・会計・労務管理・登記手続きなど多分野にまたがるため、準備や運営方針を含めた総合的な支援が重要です。熊本での医療法人設立・申請手続きは、行政書士による書類作成・申請代理と税理士による税務シミュレーションを組み合わせて進めることをおすすめします。
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
