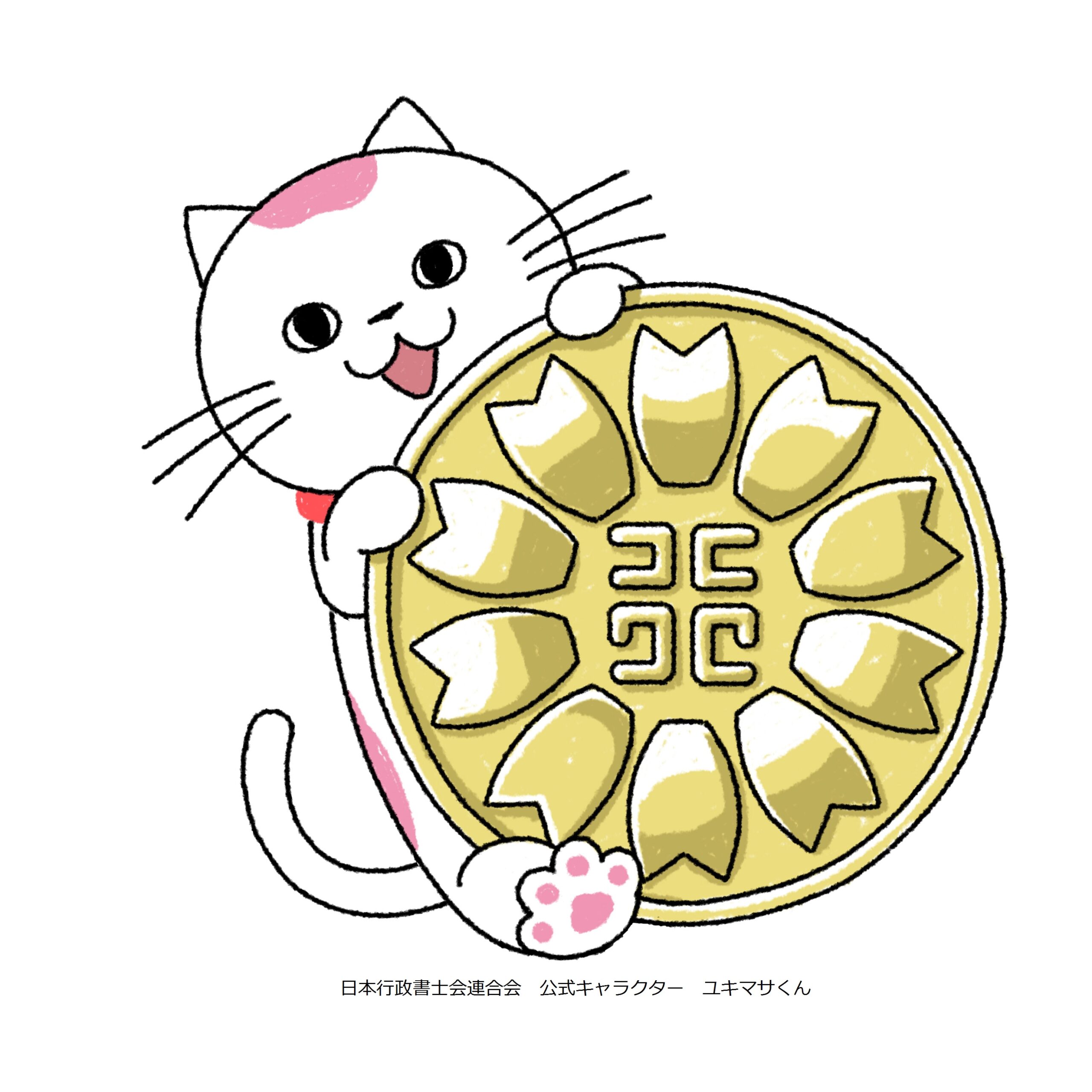
民泊事業の始め方:法律・手続き・注意点
民泊事業を始めるには、住宅宿泊事業法に基づく届け出が必要です。これは、既存の住宅を活用して旅行者などを宿泊させる事業で、通称「民泊」と呼ばれています。
住宅宿泊事業法とは
この法律では、民泊事業を行う人を住宅宿泊事業者と呼び、事業を始める際には物件のある自治体へ届け出ることが義務付けられています。
また、事業者は以下のいずれかに該当する必要があります。
- 住宅宿泊事業者: 宿泊サービスを提供する事業主
- 住宅宿泊管理業者: 民泊物件の管理を請け負う業者
- 住宅宿泊仲介業者: 宿泊予約サイトなどの仲介サービスを提供する業者
届け出の方法と必要書類
届け出は、民泊ポータルサイトを通じて行います。必要書類を添付して、物件の所在地を管轄する自治体に提出します。オンラインでの電子申請も可能ですが、行政書士に手続きを依頼する場合は、印刷した届け出書を提出します。
必要書類は、事業者が法人か個人か、また建物の所有形態や使用状況によって異なります。法人の場合に通常必要となる主な書類は以下の通りです。
- 届け出書(民泊制度運営システムで作成)
- 定款または寄付行為(原本確認が必要)
- 登記事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 役員全員の身分証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 住宅の登記事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 設備の設置状況がわかる図面
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
- 消防法令適合通知書(管轄の消防署で取得)
その他、大家の承諾書や、周辺住民への配慮を示すための書類など、ケースに応じて追加の書類が必要になる場合があります。
民泊事業を始める上での注意点
民泊事業を始める際には、いくつかの重要なポイントがあります。
1. 登記上の「建物の種類」を確認する
届け出を予定している建物の登記事項証明書に記載されている種類が「居宅」であることが原則です。これは、あくまでも住宅として利用するための制度であるためです。たとえ実際に居住していても、登記上の種類が「事務所」などになっている場合、届け出が受理されないことがあります。この場合、登記の変更手続きが必要となります。
2. 自治体の条例を確認する
一部の自治体では、独自の条例によって民泊を全面禁止していたり、営業日数に制限を設けていたりする場合があります。例えば、年間180日以内という営業日数の上限がさらに短縮されているケースもあるため、事前に必ず確認が必要です。
3. 事業系ごみの処理
宿泊料を得ている以上、排出されるごみは事業系ごみとして適切に処理しなければなりません。自治体のルールに従い、分別や回収方法を確認しましょう。
4. 消防法・建築基準法などの関連法令
住宅宿泊事業法だけでなく、消防法や建築基準法、自治体の条例などを遵守する必要があります。特に、非常用照明設備の設置は注意が必要です。
- 非常用照明設備とは、停電時に点灯し、避難経路を照らすための設備です。
- 家主が居住し、かつ宿泊室の延べ床面積が50㎡未満の場合、または特定の条件を満たす場合は設置が免除されることがあります。
- それ以外の場合は、設置が義務付けられることが多く、専門的な電気工事が必要です。資格を持った電気設備工事士に依頼しましょう。
5. 周辺住民への配慮
営業開始後に周辺住民とのトラブルを避けるため、事前に事業について周知しておくことが大切です。自治体によっては、住民説明会の開催が義務付けられている場合もあります。地域に理解を得て、良好な関係を築くよう心がけましょう。
6. 多言語対応
外国人観光客の利用を想定している場合は、施設内の案内や避難経路図などを多言語で用意することが望ましいです。特に、緊急時の通報番号(警察、消防など)は、最低限英語でも記載しておくと安心です。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。 熊本の民泊事業に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所まで。 電話:096-385-9002
