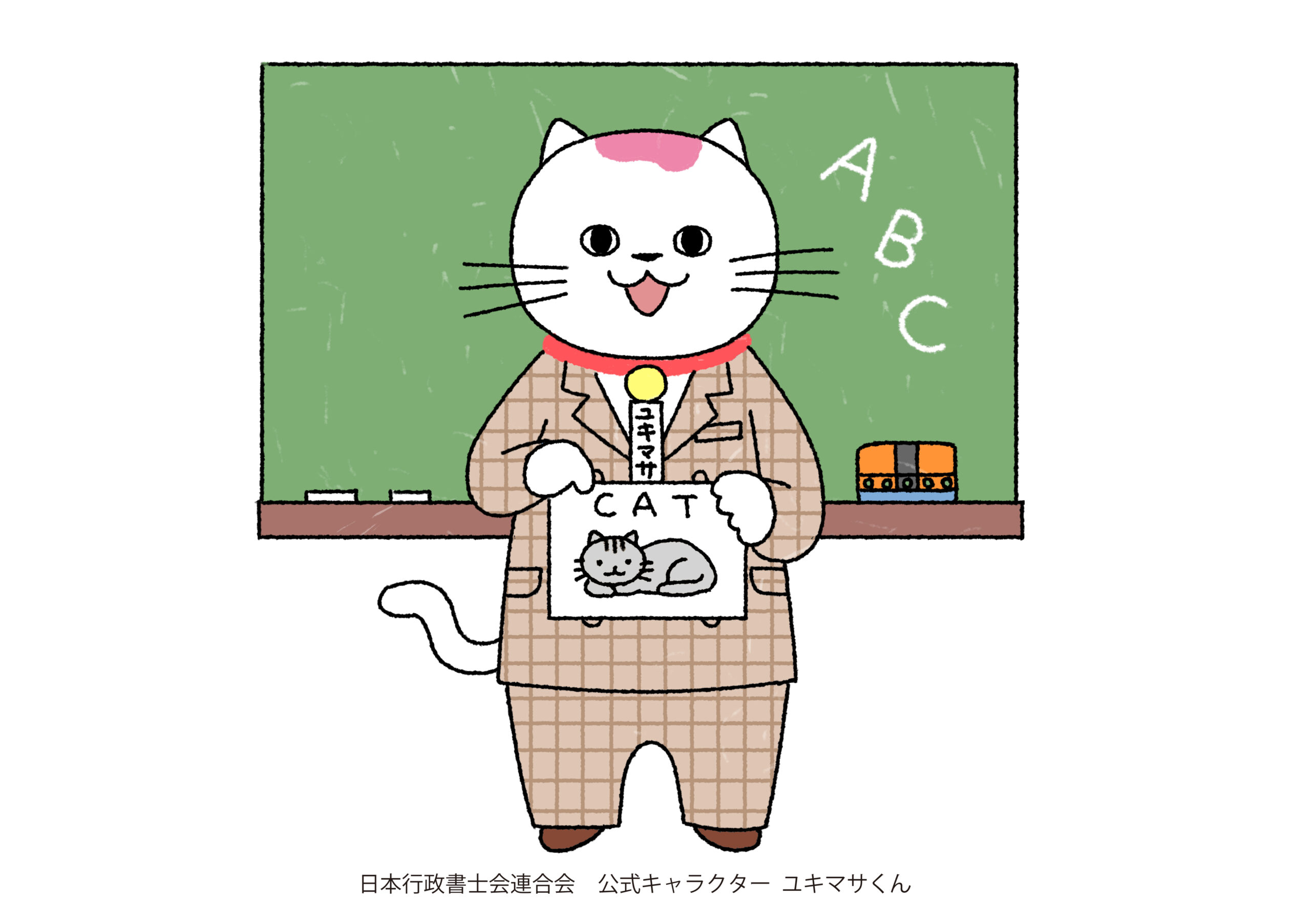
🛠️【2025年最新版】技能実習生から特定技能への移行完全ガイド:育成就労制度移行期対応版
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)
外国人在留資格・ビザ申請の専門事務所
はじめに:制度変革期における重要な選択肢
こんにちは。熊本市中央区水前寺にある行政書士法人塩永事務所です。
当事務所では、外国人の在留資格(ビザ)に関する申請支援を豊富な実績で手がけており、特に近年では「技能実習生から特定技能への在留資格変更」に関するご相談が急激に増加しています。
重要な制度変更について: 技能実習制度は2027年までに「育成就労制度」に移行することが決定しており、2030年までは両制度が併存することとなります。この制度変革期において、技能実習生にとって特定技能への移行は極めて重要な選択肢となっています。
本記事では、2025年9月時点の最新制度・法改正を踏まえ、技能実習から特定技能への移行に必要な法的要件、詳細な申請手続き、必要書類、企業側の受入体制整備まで、行政書士の専門的視点から包括的に解説いたします。
1️⃣ 特定技能制度の全体像と2025年の制度改正ポイント
制度の目的と位置づけ
特定技能制度は、2019年4月に創設された在留資格で、日本国内の深刻な人手不足を背景として、即戦力となる外国人材の受入れを目的としています。技能実習制度が「国際貢献・技能移転」を建前としているのに対し、特定技能制度は明確に「労働力確保」を目的としている点が大きな違いです。
対象分野の詳細(2025年9月現在)
特定技能制度の対象となる12分野は以下の通りです:
| 分野名 | 受入見込数(5年間) | 主な業務内容 |
|---|---|---|
| 介護 | 60,000人 | 身体介護、生活援助、機能訓練の補助等 |
| ビルクリーニング | 37,000人 | 建築物内部の清掃業務 |
| 素形材産業 | 21,500人 | 鋳造、鍛造、機械加工等 |
| 産業機械製造業 | 5,250人 | 産業用機械器具の製造・メンテナンス |
| 電気・電子情報関連産業 | 4,700人 | 電子機器・部品の製造・組立て |
| 建設 | 40,000人 | 型枠施工、左官、とび、建設機械施工等 |
| 造船・舶用工業 | 13,000人 | 溶接、塗装、機械加工、電気機器組立て等 |
| 自動車整備 | 7,000人 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備等 |
| 航空 | 2,200人 | 空港グランドハンドリング、航空機整備等 |
| 宿泊 | 22,000人 | フロント、企画・広報、接客、レストラン等 |
| 農業 | 36,500人 | 耕種農業全般、畜産農業全般 |
| 飲食料品製造業 | 34,000人 | 飲食料品製造業全般 |
| 外食業 | 53,000人 | 外食業全般(接客サービス、調理補助等) |
特定技能1号・2号の詳細比較
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 1年、6か月又は4か月毎の更新(通算5年まで) | 3年、1年又は6か月毎の更新(実質無制限) |
| 技能レベル | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能(1号を上回る技能) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子の帯同可能 |
| 対象分野 | 12分野すべて | 建設・造船・舶用工業の2分野のみ(段階的拡大予定) |
| 支援計画 | 受入機関による支援が必要 | 支援不要 |
| 転職 | 同一分野内での転職可能 | 同一分野内での転職可能 |
2025年制度改正の主要ポイント
2025年4月より、特定技能制度において出入国管理及び難民認定法施行規則の改正が施行され、以下の変更が行われています:
- 定期届出・随時届出の様式変更
- 在留資格申請書類の一部簡素化
- 受入機関の届出事項の見直し
2️⃣ 技能実習から特定技能への移行:制度的背景と法的意義
制度移行の社会的背景
技能実習制度は1993年の創設以来、「技能移転による国際貢献」を名目としてきましたが、実態として労働力確保の側面が強く、以下のような構造的問題が指摘されてきました:
- 人権侵害的な労働環境(長時間労働、低賃金、パスポート取上げ等)
- 転職禁止による労働者の固定化
- 失踪問題の頻発(年間約9,000人が失踪)
- 監理団体による中間搾取
これに対し、特定技能制度は「労働者としての権利保護」を明確に位置づけ、より透明で適正な外国人労働者受入れを目指しています。
技能実習生にとっての移行メリット
1. 労働環境の大幅改善
- 適正な賃金水準:日本人同等以上の報酬確保が法的義務
- 労働時間の適正化:労働基準法の厳格な適用
- 職場選択の自由:同一分野内での転職が可能
2. キャリア形成の継続性
- 技能向上の機会:日本で培った技能を活かした継続就労
- 長期就労の可能性:最大5年間の安定就労(1号)、さらに2号への移行も可能
- 家族帯同の将来性:2号移行により配偶者・子の帯同が実現
3. 社会保障制度の完全適用
- 厚生年金・健康保険の完全適用
- 労災保険・雇用保険による労働者保護
- 退職金制度等の企業福利厚生の享受
受入企業側のメリット
1. 即戦力人材の確保
- 実務経験豊富な人材:技能実習で培った技能・日本語能力
- 業務適応の早さ:日本の職場環境・企業文化への理解
- コミュニケーション能力:基本的な日本語能力の確保
2. 安定的な人材確保
- 離職率の大幅低下:転職可能性による満足度向上
- 長期雇用による投資回収:教育訓練投資の回収期間確保
- 企業ブランド向上:適正な外国人雇用による社会的評価向上
3. 管理コストの削減
- 監理団体費用の不要:直接雇用による中間費用削減
- 手続きの簡素化:技能試験・日本語試験の免除措置
3️⃣ 移行要件の詳細解析:法的要件と実務上の注意点
技能実習生が特定技能に移行するためには、以下の2つの必須要件を満たす必要があります。
要件① 技能実習2号の「良好な修了」
「良好な修了」の法的定義
出入国在留管理局の運用要領によれば、「良好な修了」とは以下の要件をすべて満たすことを意味します:
- 技能実習計画の適正な実施
- 技能実習計画に定められた期間(原則2年間以上)の完全履行
- 技能実習日誌の適正な記録・保管
- 監理団体による定期監査での指摘事項の改善
- 技能検定等の合格
- 技能検定基礎2級または**技能実習評価試験(専門級)**の合格
- 学科試験・実技試験の両方に合格していることが必要
- 合格証明書の有効性確認
- 素行の良好性
- 刑事処分歴:禁錮以上の刑に処せられていないこと
- 行政処分歴:入管法違反による処分歴がないこと
- 失踪歴:技能実習期間中の失踪・不法滞在がないこと
- 出入国管理上の問題がないこと
- 在留期間の更新が適正に行われていること
- 届出義務の履行(住居地届出、所属機関等に関する届出等)
- 資格外活動許可の適正取得・範囲遵守
実務上よくある「良好でない修了」のケース
❌ 移行不可となる主なケース:
- 技能実習期間中の1か月以上の無断欠勤
- 技能検定等の不合格(再受検機会があっても最終的に不合格)
- 労働基準法違反への関与(不正な残業代請求等)
- 住居地届出義務の重大な怠慢
- 在留カードの紛失・不携帯による摘発歴
要件② 従事業務の「同一性・関連性」
同一分野での移行(原則)
技能実習と特定技能で同一分野での移行が原則です。対応関係は以下の通り:
| 技能実習職種・作業 | 特定技能分野 | 従事可能業務 |
|---|---|---|
| 介護 | 介護 | 身体介護、生活援助、機能訓練補助等 |
| 建設関係職種(22職種33作業) | 建設 | 型枠施工、左官、とび、建設機械施工、土木等 |
| 農業関係(耕種農業、畜産農業) | 農業 | 耕種農業全般、畜産農業全般 |
| 食品製造関係 | 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般 |
| 繊維・衣服関係 | 繊維・衣服 | 繊維製品製造、縫製等 |
関連分野での移行(例外的措置)
一定の条件下で、関連分野への移行が認められる場合があります:
- 農業 → 飲食料品製造業:農産物加工に限定
- 漁業 → 飲食料品製造業:水産加工に限定
- 建設関係 → 造船・舶用工業:溶接・塗装作業に限定
移行不可の組み合わせ例
以下のような分野間の移行は原則として認められません:
- 介護 → 宿泊業
- 農業 → 外食業
- 建設 → ビルクリーニング
試験免除措置の詳細
技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能1号への移行時に以下の試験が免除されます:
免除される試験
- 技能測定試験(各分野で実施される技能試験)
- 日本語能力試験(原則として日本語基礎テストまたはJLPT N4以上)
免除されない場合の例外
- 介護分野:介護日本語評価試験は受験必要(安全上の理由)
- 航空分野:英語能力証明が別途必要
- 宿泊分野:接客に関する追加的な日本語能力確認あり
4️⃣ 在留資格変更手続きの詳細フロー(2025年対応版)
手続き全体の流れと標準的なタイムライン
技能実習から特定技能への移行手続きは、以下の8つのステップで構成されます:
Phase 1:事前準備・確認段階(1-2か月)
Step 1:移行可能性の診断・確認
- 技能実習修了状況の詳細確認
- 従事予定業務との適合性判定
- 受入企業の体制確認
Step 2:雇用契約の締結準備
- 労働条件の詳細協議
- 賃金水準の市場調査・設定
- 雇用契約書(日本語・母国語併記)の作成
Phase 2:受入体制整備段階(1-2か月)
Step 3:支援計画の策定
- 生活支援:住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習支援
- 職場支援:安全衛生教育、職業訓練、相談対応体制
- 社会統合支援:地域生活支援、文化理解促進
Step 4:登録支援機関との契約(委託する場合)
- 支援機関の選定・評価
- 支援委託契約書の締結
- 支援計画の共同策定
Phase 3:申請準備・提出段階(2-4週間)
Step 5:必要書類の収集・作成
- 申請書類一式の準備
- 添付書類の収集・翻訳
- 書類の適法性・完全性確認
Step 6:申請書類の提出
- 居住地管轄の出入国在留管理局への提出
- 受理証明書の取得
- 審査期間中の就労継続手続き
Phase 4:審査・許可段階(1-3か月)
Step 7:審査対応・追加資料提出
- 入管からの照会対応
- 必要に応じた追加資料提出
- 面接審査への対応
Step 8:許可・在留カード交付
- 許可通知の受領
- 新しい在留カードの交付
- 雇用開始・支援計画実施開始
熊本県内の申請窓口と管轄区域
熊本出入国在留管理局出張所
- 所在地:〒862-0971 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第2合同庁舎
- 管轄区域:熊本県全域
- 受付時間:平日 9:00-16:00(12:00-13:00除く)
- 予約制:事前予約制(オンライン予約システム利用)
申請時の注意点
- 事前予約必須:新型コロナウイルス感染拡大防止のため完全予約制
- 代理申請:行政書士等への委任による代理申請が可能
- 審査期間:標準処理期間1-3か月(複雑な案件は延長可能性あり)
5️⃣ 必要書類の包括的ガイドと作成ポイント
申請者(外国人)が準備する書類
基本書類群
| 書類名 | 詳細内容・注意点 | 有効期限等 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | ・法務省様式第5号<br>・楷書で正確に記載<br>・修正液使用不可 | – |
| パスポート | ・原本提示<br>・全ページコピー提出<br>・有効期限6か月以上残存 | 有効なもの |
| 在留カード | ・両面コピー<br>・記載事項変更がないか確認 | 有効なもの |
| 顔写真 | ・縦4cm×横3cm<br>・3か月以内撮影<br>・無帽・正面向き | 3か月以内 |
技能実習修了関連書類
| 書類名 | 取得先・詳細 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 技能実習修了証明書 | ・監理団体が発行<br>・技能実習2号の修了証明 | 修了日・期間の正確性確認 |
| 技能検定合格証明書 | ・技能検定機関発行<br>・基礎2級以上の合格証明 | 合格年月日・等級の確認 |
| 技能実習評価試験合格証明書 | ・実施機関発行<br>・専門級合格証明 | 試験実施機関の正当性確認 |
雇用・労働条件関連書類
| 書類名 | 作成者・内容 | 法的要件 |
|---|---|---|
| 雇用契約書 | ・受入機関作成<br>・日本語・母国語併記<br>・労働条件明示 | 労働基準法15条準拠 |
| 労働条件通知書 | ・受入機関作成<br>・詳細な労働条件記載 | 労働基準法施行規則5条準拠 |
| 給与明細書(前職分) | ・前職場発行<br>・直近3か月分 | 賃金水準比較のため |
生活関連書類
| 書類名 | 内容・取得方法 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 住民票 | ・居住地市町村発行<br>・世帯全員記載<br>・マイナンバー記載なし | 発行から3か月以内 |
| 賃貸借契約書 | ・不動産契約書の写し<br>・住居確保の証明 | 契約名義人の確認 |
| 健康診断書 | ・指定医療機関発行<br>・結核検査含む | 3か月以内受診 |
受入機関(企業)が準備する書類
企業基本情報書類
| 書類名 | 内容・重要性 | 更新頻度 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | ・法人格の証明<br>・代表者・事業目的確認<br>・法務局発行 | 3か月以内発行 |
| 決算書類一式 | ・貸借対照表<br>・損益計算書<br>・事業報告書 | 直近3期分 |
| 法人税納税証明書 | ・税務署発行<br>・その1(納税額証明)<br>・その2(所得金額証明) | 3か月以内発行 |
| 労働保険概算・確定保険料申告書 | ・労働局提出控<br>・適正な労働保険加入証明 | 直近分 |
受入体制・業務関連書類
| 書類名 | 作成のポイント | 審査での重要性 |
|---|---|---|
| 会社案内・事業概要 | ・事業内容の詳細説明<br>・組織図・従業員数<br>・事業実績 | 事業安定性の判断材料 |
| 受入れ体制に関する説明書 | ・外国人受入実績<br>・指導体制・責任者<br>・安全管理体制 | 受入能力の重要指標 |
| 業務内容説明書 | ・従事予定業務の詳細<br>・技能実習との関連性<br>・キャリアパス | 業務適合性の判断 |
| 雇用に関する誓約書 | ・労働法令遵守の誓約<br>・適正処遇の確約<br>・差別禁止の誓約 | 法的コンプライアンス |
特定技能外国人支援計画書
支援計画書は、特定技能外国人の日本社会への適応を支援するための包括的な計画書で、以下の10項目の支援内容を詳細に記載します:
必須支援項目と具体的内容:
- 事前ガイダンス
- 労働条件・活動内容の説明
- 入国手続き・生活ルールの説明
- 相談・苦情対応窓口の案内
- 出入国時の送迎
- 空港等への送迎サービス
- 入国時の同行支援
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 住居の確保支援
- 銀行口座開設・携帯電話契約等の支援
- 生活オリエンテーション
- 日本の生活ルール・マナーの説明
- 公共交通機関の利用方法
- 医療機関・行政手続きの案内
- 公的手続等への同行
- 住民登録・税務手続きの同行支援
- 社会保険手続きの支援
- 日本語学習の機会の提供
- 日本語教室の案内・斡旋
- 学習教材の提供
- 学習進捗の管理
- 相談・苦情への対応
- 専用相談窓口の設置
- 母国語対応可能な相談体制
- 24時間対応体制(緊急時)
- 日本人との交流促進
- 地域イベントへの参加促進
- 職場内交流活動の企画
- 転職支援(離職時)
- 転職先の情報提供
- ハローワーク同行支援
- 必要書類作成支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
- 月1回以上の定期面談
- 問題発生時の適切な通報
登録支援機関関連書類(委託する場合)
| 書類名 | 内容・確認事項 | 重要性 |
|---|---|---|
| 登録証明書の写し | ・法務大臣登録証明<br>・登録番号・有効期限確認 | 支援機関の正当性確認 |
| 支援委託契約書 | ・委託範囲の明確化<br>・費用・責任分担<br>・契約期間 | 支援実施の担保 |
| 支援実績報告書 | ・過去の支援実績<br>・支援内容・成果<br>・問題対応事例 | 支援能力の評価材料 |
書類作成時の共通注意点
形式面での注意事項
- 使用言語:日本語での作成が原則(翻訳書類は翻訳者明記)
- 用紙・様式:A4判での統一、可読性の確保
- 製本・整理:項目別インデックス付きでの整理
- コピー品質:鮮明で判読可能なコピーの提出
内容面での重要ポイント
- 一貫性の確保:各書類間での記載内容の整合性
- 具体性の重視:抽象的表現を避け、具体的数値・事例の記載
- 法令適合性:労働法令・入管法令への完全な適合
- 将来計画:外国人のキャリア形成に資する具体的計画
6️⃣ 受入機関の法的義務と実務上の重要ポイント
特定技能外国人受入れの法的要件
特定技能外国人を受け入れる企業は、入管法および関連法令に基づき、以下の厳格な要件を満たす必要があります:
基本的受入れ要件
1. 企業としての適格性要件
- 5年以内の労働関係法令違反がないこと
- 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等
- 違反した場合の改善措置完了から5年経過が必要
- 5年以内の入管法違反がないこと
- 不法就労助長罪、虚偽申請等の処罰歴なし
- 欠格事由に該当しないこと
- 役員が暴力団構成員等でないこと
- 破産手続き中でないこと
