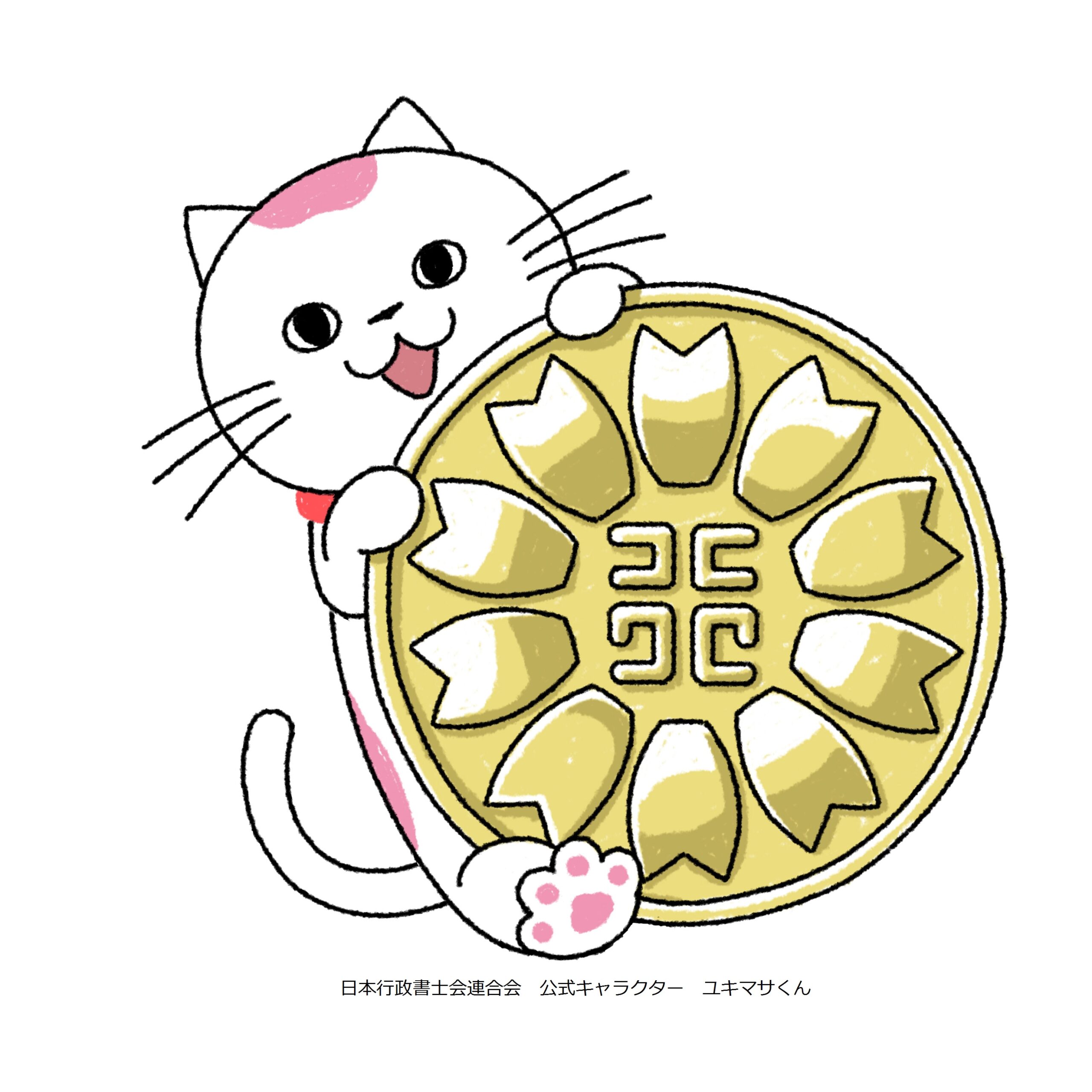
行政書士が解説|日本版DBS(こども性暴力防止法)における「犯罪事実確認」業務の完全実施ガイド
1. 制度概要と法的根拠
法的基盤と施行スケジュール
日本版DBS(Disclosure and Barring Service)は、正式名称「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第57号)に基づく制度です。
重要なスケジュール:
- 2024年6月19日: 国会成立
- 2024年6月26日: 法律公布
- 2025年度: 政令・ガイドライン策定、システム構築、事務マニュアル整備
- 2026年度中: 制度開始予定
制度の目的と法的意義
この制度は、子どもの安全確保を最優先とし、性犯罪の前歴がある者が子どもと接する職場に従事することを防止する予防的措置として機能します。同時に、職業選択の自由、プライバシー権、営業の自由といった基本的人権との調和を図りながら、必要最小限の範囲で運用される点が重要な特徴です。
2. 対象事業者と適用範囲
学校設置者等
- 学校(小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等)
- 幼稚園、認定こども園
- 児童福祉施設(保育所、放課後児童クラブ、児童館等)
- 社会教育施設(図書館、博物館、公民館等)
民間教育保育等事業者
- 学習塾、進学塾、各種教室(音楽、スポーツ等)
- ベビーシッター業
- 放課後等デイサービス
- その他、子どもと接する機会がある教育・保育関連事業
対象従事者
- 新規従事者: 採用予定者、転職者
- 現職者: 制度開始時点で既に従事している職員
- 派遣職員: 派遣元・派遣先双方での確認が必要
- ボランティア: 継続的に子どもと接する活動に従事する者
- 業務委託者: 清掃、警備、給食等で子どもと接触する可能性のある業務従事者
3. 特定性犯罪の範囲と照会期間
対象となる特定性犯罪
身体的性暴力:
- 強制性交等罪(刑法第177条)
- 強制わいせつ罪(刑法第176条)
- 準強制性交等罪(刑法第178条)
- 監護者わいせつ罪・監護者性交等罪(刑法第179条)
児童対象犯罪:
- 児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反
- 児童福祉法第34条違反(淫行をさせる行為等)
その他:
- 上記各罪の未遂罪
- 組織的犯罪処罰法に基づく加重処罰対象となった上記犯罪
犯罪歴照会期間
拘禁刑(実刑)の場合:
- 刑の執行終了日から20年間
拘禁刑(執行猶予)の場合:
- 裁判確定日から10年間(猶予期間満了後も継続)
罰金刑の場合:
- 刑の執行終了日から10年間
4. 犯罪事実確認業務フローの詳細解説
Step 1:制度説明と事前準備(Implementation Planning)
事業者の準備事項:
- 従事者への制度説明
- 法的義務としての位置づけ
- 個人情報保護措置の詳細
- 拒否した場合の法的・契約的帰結
- 結果に応じた対応方針の事前通知
- 内部体制の整備
- 情報管理責任者の指定
- 戸籍情報取扱担当者の指定と研修
- セキュリティ対策の強化
- 緊急時対応マニュアルの作成
- 規程・契約書の改定
- 就業規則への犯罪事実確認条項の追加
- 雇用契約書・業務委託契約書の改定
- 個人情報取扱い規程の更新
- 守秘義務規定の強化
Step 2:戸籍情報の収集と登録(Personal Information Collection)
戸籍情報の種類と取得方法:
- 電算化戸籍
- 市区町村の戸籍システムで電子化されている戸籍
- 最も迅速に取得可能(通常1-3日)
- 本籍地の市区町村窓口での申請
- イメージ除籍
- 紙の戸籍をスキャンしてデジタル化したもの
- 取得に1-2週間程度を要する場合あり
- 紙媒体戸籍
- 原本が紙のまま保管されている戸籍
- 最も時間を要する(2-4週間)
- 古い戸籍や特定地域で発生
必要書類と手続き:
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 従事者本人の身分証明書
- 委任状(事業者が代理取得する場合)
- 使用目的証明書
Step 3:システム申請とデータ送信(System Application)
申請プロセスの詳細:
- 事業者認証
- 事業者登録番号の取得
- 電子証明書の発行・インストール
- システムアクセス権限の設定
- 従事者情報の登録
- 基本情報(氏名、生年月日、性別)
- 戸籍情報(本籍地、戸籍筆頭者等)
- 従事予定業務の詳細
- 新規/現職の区分
- 特例適用の申請
- 「いとま特例」の要件確認
- やむを得ない事情の詳細記載
- 代替措置計画の提出
Step 4:行政機関による確認・照会(Administrative Verification)
こども家庭庁による処理:
- 本人確認作業
- 戸籍情報と申請者情報の照合
- 同姓同名者の区別
- 戸籍の変動履歴の確認
- 法務省への照会
- 検察総合情報管理システムへのアクセス
- 特定性犯罪前歴の検索
- 処罰歴の詳細確認
- 処理期間
- 標準処理期間:申請から2週間以内
- 複雑案件:最大1ヶ月
- 緊急案件:5営業日以内(特例対応)
Step 5:結果通知と対応措置(Result Notification and Response)
通知内容と形式:
- 犯罪事実確認書の交付
- 「特定性犯罪前歴なし」
- 「特定性犯罪前歴あり」
- 通知書番号・発行日・有効期限
- 従事者本人への通知
- 結果の同時通知(プライバシー保護)
- 誤認の場合の訂正請求権
- 訂正請求期限:2週間以内
結果に応じた具体的措置:
特定性犯罪前歴がある場合:
- 原則として教育・保育業務への従事禁止
- 配置転換(事務職等への異動)
- やむを得ない場合の契約解除
- 本人への十分な説明と相談対応
いとま特例適用時の必須措置:
- 子どもと1対1になる状況の完全排除
- 複数職員による常時監督体制
- 防犯カメラ等による客観的監視
- 定期的な研修受講の義務付け
- 3ヶ月以内の正式確認完了
Step 6:情報管理と記録保存(Information Management)
情報管理の原則:
- 最高機密レベルでの取扱い
- アクセス権限者の限定(管理職のみ)
- 物理的・技術的安全管理措置
- 暗号化による保存・送信
- 記録媒体の適切な廃棄
- 保存期間と廃棄
- 基本保存期間:5年間
- 離職時の即座廃棄
- 廃棄記録の作成・保存
- 廃棄証明書の発行
- 第三者提供の禁止
- 法令に基づく場合を除き提供禁止
- 司法機関からの照会への対応
- 監督官庁の調査への協力
Step 7:監督・報告義務(Supervision and Reporting)
所轄庁による監督:
- 定期監督
- 年1回以上の実施状況確認
- 書面調査と実地調査
- 改善指導・勧告の実施
- 報告義務
- 定期報告: 年1回、実施状況の詳細報告
- 緊急報告: 性暴力事案発生時の即時報告
- 変更報告: 体制変更時の事前報告
報告内容の詳細:
- 確認実施件数・結果統計
- 防止措置の実施状況
- 研修実施記録
- システム障害・不具合の発生状況
- 個人情報漏洩・紛失事案
Step 8:継続的改善と再発防止(Continuous Improvement)
PDCAサイクルの実装:
- Plan(計画)
- 年次防止計画の策定
- リスク評価の実施
- 改善目標の設定
- Do(実行)
- 防止措置の確実な実施
- 職員研修の定期実施
- 環境整備の継続
- Check(評価)
- 月次・四半期点検の実施
- 職員アンケートの実施
- 外部評価の導入
- Act(改善)
- 問題点の分析・改善
- 制度の見直し・更新
- 好事例の水平展開
5. 実務担当者向け業務チェックリスト
制度導入準備段階
- 法令・ガイドラインの最新版確認
- 内部規程の改定作業完了
- 情報管理システムの構築・テスト
- 職員研修プログラムの作成
- 外部専門家(行政書士等)との連携体制構築
日常業務実施段階
- 新規従事者の確認漏れ防止
- 戸籍情報取得の適切な管理
- システム申請の正確な入力
- 結果通知の適切な処理
- 情報の安全な保管・管理
継続管理段階
- 定期報告書の作成・提出
- 職員研修の定期実施
- 情報廃棄手続きの確実な実行
- 制度見直しのタイミング把握
- 緊急時対応手順の定期確認
6. よくある質問と実務対応
Q1:従事者が戸籍提出を拒否した場合の対応
法的根拠: こども性暴力防止法に基づく事業者の義務として、従事者には協力義務があります。
対応手順:
- 制度の法的意義と必要性を再説明
- 個人情報保護措置の詳細説明
- 就業規則に基づく服務命令として位置づけ
- それでも拒否する場合は、契約解除も含めた対応を検討
Q2:「いとま特例」の適正な運用基準
適用要件(すべてを満たす必要):
- 急な欠員による業務継続の必要性
- 他に適任者が確保できない状況
- 子どもの安全に重大な支障が生じるリスク
- 3ヶ月以内の正式確認完了の見込み
必須の代替措置:
- 複数職員による常時監督
- 1対1接触の完全回避
- 監視カメラ等による記録
- 緊急時連絡体制の整備
Q3:システム障害時の緊急対応
基本方針:
- 子どもの安全を最優先
- システム復旧を第一選択
- やむを得ない場合の代替手段の検討
具体的対応:
- システム運営者への即時連絡
- こども家庭庁への状況報告
- 復旧見込みの確認
- 必要に応じた業務停止の検討
Q4:過去の性犯罪歴が判明した現職者への対応
法的留意点:
- 解雇権濫用法理の適用
- 労働契約上の信頼関係破綻
- 配置転換可能性の検討
推奨対応手順:
- 本人との十分な面談
- 配置転換の可能性検討
- 労働組合・労働基準監督署への相談
- 専門家(弁護士・社労士)の助言取得
7. 地域特性を踏まえた実践ポイント
熊本県内事業者向けの特別配慮事項
地理的要因:
- 熊本市及び周辺自治体の戸籍事務処理期間
- 近隣自治体との連携
- 県内の教育・保育事業者ネットワークの活用
実務上の工夫:
- 地域の行政書士会との連携強化
- 同業他社との情報共有(個人情報に配慮)
- 地方自治体の理解促進と協力体制構築
8. 今後の課題と発展的検討事項
制度運用上の課題
技術的課題:
- システムの安定性・処理能力
- セキュリティ対策の継続強化
- 利用者インターフェースの改善
運用面での課題:
- 事業者・従事者の理解促進
- 個人情報保護との適切なバランス
- 監督体制の実効性確保
将来的な制度発展の方向性
対象拡大の可能性:
- 他の犯罪類型への拡張検討
- 対象事業者の範囲見直し
- 国際的な犯罪歴照会制度との連携
技術革新への対応:
- デジタル化の更なる推進
- AIを活用したリスク評価
- ブロックチェーン技術による情報管理
まとめ
日本版DBS(こども性暴力防止法)における犯罪事実確認制度は、子どもたちを性暴力から守るための重要な法制度です。事業者にとっては新たな法的義務となりますが、適切な準備と運用により、より安全な教育・保育環境を実現できます。
成功の鍵となる4つの原則:
- 透明性: 制度の目的・手続きを明確に説明
- 正確性: 法令に従った厳格な手続き実行
- 継続性: 持続可能な運用体制の構築
- 機密性: 最高レベルの情報管理体制維持
事業者の皆様が制度を適切に理解・運用し、子どもたちの安全な環境づくりに貢献できるよう、継続的にサポートしてまいります。弁護士、社会保険労務士等の他士業とも密接に連携し、法的リスクを最小化しながら実効性のある制度運用を実現するため、総合的な支援体制を提供いたします。
準備は早めに、実施は慎重に。子どもたちの未来のために、一歩ずつ確実に前進していきましょう。
