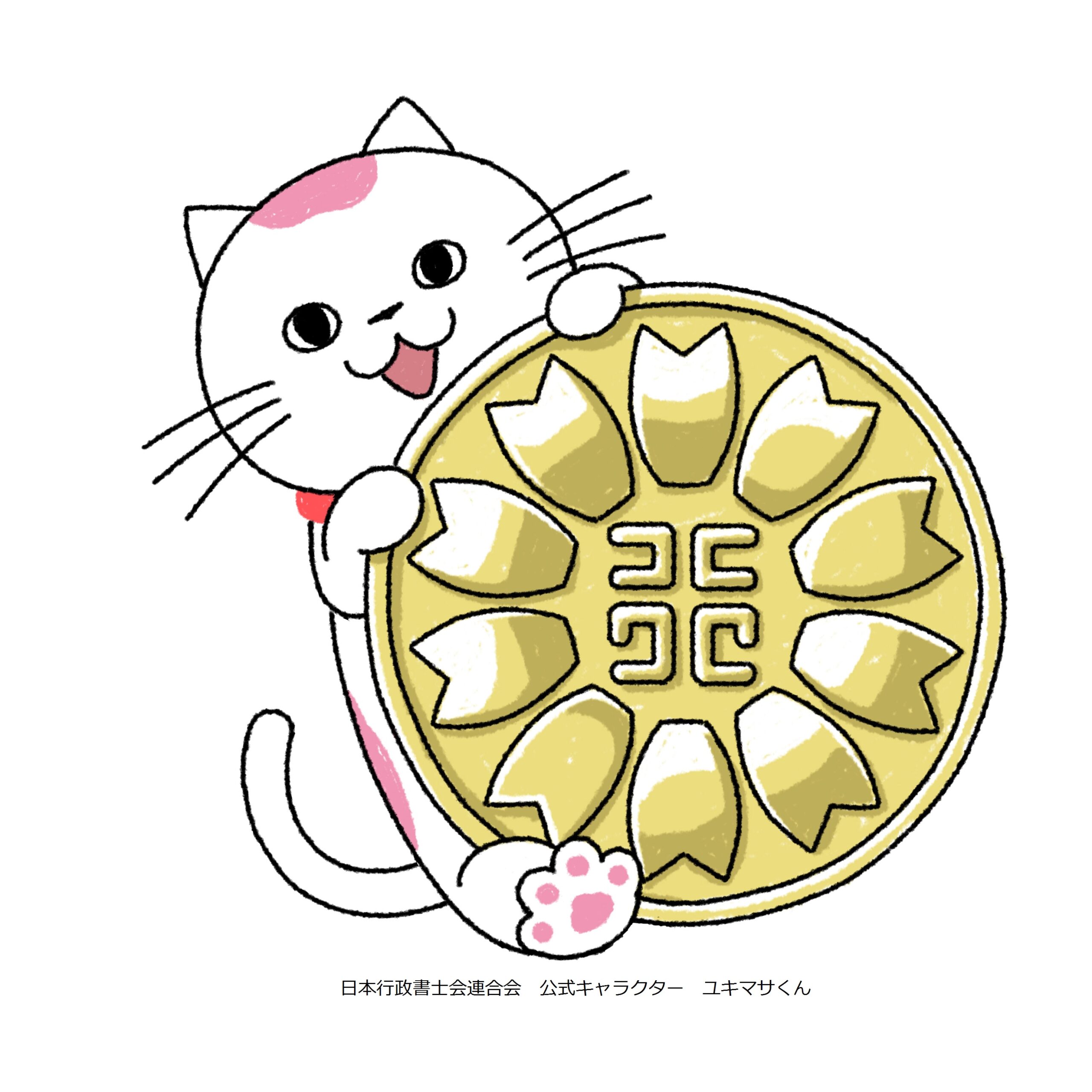
技能実習生から特定技能への在留資格変更:申請のポイントと注意点を徹底解説
こんにちは。熊本市中央区水前寺に拠点を置く行政書士法人塩永事務所です。当事務所は、外国人の在留資格(ビザ)申請に関する豊富な経験を有し、特に技能実習生から特定技能への在留資格変更に関するご相談が急増しています。2025年時点の最新の法改正情報と実務上の注意点を踏まえ、技能実習生が特定技能へスムーズに移行するための要件、手続きの流れ、必要書類、受入れ企業が準備すべき事項を、専門家の視点から詳しく解説します。
1. 特定技能制度とは?特定技能は、2019年4月に創設された日本の在留資格で、深刻な人手不足に対応するため、特定の産業分野で外国人労働者の就労を認める制度です。2025年4月時点で対象は12分野(※今後拡大の可能性あり)で、以下の2つのカテゴリーがあります:(1)特定技能1号
- 在留期間:通算5年(更新制、1年・6か月・4か月ごと)
- 技能レベル:相当程度の知識または経験を要する技能(現場作業レベル)
- 家族帯同:原則不可
- 特徴:技能実習2号修了者にとって主要な移行先。技能試験および日本語試験が免除される場合が多い。
(2)特定技能2号
- 在留期間:更新制(実質無制限)
- 技能レベル:熟練した技能(管理・監督レベル)
- 家族帯同:可能(配偶者・子)
- 特徴:現在は「建設」「造船・舶用工業」の2分野に限定。今後、対象分野の拡大が検討中。
対象分野(2025年4月時点): 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業特定技能制度は、労働者保護と適正な労働環境の確保を重視し、技能実習制度の課題を補完する形で設計されています。
2. 技能実習から特定技能への移行のメリットと背景(1)制度の背景技能実習制度は、国際貢献を目的に技術移転を促進する制度ですが、労働者保護の不十分さや実態との乖離が課題とされてきました。特定技能制度は、労働者としての権利保護を強化し、適正な労働条件での就労を目的とする在留資格として導入されました。(2)メリット
- 技能実習生:日本で培った専門スキルや日本語能力を活かし、安定した労働条件で長期就労が可能。特定技能1号では最長5年の在留、2号では実質無制限の在留が認められる。
- 受入れ企業:即戦力となる人材を確保でき、採用コストや教育負担を軽減。技能実習生の継続雇用により、業務の継続性や信頼関係を維持可能。
3. 技能実習生が特定技能に移行するための主要条件技能実習生が特定技能1号への在留資格変更を申請するには、以下の条件を満たす必要があります:(1)技能実習2号を「良好に」修了
- 定義:技能実習計画に基づき、原則2年以上の実習を問題なく修了。
- 要件:
- 在留期間中の不正行為(不法就労、犯罪行為等)や失踪、自己都合による途中帰国がないこと。
- 技能実習評価試験(実技・学科)に合格していること(例:技能検定3級相当)。
- 証明:監理団体または実習実施者が発行する「技能実習修了証明書」が必要。
(2)業務の関連性
- 特定技能で従事する業務は、技能実習で従事した分野と「同一」または「密接に関連」している必要があります。
- 例:介護分野の技能実習生は、特定技能でも介護分野に限定。飲食料品製造業の技能実習生は、同分野の特定技能へ移行可能。
- 注意:異なる分野への移行は原則不可(例:農業→介護は不可)。
(3)試験免除の特例
- 技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能1号に必要な以下の試験が免除される:
- 技能試験(特定技能評価試験)
- 日本語試験(日本語能力試験N4相当または国際交流基金日本語基礎テスト)
- 例外:一部の分野(例:介護)では、追加の試験や評価が必要な場合がある。
(4)その他の条件
- 健康状態が良好であること(健康診断書の提出が必要)。
- 受入れ企業の労働条件が、特定技能の基準(日本人と同等以上の報酬、適正な労働時間等)を満たしていること。
4. 技能実習から特定技能への変更手続きの流れ(2025年版)在留資格変更手続きは、以下のステップで進行します:(1)技能実習2号修了の確認
- 監理団体を通じて「技能実習修了証明書」を取得。
- 技能実習中の実績(出勤状況、評価試験結果等)を整理。
(2)受入れ企業との雇用契約締結
- 特定技能として雇用する企業(元の実習先企業も可)と雇用契約を締結。
- 契約内容:
- 日本人と同等以上の報酬(地域の最低賃金や同業種の賃金水準を参照)。
- 特定技能の対象業務に合致した職務内容。
- 労働時間や休日等の労働条件が法令遵守。
(3)支援計画の策定
- 特定技能1号では、外国人労働者の生活・職場適応を支援する「支援計画」の策定が義務。
- 支援内容(例):
- 入国時の空港送迎
- 住居確保の支援
- 日本語学習や生活オリエンテーション
- 定期的な面談や相談対応
- 支援は受入れ企業が直接実施するか、登録支援機関に委託可能。当事務所は、信頼できる登録支援機関の紹介も行います。
(4)在留資格変更許可申請
- 必要書類を揃え、申請者の居住地を管轄する出入国在留管理局(熊本県の場合、福岡出入国在留管理局熊本出張所)に提出。
- 申請書類は正確性と一貫性が求められ、不備があると不受理や不許可のリスクが高まる。
(5)審査および許可
- 審査期間:通常1~3か月(書類不備や追加提出が必要な場合は延長の可能性あり)。
- 許可後、新しい在留カード(特定技能1号)が交付され、正式に移行完了。
5. 在留資格変更許可申請の必要書類(技能実習2号 → 特定技能1号)以下は、申請に必要な主な書類の一例です。個別の状況や分野により追加書類が必要な場合があります。(1)申請者に関する書類
- 在留資格変更許可申請書:出入国在留管理庁指定の様式。
- 技能実習修了証明書:監理団体または実習実施者発行。
- パスポートおよび在留カード:有効期限内の写し。
- 健康診断書:直近の健康状態を証明。
- 顔写真:規定サイズ(3cm×4cm、最近3か月以内に撮影)。
(2)雇用契約に関する書類
- 雇用契約書または労働条件通知書:報酬、職務内容、労働時間等を明記。
- 賃金台帳または給与明細(元の実習先企業で継続雇用の場合):過去の実績を確認。
(3)受入れ企業に関する書類
- 商業登記簿謄本:発行3か月以内のもの。
- 直近の決算書:貸借対照表、損益計算書等。
- 事業内容を証明する資料:会社案内、事業計画書、ウェブサイトの写し等。
- 特定技能受入れ体制の説明書:労務管理、住居確保、支援体制の詳細。
(4)支援計画に関する書類
- 特定技能外国人支援計画書:支援内容を具体的に記載。
- 登録支援機関の契約書(委託の場合):登録番号、契約内容を記載。
- 登録支援機関の登録証明書の写し。
(5)その他
- 納税証明書:受入れ企業の税務コンプライアンスを証明。
- 賃貸借契約書:特定技能外国人の住居を証明(必要に応じて)。
注意:書類の不備や受入れ企業の体制が基準を満たさない場合、不許可となるリスクが高い。事前の確認と準備が重要。
6. よくあるご質問(Q&A)Q1. 技能実習で学んだ業種と異なる分野で特定技能として働くことは可能ですか?A:原則不可。特定技能への移行は、技能実習で培った知識・経験を活かすことを前提とし、同一または関連分野に限定されます。例:建設分野の技能実習生が介護分野の特定技能へ移行することは認められません。Q2. 技能実習を途中で辞めた場合、特定技能に移行できますか?A:原則不可。「技能実習2号を良好に修了」は必須条件であり、不正行為、失踪、自己都合による途中帰国等がある場合、移行は極めて困難です。ただし、特別な事情(例:実習先の倒産等)がある場合は、個別相談が必要です。Q3. 支援計画は企業が自ら作成・実施する必要がありますか?A:企業が直接実施する場合は、支援体制の構築が求められますが、出入国在留管理庁に登録された登録支援機関に委託可能です。当事務所は、熊本エリアで実績のある登録支援機関を紹介し、適切な支援計画の策定をサポートします。Q4. 特定技能1号から2号への移行は可能ですか?A:可能ですが、特定技能2号は熟練技能が求められ、対象分野が限定(2025年時点で建設、造船・舶用工業のみ)。2号への移行には、特定技能評価試験(上級)合格等の追加要件が必要です。
7. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容特定技能への在留資格変更は、技能実習制度、特定技能制度、労働法規、支援制度等に関する専門知識が必要な複雑な手続きです。書類の不備や体制不足により不許可となるケースも多く、専門家の支援が不可欠です。当事務所では、以下のようなトータルサポートを提供します:
- 適否診断:申請者および受入れ企業の状況を詳細に分析し、特定技能の要件を満たしているか事前確認。
- 書類作成・翻訳:入管指定の様式に基づく正確な書類作成、必要に応じた翻訳対応。
- 支援計画策定支援:企業や登録支援機関と連携し、法令に適合した支援計画を作成。
- 受入れ体制構築支援:労務管理、住居確保、支援体制の整備をアドバイス。
- 申請代行:福岡出入国在留管理局熊本出張所への申請手続きを代行し、スムーズな進行を確保。
- アフターフォロー:許可後の在留カード更新や支援計画の実施サポート。
熊本県内の建設、介護、飲食料品製造業等の事業者様を中心に、多数の成功実績を有しています。
8. 最後に:スムーズな移行のために技能実習から特定技能への移行は、外国人労働者にとってキャリアアップの機会であり、企業にとっては優秀な人材確保の重要なステップです。しかし、複雑な手続きや厳格な審査基準により、専門知識がない場合に不許可となるリスクがあります。熊本で特定技能への在留資格変更をお考えなら、行政書士法人塩永事務所にお任せください。豊富な経験と地域密着のサポートで、外国人労働者と企業の双方に最適なソリューションを提供します。初回相談は無料で承りますので、まずはお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ行政書士法人塩永事務所
住所:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1丁目9番6号
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日9:00~17:00(事前予約で土日対応可)
