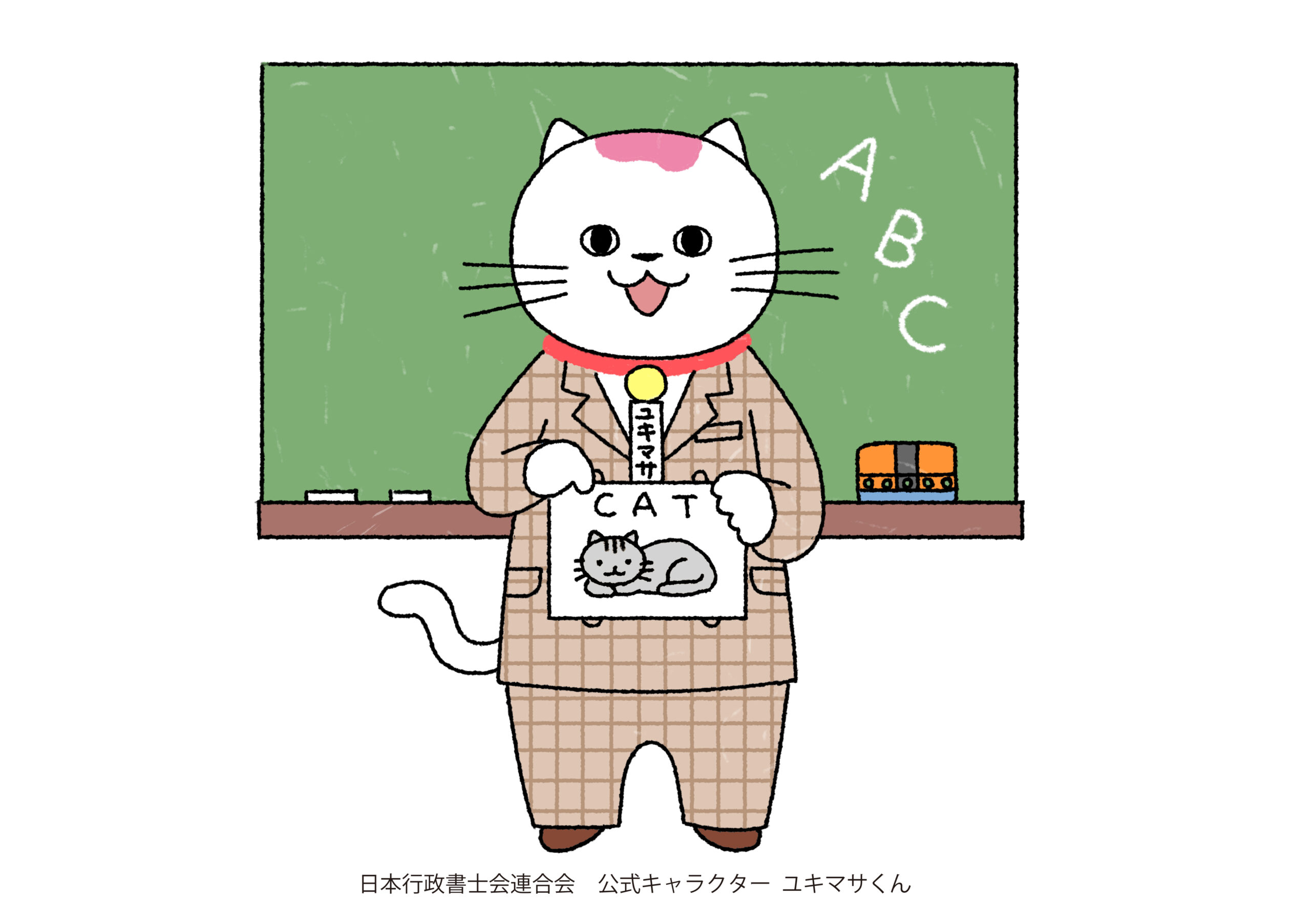
技能実習生受け入れにおける入国後講習・法的保護講習の講師依頼について
行政書士法人塩永事務所の入国後講習講師サービス
技能実習生の受け入れにおいて、適切な入国後講習の実施は法的義務であり、特に「法的保護講習」については高度な専門知識を持つ講師が必要です。行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と深い専門知識を基に、質の高い法的保護講習を提供いたします。
入国後講習制度の概要
法的根拠と実施義務
技能実習法第9条第1号および技能実習法施行規則第12条に基づき、監理団体は技能実習生の入国後、実習開始前に入国後講習を実施することが法的に義務付けられています。この講習は、技能実習生が日本での生活と実習を安全かつ適切に行うための基礎知識を習得する重要な機会です。
講習期間と実施時期
標準的な講習期間
- 第1号技能実習:1カ月以上2カ月以内
- 一般的には1カ月間(約160時間以上)での実施が主流
- 宿泊施設での集中講習形式が基本
実施時期
- 技能実習生の入国直後
- 実習実施者での実習開始前
- 在留資格「技能実習1号イ」または「技能実習1号ロ」での滞在期間中
入国後講習の構成内容
法定講習科目(技能実習法施行規則第12条)
1. 日本語講習
- 基本的な日常会話能力の習得
- 実習現場で必要な専門用語の理解
- ひらがな、カタカナの読み書き
- 簡単な漢字の理解
2. 日本での生活一般に関する知識
- 日本の文化・慣習・マナー
- 公共交通機関の利用方法
- 医療機関の利用方法
- 銀行口座開設・金銭管理
- 住民登録等の各種手続き
- 緊急時の対応方法
3. 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知った時の対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(法的保護講習)
- 技能実習法に関する基礎知識
- 入管法令の理解
- 労働関係法令の知識
- 人権保護に関する情報
- 相談・苦情申立て窓口の案内
4. その他日本での円滑な技能等の習得等に資する知識
- 実習職種に関する基礎知識
- 安全衛生管理の基本
- 技能検定制度の理解
- 帰国後の技能活用方法
時間配分の詳細
全体時間数:160時間以上
- 日本語:約100~120時間(60~75%)
- 日本での生活一般:約30~40時間(20~25%)
- 法的保護講習:8時間以上(必須)
- その他の知識:約12~22時間
法的保護講習の重要性と詳細内容
法的位置づけと重要性
法的保護講習は、技能実習生が日本滞在中に遭遇する可能性のある法的問題を予防し、適切な対応ができるようにするための極めて重要な講習です。技能実習法第9条第1号ハに明確に規定されており、専門的知識を有する者による実施が求められています。
詳細講習内容(最低8時間以上)
1. 技能実習法関連(2時間以上)
- 技能実習制度の目的と理念
- 技能実習生の権利と義務
- 禁止行為(強制労働、違約金設定等)
- 技能実習計画の内容と重要性
- 監理団体の役割と責任
- 実習実施者の義務
2. 入管法令関連(2時間以上)
- 在留資格「技能実習」の内容
- 在留期間と更新手続き
- 活動内容の制限
- 届出義務(住居地変更等)
- 違反行為とその結果
- 帰国手続きの流れ
3. 労働関係法令(2時間以上)
- 労働基準法の基本原則
- 労働時間・休日・休暇の権利
- 賃金支払いの原則
- 安全衛生管理の重要性
- 労働災害時の対応
- 労働組合結成の権利
4. その他法的保護に必要な情報(2時間以上)
- 人権侵害の防止
- 相談窓口の利用方法(OTIT、労働基準監督署等)
- 苦情申立て制度の活用
- 緊急時の連絡先
- 法的支援制度の紹介
- 通報・相談時の秘密保持
講師の資格要件
専門的知識を有する者の要件
- 弁護士、行政書士、社会保険労務士等の有資格者
- 技能実習制度に関する深い理解
- 関連法令についての最新知識
- 実務経験に基づく具体的指導能力
- 多言語対応能力(通訳を介する場合を含む)
行政書士法人塩永事務所の法的保護講習サービス
当事務所の専門性と実績
豊富な経験と実績
- 多様な職種・国籍の技能実習生への対応経験
- 監理団体とのパートナーシップ
高度な専門知識
- 技能実習法、入管法、労働法の最新動向への対応
- 法改正に伴う講習内容の適時更新
- 実務に即した具体的事例の豊富な蓄積
- 行政機関との密接な連携による正確な情報提供
講習の特色
1. 実践的な内容構成
- 机上の理論だけでなく、実際のケーススタディを多用
- 技能実習生が直面する可能性の高い問題への具体的対応方法
- Q&A形式による双方向の講習
- 理解度確認テストによる習得状況の把握
2. 多言語対応
- 主要送出国言語(中国語、ベトナム語、インドネシア語等)での資料提供
- 経験豊富な通訳者との連携
- 文化的背景を考慮した説明方法の採用
3. 継続的サポート体制
- 講習終了後の相談窓口の提供
- 実習期間中の法的問題への対応支援
- 監理団体への改善提案とフォローアップ
講習実施形式
対面講習(推奨)
- 監理団体の講習施設での実施
- 直接的なコミュニケーションによる理解度向上
- 個別質問への即座の対応
- 実際の書類やツールを用いた実践的指導
オンライン講習(必要に応じて)
- 感染症対策等で対面が困難な場合
- 地理的制約がある場合の柔軟な対応
- 録画機能による復習機会の提供
講習資料とツール
1. オリジナル教材
- 当事務所独自開発の講習テキスト
- 最新法令に基づく内容の定期更新
- 図解・イラストを多用した分かりやすい構成
- 多言語対応版の準備
2. 実務的ツール
- 緊急連絡先一覧カード
- 相談窓口利用ガイド
- 基本的な日本語フレーズ集
- 重要書類の記入例集
料金体系とサービス内容
基本料金(法的保護講習8時間)
標準料金
- 講師料:50,000円(税別)
- 交通費:実費
- 教材費:○,000円/人(税別)
- 通訳費:○○,000円(必要に応じて)
グループ割引
- 10名以上:○%割引
- 20名以上:○%割引
- 継続契約:年間契約で○%割引
追加オプションサービス
1. 個別相談対応
- 講習後の個別質問対応:○,000円/時間
- 電話・メール相談:月額○,000円
2. カスタマイズ講習
- 特定職種に特化した内容:追加○,000円
- 送出国別の文化的配慮:追加○,000円
3. フォローアップサービス
- 3ヶ月後の理解度確認:○,000円
- 年1回の復習講習:○,000円
依頼から実施までの流れ
1. 初回相談・打ち合わせ
- 監理団体のニーズ確認
- 技能実習生の概要(人数、国籍、職種等)把握
- 実施日程の調整
- 会場・設備の確認
2. 講習計画の策定
- 詳細なカリキュラムの作成
- 使用教材の選定・準備
- 通訳の手配(必要に応じて)
- 理解度確認方法の決定
3. 事前準備
- 技能実習生の基礎情報収集
- 教材の印刷・配布準備
- 会場設営の確認
- 機材の動作確認
4. 講習の実施
- 法的保護講習(8時間以上)の実施
- 参加者の理解度確認
- 質疑応答への対応
- 出席状況の記録
5. 講習後のフォロー
- 講習実施報告書の提出
- 参加者の理解度評価
- 今後の改善提案
- 継続的相談窓口の案内
よくある質問(FAQ)
Q1. 法的保護講習は必ず8時間実施する必要がありますか?
A1. はい。技能実習法施行規則により、最低8時間の実施が義務付けられています。当事務所では、内容の充実を図るため、通常8~10時間での実施をお勧めしています。
Q2. 通訳は必要ですか?
A2. 技能実習生の日本語理解度によって判断します。入国直後の技能実習生には通訳を推奨しており、当事務所では経験豊富な通訳者の手配も可能です。
Q3. 講習資料は技能実習生が持ち帰れますか?
A3. はい。講習で使用した資料は全て技能実習生にお渡しします。実習期間中の参考書として活用していただけます。
Q4. 講習後の相談対応は可能ですか?
A4. 可能です。当事務所では講習参加者への継続的なサポート体制を整えており、実習期間中の法的な相談にも対応いたします。
Q5. オンライン講習の効果はどうですか?
A5. 対面講習に比べて双方向性に制約がありますが、適切な準備と運営により効果的な講習が可能です。状況に応じて最適な形式をご提案いたします。
監理団体の皆様へ
技能実習制度の適正な運営において、入国後講習は技能実習生の日本での生活基盤を築く重要な出発点です。特に法的保護講習は、技能実習生の権利保護と制度の健全な発展に直結する極めて重要な要素です。
行政書士法人塩永事務所では、長年にわたる豊富な経験と深い専門知識を基に、質の高い法的保護講習を提供し、監理団体の皆様の制度運営を全面的にサポートいたします。
技能実習生、監理団体、実習実施者、そして日本社会全体にとって有益な技能実習制度の実現に向けて、当事務所は専門家としての責任を果たしてまいります。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
- 電話:[096-385-9002]
- メール:[info@shionagaoffice.jp]
- 営業時間:平日9:00~18:00
- 緊急時対応:[090-3329-2392]
法的保護講習の講師依頼、技能実習制度に関するご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門スタッフが、監理団体の皆様のニーズに合わせた最適なソリューションをご提案いたします。
