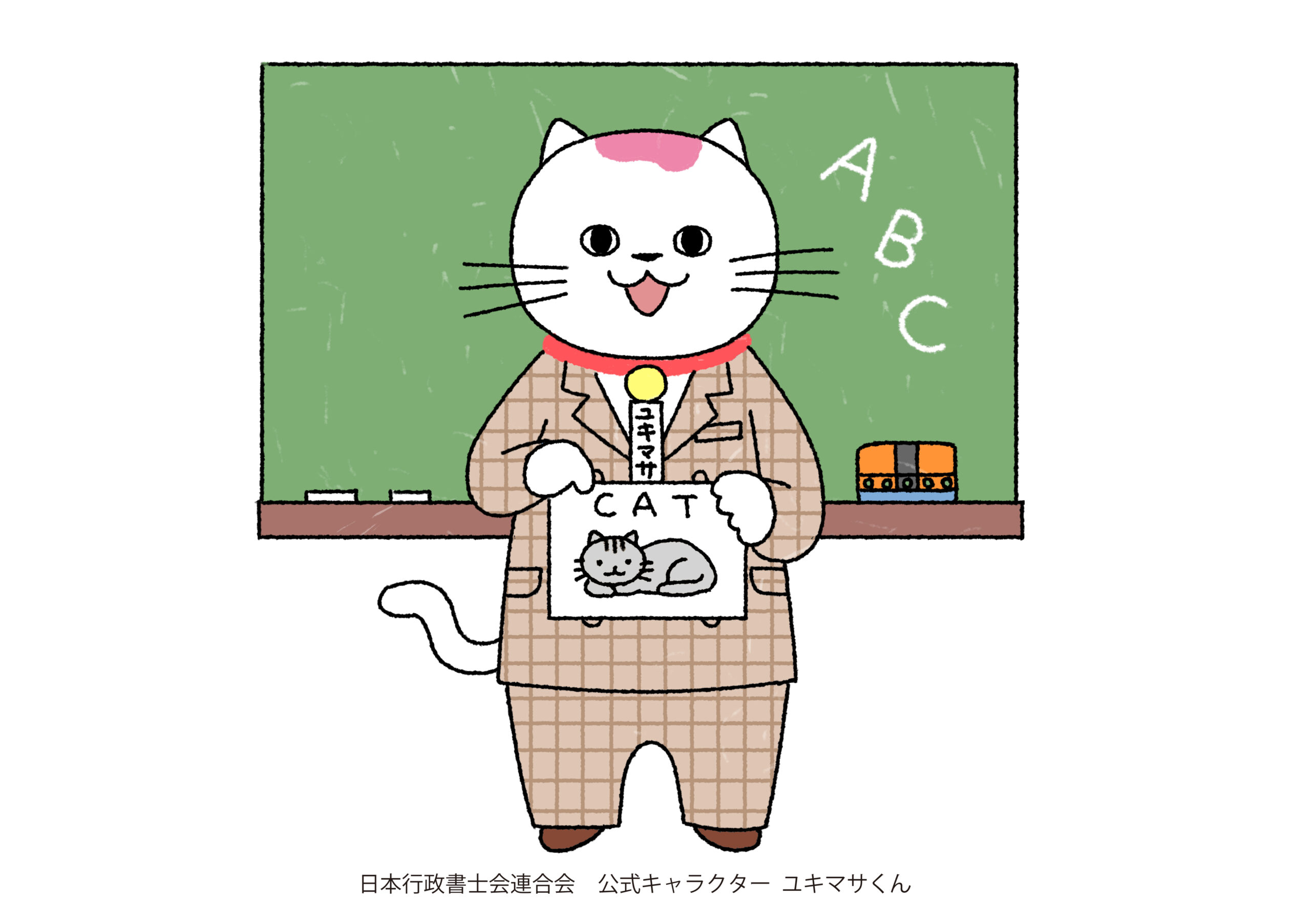
行政書士法人塩永事務所 特定技能1号と2号の7つの違いを徹底比較!取得要件や在留期間に注目
2019年4月に創設された在留資格**「特定技能」**は、深刻な人手不足が課題となっている特定産業分野において、外国人材の受け入れを可能にする制度です。近年、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されたことで、特定技能制度への注目がさらに高まっています。
しかし、「特定技能1号と2号には具体的にどのような違いがあるのか?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。本記事では、特定技能1号と2号の主な違いを7つのポイントに絞って徹底的に比較し、取得要件や在留期間など、企業様が外国人材の受け入れを検討する際に知っておくべき情報を、行政書士が詳しく解説します。
特定技能制度の概要
特定技能は、日本の労働力が特に不足している12の特定産業分野で、外国人材の就労を可能にする在留資格です。この制度は、主に単純労働ができない他の就労系在留資格とは異なり、単純労働を含む業務にも従事できるため、幅広い業務で活躍してもらえるのが特徴です。
特定技能には、**「特定技能1号」と「特定技能2号」**の2種類があり、それぞれ要件や可能な活動内容が異なります。
※介護分野は、特定技能1号の対象ですが、他に「介護」という在留資格があることから、特定技能2号の対象からは除外されています。
特定技能1号と2号の7つの違い
特定技能1号と2号の主な違いを、以下の表と詳細な解説で比較します。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | | 1. 在留期間の上限 | 1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新<br>通算5年が上限 | 3年・1年・6ヶ月ごとの更新<br>更新の上限なし | | 2. 永住権の要件 | 永住許可申請の要件を満たせない | 永住許可申請の要件を満たせる可能性がある | | 3. 求められる技能水準 | 相当程度の知識または経験を要する技能 | 熟練した技能<br>(各分野の技能試験で確認) | | 4. 外国人支援の必要性 | 必須<br>(支援計画の策定・実施義務あり) | 不要<br>(支援計画の策定・実施は任意) | | 5. 家族の帯同 | 基本的に不可 | 配偶者と子に限り可能 | | 6. 日本語能力試験 | 技能試験と併せて必須 | 取得要件としては定められていない<br>(試験合格が日本語能力の証明となる場合あり) | | 7. 試験の実施状況 | 国内外で定期的に実施 | 国内でのみ実施<br>(分野により実施時期が異なる) |
1. 在留期間の上限
特定技能1号の在留期間は、通算で最大5年間と定められています。一方で、特定技能2号には在留期間の上限がありません。これは、更新手続きをすることで事実上永続的に日本に在留できることを意味します。ただし、就労ビザであるため、雇用関係が継続していることが前提です。
2. 永住権の取得要件
特定技能1号での在留期間は、永住許可申請の要件となる在留期間(原則10年間)に算入されません。
これに対し、特定技能2号での在留期間は、永住許可申請の要件となる「就労資格での5年間の在留」に該当します。そのため、特定技能2号で在留を続けた場合、永住権取得の可能性が出てきます。永住権を取得すれば、在留期間の更新や就労制限がなくなり、外国人材の日本でのキャリア形成がより安定します。
3. 求められる技能水準
特定技能1号では、業務を遂行するために「相当程度の知識または経験」が求められます。これに対し、特定技能2号では、日本の専門家や熟練者と同等以上の「熟練した技能」が求められます。
例えば、建設分野の「配管」を例にとると、1号では「指導者の指示・監督を受けながら作業に従事する」レベルであるのに対し、2号では「複数の技能者を指導し、工程を管理する」といった指導的な役割を担うことが期待されます。
4. 外国人支援の必要性
特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、外国人材が安心して日本で生活・就労できるよう、生活支援の実施が義務付けられています。自社で支援が難しい場合は、登録支援機関への委託が必要です。
特定技能2号では、外国人材がすでに日本での生活に慣れ、熟練した技能を持っているとみなされるため、企業による支援は義務ではありません。
5. 家族帯同の可否
特定技能1号では、原則として家族の帯同は認められていません。しかし、特定技能2号では、配偶者と子に限り、在留資格を取得して本国から呼び寄せることが可能です。これにより、外国人材は家族と一緒に日本で生活できます。
6. 日本語能力の確認試験
特定技能1号の取得には、技能評価試験に加えて日本語能力試験への合格が必須です。
一方、特定技能2号の取得要件に日本語能力試験は定められていません。ただし、特定技能2号の技能評価試験に合格することで、日本語能力が一定水準以上であると判断されます。
7. 試験の実施状況
特定技能1号の試験は、分野によって頻度は異なりますが、日本国内だけでなく海外でも定期的に実施されています。
特定技能2号の試験は、対象分野が拡大されたことで各分野で順次開始されていますが、実施場所は基本的に国内のみです。
特定技能1号と2号の取得方法
特定技能1号の取得方法
特定技能1号は、以下の2つの方法で取得できます。
- 技能試験と日本語能力試験に合格する:各分野で定められた技能評価試験と、日本語能力試験(国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上)の両方に合格する必要があります。
- 技能実習2号から移行する:技能実習2号を「良好に」修了し、かつ技能実習の職種・作業内容と特定技能1号の業務に関連性がある場合、試験が免除されます。
特定技能2号の取得方法
特定技能2号は、以下の要件を満たすことで取得できます。
- 特定技能2号の技能評価試験に合格すること
- 各分野で定められた実務経験を有すること(管理・指導経験など、分野により要件は異なる)
特定技能2号の申請には、企業側による「管理職相当の実務経験を証明する書面」の提出が必要となるため、企業によるサポートが不可欠です。
特定技能2号を見据えた育成の重要性
特定技能2号の対象分野拡大により、外国人材が日本で長期的に働く選択肢が増えました。これにより、外国人材が特定技能1号から2号への移行を目標にキャリアを築くケースが増えていくと予想されます。
長期的な雇用を視野に入れている企業様や、優秀な外国人材に選ばれる企業を目指すのであれば、特定技能1号の段階から2号への移行を見据えた採用・人材育成を検討することをおすすめします。
特定技能制度に関するご質問や、具体的な申請手続きについてのご相談がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
