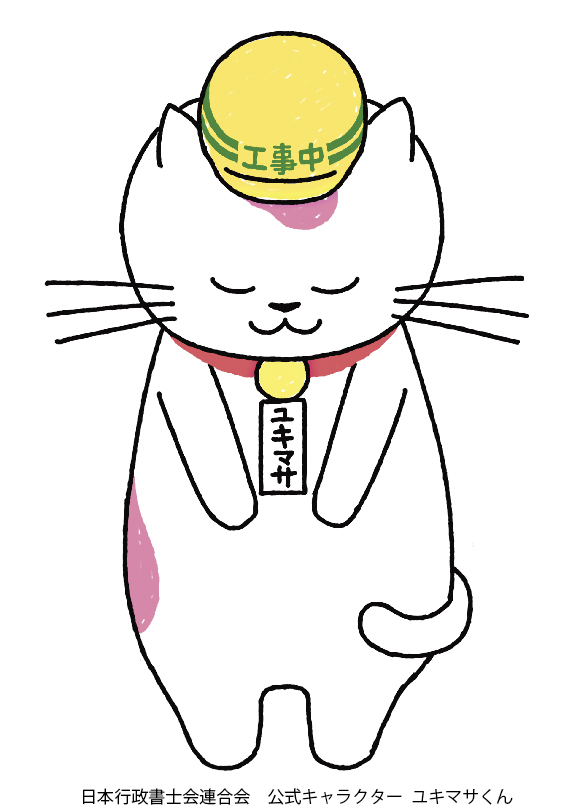
建設業(建築・とび・土工等)の許認可申請手続きの詳細【行政書士法人塩永事務所】建設業(建築、とび・土工、土木工事など)を営むには、日本国内で「建設業許可」を取得する必要があります。この許可は、建設業法に基づき、一定規模以上の工事を受注する際に必須となるものです。特に、建築やとび・土工工事は、高い安全性と品質が求められるため、厳格な審査が行われます。行政書士法人塩永事務所では、建設業許可申請の専門知識と豊富な経験を活かし、全国の事業者様をサポートしています。本記事では、建設業許可の種類、要件、申請手続きの流れ、必要書類、注意点について詳しく解説し、弊所のサービスをご紹介します。
1. 建設業許可の概要建設業許可が必要なケース建設業法では、元請け・下請けを問わず、以下の工事を行う場合に建設業許可が必要です:
- 建築一式工事:建築物の新築、増改築など(例:住宅、ビル、工場)。
- とび・土工・コンクリート工事:足場の設置、土砂掘削、コンクリート打設など。
- その他の専門工事:電気、管工事、舗装工事など(建設業法で定める29業種)。
ただし、以下の場合は許可が不要です:
- 軽微な工事(建築一式工事:1件あたり1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)。
- その他の専門工事:1件あたり500万円未満の工事。
建設業許可の種類建設業許可は、以下の区分に分かれます:
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合(国土交通大臣が発行)。
- 知事許可:1つの都道府県内に営業所を設置する場合(都道府県知事が発行)。
- 一般建設業許可:元請けまたは下請けとして工事を行う場合。
- 特定建設業許可:4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の工事を元請けとして受注する場合。
特に、建築やとび・土工工事では、特定建設業許可が必要となるケースが多く、許可取得の難易度が高いです。
2. 建設業許可の要件建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を満たす必要があります。審査は厳格で、書類による証明が求められます。
- 経営業務の管理責任者(経管)の設置
- 建設業の経営経験を持つ者が事業者にいること。
- 例:建設業の役員経験5年以上、または許可業種での実務経験7年以上。
- 証明書類:過去の契約書、工事請負証明書、役員登記簿など。
- 専任技術者(専技)の設置
- 各業種に対応する技術資格(例:1級・2級建築施工管理技士)または実務経験(10年以上)を持つ者が常勤でいること。
- とび・土工工事の場合:1級・2級土木施工管理技士や実務経験が求められる。
- 証明書類:資格証明書、実務経験証明書、常勤証明(健康保険証など)。
- 財産的基礎または金銭的信用
- 一般建設業:直近の決算書で自己資本500万円以上、または金融機関発行の預金残高証明書。
- 特定建設業:欠損額が資本金の20%以下、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上など。
- 証明書類:直近の決算書、預金残高証明書。
- 誠実性
- 申請者や役員が、詐欺、脅迫、建設業法違反などの不正行為を行っていないこと。
- 証明書類:誓約書、登記されていないことの証明書。
- 欠格事由に該当しないこと
- 破産者、犯罪歴、税金滞納がないこと。
- 証明書類:身分証明書、納税証明書。
3. 申請手続きの流れ建設業許可の申請は、営業所を管轄する都道府県庁または国土交通省(大臣許可の場合)に対して行います。以下は、一般的な申請手続きの流れです:
- 事前準備(1~2ヶ月)
- 必要書類の収集:経管や専技の証明書類、決算書、納税証明書など。
- 取引先や工事実績の整理:実務経験を証明するための契約書や請求書。
- 弊所では、書類のチェックリストを提供し、不足書類の特定を支援します。
- 申請書類の作成(2~4週間)
- 建設業許可申請書(様式第1号)および添付書類を作成。
- 書類例:営業所の賃貸契約書、役員の履歴書、財務諸表、資格証明書。
- 弊所では、正確な書類作成を代行し、誤記や不備を防ぎます。
- 申請書類の提出
- 管轄の窓口(都道府県庁または地方整備局)に提出。
- 申請手数料:知事許可は9万円、大臣許可は15万円。
- 電子申請の導入が進む地域もありますが、紙ベースが主流です()。
- 審査期間(1~3ヶ月)
- 都道府県知事許可:約1~2ヶ月。
- 国土交通大臣許可:約2~3ヶ月。
- 審査では、書類の整合性や現地調査(営業所の確認)が実施される場合があります。
- 許可通知と登録
- 許可が下りると、許可通知書が発行され、許可番号が付与されます。
- 許可後は、5年ごとに更新申請が必要です()。
4. 必要書類の詳細建設業許可申請には、以下の書類が必要です(業種や許可区分により異なる場合があります):
- 申請書類:
- 建設業許可申請書(様式第1号)。
- 役員等の一覧表(様式第2号)。
- 営業所一覧表(様式第3号)。
- 添付書類:
- 経営業務の管理責任者証明書(実務経験や役員経験の証明)。
- 専任技術者の資格証明書または実務経験証明書。
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書)。
- 納税証明書(法人税、消費税、事業税など)。
- 営業所の賃貸契約書または登記簿謄本。
- 身分証明書、登記されていないことの証明書。
- その他:
- 工事実績証明書(契約書、請求書、完工証明書など)。
- 健康保険証や給与明細(常勤証明用)。
書類の収集や作成は煩雑で、特に実務経験の証明は過去の契約書類の整理が必要です。行政書士法人塩永事務所では、書類収集のサポートから作成代行まで一貫して対応します。
5. 注意点とよくある課題
- 実務経験の証明が難しい
- 経管や専技の実務経験を証明するには、工事の契約書や請求書が必要です。過去の書類が不足している場合、代替書類(例:工事台帳、写真)の準備が必要。
- 弊所では、代替書類の提案や証明方法のアドバイスを提供します。
- 営業所の要件
- 営業所は、単なる住所ではなく、建設業の業務を行うための物理的な事務所である必要があります。電話やバーチャルオフィスだけでは認められません。
- とび・土工工事では、資材保管スペースの確認が求められる場合も。
- 申請の複雑さと時間
- 書類不備や要件不足で再提出を求められるケースが多く、申請期間が長引くことがあります。
- 外国企業や新規参入企業にとって、日本の行政手続きは特に複雑に感じられることが多いです()。
- 特定建設業許可の厳格な基準
- 特定建設業許可は、財産的基礎の基準が厳しく、資本金や流動比率の証明が難しい場合があります。
- 大規模な建築・とび・土工工事を受注する場合は、事前に財務状況を整える必要があります。
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート行政書士法人塩永事務所では、建設業許可申請の専門家として、以下のようなサービスを提供しています:
- 無料初回相談:全国対応で、電話、メール、オンラインにて初回相談を無料で承ります()。
- 書類作成・収集代行:煩雑な書類の準備を代行し、迅速かつ正確な申請をサポート。
- 要件診断:経管や専技の要件を事前に診断し、不足書類の補完方法を提案。
- 全国対応:各都道府県の申請窓口の違いを熟知し、全国の事業者様に対応。
- 更新・変更手続き:許可取得後の更新申請や営業所・役員の変更手続きもサポート。
特に、建築やとび・土工工事は、足場の設置や高所作業など高リスクな業務が多く、許可要件の証明が複雑です。弊所では、これらの業種に特化した経験を活かし、スムーズな申請を実現します。
7. さいごに建設業許可は、建築・とび・土工などの事業を拡大する上で欠かせないものです。しかし、申請手続きは複雑で、書類の準備や要件の証明に多くの時間と労力を要します。行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請のプロフェッショナルとして、事業者様のニーズに応じたきめ細やかなサポートを提供します。お近くに建設業許可に詳しい行政書士が見つからない場合や、申請手続きの負担を軽減したい場合は、ぜひ弊所にご相談ください。全国対応で、電話、メール、オンラインでのやり取りで完結します。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
