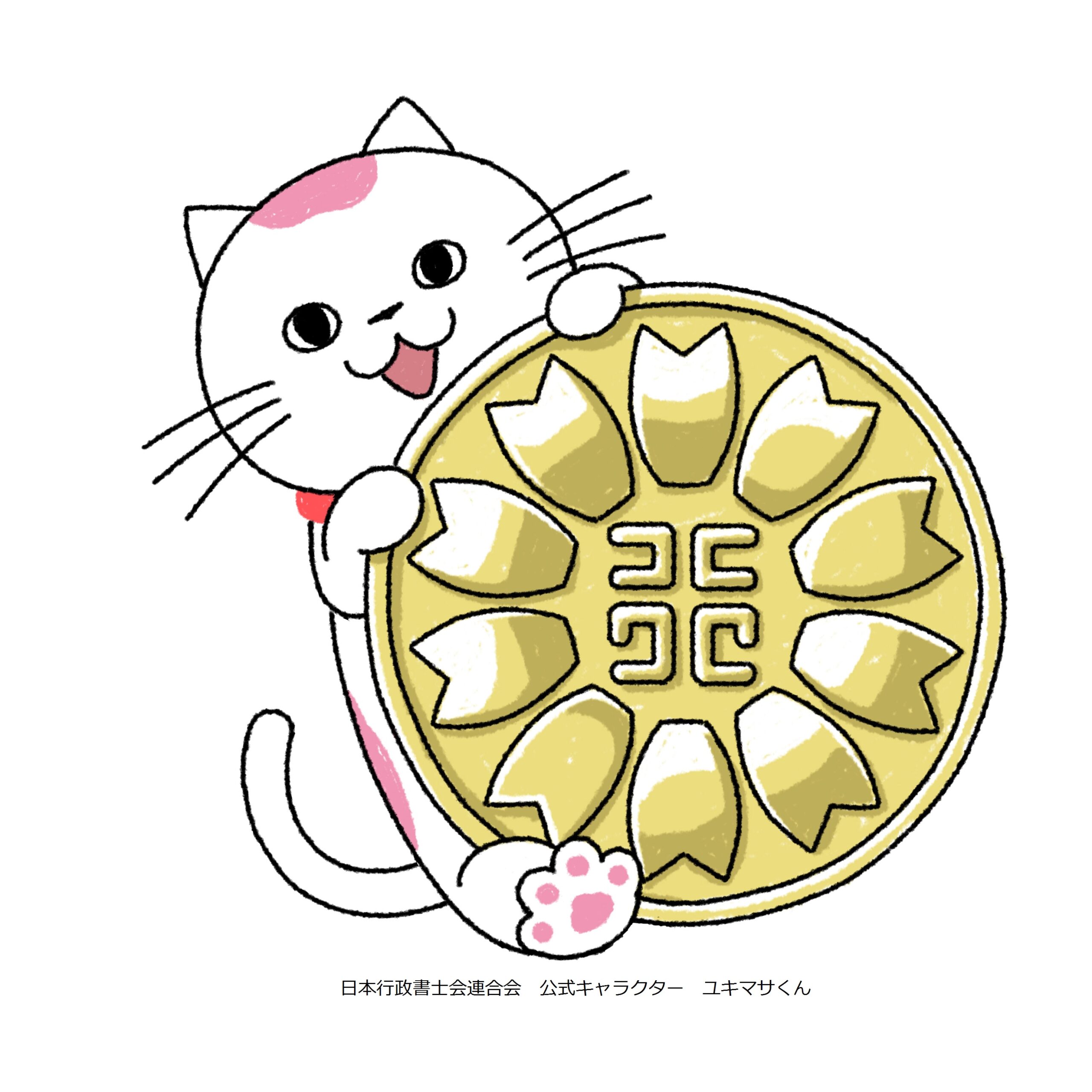
成長が見込まれる日本酒の輸出 ― 必要な免許と手続きのすべて
なぜ今、日本酒の輸出が注目されているのか?
近年、日本酒、焼酎、ウイスキー、ジンなど、日本産の酒類が海外で高く評価され、輸出に関するお問い合わせが急増しています。特に健康志向と日本食ブームの後押しにより、欧米やアジアを中心に需要が高まっており、国税庁も「日本酒輸出ハンドブック」を発行し、輸出促進に積極的に取り組んでいます。
一方で、国内市場の縮小や飲食業界の変化による売上減少を受け、酒類メーカーや卸業者は、新たな収益源として輸出に活路を見出しています。
海外輸出には「輸出酒類卸売業免許」が必要です
輸出酒類卸売業免許とは?
「輸出酒類卸売業免許」とは、申請者が直接、海外の事業者または一般消費者に対して日本国内で製造された酒類を輸出・販売できる免許です。
注意点として、国内の別業者に輸出用の酒類を販売する場合はこの免許では対応できず、別の卸売業免許が必要です。
また、海外の一般消費者に対してネット通販などで酒類を販売する場合もこの免許が必要です。よく誤解されますが、名称に「卸売」とあるものの、小売のような直接販売にも対応します。
輸出酒類卸売業免許の要件
1. 人的要件
-
税金の滞納がないこと
-
酒税法違反などの行政処分歴がないこと
2. 経営基礎要件
-
直近3年の決算で大きな累積赤字がないこと
-
貿易実務や輸出ビジネスに関する知識・経験があること(輸出経験がない場合は、パートナー企業の実績などで補完可能)
3. 場所的要件
-
輸出に関する業務(受注・管理)ができる専用の事務所があること
-
販売場が不適当な場所(違法建築物、住居専用地域など)にないこと
免許取得時の重要ポイント
✅ 「何を、誰に、どのように売るか」が明確であること
申請時には、以下の情報と書類の準備が必須です:
-
取扱予定のお酒の種類(例:日本酒、焼酎、ウイスキーなど)
-
仕入先との関係書類(承諾書や契約書)
-
輸出先(海外バイヤー)との契約書または同意書
※輸出先や仕入先との関係が不明確な場合、「免許取得後に決める」といった姿勢では申請は通りません。
貿易実務の知識も必須です
輸出には、「輸出酒類卸売業免許」の他にも、次の2つの役所手続きが必要です:
1. 輸出契約前の免許申請
-
所轄の税務署に申請し、審査を受けます。
-
標準処理期間は約2か月。申請書類の準備にはさらに1か月以上かかることが一般的です。
2. 輸出前に必要な公的証明書類の取得
輸入国によって異なりますが、よく求められるのは以下のような書類です:
-
製造証明・原材料証明・放射能安全証明(福島関連)
-
製造工程や製造者登録の証明
-
産地証明書
-
輸入ライセンスの有無の確認書類
※輸出後には取得できない書類もあるため、出荷前に確実に取得し、輸出先に送付する必要があります。
輸出酒類卸売業免許の取得サポート内容
サポートの流れ:
-
無料相談(電話・LINE・メール)
-
ヒアリング・免許取得可能性の判断
-
お見積りとご契約
-
書類の収集・作成(代行対応可能)
-
税務署への申請と追加対応
-
免許通知後、登録免許税の納付
よくあるご質問(FAQ)
Q. 通販で海外の個人へ酒を売るには?
A. 海外向け通販でも輸出酒類卸売業免許が必要です。
Q. 日本酒以外の酒類も輸出できる?
A. 基本的に制限はありませんが、免許申請時の書類内容によっては品目制限が付く場合があります。
Q. 経験がなくても申請できる?
A. 酒類販売経験は不要ですが、貿易実務の知識や体制が求められます。足りない場合は、貿易経験のある会社と連携することでカバーできます。
輸出酒類卸売業免許の取得を丁寧にサポートします
弊所では、酒類販売業務に精通した専門行政書士が、法人設立、融資支援、書類代行までをワンストップで対応。経験に基づく適切なアドバイスで、スムーズな免許取得を実現します。
☎ 初回相談は無料。全国対応で、電話・メール・郵送だけで完結。
日本のお酒を世界に届けたい方へ。確かな手続きと戦略で、海外市場への第一歩をサポートいたします。
