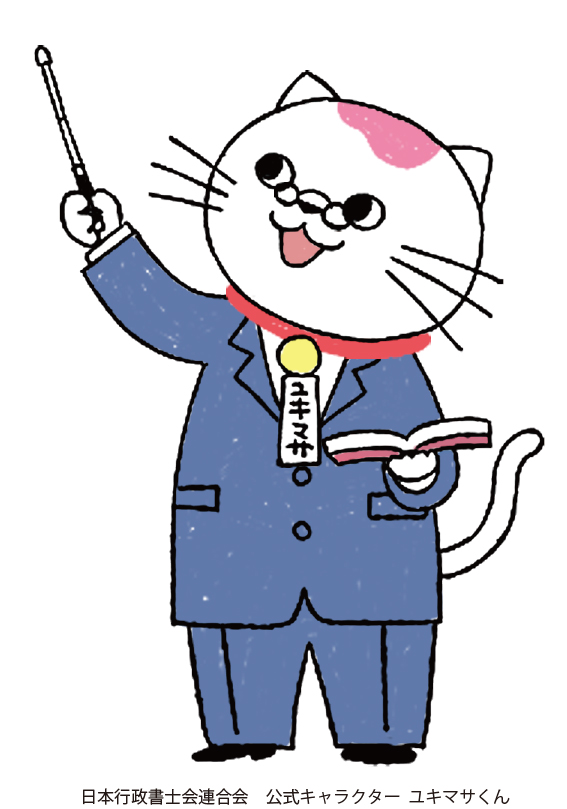
近年、日本酒やワインなど、世界中で「お酒」に対する関心が高まっています。それに伴い、お酒の輸出入ビジネスへの参入を検討される方が増えており、特に**「国産酒類の海外輸出」や「海外からの酒類輸入」**に関するご相談を多数いただいております。
弊社には、すでに他品目の貿易事業を展開されている方が、新たにお酒の取り扱いを希望されるケースや、日本在住の外国人の方が母国への日本酒輸出、あるいは母国からの酒類輸入を目指すケースなど、様々な背景を持つお客様から日々お問い合わせが寄せられています。酒類販売業免許申請の専門家として、多岐にわたるご相談に対応しておりますので、ご安心ください。
輸出入酒類卸売業免許とは
酒類販売業免許は、大きく分けて**「小売業免許」と「卸売業免許」**の2種類があります。厳密には「酒類販売媒介業免許」も存在しますが、該当するケースは非常に稀なため、ここでは割愛します。
この卸売業免許の中に、**「輸出入酒類卸売業免許」という種類の免許が存在します。実際には、「輸出入酒類卸売業免許」という一括りの免許ではなく、「輸入酒類卸売業免許」と「輸出酒類卸売業免許」**に分けて申請・取得することになります。
- 輸入酒類卸売業免許: 外国から酒類を仕入れ、国内の酒類販売業者(小売業者や他の卸売業者など)に対して販売する場合に必要です。
- 輸出酒類卸売業免許: 日本国内で製造された酒類を外国へ輸出して販売する場合に必要です。
輸出入卸売免許取得における主な注意点
輸出入酒類卸売業免許の取得要件は、基本的に他の卸売免許と共通していますが、以下の点に特に注意が必要です。
貿易業務の経験
審査の過程で、申請者の貿易業務経験が確認されることがあります。これは必須要件として明記されているわけではありませんが、実際にこの免許を取得される方の多くは、すでにお酒以外の品目で貿易事業を行っており、今回お酒を取り扱い品目に追加したいと考えているケースがほとんどです。
このような方は、既にお酒以外の貿易業務を日常的に行っているため、貿易業務経験の点で問題なく審査が進む傾向にあります。
しかし、**全く貿易経験がないからといって、直ちに申請ができないわけではありません。**その場合は、今後どのように貿易業務を展開していくのか、具体的な事業スキームを明確に提示する必要があります。
取引承諾書の入手
卸売免許全般の申請において、仕入先と販売先の取引承諾書の提出が必須書類となります。
- 輸入酒類卸売業免許の場合: 外国の酒類メーカーなどが仕入先となり、国内の酒類販売業者(酒販店や飲食店など)が販売先となります。
- 輸出酒類卸売業免許の場合: 国内の酒造メーカーなどが仕入先となり、外国の輸入業者(インポーター)などが販売先となります。
**申請時には、最低でも仕入先と販売先それぞれ1社ずつから、具体的な取引を予定していることを示す取引承諾書を入手している必要があります。**漠然と「免許を取得したら、いずれかの国のお酒を仕入れたい」といった状態では、申請を行うことはできません。事前に、具体的な取引先との関係を構築し、承諾を得ておくことが重要です。
販売場の問題
酒類販売業免許は、**酒類販売業務を行う場所(販売場)**に対して取得するものです。
例えば、法人の本店所在地が東京都港区にあったとしても、実際に酒類販売を行う店舗や事務所が北海道にある場合、その北海道の販売場の所在地を管轄する税務署に対して免許申請を行います。
「会社の名前で免許を取得すれば、どこでも酒類を販売できる」あるいは「店頭販売せず事務所としてのみなら、電話とスマートフォンがあればどこでもできる」と誤解されているケースが非常に多く見受けられますが、これは大きな間違いです。**この「販売場の要件」が、免許取得の大きなハードルとなる方も少なくありません。**実際に酒類を取り扱う物理的な場所を確保し、その場所の所在地を管轄する税務署に申請する必要があることをご留意ください。
最後に
お酒の輸出入ビジネスは、国際的な注目度も高く、お問い合わせが非常に多く寄せられています。しかし、酒類販売業免許は非常に複雑で、多くのケースを経験しないと把握しにくいポイントが多々あるのも事実です。
お住まいの地域で酒類販売業免許に詳しい行政書士が見つからない場合は、お気軽にご相談ください。電話、メール、郵送でのやり取りで完結するため、全国からのご相談に対応しております。
