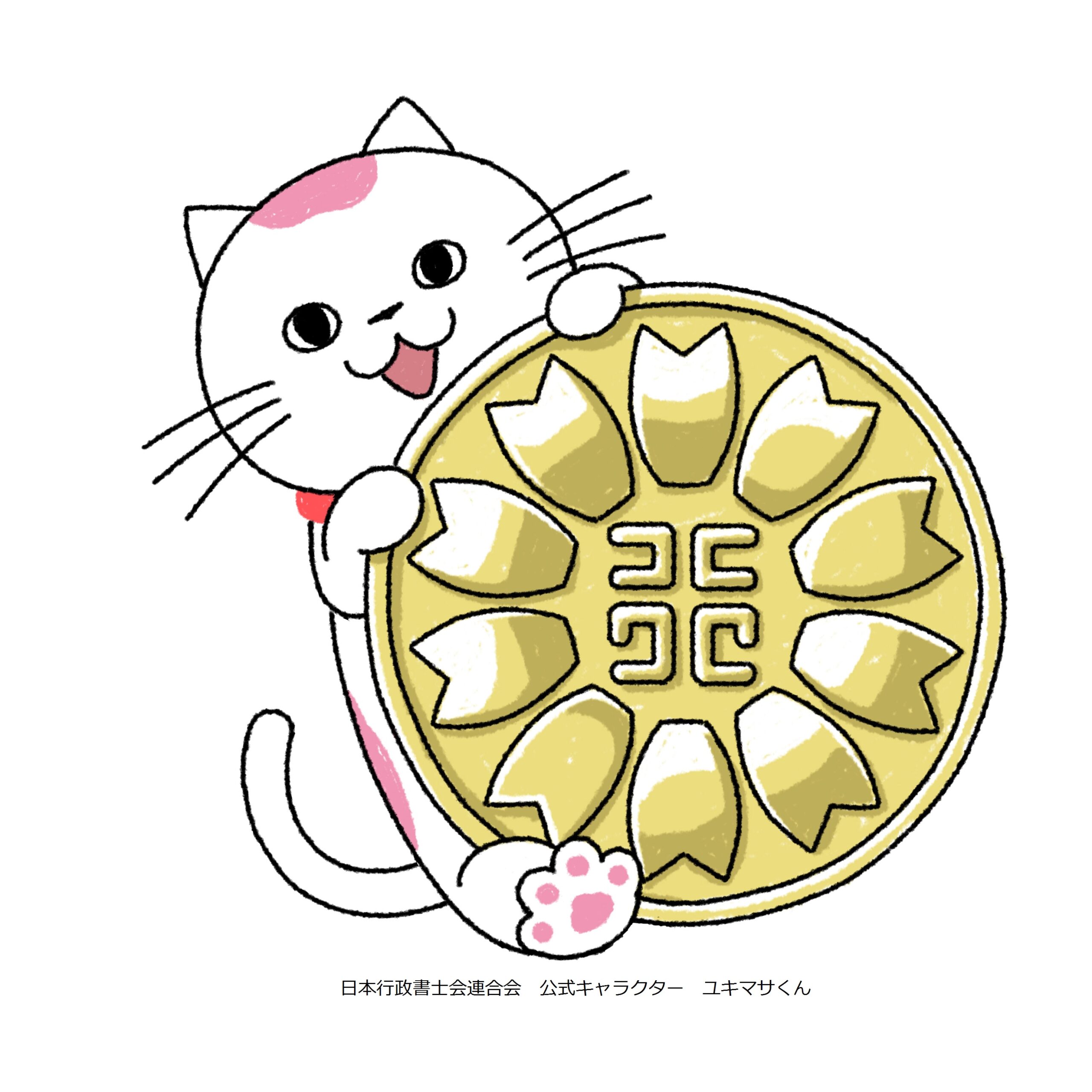
簡易宿所営業の許可申請手続きを徹底解説!~行政書士法人塩永事務所民泊やゲストハウス、貸別荘など、宿泊ビジネスを始める際、旅館業法に基づく「簡易宿所営業」の許可取得は重要なステップです。行政書士法人塩永事務所では、簡易宿所営業許可の申請手続きをスムーズに進めるためのサポートを提供しています。本記事では、簡易宿所営業の許可申請手続きの詳細を、初心者の方にも分かりやすく解説します。1. 簡易宿所営業とは?簡易宿所営業は、旅館業法に定められた宿泊形態の一つで、「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」と定義されています(旅館業法第2条第4項)。具体的には、ゲストハウス、カプセルホテル、貸別荘などがこれに該当します。一般的なホテルや旅館とは異なり、浴室やトイレ、洗面所などの設備が共用であることが特徴です。
簡易宿所営業のメリット
- 宿泊者側: 1人当たりの宿泊料金が比較的安価。
- 事業者側: 限られたスペースに多くの宿泊者を収容可能。
- 営業日数: 民泊(住宅宿泊事業)の年間180日制限がなく、365日営業が可能。
2. 簡易宿所営業の許可取得に必要な条件簡易宿所営業の許可を取得するためには、旅館業法および各自治体の条例に基づく構造設備基準や衛生基準を満たす必要があります。以下は主な要件です。2.1 構造設備基準
- 客室の延床面積: 原則として33㎡以上。ただし、宿泊者数が10人未満の場合は「3.3㎡×宿泊者数」で算出された面積以上で可。
- 2段ベッドの場合: 上段と下段の間隔が約1m以上必要。ただし、2段ベッドの面積を別々に計算して延床面積に含めることはできない場合があるため、事前に保健所に確認を。
- 共用設備: 浴室、トイレ、洗面所は宿泊者の需要を満たす規模で共用であること。自治体によってはトイレの数が男女別で2つ以上必要とされる場合も。
- 玄関帳場(フロント): 国の法令上は設置義務がないが、自治体によっては条例で基準が設けられている場合あり。玄関帳場を設置する場合、宿泊者の出入りを直接確認できる場所に設置し、カーテンや囲いがないこと。
- その他: 履物保管スペースや、近隣に公衆浴場がない場合は入浴設備の設置が必要。
2.2 衛生基準
- 施設の清潔保持(客室、共用設備の清掃)。
- 飲用水の安全確保(水道水以外の場合は水質検査成績書の提出が必要)。
- ごみ処理や騒音対策など、近隣住民とのトラブル防止策。
2.3 用途地域の確認簡易宿所営業は、建築基準法に基づく用途地域の制限を受けます。特に、住居専用地域では営業が認められない場合があるため、事前に自治体の都市計画課で確認が必要です。
2.4 消防法の遵守消防設備(消火器、誘導灯、避難経路の確保など)の設置が必須です。消防署との事前協議を行い、基準を満たす必要があります。
3. 許可申請手続きの流れ簡易宿所営業の許可申請は、施設所在地を管轄する保健所を通じて行います。以下は一般的な手続きの流れです。3.1 事前相談
- 窓口: 施設所在地を管轄する保健所(自治体によっては保健福祉事務所)。
- 必要な資料:
- 施設の平面図・立面図・断面図。
- 周辺地図(施設から約100~150m以内の学校、保育所、公園などの位置を示す)。
- 建築確認申請書や賃貸借契約書(施設の権原を証明)。
- ポイント: 新築や改築の場合は、着工前に保健所、建築審査課、消防署に相談。基準を満たさない場合、工事のやり直しが必要になる可能性があります。
3.2 必要書類の準備申請書類は自治体によって異なりますが、以下は一般的な例(京都府の場合を参考)です。
- 許可申請書。
- 施設の図面(平面図、立面図、断面図など)。
- 施設周辺の状況図(学校等の位置と距離を示す)。
- 水質検査成績書(水道水以外の場合)。
- 登記事項証明書や賃貸借契約書の写し(施設の権原を証明)。
- 消防法適合証明書(消防署発行)。
- その他、自治体が求める書類(例: 自主管理の手引き、点検表)。
3.3 申請書提出と審査
- 提出先: 管轄の保健所。
- 手数料: 自治体により異なる(例: 約7,400円~22,000円程度)。
- 審査期間: 書類提出後、15日以内(土日祝日除く)。書類審査と現地調査が行われ、基準適合が確認されれば許可が下ります。
3.4 現地調査保健所の監視員が施設を訪問し、構造設備基準や衛生基準の適合性を確認します。不適合箇所がある場合、改善が求められます。
3.5 許可証の発行審査を通過すると、営業許可証が発行され、営業開始が可能となります。4. 許可取得後の注意点
- 変更届出: 施設の構造や運営者の情報に変更があった場合、10日以内に保健所に届け出る。
- 近隣対応: 近隣住民からの苦情に対応するための手引きを作成し、適切な対応を徹底する。
- 消防・衛生管理: 定期的な点検と記録保持が求められる。
- 無許可営業のリスク: 許可なく営業した場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート簡易宿所営業の許可申請は、書類作成や自治体との調整、消防・建築基準の確認など、専門知識を要するプロセスが多く含まれます。行政書士法人塩永事務所では、以下のサービスを提供し、スムーズな許可取得をサポートします。
- 事前調査: 施設が許可基準を満たしているかの確認。
- 書類作成・提出代行: 複雑な申請書類の作成と保健所への提出を代行。
- 関係機関との調整: 保健所、消防署、建築審査課との事前協議をサポート。
- トータルコンサルティング: 民泊から簡易宿所への切り替えや、物件の有効活用に関するアドバイス。
ご興味のある方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。全国対応で、貴方の宿泊ビジネスを成功に導きます!
6. よくある質問Q1. 知人や友人を宿泊させる場合も許可が必要?
A1. 宿泊料を受け取らず、継続反復の意図がない場合は許可不要です。ただし、宿泊者を募集する場合は許可が必要です。
Q2. 民泊と簡易宿所営業の違いは?
A2. 民泊(住宅宿泊事業)は年間180日以内の営業に制限されますが、簡易宿所営業は365日営業可能です。ただし、許可基準は簡易宿所の方が厳格です。
Q3. 許可取得にかかる費用は?
A3. 保健所の手数料(約7,400円~22,000円)に加え、改装費用や消防設備費用、保険料などが発生します。詳細は物件の状況により異なります。
行政書士法人塩永事務所では、簡易宿所営業許可の取得から運営開始後のサポートまで、トータルでサポートいたします。宿泊ビジネスの第一歩を踏み出すなら、ぜひ当事務所にお任せください。ご相談は お電話にてお気軽にどうぞ!
