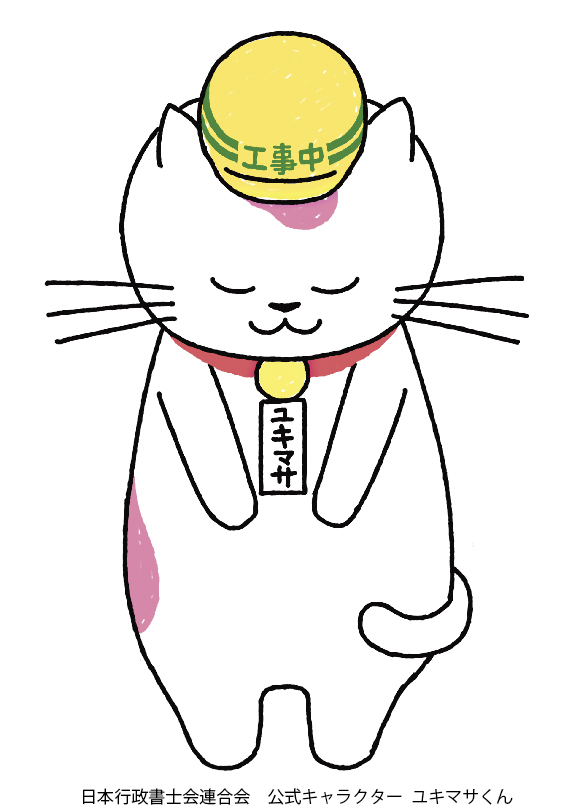
建設業許可取得の完全マニュアル – 建築・とび・土工業者必見の申請ガイド
行政書士法人塩永事務所
建設業許可は本当に必要?まずは基本を理解しよう
建設業を営む皆様にとって、「建設業許可」は避けて通れない重要な手続きです。しかし、「手続きが複雑そう」「何から始めればいいかわからない」という声を多く耳にします。
実際、建設業許可の取得には時間と労力が必要ですが、正しい知識と適切な準備があれば、必ず取得できます。本記事では、建設業許可の「なぜ」「何を」「どのように」を、わかりやすく解説いたします。
そもそも建設業許可って何?
建設業許可とは、建設業法に基づいて、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要となる国の許可制度です。これは建設工事の適正な施工と発注者の保護を目的としています。
許可が必要な工事の境界線
| 工事の種類 | 許可が必要な金額 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1,500万円以上 または 木造住宅で延べ面積150㎡以上 |
| その他の専門工事 | 500万円以上 |
つまり、これらの金額を超える工事を請け負う場合は、建設業許可が必須となります。
建設業許可の「2つの選択肢」を理解する
建設業許可には、営業エリアと営業規模によって選択肢があります。
営業エリアによる区分
都道府県知事許可
- 1つの都道府県内のみで営業
- 申請先:都道府県庁
- 審査期間:約30日
国土交通大臣許可
- 複数の都道府県で営業
- 申請先:地方整備局
- 審査期間:約45日
営業規模による区分
一般建設業許可
- 下請契約金額が4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満)
- 比較的取得しやすい
- 多くの事業者が該当
特定建設業許可
- 下請契約金額が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)
- 厳しい財産的要件あり
- 大規模工事を扱う事業者向け
建設業29業種 – あなたの事業はどれに該当?
建設業許可は29の業種に分かれており、それぞれに専門的な技術者が必要です。
主要な業種と具体例
土木一式工事業
- 道路、橋梁、ダム、港湾、空港などの土木工作物の建設
- 代表的な工事:道路舗装工事、橋梁架設工事、河川改修工事
建築一式工事業
- 住宅、ビル、工場などの建築物の建設
- 代表的な工事:戸建住宅建築、マンション建設、商業施設建築
とび・土工工事業
- 足場組立、掘削、コンクリート打設等の基礎的工事
- 代表的な工事:足場組立工事、基礎工事、解体工事、杭打工事
大工工事業
- 木材を使用した建築工事
- 代表的な工事:木造住宅建築、造作工事、木製建具取付工事
左官工事業
- 壁や天井の塗装・仕上げ工事
- 代表的な工事:内外装塗装工事、モルタル塗工事、漆喰塗工事
電気工事業
- 電気設備の設置・配線工事
- 代表的な工事:屋内配線工事、照明設備工事、電気設備工事
管工事業
- 配管・空調・衛生設備工事
- 代表的な工事:給排水工事、空調設備工事、ガス設備工事
建設業許可取得の「5つの関門」
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 経営業務管理責任者(経管)の配置
この要件のポイント
- 法人なら常勤役員、個人なら本人が該当
- 建設業での経営経験が必要
- 継続的な経営管理の実務経験が証明できること
必要な経験年数
- 同じ業種:5年以上の経営経験
- 異なる業種:6年以上の経営経験
- 準ずる地位:6年以上の経験
2. 営業所専任技術者の配置
この要件のポイント
- 各営業所に技術者を専任で配置
- 申請業種に応じた資格または経験が必要
- 他の営業所との兼務は原則不可
技術者になれる人
- 国家資格者(建築士、施工管理技士等)
- 学歴+実務経験者
- 長期実務経験者(10年以上)
3. 財産的基礎・金銭的信用
一般建設業の場合 以下のいずれかを満たす:
- 自己資本500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力
- 直前5年間の継続営業実績
特定建設業の場合 すべて満たす必要:
- 資本金2,000万円以上
- 自己資本4,000万円以上
- 欠損比率20%以下
- 流動比率75%以上
4. 誠実性の確保
確認される事項
- 請負契約における誠実性
- 法令遵守の姿勢
- 暴力団等との関係の有無
5. 欠格要件に該当しないこと
欠格要件の例
- 成年被後見人、被保佐人
- 破産者で復権していない者
- 建設業法違反による処分を受けた者
- 暴力団員またはその関係者
業種別専任技術者要件 – 実務に即した詳細解説
建築工事業
国家資格による場合
- 1級建築士
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築士
- 2級建築施工管理技士
学歴+実務経験による場合
- 大学の建築学科卒業 + 実務経験3年以上
- 高等学校の建築学科卒業 + 実務経験5年以上
実務経験のみの場合
- 建築工事の実務経験10年以上
とび・土工工事業
国家資格による場合
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
技能検定による場合
- とび1級
- とび2級 + 実務経験1年以上
学歴+実務経験による場合
- 大学の土木工学科卒業 + 実務経験3年以上
- 高等学校の土木科卒業 + 実務経験5年以上
実務経験のみの場合
- とび・土工工事の実務経験10年以上
大工工事業
技能検定による場合
- 建築大工1級
- 建築大工2級 + 実務経験1年以上
学歴+実務経験による場合
- 大学の建築学科卒業 + 実務経験3年以上
- 高等学校の建築科卒業 + 実務経験5年以上
実務経験のみの場合
- 大工工事の実務経験10年以上
申請書類の準備 – 「書類の山」を攻略する
建設業許可申請には多くの書類が必要です。効率的な準備のために、カテゴリー別に整理しました。
基本申請書類
必須書類
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 役員等の一覧表(様式第11号)
- 営業所一覧表(様式第1号別紙1)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 誓約書(様式第6号)
人的要件関係書類
経営業務管理責任者関係
- 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
- 経営業務の管理責任者の略歴書(様式第8号)
- 常勤性を証明する書類(健康保険証の写し等)
専任技術者関係
- 専任技術者証明書(様式第9号)
- 専任技術者の略歴書(様式第10号)
- 資格証明書または卒業証明書
- 実務経験証明書(必要な場合)
財産的要件関係書類
決算関係書類
- 貸借対照表(様式第16号)
- 損益計算書(様式第17号)
- 株主資本等変動計算書(様式第17号の2)
- 注記表(様式第17号の3)
- 附属明細書(様式第18号)
その他財産関係
- 預金残高証明書
- 融資証明書(資金調達能力を証明する場合)
法人・個人別必要書類
法人の場合
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し
- 株主名簿
個人の場合
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
申請の流れと注意点 – 失敗しないための実践ガイド
STEP1: 事前準備・要件確認(1-2ヶ月)
やるべきこと
- 許可要件の詳細確認
- 必要書類のリストアップ
- 専門家への相談
注意点
- 資格証明書の有効期限確認
- 実務経験の証明方法検討
- 財産要件の事前確認
STEP2: 書類収集・作成(1-2ヶ月)
やるべきこと
- 証明書類の取得
- 申請書類の作成
- 添付書類の準備
注意点
- 証明書類の有効期限(3ヶ月)
- 工事経歴の整理
- 常勤性証明書類の準備
STEP3: 申請書提出
提出前チェック
- 記載内容の確認
- 添付書類の確認
- 手数料の準備
提出方法
- 窓口提出(推奨)
- 郵送提出(一部自治体)
- 代理人による提出
STEP4: 審査期間中の対応
審査期間
- 知事許可:30日
- 大臣許可:45日
補正対応
- 迅速な補正書類提出
- 追加質問への対応
- 必要に応じた説明
STEP5: 許可証受領・営業開始
許可後の手続き
- 許可証の受領
- 標識の掲示
- 営業開始
費用の全体像 – 予算計画を立てよう
申請手数料
新規申請
- 知事許可:90,000円
- 大臣許可:150,000円
更新申請
- 知事許可:50,000円
- 大臣許可:50,000円
業種追加
- 知事許可:50,000円
- 大臣許可:50,000円
その他必要経費
証明書取得費用
- 登記事項証明書:600円
- 住民票:300円
- 印鑑証明書:300円
- 納税証明書:400円
専門家報酬
- 行政書士報酬:15万円~30万円
- 税理士報酬:5万円~15万円
年間維持費用
決算変更届
- 行政書士報酬:5万円~10万円
各種変更届
- 1件あたり:1万円~3万円
許可取得後の重要な義務 – 忘れがちな継続手続き
建設業許可は取得して終わりではありません。継続的な義務があります。
標識の掲示義務
営業所での掲示
- 建設業許可票の掲示
- 見やすい場所への設置
- 記載事項の正確性確保
工事現場での掲示
- 建設業許可票の掲示
- 主任技術者等の氏名表示
- 施工体系図の掲示
決算変更届の提出
提出期限
- 事業年度終了後4ヶ月以内
提出書類
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)
注意点
- 提出を怠ると更新申請ができない
- 正確な工事実績の記録が必要
各種変更届
変更届が必要な事項
- 商号または名称の変更
- 営業所の新設・廃止・移転
- 資本金の変更
- 役員の変更
提出期限
- 変更後30日以内
よくある質問と解決策
Q1: 個人事業主から法人成りした場合の許可はどうなりますか?
A1: 個人事業主の建設業許可は法人には引き継がれません。法人として新規で許可を取得する必要があります。ただし、経営業務管理責任者の経験は個人事業主時代のものも算入できます。
Q2: 専任技術者が退職した場合はどうすればよいですか?
A2: 専任技術者が退職した場合、2週間以内に後任者を選任し、変更届を提出する必要があります。後任者が見つからない場合は、営業停止となる可能性があります。
Q3: 建設業許可を取得すれば、どんな工事でも請け負えますか?
A3: 許可を受けた業種の工事のみ請け負うことができます。他の業種の工事を請け負う場合は、業種追加の申請が必要です。
Q4: 更新申請はいつから可能ですか?
A4: 許可の有効期間満了日の3ヶ月前から申請可能です。期限を過ぎると新規申請となりますので、早めの準備が重要です。
実際の申請事例 – 成功と失敗のポイント
成功事例:とび・土工工事業者A社
背景
- 個人事業主として10年間営業
- 従業員5名、年商8,000万円
- 500万円超の工事受注機会増加
取得のポイント
- 個人事業主時代の経営経験を活用
- とび1級技能士の資格を活用
- 工事実績の詳細な記録保管
結果
- 申請から28日で許可取得
- 大型工事の受注に成功
- 年商1億5,000万円に拡大
失敗事例:大工工事業者B社
背景
- 法人設立3年目
- 代表者に建設業経営経験なし
- 技術者の常勤性に問題
失敗のポイント
- 経営業務管理責任者の要件不備
- 専任技術者の常勤性証明不足
- 財産要件の確認不足
対策後の成功
- 経営経験者の役員招聘
- 技術者の専任化
- 財産要件の整備
トラブル回避のための実践的アドバイス
申請前の準備段階
重要チェックポイント
- 経営業務管理責任者の経験年数計算
- 専任技術者の資格・経験確認
- 財産要件の数値確認
- 工事実績の証明書類確認
よくある落とし穴
- 経験年数の計算間違い
- 資格証明書の有効期限切れ
- 常勤性証明書類の不備
- 工事実績の証明不足
申請後の対応
補正指示への対応
- 迅速な書類提出
- 正確な追加情報提供
- 担当者との密な連携
審査期間中の注意点
- 申請内容の変更は原則不可
- 追加質問への誠実な回答
- 必要に応じた説明資料作成
行政書士法人塩永事務所の強み
建設業許可申請での実績
豊富な経験と高い成功率
- 年間100件以上の申請実績
- 許可取得率98%以上
- 全29業種に対応
スピード対応
- 最短30日での許可取得実績
- 緊急案件への柔軟対応
- 効率的な書類作成システム
総合的なサポート体制
ワンストップサービス
- 要件確認から許可取得まで一貫サポート
- 税理士・社会保険労務士との連携
- 許可取得後の継続サポート
お客様第一の姿勢
- 丁寧な説明とコミュニケーション
- 透明性の高い料金体系
- アフターフォローの充実
具体的なサービス内容
建設業許可関連
- 新規申請・更新申請
- 業種追加・許可換え新規
- 決算変更届・各種変更届
- 経営事項審査申請
その他関連業務
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 宅地建物取引業免許
- 古物商許可
- 各種法人設立
まとめ:建設業許可取得への道筋
建設業許可の取得は、事業拡大の重要な一歩です。複雑な手続きではありますが、適切な準備と専門家のサポートにより、確実に取得できます。
成功のための5つのポイント
- 早期の準備開始:余裕を持ったスケジュール設定
- 要件の正確な把握:5つの許可要件の詳細確認
- 書類の完璧な準備:不備のない申請書類作成
- 専門家の活用:行政書士等への相談・依頼
- 継続的な管理:許可取得後の義務履行
次のステップ
建設業許可の取得をお考えの方は、まずは現在の状況を整理し、許可要件を満たしているかを確認することから始めましょう。
不明な点や心配な点がございましたら、行政書士法人塩永事務所まで、お気軽にご相談ください。お客様の事業発展を全力でサポートいたします。
お問い合わせ・ご相談はこちら
行政書士法人塩永事務所
- 初回相談:無料
- 土日祝日:対応可能
- 全国対応:可能
- 料金体系:明確・明朗
建設業許可取得のプロフェッショナルが、あなたの事業の成長をサポートします。
