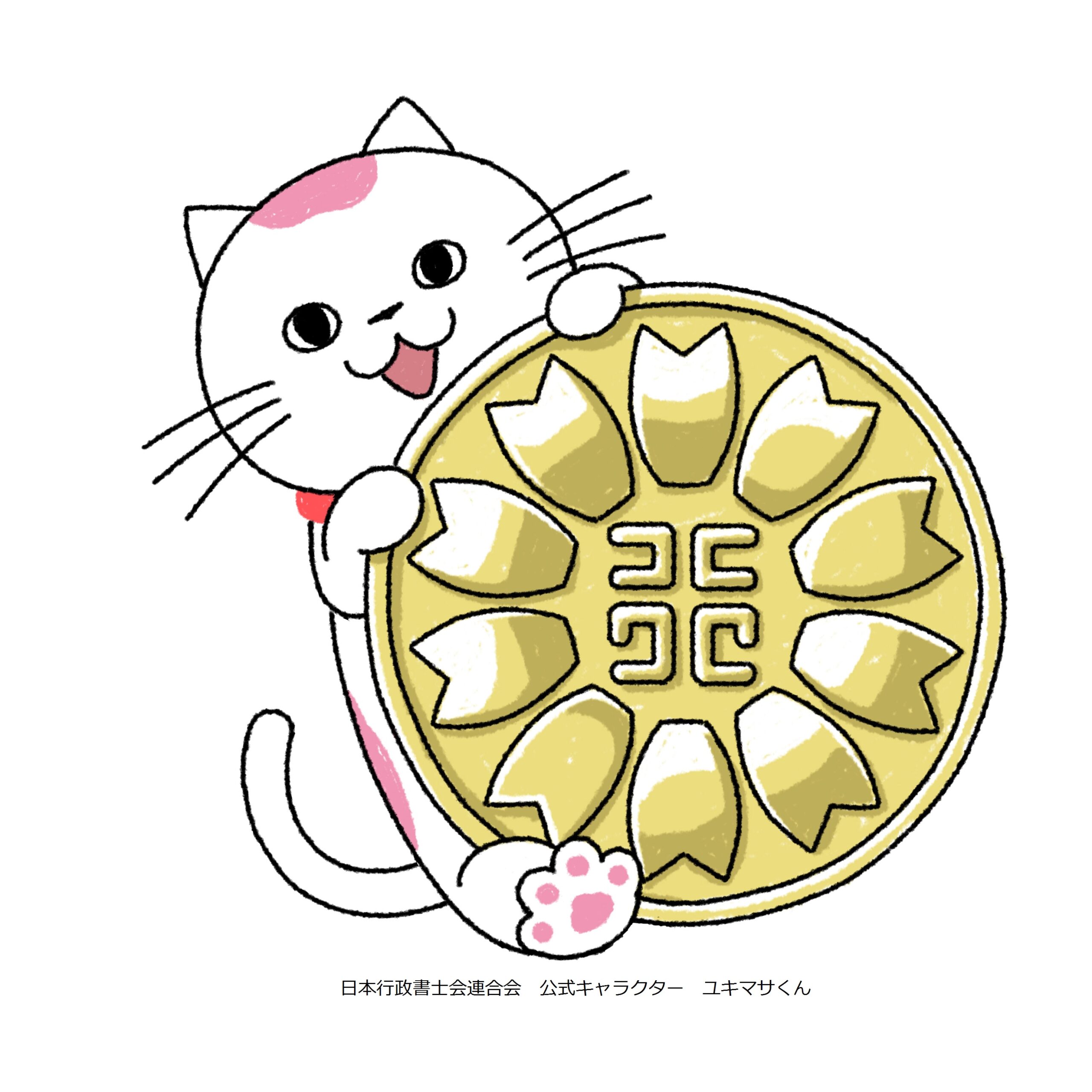
永住許可申請とは永住許可申請とは、就労活動や在留期間に制限のない「永住者」の在留資格を取得するための手続きです。この在留資格を取得することで、日本での生活や活動において高い自由度が得られ、長期的な安定が期待できます。永住許可申請と帰化申請の違い
- 永住許可申請
永住許可申請は、現在の在留資格を「永住者」に変更するための手続きです。この申請は個人単位で行われ、家族全員が同時に申請する必要はありません。例えば、家族の一部が帰化の要件を満たさない場合でも、個人で永住許可を取得し、その後、家族を「永住者の配偶者等」の在留資格に変更する申請を行うことが可能です。 - 帰化申請
帰化申請は日本国籍を取得するための手続きであり、通常は家族単位で申請されます。帰化は日本国籍を取得することを目的とするため、永住許可とは異なり、国籍変更を伴います。
永住許可の要件永住許可を取得するためには、以下の3つの主要な要件を満たす必要があります。(1) 素行が善良であること
- 日本の法律を遵守し、社会のルールを守って生活していることが求められます。
- 犯罪歴や重大な違反がないこと、日常生活において誠実であることが評価されます。
(2) 独立した生計を営む能力があること
- 生活保護などの公的支援に依存せず、安定した生活を送れる経済的基盤や技能を持つことが必要です。
- 十分な収入や資産があり、家族を含めた生活を維持できることが求められます。
(3) 永住が日本の利益になると認められること以下の具体的な条件が含まれます:
- 在留期間
- 原則として、10年以上継続して日本に在留していること。
- そのうち、就労資格(例:技術・人文知識・国際業務、技能など)または居住資格(例:日本人の配偶者等、定住者など)で5年以上継続して在留していること。
- 現在の在留資格において、最長の在留期間(例:5年、3年など)で在留していること。
- 法令遵守と公的義務の履行
- 罰金刑や懲役刑などの前科がないこと。
- 納税義務(所得税、住民税など)、社会保険料の支払い、年金加入など、公的義務を適切に履行していること。
- 公衆衛生
- 公衆衛生上、日本に有害となるおそれがないこと(例:重大な感染症を有していないこと)。
在留期間の特例(10年要件の短縮)特定の条件を満たす場合、10年以上の在留期間が短縮される特例が適用されます。
- 日本人、永住者、特別永住者の配偶者
- 結婚後3年以上日本に在留していること。
- 海外で結婚し同居していた場合は、結婚後3年以上経過し、かつ日本で1年以上在留していること。
- 日本人、永住者、特別永住者の実子または特別養子
- 1年以上継続して日本に在留していること。
- 定住者の在留資格を持つ者
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
- 難民認定を受けた者
- 難民認定後、5年以上継続して日本に在留していること。
- 日本への貢献が認められる者
- 外交、社会、経済、文化などの分野で日本への顕著な貢献があると認められる場合、5年以上継続して日本に在留していれば申請が可能です。
永住許可申請のメリット
- 活動制限の解除
就労や活動内容に制限がなくなり、自由に職業を選択したり、起業したりすることが可能になります。 - 在留期間の安定
在留期間の更新が不要となり、長期的な生活設計がしやすくなります。 - 家族の在留資格変更の可能性
永住者となった後、配偶者や子を「永住者の配偶者等」や「定住者」などの在留資格に変更する申請が可能です。
注意点
- 審査の厳格さ
永住許可の審査は非常に厳格で、書類の準備や要件の証明が重要です。納税証明書、収入証明、在留履歴など、詳細な書類提出が求められます。 - 個別の状況に応じた対応
申請者の状況(家族構成、職業、在留歴など)によって必要書類や審査のポイントが異なるため、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。
熊本県での永住許可申請は塩永事務所へ熊本県で永住許可申請や帰化申請をご検討の方は、水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。経験豊富な専門家が、丁寧かつ迅速に対応し、申請手続きをサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
