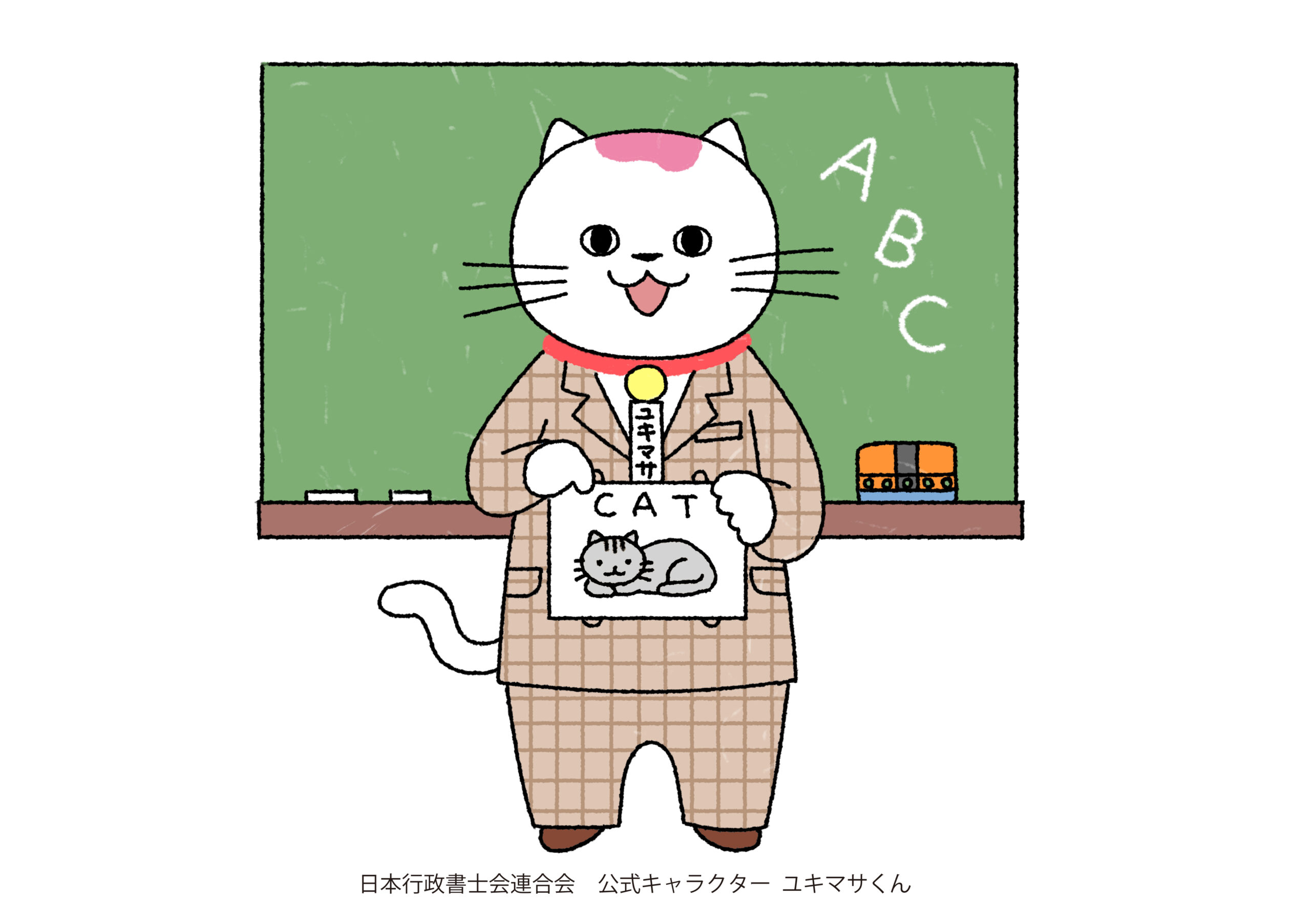
【2025年最新版】技能実習生から特定技能への在留資格変更:申請のポイントと注意点を徹底解説
こんにちは。熊本市中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所です。
当事務所では、外国人の在留資格(ビザ)に関する申請サポートを数多く手掛けており、特に技能実習生から特定技能への在留資格変更に関するご相談が近年著しく増加しています。
この記事では、2025年時点の最新の法改正情報と実務上の注意点を踏まえ、技能実習生が特定技能へスムーズに移行するための要件、詳細な手続き、必要書類、そして受入れ企業側が準備すべき事項までを、専門家ならではの視点から徹底的に解説します。
1. 特定技能制度とは?
特定技能は、2019年4月に創設された、日本における新たな外国人の在留資格です。日本国内で人手不足が特に深刻な12分野(※2025年4月時点。今後拡大の可能性あり)において、外国人労働者の就労を可能にすることで、日本の労働力不足を補うことを目的としています。
特定技能には以下の2種類があります。
- 特定技能1号:
- 在留期間: 最長5年
- 技能レベル: 特定の分野において相当程度の知識または経験を要する技能(現場作業レベル)
- 家族帯同: 原則不可
- 特徴: 技能実習を修了した外国人の主要な移行先となります。
- 特定技能2号:
- 在留期間: 更新制(実質的に上限なし)
- 技能レベル: 特定の分野において熟練した技能(熟練技能者レベル)
- 家族帯同: 可能(配偶者、子)
- 特徴: 現在は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野に限られていますが、今後対象分野の拡大が検討されています。
2. 技能実習から特定技能への移行のメリットと制度の背景
技能実習制度は、国際貢献を目的としつつも、一部で労働者の保護が不十分であるといった課題が指摘されてきました。これに対し、特定技能制度は、労働者としての権利保護をより重視し、実態に即した労働を目的とする在留資格として注目されています。
技能実習生にとっては、日本で培った専門的なスキルや知識を活かし、引き続き日本でより安定した条件で働くことが可能になる点が大きなメリットです。受入れ企業側にとっても、即戦力となる人材を確保しやすくなります。
3. 技能実習生が特定技能に移行するための主要条件
技能実習生が特定技能への在留資格変更許可を受けるためには、特に以下の2つの条件を必ず満たす必要があります。
- 1. 技能実習2号を「良好に」修了していること:
- これは、技能実習計画に基づき、定められた期間(原則2年間以上)を問題なく修了していることを意味します。
- 具体的には、在留期間中の不正行為(例:不法就労、犯罪行為など)や失踪、途中帰国などがなく、真面目に実習に取り組んでいたことが求められます。
- 技能実習評価試験(実技・学科)に合格していることも重要です。
- 2. 特定技能として従事する業務が、技能実習で培った分野と「同一」または「関連する分野」であること:
- 例えば、介護分野で技能実習を行っていた方は、特定技能としても介護分野での就労が可能です。
- 飲食料品製造業で実習していた方は、引き続き飲食料品製造業の特定技能として働くことになります。
- 異なる分野への変更は、原則として認められません。
**上記の2つの条件をクリアしていれば、特定技能として通常求められる「技能水準を測る技能試験」と「日本語能力を測る日本語試験」が免除されます。**ただし、一部の分野や状況によっては例外的に試験が必要となるケースもありますので、個別の確認が必要です。
4. 技能実習から特定技能への変更手続きの流れ(2025年版)
在留資格変更の手続きは、以下のステップで進みます。
- 実習先での技能実習2号修了の確認:
- 技能実習生が在籍していた監理団体を通じて、「技能実習修了証明書」が発行されます。これが、実習を良好に修了したことの最も重要な証明となります。
- 新しい受入企業との雇用契約締結:
- 特定技能外国人として就労する企業との間で、雇用契約を締結します。元の実習先企業で引き続き特定技能として働くことも可能です。この際、特定技能の基準に合致した労働条件(報酬、業務内容、労働時間など)であることが求められます。
- 支援計画の策定と登録支援機関の確認:
- 特定技能外国人に対しては、日本での生活や職場への適応を支援する「支援計画」の策定が義務付けられています。
- この支援は、特定技能外国人を受け入れる企業自身が行うか、または出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」に委託することができます。当事務所では、信頼できる登録支援機関のご紹介も可能です。
- 在留資格変更許可申請書類の作成・提出:
- 必要書類をすべて揃え、正確に記入・作成します。
- 申請は、申請者の居住地を管轄する出入国在留管理局(熊本県にお住まいの方は、福岡出入国在留管理局熊本出張所など)に提出します。
- 審査・許可:
- 提出された書類に基づき、出入国在留管理庁が審査を行います。通常、審査期間は1か月から3か月程度ですが、状況によってはこれより長くなることもあります。
- 新しい在留カードの受領:
- 審査が許可されると、新しい在留カードが交付され、正式に「特定技能1号」への移行が完了します。
5. 在留資格変更許可申請の必要書類一例(技能実習2号 → 特定技能1号)
申請には多岐にわたる書類が必要です。主な書類は以下の通りですが、個別のケースによって追加書類が求められることがあります。
- 在留資格変更許可申請書: 所定の様式に正確に記入したもの。
- 技能実習修了証明書: 監理団体または実習実施機関が発行したもの。
- パスポートおよび在留カード: 有効期限内のもの。
- 特定技能外国人との雇用契約書: 労働条件などが明記されたもの。
- 特定技能外国人支援計画書: 支援内容が具体的に記載されたもの。
- 受入れ企業に関する書類:
- 会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 直近の決算報告書(損益計算書、貸借対照表など)
- 事業内容を証明する資料(会社案内、パンフレットなど)
- 特定技能外国人を受け入れる体制が整っていることを示す資料
- 登録支援機関に関する書類(登録支援機関に支援を委託する場合):
- 登録支援機関との支援委託契約書
- 登録支援機関の登録証明書の写しなど
- その他: 賃貸借契約書(住居)、健康診断書など、個別の状況に応じた書類。
⚠️ 特に注意すべき点として、受入れ企業の体制が特定技能外国人を受け入れる基準を満たしていない場合、申請が不許可となるケースが少なくありません。 事前の準備と確認が非常に重要です。
6. よくあるご質問(Q&A)
Q1. 技能実習で学んだ業種と異なる分野で特定技能として働くことはできますか?
A. 原則としてできません。 特定技能への移行は、技能実習で培った知識や経験を活かすことを前提としています。そのため、技能実習で従事していた分野と「同一」または「関連する分野」での特定技能に限られます。 例えば、農業の技能実習生が介護の特定技能になることは認められません。
Q2. 技能実習を途中で辞めてしまった場合でも特定技能に移行できますか?
A. 原則として不可です。 特定技能への移行の最も重要な条件の一つが、「技能実習2号を良好に修了していること」です。不正行為、失踪、自己都合による途中帰国などがあった場合は、「良好な修了」とは認められず、特定技能への移行は極めて困難となります。
Q3. 特定技能外国人の支援計画は、企業が自ら作成・実施しないといけないのでしょうか?
A. いいえ、必ずしも企業がすべてを行う必要はありません。 特定技能外国人への支援は、出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」に委託することができます。登録支援機関は、支援計画の作成から、生活相談、各種手続きの補助など、包括的な支援を提供します。
7. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
特定技能への移行手続きは、技能実習制度、特定技能制度、労働関係法規、支援制度など、多岐にわたる専門知識と複雑な手続きが絡み合います。一つでも不備があると不許可につながるリスクがあります。
当事務所では、外国人本人と受入れ企業の双方を丁寧にサポートするため、以下のトータルサポートを提供しています。
- 在留資格変更の適否チェック: 申請者の状況や企業の受入れ体制が、特定技能の要件を満たしているか事前に詳細に確認します。
- 必要書類一式の作成・翻訳対応: 入管が求める形式に沿った書類作成、必要に応じた翻訳を行います。
- 特定技能外国人支援計画の作成支援: 企業様や登録支援機関と連携し、適切な支援計画の策定をサポートします。
- 企業側の体制づくりサポート: 特定技能外国人を受け入れる上で企業に求められる体制(労務管理、住居確保など)についてアドバイスし、準備を支援します。
- 出入国在留管理局への申請代理: 複雑な入管への申請手続きを、お客様に代わって行います。
8. 最後に|まずはお気軽にご相談ください
技能実習から特定技能への移行は、外国人労働者にとってはキャリアアップの機会であり、受入れ企業にとっては優秀な人材を確保する上で非常に重要なステップです。しかし、その手続きは専門的で、些細なミスが不許可につながることもあります。
熊本での在留資格変更手続きでお困りでしたら、豊富な実績と専門知識を持つ行政書士法人塩永事務所へ、まずはお気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせた最適なサポートをご提案いたします。
■ お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1丁目9番6号 📞 096-385-9002 📩 info@shionagaoffice.jp
