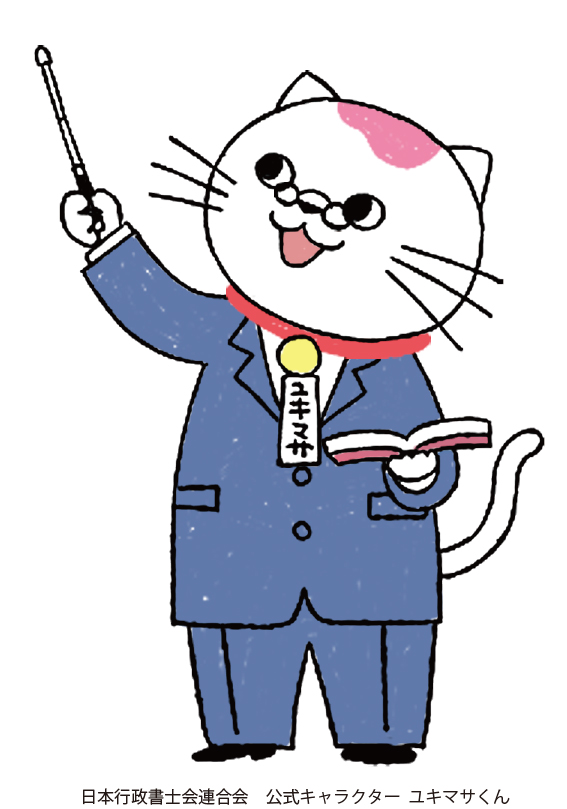
遺産分割とは、亡くなられた方(被相続人)の財産を相続人全員で話し合い、誰がどの財産を引き継ぐかを決める手続きです()。遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合に必要となります。遺産分割協議には、法定相続人全員の参加が必須であり、一人でも欠けると協議は無効となります()。
-
目的: 遺産分割協議に参加すべき法定相続人を正確に特定します。
-
必要書類:
-
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍含む)
-
相続人全員の戸籍謄本
-
-
手続き:
-
本籍地が複数ある場合、各地の市町村役場で戸籍を取得します。遠方の場合は郵送での取り寄せも可能です()。
-
行政書士法人塩永事務所では、職務上請求権を活用し、戸籍謄本の収集を代行します。これにより、相続人様の負担を軽減します。
-
-
目的: 被相続人が所有していた財産(不動産、預貯金、株式など)および負債を把握します。
-
手続き:
-
不動産: 登記事項証明書や固定資産税評価証明書を取得し、所有不動産を確認。
-
預貯金: 金融機関に問い合わせ、口座の有無や残高を確認。
-
その他: 株式、自動車、生命保険(みなし相続財産)なども調査対象。
-
当事務所では、財産目録の作成をサポートし、遺産の全体像を明確化します()。
-
-
内容: 相続人全員で、どの財産を誰がどれだけ相続するかを話し合います。法定相続分と異なる分割も可能です()。
-
注意点:
-
未成年者が相続人に含まれる場合、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります()
-
遠方の相続人がいる場合、書面やオンラインでの協議も可能です()
-
-
成果物: 協議の合意内容を「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印します。印鑑証明書の添付も求められる場合があります()
-
記載内容:
-
被相続人の氏名、死亡日、最後の住所
-
相続人全員の氏名、住所
-
各相続人が取得する財産の詳細(例: 不動産の地番、預貯金の口座番号など)
-
協議日付、相続人全員の署名・実印
-
-
ポイント:
-
遺産分割協議書に有効期限はありませんが、金融機関などでは発行後3~6ヶ月以内の印鑑証明書を要求される場合があります()。
-
当事務所では、書類の形式や内容が法務局や金融機関の要求に適合するよう、正確な作成を代行します。
-
-
概要: 不動産の所有権を相続人名義に変更する手続きで、2024年4月1日より義務化されました。相続開始または遺産分割成立から3年以内に申請が必要です()。
-
必要書類:
-
遺産分割協議書(法定相続分と異なる場合)
-
相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
-
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票
-
不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書
-
登記申請書(法務省の様式に基づく)
-
-
費用:
-
登録免許税: 固定資産税評価額の0.4%(例: 評価額4,000万円の場合、16万円)()
-
司法書士報酬: 3万~12万円程度(当事務所では提携司法書士をご紹介可能)
-
書類取得費用: 戸籍謄本等で約5,000円(
-
-
手続きの流れ:
-
必要書類を収集し、登記申請書を作成。
-
不動産を管轄する法務局に提出。
-
書類に不備がなければ、1~2週間で登記完了()。
-
-
当事務所のサポート: 戸籍収集から登記申請書の作成、司法書士との連携まで一括代行します。
-
概要: 被相続人名義の口座は死亡確認後に凍結され、遺産分割協議書に基づいて解約または名義変更を行います()。
-
必要書類:
-
遺産分割協議書
-
相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
-
被相続人の戸籍謄本、住民票の除票
-
金融機関指定の相続手続き依頼書
-
通帳、キャッシュカード()
-
ポイント:
-
遺産分割前でも、葬儀費用等のために一定額の払戻しが可能な制度があります()。
-
当事務所では、金融機関ごとの書類要件を確認し、迅速な手続きを代行します。
-
-
-
株式:
-
証券会社に相続手続きを依頼。相続人用の証券口座開設が必要な場合があります()。
-
必要書類は預貯金と同様で、遺産分割協議書が中心。
-
-
自動車:
-
運輸支局で名義変更。車検証、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書等が必要。
-
-
当事務所のサポート: 多岐にわたる財産の名義変更手続きを一括で管理し、相続人様の負担を最小限にします。
-
ワンストップサービス: 戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書の作成、名義変更手続きまで一貫して対応。
-
専門家連携: 司法書士や税理士と連携し、相続登記や相続税申告もスムーズに処理。
-
全国対応:
-
負担軽減: 相続人様が役所や金融機関に足を運ぶ必要なく、書類収集から提出まで代行()。
-
無料相談: 初回相談は無料で、相続の全体像や必要手続きを丁寧にご説明します。
-
相続登記の義務化: 2024年4月1日以降、相続開始または遺産分割成立から3年以内に登記申請が必要です。違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります()。
相続税申告: 相続開始から10ヶ月以内に申告・納付が必要です()。当事務所では税理士をご紹介し、申告をサポート。
-
-
早期手続きの重要性: 時間が経過すると数次相続が発生し、権利関係が複雑化する恐れがあります()。
-
連絡先: [096-385-9002] / [info@shionagaoffice.jp]
-
受付時間: 平日9:00~18:00
行政書士法人塩永事務所は、相続手続きの「かかりつけのホームドクター」として、皆様の安心をサポートします()。
