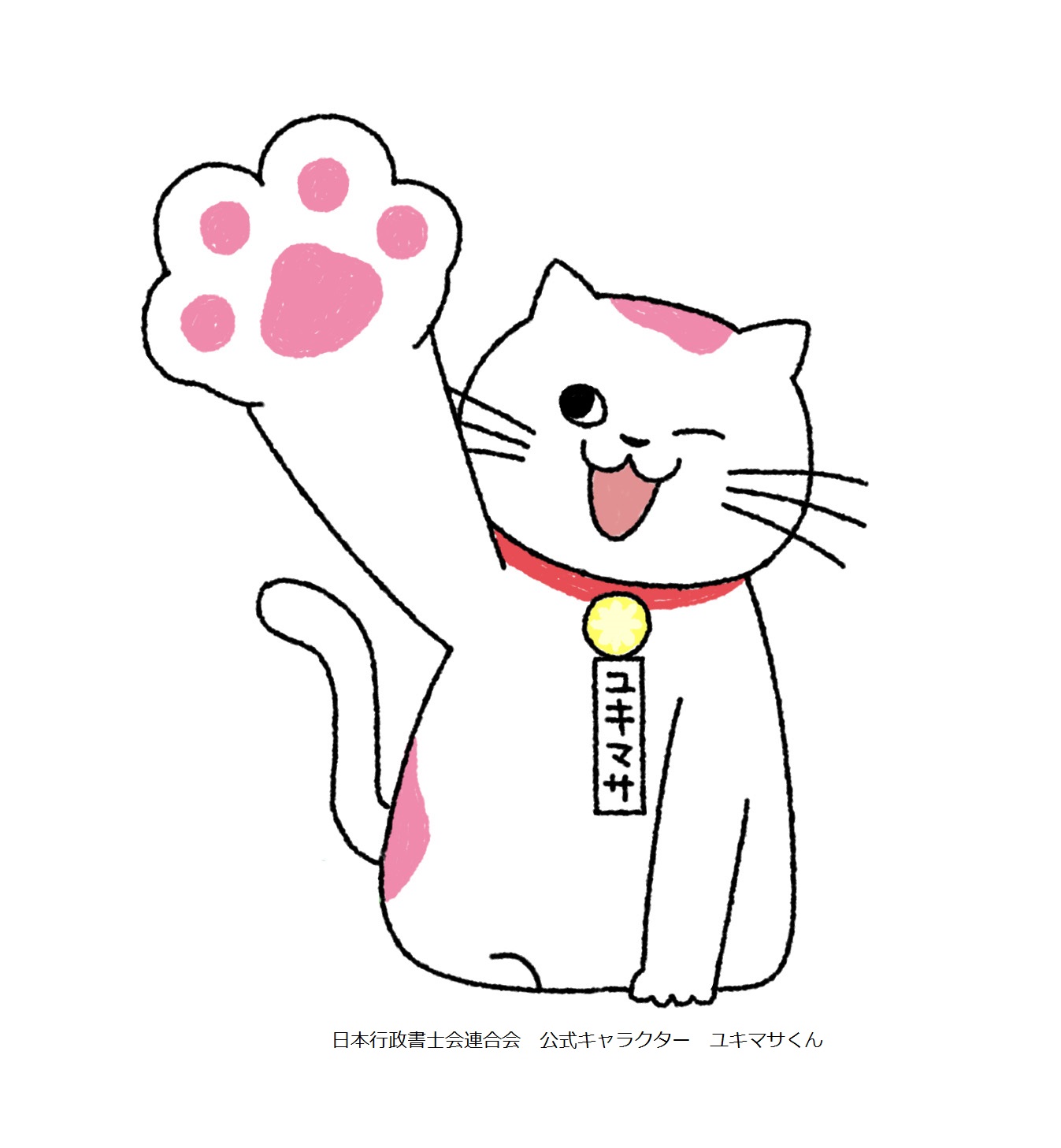
【保存版】建設業許可申請の完全ガイド|行政書士法人塩永事務所
こんにちは。熊本県の行政書士法人、行政書士法人塩永事務所です。
当事務所では、幅広いお客様の建設業許可申請をサポートしています。
建設業許可は、単なる「許可」ではありません。
それは貴社の社会的信用を高め、より大きな受注チャンスを掴み、事業拡大へと導くための経営基盤の一部です。
この記事では、建設業許可の基礎知識から制度の背景、許可要件、具体的な申請方法、注意点、そして許可取得後のフォロー体制に至るまで、6000文字超の完全解説を行います。
1. 建設業許可とは?制度の目的と必要性
建設業は、一般的な業種と異なり、公共性が高く、専門性・安全性が問われる分野です。そのため、法律(建設業法)により一定の条件を満たさなければ事業を営めない仕組みになっています。
■ 許可が必要なケース
建設工事の請負において、以下の金額を超える工事を1件でも受注する場合には、建設業許可が必要です。
-
建築一式工事:1件あたり1,500万円以上(木造住宅は延床面積150㎡以上)
-
その他の工事:1件あたり500万円以上
※消費税を含む金額です。
■ 許可がないとどうなる?
-
上記の金額を超える工事を請け負うことができない
-
元請やゼネコンとの取引に参加できない
-
公共工事や入札に参加できない
-
社会的信用が低下し、金融機関や取引先からの評価が下がる
つまり、許可を持っていないことが事業拡大の障壁になるのです。
2. 建設業許可の種類と業種
■ 許可の区分:知事許可と大臣許可
| 区分 | 営業所の所在地 | 対象事業者 |
|---|---|---|
| 知事許可 | 1つの都道府県内 | 熊本県のみなど |
| 国土交通大臣許可 | 複数の都道府県に営業所がある | 熊本+福岡など |
熊本県内のみで営業している事業者は「熊本県知事許可」が対象です。
■ 許可の区分:一般建設業と特定建設業
| 区分 | 工事の内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 一般建設業 | 元請または下請で、下請契約が4,000万円未満 | 中小建設業者 |
| 特定建設業 | 元請として、下請契約総額が4,000万円以上 | 大規模工事・JV等 |
■ 建設業の業種分類(全29業種)
建設業許可は、業種ごとに取得する必要があります。主な業種は以下のとおりです:
-
建築一式工事
-
土木一式工事
-
とび・土工・コンクリート工事
-
電気工事
-
管工事
-
塗装工事
-
内装仕上工事 など全29業種
それぞれの工種ごとに専任技術者などの要件があります。
3. 建設業許可を取得するための5要件
① 経営業務の管理責任者(経管)
企業としての経営体制が整っていることを証明するため、「経営業務の管理責任者(通称:経管)」の設置が必要です。
要件(いずれかを満たす必要)
-
許可業種に関して5年以上の経営経験(個人・法人役員等)
-
許可業種以外の経験でも、他条件と組み合わせることで認定されるケースあり
-
近年の法改正により「補佐経験」「共同体制」でも一部要件緩和あり
② 専任技術者
営業所ごとに1名以上の専任技術者を配置する必要があります。
要件
-
該当業種の実務経験10年以上
-
国家資格(例:一級建築士、施工管理技士 等)
-
指定学科の学歴+3~5年の実務経験
現場の責任者というよりは、技術力の「証明者」として位置づけられます。
③ 財産的基礎
適正に工事を遂行する財務的な裏付けが求められます。
| 許可区分 | 財産要件 |
|---|---|
| 一般建設業 | 自己資本500万円以上 or 直近5営業日平均で500万円以上の預金残高 |
| 特定建設業 | 資本金2,000万円以上+自己資本4,000万円以上等、厳格な要件 |
※残高証明での立証は、タイミングや形式を誤ると審査で否認されます。
④ 誠実性
過去に不正・違法行為がないかを審査されます。
-
建設業法違反、詐欺・背任などの経歴がないこと
-
暴力団関係者が役員・株主等に含まれていないこと
⑤ 欠格要件に該当しないこと
以下のいずれかに該当すると、許可取得はできません。
-
破産手続中(免責前)
-
禁固以上の刑罰から5年以内
-
許可取消処分から5年以内
役員全員が対象となるため、共同経営の場合は慎重にチェックが必要です。
4. 建設業許可の申請手続き|フローと期間
■ 許可取得までのステップ
-
要件確認・無料診断(塩永事務所で対応)
-
必要書類の収集
→ 登記簿謄本、納税証明書、資格証明、工事実績資料、決算書など -
書類作成・チェック(専門家のノウハウが重要)
-
県庁・国交省への申請提出
-
審査(約30~45日)後、許可証交付
■ 所要期間
-
通常:約1~2ヶ月程度
-
書類準備が整っていれば、最短1ヶ月での取得も可能です。
5. 建設業許可取得の落とし穴と注意点
■ よくある失敗例
-
実務経験の立証資料が不十分
-
資本金・残高証明のタイミングが不適切
-
書類の記載ミス・押印漏れ
-
必要書類の「写し」の不備(行政庁の指定書式があることも)
■ こんなケースに注意!
-
親族経営で代表者と役員が同一人物 → 経管と技術者の兼任ができない
-
技術者の資格が別業種 → 許可業種とマッチしないため不受理になる
-
合併・分割・相続などでの継承手続が漏れている
建設業許可の申請には、法律知識+実務経験+行政対応力が必要不可欠です。
6. 許可取得後の義務・メンテナンス
■ 許可を維持するための主な手続
-
【毎年】事業年度終了報告(決算変更届)
-
【5年ごと】許可更新申請(更新を忘れると失効)
-
【随時】役員・技術者・営業所等の変更届
-
【業種追加】新たな工事を始める際は追加申請が必要
これらの届出を怠ると、「営業停止」「許可取消」のリスクが生じます。
7. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
私たちは、熊本県内最多の行政書士職員数を誇り、以下のようなフルサポート体制を整えています。
■ 初回相談・要件診断無料
経験豊富な専門スタッフが、現状を丁寧にヒアリング。取得可能性を正確に診断します。
■ 書類作成から提出代行までワンストップ
複雑な申請書類・証明書・補足資料まで、全てプロが代行・チェック。
■ 許可後の更新・追加申請にも継続対応
1年ごとの事業報告や、5年更新もお任せください。契約継続率も非常に高く、多くの建設業者様に長期的に信頼いただいています。
■ 複数業種・大臣許可・特定建設業の対応も可
高度な許可申請や複雑な組織変更、JV対応なども実績多数。
8. 熊本の建設業者の皆さまへ|許可取得は信頼の第一歩
建設業許可を取得することは、単に「条件を満たす」ということではなく、
「社会的信用を得て、継続的・健全な経営を行う」という事業者の覚悟の表れです。
行政書士法人塩永事務所は、建設業に特化した専門部門を設け、これまで数百件に及ぶ許可申請をサポートしてきました。
-
地域密着型の手厚い対応
-
熊本県庁・国交省との豊富な対応実績
-
他士業との連携によるワンストップサービス
安心してお任せください。
お問い合わせ・ご相談はこちら
建設業許可の取得をお考えの方、すでに許可をお持ちで更新や業種追加を検討中の方も、まずはお気軽にご相談ください。
📞【096-385-9002】
🌐【公式ホームページお問い合わせフォーム info@shionagaoffice.jp】
行政書士法人塩永事務所は、あなたの建設業経営を全力でサポートいたします。
