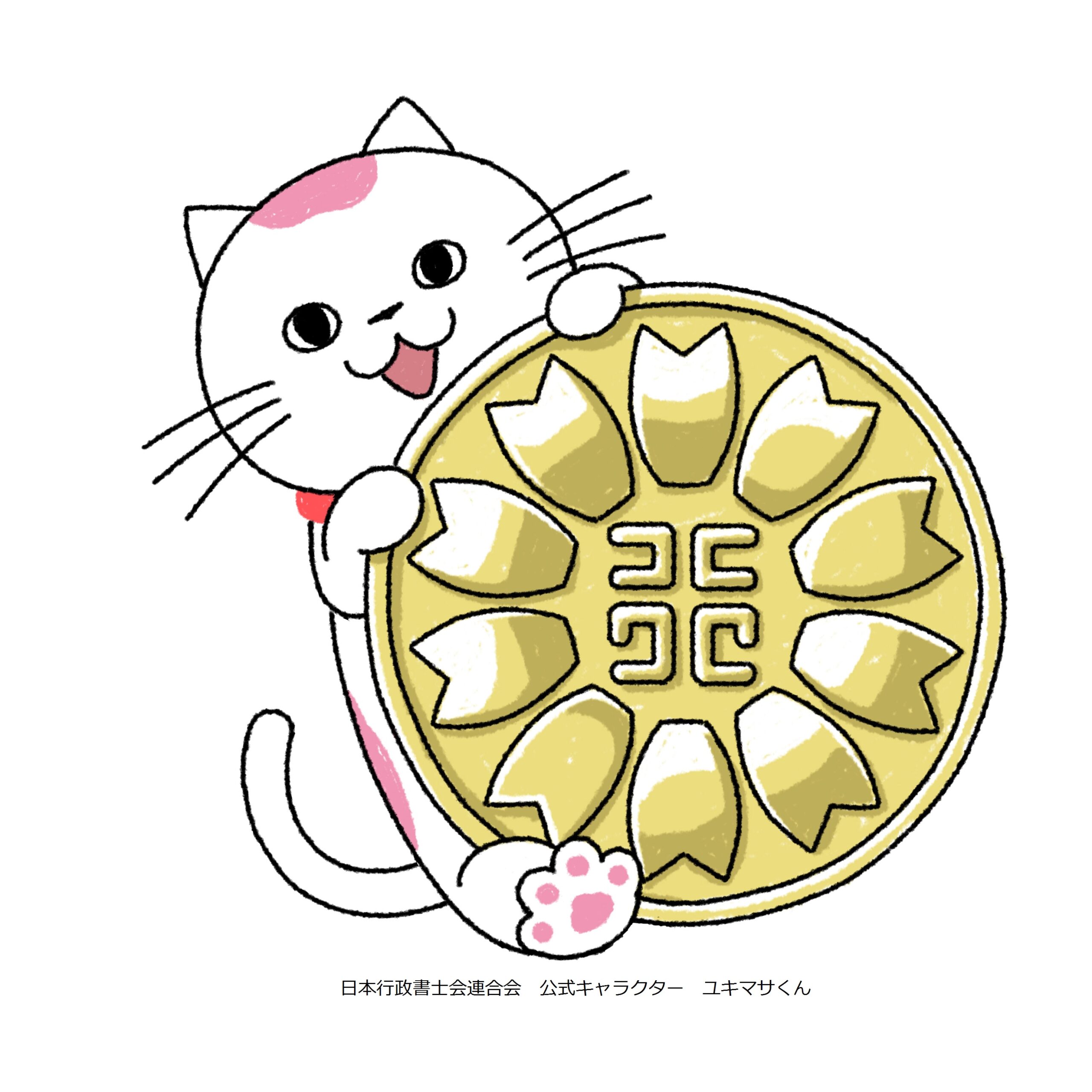
一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業は、トラックなどの車両を用いて、他人の貨物を有償で運送する事業です。この事業を営むには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受ける必要があります。
許可取得のための要件
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 人的要件
-
役員:欠格事由に該当しないこと。
-
運行管理者:営業所ごとに必要な人数を選任し、運行管理者資格者証の交付を受けていること。
-
整備管理者:資格要件を満たした者を選任すること。
-
運転者:車両数以上の運転者を確保し、日雇いや短期雇用者を除くこと。
2. 物的要件
-
営業所:使用権限を有し、関係法令に適合していること。
-
休憩・仮眠施設:営業所または車庫に併設し、1人当たり2.5㎡以上の面積を確保すること。
-
車庫:営業所に併設または直線距離で10km以内に設置し、関係法令に適合していること。
-
車両:軽自動車を除く5台以上の車両を確保し、使用権限を有すること。
3. 財産的要件
-
資金計画:車両費、建物費、土地費、保険料、各種税、運転資金などを含む、合理的かつ確実な資金計画を策定すること。
-
資金調達:自己資金や預貯金など、資金調達の裏付けが求められる。
-
損害賠償能力:対人賠償保険は無制限、対物賠償保険は200万円以上の任意保険に加入すること。
4. 法令試験の合格
法人の場合は常勤役員のうち1名、個人事業主の場合は本人が、法令試験に合格する必要があります。
-
試験内容:貨物自動車運送事業法をはじめとする13の法令が対象です。
-
合格率:過去の合格率は50~80%程度です。
-
受験回数:1回の申請で試験を受けられるのは2回までです。
許可申請の手続き
一般貨物自動車運送事業の許可申請手続きは、以下のステップで進められます。
1. 申請書類の準備
-
事業計画書:現実的かつ実行可能な内容で作成します。
-
必要書類:営業所や車庫の図面、資金計画書、任意保険の証明書など、多岐にわたる書類を準備します。
2. 申請書の提出
管轄の運輸支局に申請書類を提出します。
3. 審査期間
申請から許可が下りるまでの期間は、通常4~5ヶ月程度です。
4. 法令試験の受験
申請後、指定された日時に法令試験を受験します。
5. 許可証の交付
審査に合格し、法令試験に合格すると、許可証が交付されます。
許可取得後の手続き
許可を取得した後、事業を開始するまでに以下の手続きを行う必要があります。
1. 運行管理者・整備管理者の選任届出
資格を有する者を選任し、運輸支局に届出を行います。
2. 運送約款の認可
標準約款以外を使用する場合は、認可を受ける必要があります。
3. 車両登録と緑ナンバーの取得
事業用自動車等連絡書を運輸支局へ提出し、営業ナンバー(緑ナンバー)への変更を行います。
4. 自動車保険の変更
自賠責保険・任意保険ともに事業用に変更する手続きが必要です。
5. 運賃・料金の設定届出
運賃料金表を作成し、届出を行います。
6. 労働基準監督署への届出
従業員が10名以上の場合は就業規則の作成・届出が必要です。また、時間外労働を行う場合は、36協定を締結して届出を行います。
7. 運転者の適性診断
運転者全員が「運転者適性診断」を受診する必要があります。
8. 社会保険への加入
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の加入手続きを行います。
9. 運輸開始届の提出
変更後の車検証の写し等を添えて、運輸支局へ届出を行います。許可取得後1年以内に運輸開始届を提出しない場合、許可が失効します。
10. 巡回指導
運輸開始届提出後6ヵ月以内に、適性化実施機関による巡回調査があります。帳票類が整備されていない、申請と違うなどの場合には行政処分の対象となります。
まとめ
一般貨物自動車運送事業の許可取得には、複数の要件を満たす必要があり、申請手続きも複雑です。行政書士法人塩永事務所では、これらの手続きを専門的にサポートし、スムーズな許可取得をお手伝いいたします。
運送業界の最新動向や法改正にも対応し、許可取得後のフォローアップも万全です。新たに運送業を始めたい方や、許可取得に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。
