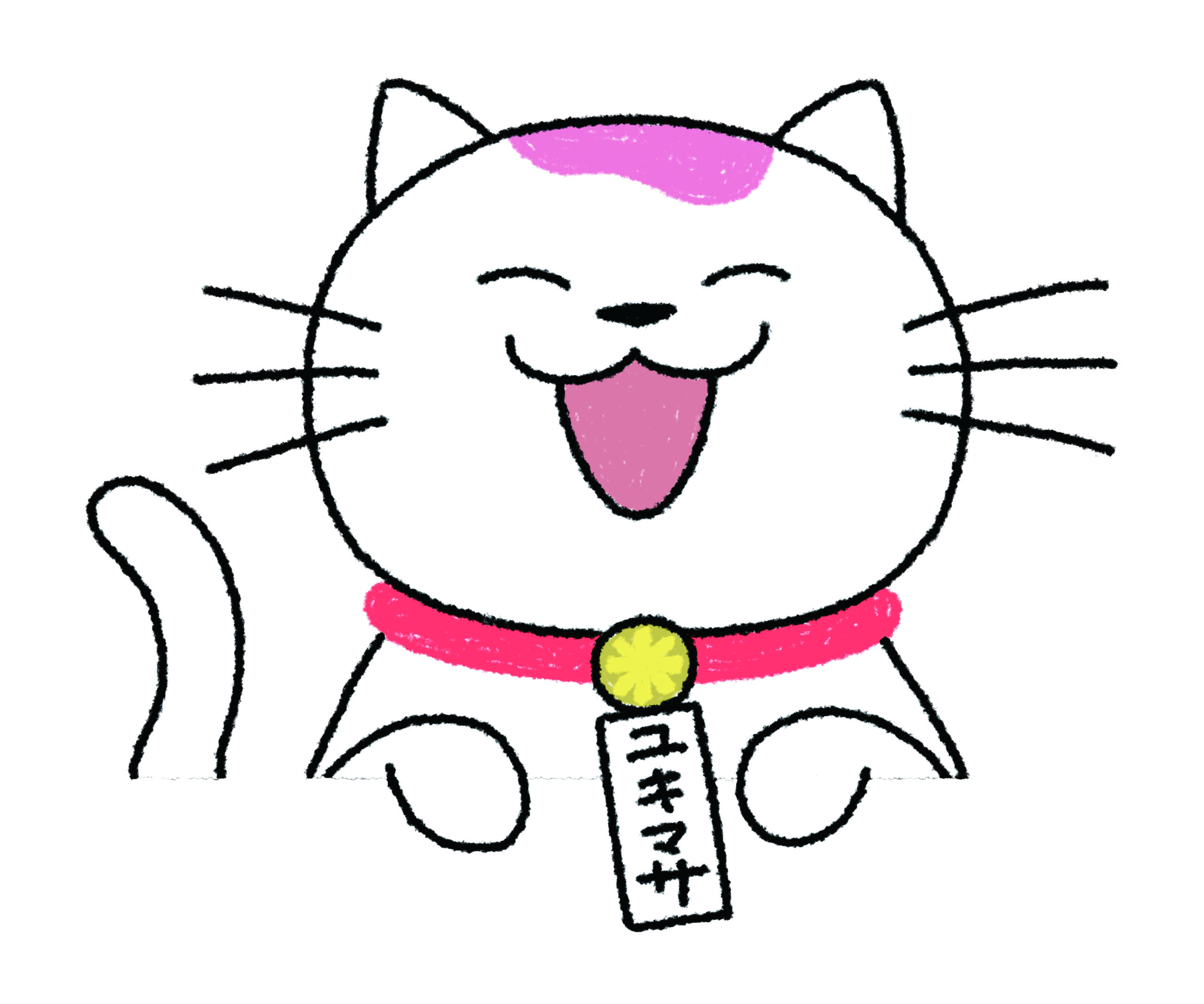
建設業許可申請に関する実務解説
―行政書士法人塩永事務所―
1. 緒言
建設業は、社会インフラの整備や地域経済の発展を支える基幹産業であり、その健全な発展のためには、法令遵守と適切な許可制度の運用が不可欠である。建設業法に基づく建設業許可制度は、一定規模以上の建設工事を請負う者に対し、その技術的能力・財務的基盤・法令遵守体制を審査し、業としての適格性を確認するためのものである。本稿では、建設業許可申請に関する要件、手続、及び関連実務について、専門的な観点から解説する。
2. 建設業許可制度の概観
2.1 許可の分類
建設業許可は、その事業規模及び営業範囲に応じ、下記の二軸により分類される。
(1) 許可の区分(一般・特定)
-
一般建設業許可
下請負契約の総額が原則として4,000万円(建築一式工事は6,000万円)未満の工事を元請として請負う場合に必要。 -
特定建設業許可
上記金額以上の工事を元請として受注し、かつ複数の下請業者に再委託する場合に必要。
(2) 許可の種別(知事・大臣)
-
都道府県知事許可:営業所が一つの都道府県内のみに所在する場合。
-
国土交通大臣許可:営業所が二以上の都道府県に所在する場合。
3. 許可申請における必要要件
建設業許可を新規取得するにあたっては、以下の5要件をすべて満たさねばならない。
3.1 経営業務の管理責任者(経管)要件
過去5年以上、建設業における経営業務の管理的地位にあった者が、申請者の役員等に就任している必要がある。2020年10月の制度改正により、一定の補助的立場での管理経験も評価対象とされるが、実態としては代表者又は役員としての経歴が強く要請される。
3.2 専任技術者要件
営業所ごとに、下記のいずれかを満たす専任技術者を配置しなければならない。
-
国家資格(例:1級・2級施工管理技士、技術士等)の保有
-
大学・高等専門学校等の所定学科卒業後、3年以上の実務経験
-
学歴不問で10年以上の実務経験
なお、特定建設業許可の場合は、一定の指導監督的実務経験または1級施工管理技士等の資格が必要。
3.3 財産的基礎
-
一般建設業の場合
自己資本額500万円以上、または金融機関からの融資証明により同等の資金調達能力を証明することが必要。 -
特定建設業の場合
資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上に加え、直前5年以内に欠損が生じていないこと等の条件を満たす必要がある。
3.4 誠実性要件
請負契約の履行に関して不正又は不誠実な行為を行った実績がないこと。過去に重大な瑕疵工事や公的契約における違約等がある場合は審査対象となる。
3.5 欠格事由の不存在
暴力団関係者、破産者(復権していない者)、禁固以上の刑を受けた者等が、申請者または役員等に含まれていないこと。
4. 建設業許可申請の実務手続
4.1 申請に必要な書類
建設業許可の申請に際しては、以下の主要書類を含む多数の添付資料を準備する必要がある。
-
許可申請書(様式第1号)
-
経営業務の管理責任者証明書
-
専任技術者証明書
-
財務諸表(直近2期分)
-
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
-
納税証明書(法人税、所得税、消費税)
-
営業所の使用権限を証する書類(賃貸契約書等)
4.2 審査期間と標準処理期間
申請書提出後、都道府県における標準処理期間は通常4週間〜6週間程度。審査は形式・実質両面から行われ、不備がある場合は再提出・補正が求められる。
4.3 手数料
-
新規申請(知事許可):90,000円
-
更新申請:50,000円
-
業種追加申請:50,000円
※別途、行政書士報酬が必要。
5. 許可取得後の義務
建設業許可取得後も、以下の法定義務が継続的に課される。
5.1 年次報告(決算変更届)
事業年度終了後、4か月以内に「事業報告書」等の提出が義務付けられている。提出を怠ると、更新審査に支障を来す場合がある。
5.2 変更届
代表者・役員・営業所・資本金等に変更が生じた際は、原則として30日以内に変更届を提出する必要がある。
5.3 更新手続
許可の有効期間は5年間であり、引き続き業を継続する場合は、有効期限満了の30日前までに更新申請を行う必要がある。
6. おわりに
建設業許可制度は、建設業者の健全性と技術的信頼性を担保する制度であり、事業の対外的信用力を高める上でも重要な法的基盤となる。行政書士法人塩永事務所では、熊本県内を中心に、建設業許可に関する新規申請・更新・変更・相談対応を一括して行っており、制度改正動向も踏まえた実務的支援を行っている。許可取得をご検討中の事業者様は、ぜひ当事務所にご相談いただきたい。
