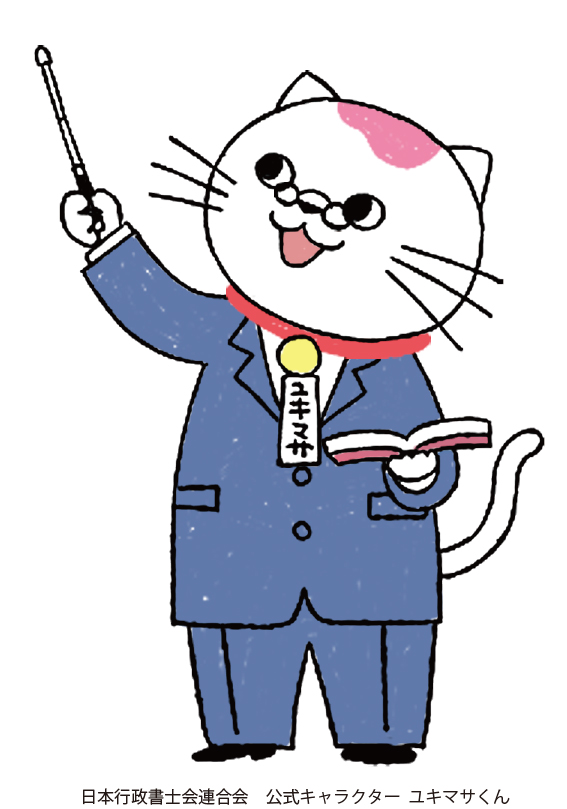
最終更新日:2025年5月7日
厚生労働省の最新データによると、2022年の日本の離婚率は人口1,000人あたり1.47件であり、2019年以降3年連続で減少傾向にあります。同年に登録された離婚件数は約179,000件で、2013年の約231,400件から大幅に減少しています。一方、2023年には離婚率が前年比で約2%上昇したとの報告もあり、ポストコロナの社会変化が影響している可能性が指摘されています。
特に注目すべきは、20年以上連れ添った夫婦の離婚(いわゆる「熟年離婚」)の割合が過去最高を記録している点です。2022年の統計では、離婚全体の23.5%(約38,991件)が20年以上の婚姻期間を経たカップルによるもので、1947年の統計開始以来最高の割合です。この背景には、平均寿命の延伸による夫婦の長期同居期間の増加や、子育て終了後の価値観の相違が挙げられます。
また、国際結婚の離婚率は日本人同士の結婚よりも高く、2020年時点で日本人と外国人のカップルの離婚率は50.5%に対し、日本人同士は34.9%でした。地域別では、沖縄県が人口1,000人あたり2.36件で離婚率が最も高く、東京都は27.45%と低い傾向にあります。
コロナ禍後の経済的不確実性が、家庭内のストレスを増大させています。失業や収入減少による生活不安が、夫婦間の対立を助長するケースが増加しています()。特に、物価上昇と賃金停滞が続く中、経済的理由での離婚が増える傾向にあります。
女性の社会進出が進み、伝統的な性別役割が変化しています。2023年には、女性の労働参加率の上昇に伴い、経済的自立を背景とした離婚の増加が報告されています。特に若い世代の女性は、従来の「我慢する結婚」から脱却し、自己実現を重視する傾向が強まっています。
かつて離婚は社会的なスティグマを伴いましたが、近年はその意識が薄れ、離婚を選択するハードルが低下しています。特に、若年層や都市部では、離婚を「新たなスタート」と捉える価値観が広がっています。
日本の高齢化が進む中、熟年離婚が増加しています。子供の独立後、夫婦間の価値観の相違や生活スタイルの不一致が顕在化し、離婚に至るケースが多いです。また、2007年の法改正により、離婚後の妻が夫の企業年金の50%を受け取れるようになったことも、熟年離婚の増加要因とされています。
離婚手続きにおいて、離婚協議書は夫婦間の合意内容を明確化し、将来の紛争を予防する重要な文書です。日本では、離婚の約90%が協議離婚(相互合意による離婚)であり、離婚協議書の作成が一般的です。以下に、離婚協議書の主要な役割を解説します:
子を持つ夫婦の場合、親権者や養育費の支払い条件を明確に定める必要があります。日本では、離婚後の親権は原則として一方の親に付与され、母親が親権を得るケースが約75%を占めます。養育費の支払い義務は法的にも明確ですが、離婚協議書に金額や支払い期間を明記することで、履行の確実性を高めます。
-
法的正確性:民法や家事事件手続法に基づき、適法な内容で作成する必要があります。曖昧な表現や法的に無効な条項は、将来の紛争の原因となります。
-
双方の合意:協議離婚は夫婦の合意が前提であり、強制や脅迫による合意は無効です。公正な話し合いを基に作成することが求められます。
-
将来の変更可能性:子供の成長や経済状況の変化に伴い、養育費等の見直しが必要な場合があります。こうした柔軟性を考慮した条項の設定が重要です。
-
専門家の関与:行政書士や弁護士等の専門家によるチェックを受けることで、法的リスクを最小限に抑えられます。
-
政策対応:政府は、離婚増加に伴う単親家庭の経済的負担を軽減するため、養育費の履行確保策や就労支援の強化を検討しています。2025年には、共同親権制度の導入議論が進展する可能性があり、離婚協議書の作成にも影響を与えるでしょう。
-
ワークライフバランスの改善:長時間労働や経済的ストレスが離婚の一因となる中、企業や政府によるワークライフバランス施策が、家庭の安定に寄与する可能性があります。
-
高齢者向け支援:熟年離婚の増加に伴い、離婚後の高齢者の生活支援や再就職支援が求められています。
行政書士法人塩永事務所
〒[熊本市中央区水前寺1-9-6]
電話:[096-385-9002]
メール:[info@shionagaoffice.jp]
