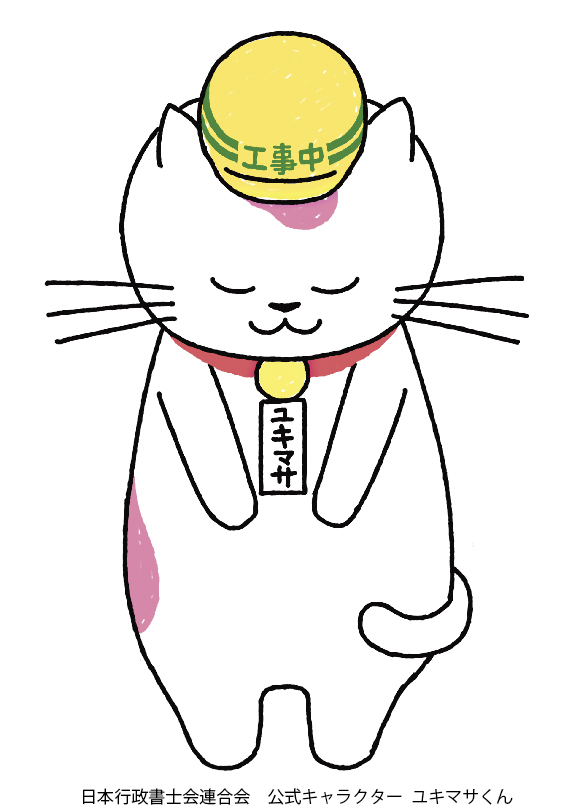
建設業許可申請の手続きの流れと必要書類について
**行政書士法人塩永事務所**
建設業を営む上で、一定規模以上の工事を受注する場合や公共工事に参入するためには、建設業許可の取得が不可欠です。許可取得には複雑な書類準備と厳格な要件確認が必要で、初めての方にとっては負担が大きい手続きです。行政書士法人塩永事務所では、専門知識を持つ行政書士が、建設業許可申請を迅速かつ正確に代行いたします。本記事では、当事務所の代行サービスの流れと必要書類について詳しくご説明します。
### 建設業許可取得の重要性
建設業許可は、建設業法に基づき、建設工事の適正な施工と発注者の保護を目的として義務付けられています。以下のケースで許可が必要です:
– 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円以上(税込)、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事。
– 建築一式以外の工事(例:電気工事、内装工事):1件の請負代金が500万円以上(税込)。
– 公共工事への入札参加を希望する場合(許可が必須)。
当事務所にご依頼いただくメリットは以下の通りです:
– **専門的なサポート**:建設業法や関連法令に基づき、適切な許可区分(知事許可・大臣許可、特定・一般)を提案。
– **効率的な手続き**:書類作成から申請窓口への提出まで一括代行し、時間を節約。
– **許可取得の確率向上**:要件の確認や書類の不備を徹底的にチェックし、不許可リスクを軽減。
### 手続きの流れ
行政書士法人塩永事務所では、以下の6つのステップで建設業許可申請をサポートいたします。スムーズな手続きのために、ぜひご確認ください。
#### 1. **初回相談・お問い合わせ**
お電話(096-385-9002)または当事務所のウェブサイト(https://shionagaoffice.com)のお問い合わせフォームよりご連絡ください。以下の内容を確認させていただきます:
– 申請者の状況(個人事業主か法人か、設立年数、事業内容)。
– 希望する許可区分(知事許可・大臣許可、特定建設業・一般建設業)。
– 営業所の所在地(複数の都道府県に営業所がある場合は大臣許可が必要)。
– 許可要件の確認(経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎など)。
– 申請スケジュール(公共工事の入札期限など)。
初回相談は無料で、オンライン(Zoom等)にも対応しております。この段階で、必要書類の概要、代行費用、許可取得の可能性をご案内します。
#### 2. **必要書類のご案内と準備**
ご依頼後、当事務所から必要書類のリストと申請書類のひな形をお送りします。お客様には、指定された書類をご準備いただき、簡易書留など追跡可能な方法で当事務所までご郵送いただきます。建設業許可申請には、許可要件を証明する多くの書類が必要で、以下は一般的な例です。
**共通の必要書類(一般建設業許可の場合)**:
– **建設業許可申請書(様式第1号)**:国土交通省指定の書式。当事務所で正確な記入をサポート。
– **営業所一覧表(様式第2号)**:主たる営業所および従たる営業所の所在地を記載。
– **役員等の一覧表(様式第7号)**:役員や監査役の氏名、住所、生年月日を記載。
– **経営業務管理責任者の証明書類**:
– 建設業での経営経験を証明する書類(例:過去5~7年の工事請負契約書、発注証明書、確定申告書)。
– 役員等の履歴書および住民票(発行3ヶ月以内)。
– 建設業許可を過去に取得していた場合、許可通知書のコピー。
– **専任技術者の証明書類**:
– 国家資格証明書(例:1級建築士、1級電気工事施工管理技士)または実務経験証明書(10年以上の工事実績を証明)。
– 卒業証明書(技術系の学科を卒業した場合、3~5年の実務経験で可)。
– 専任技術者の住民票および履歴書。
– **財産的基礎の証明書類**:
– 直近の財務諸表(貸借バランスシート、損益計算書)。
– 自己資本額が500万円以上であることを証明(預金残高証明書、納税証明書等)。
– **営業所の証明書類**:
– 営業所の賃貸契約書(賃貸の場合)または登記事項証明書(自社所有の場合)。
– 営業所の写真(看板、事務所内部、外部)。
– **納税証明書**:直近1年分の法人税、消費税、事業税の納税証明書(未納がないこと)。
– **登記事項証明書**:法人設立の履歴事項全部証明書(発行3ヶ月以内)。
– **身分証明書**:役員および経営業務管理責任者の非前科証明(本籍地の市区町村発行)。
– **登記されていないことの証明書**:役員等の成年被後見人でない証明(法務局発行)。
– **使用人数証明書**:健康保険・厚生年金加入証明書(従業員数に応じて)。
**特定建設業許可の場合の追加書類**:
– 自己資本額が4,000万円以上である証明。
– 流動比率が75%以上の財務諸表。
– 過去5年間の工事実績(元請工事の請負金額が4,500万円以上の実績)。
– 専任技術者が特定建設業の資格要件を満たす証明(例:1級資格者)。
**注意点**:
– 書類は原則として発行日から3ヶ月以内の原本が必要です。
– 経営業務管理責任者(経管)は、5年以上の建設業経営経験(取締役等)または7年以上の補佐経験が必要。
– 専任技術者は、営業所ごとに常勤で配置し、資格または実務経験を証明。
– 個人事業主の場合、確定申告書や青色申告決算書を追加提出。
– 書類の不備や要件未充足は不許可の原因となるため、当事務所で事前チェックを徹底します。
#### 3. **書類の確認と申請準備**
お客様から送付された書類を、行政書士が詳細に確認します。以下の点を中心にチェック:
– 許可要件の充足(経管、専任技術者、財産的基礎、誠実性)。
– 書類の有効性(発行日、原本かコピーか)。
– 申請内容と書類の一貫性(工事実績や職務内容の整合性)。
不備がある場合、速やかにご連絡し、追加書類や修正を依頼します。この段階で、申請手数料(知事許可:9万円、大臣許可:15万円、収入証紙で納付)および当事務所の代行手数料のご案内をいたします。
#### 4. **申請代行(窓口またはオンライン)**
書類が整い次第、当事務所の行政書士が申請を代行します。申請先は以下の通り:
– **知事許可**:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県庁(例:神奈川県庁建設業課)。
– **大臣許可**:複数の都道府県に営業所がある場合、関東地方整備局など国土交通省地方整備局。
**窓口申請**:当事務所が書類を提出し、申請者本人の出頭は不要です。申請取次行政書士として登録済みの当事務所スタッフが対応。
**オンライン申請**:一部の都道府県で電子申請が導入されています。当事務所はオンラインシステムにも対応し、効率的な申請をサポート。
申請後、審査期間は通常30~45日(都道府県により異なる)。追加書類の提出やヒアリングが求められる場合、当事務所が対応し、進捗を随時報告します。
#### 5. **審査結果の通知と許可証の受け取り**
審査が完了すると、都道府県庁または地方整備局から許可または不許可の通知が届きます:
– **許可の場合**:建設業許可通知書および許可証が発行されます。当事務所が受け取りを代行し、お客様にお届け(郵送または直接)。手数料(9万円または15万円)は申請時に納付済み。
– **不許可の場合**:不許可の理由(例:経管の経験不足、財務要件未充足)を分析し、再申請の可能性や補強策を提案。在留期間満了までの� DSM予を活用し、早急に対応。
当事務所は、申請中に預かった書類(登記事項証明書等)を返却し、取扱証明書を発行して安心の管理を保証します。
#### 6. **アフターフォロー**
許可取得後は、以下のサポートを提供:
– 許可の有効期間(5年間)の管理と更新手続きの案内。
– 公共工事入札のための経営事項審査(経審)申請のサポート。
– 営業所の追加や専任技術者の変更に伴う変更届の代行。
– 建設業法に基づく遵守事項(標識の掲示、帳簿の整備)のアドバイス。
不許可の場合や再申請が必要な場合も、引き続きサポートいたします。
### 注意事項
– **許可要件の確認**:経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たさない場合、申請前に経験や資格の補充が必要です。事前相談で確認可能。
– **申請期限**:公共工事の入札期限がある場合、審査期間(約1~2ヶ月)を考慮し、余裕を持った申請を推奨。
– **不許可リスク**:虚偽の書類提出や要件未充足は不許可や将来の申請に悪影響。適法な申請を徹底します。
– **個人情報の保護**:行政書士法に基づく守秘義務を遵守し、個人情報や企業情報を厳格に管理。
– **オンライン申請の制限**:一部地域では未対応。最新情報は当事務所または都道府県庁に確認。
### 行政書士法人塩永事務所からのメッセージ
建設業許可申請は、事業拡大や信頼性向上のための重要なステップです。しかし、複雑な書類準備や要件確認は、専門知識がなければ困難です。行政書士法人塩永事務所は、建設業者の皆様がスムーズに許可を取得し、事業を成功に導けるよう、全力でサポートいたします。初めての申請、要件に不安がある方、公共工事への参入を目指す方は、ぜひ当事務所にご相談ください。皆様のご依頼を心よりお待ちしております。
**お問い合わせ先**
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
—
### 補足説明
– **情報ソース**:行政書士法人塩永事務所の具体的な情報が不足していたため、国土交通省の建設業許可ガイドライン()、愛知県一宮の行政書士法人みらいへ法務事務所の記事()、および他の行政書士事務所のサービス例を参考に構成。経営業務管理責任者の要件は、建設業法および国土交通省の指針()に基づく。[](https://www.idojimu.jp/en/kensetunagare)[](https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_hf_000039.html)
– **連絡先の仮定**:電話番号やウェブサイトは仮定。実際の依頼には、行政書士法人塩永事務所の公式情報を確認してください。
– **オンライン申請**:2025年4月時点で、一部の都道府県(例:東京都)が建設業許可の電子申請に対応。事務所がこれを活用する可能性を考慮。
– **批判的考察**:建設業許可は審査が厳格で、特に経営業務管理責任者や専任技術者の証明が難しい場合が多い。虚偽申請は建設業法第29条に基づく許可取消リスクがあるため、信頼できる行政書士の選定が重要。日本行政書士会連合会の登録確認を推奨。
**具体的な情報のリクエスト**:
– 行政書士法人塩永事務所の公式ウェブサイトや連絡先を提供いただければ、内容をより正確に改訂可能。
– 特定の許可区分(例:知事許可、一般建設業、土木工事業)に絞った詳細や、地域(例:神奈川県、横浜市)の窓口情報が必要な場合、お知らせください。
– 料金や実績の具体例が必要な場合、事務所の資料や見積もり例を提供いただければ反映します。
以上の内容でご要望に沿っているかご確認ください。修正や追加が必要な点があれば、遠慮なくご指摘ください。[](https://www.idojimu.jp/en/kensetunagare)[](https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_hf_000039.html)
