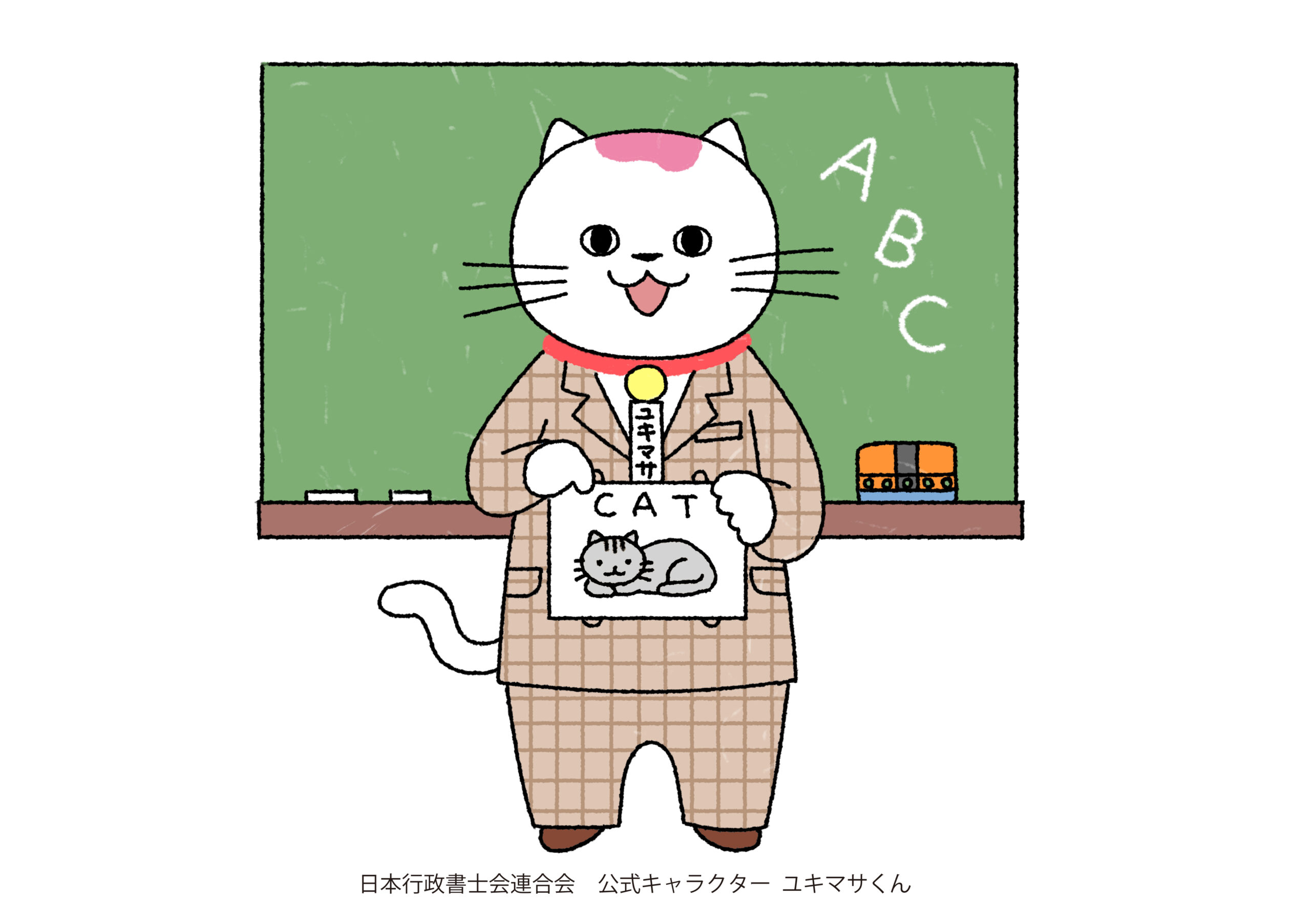
育成就労制度は、外国人材を最長3年間育成し、特定技能1号の水準に到達させることを目標とする在留資格制度です。従来の技能実習制度が「国際貢献」を名目に技能移転を目的としていたのに対し、育成就労制度は日本の産業を支える人材の育成と確保を明確に掲げています。2024年6月14日に「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が可決・成立し、2027年までの施行が予定されています。
監理支援機関は、育成就労制度において、外国人材の受け入れを適切に管理・支援する組織です。技能実習制度における「監理団体」の後継に当たりますが、より厳格な許可要件と強化された監理・支援機能が特徴です。監理支援機関は、受け入れ企業と外国人材の間を取り持ち、制度の適正な運用と外国人材の保護を確保します。
-
国際的なマッチング:海外の送出機関と連携し、適切な外国人材を日本企業に紹介。
-
育成就労計画の支援:受け入れ企業が作成する育成就労計画(育成期間、業務内容、技能・日本語能力の目標等)の策定を支援。計画は法務省の認定を受ける必要あり。
-
監理・指導:受け入れ企業に対し、労働条件や教育環境が法令に適合しているかを監査し、指導を行う。
-
外国人材の支援・保護:生活支援、日本語教育、相談対応、転籍時の調整等を通じて、外国人材の権利を守る。
-
外部監査:外部監査人を設置し、受け入れ企業の法令遵守状況を定期的にチェック。
-
転籍支援:外国人材の意向ややむを得ない事情による転籍が発生した場合、関係機関との連絡調整を担当。
-
許可要件の厳格化:受け入れ企業と密接な関係を持つ役職員の関与が制限され、外部監査人の設置が義務付けられる。
-
支援機能の強化:外国人材の日本語教育や生活支援、転籍時のサポートがより明確に求められる。
-
申請の再手続き:現行の監理団体は自動的に監理支援機関にはなれず、新たに許可申請が必要。
-
優良要件の検討:技能実習制度の優良要件を基盤に、日本語能力修得実績や相談支援体制の評価が追加される方向で検討中。
-
組織の独立性:受け入れ企業との密接な関係(資本関係や役員の兼務等)が制限され、公平な監理が求められる。
-
外部監査人の設置:外部の専門家による監査体制を構築し、受け入れ企業の法令遵守を確保。
-
人員配置:受け入れ企業数に応じた適切な職員数を配置し、十分な監理・支援能力を保持。
-
財務基盤:安定した運営のための財務状況が求められる。
-
実績の評価:日本語教育や技能修得の支援実績、相談支援体制の整備状況が許可の判断基準に含まれる可能性。
-
監理型育成就労:監理支援機関が受け入れ企業と外国人材の間に入り、計画策定、監査、支援を行う。一般的な形態で、派遣形態も可能(特に農業や漁業等の季節性分野)。
-
単独型育成就労:海外の子会社や支店の社員を直接受け入れる形態。監理支援機関の関与は限定的だが、計画の認定や外国人材の保護は必要。
-
育成就労計画の策定:監理支援機関の支援を受け、技能・日本語能力の到達目標を明確にした計画を作成。法務省の認定が必要。
-
コストと負担:監理支援機関への手数料が発生するが、適切な支援により法令違反リスクが軽減。
-
転籍対応:外国人材の意向ややむを得ない事情による転籍が可能となり、監理支援機関が調整を支援。
-
優良基準:優良な受け入れ機関として認定されると、受け入れ人数枠の拡大等のメリットが検討中。
-
保護の強化:監理支援機関による生活支援や相談対応が充実し、過度な手数料の負担が制限される。
-
転籍の柔軟性:本人の意向や職場環境の悪化等による転籍が認められ、キャリアの選択肢が拡大。
-
キャリアアップ:3年間の育成を経て特定技能1号への移行が可能となり、長期就労の道が開ける。
-
監理支援機関の許可申請支援:必要書類の作成、申請手続きの代行、要件適合性の事前チェック。
-
育成就労計画の策定支援:受け入れ企業向けに、法令に適合した計画の作成と認定申請をサポート。
-
法改正対応コンサルティング:制度の最新情報を提供し、技能実習制度からの移行を円滑に支援。
-
外国人材の在留資格手続き:育成就労や特定技能への移行に伴う在留資格申請の代行。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
ウェブサイト:https://shionagaoffice.jp
