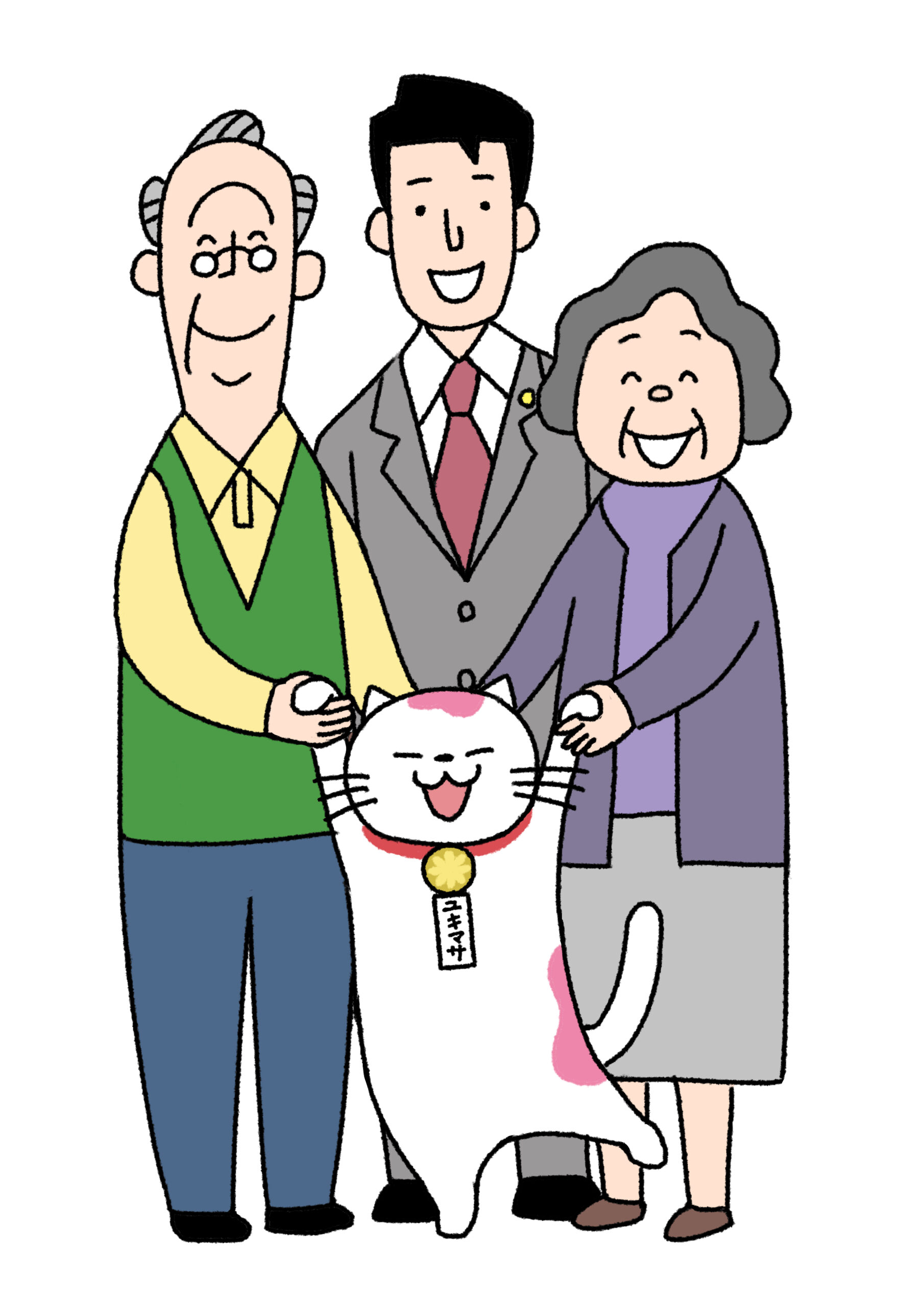
遺言とは
行政書士法人塩永事務所
遺言は、相続手続きの際のトラブルを防ぐ有効な手段の一つとして注目されています。法定相続分よりも遺言による相続分が優先されるため、自分の財産を誰にどのように相続させるのか、最終的な意思を自由に決めることができます。行政書士等の専門家の手助けを受けながら遺言書を作成すれば、遺言者の意思を明確にした法的に有効な遺言書を残すことができ、相続争いを防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることが可能になります。
また、付言として、法的に効力のある内容のほかに、相続人に向けたメッセージを残すこともできます。行政書士法人塩永事務所では、遺言書を作成するに至った経緯や遺産分割の理由、遺された家族へのメッセージなど、遺言者の意向を詳細に聞き取り、付言を有効に活用することで、相続時のトラブルを最小限に抑える遺言書の作成を支援します。
法的に効力のある遺言の内容は民法に定められており、遺言のメインの内容となる財産の分け方を決めることができます。法定相続分にとらわれずに、相続人の中の誰にどのように分配するかを自由に決めることができるほか、相続権のない人や法人にも財産を分ける「遺贈」も可能です。
また、子の認知、後見人の指定など、身分に関わることも遺言で決めることができます。ただし、すべての希望が法的に実現されるわけではなく、例えば「葬儀をこうしたい」といった希望は附言事項として記載します。
相続人間で財産の所有が決まっていたとしても、第三者に対してその相続不動産を単独で主張することはできません。遺言は必ず書面で作成する必要があり、法的に効力を持たせるためには、所定の要件を満たす必要があります。要件を欠いた遺言は無効になる場合があるため、行政書士等の専門家の助言を受けることをお勧めします。
遺言書作成のススメ
以下のようなケースでは、遺言書の作成が特に推奨されます。
1. 子供がいない場合
配偶者に財産をすべて相続させたい場合、その旨を遺言書に明記しましょう。被相続人の祖父母には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書があれば配偶者が全財産を相続できます。
2. 相続人がいない場合
相続人がいない場合、財産は国庫に帰属します。自分の財産を社会のために役立てたい場合は、遺言書で遺贈先を指定しましょう。
3. 相続関係が複雑な場合
再婚していて先妻との間に子供がいるなど、相続関係が複雑な場合は、遺言を残すことで後のトラブルを防げます。
4. 相続人の中で財産を相続させたくない人がいる場合
相続人を排除するには、著しい非行などの相当な理由が必要で、家庭裁判所への申し立てが必要ですが、遺言に理由を明記しておくことで、有力な証拠となります。
行政書士法人塩永事務所に、遺言書作成の起案や遺言書の作成をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。
