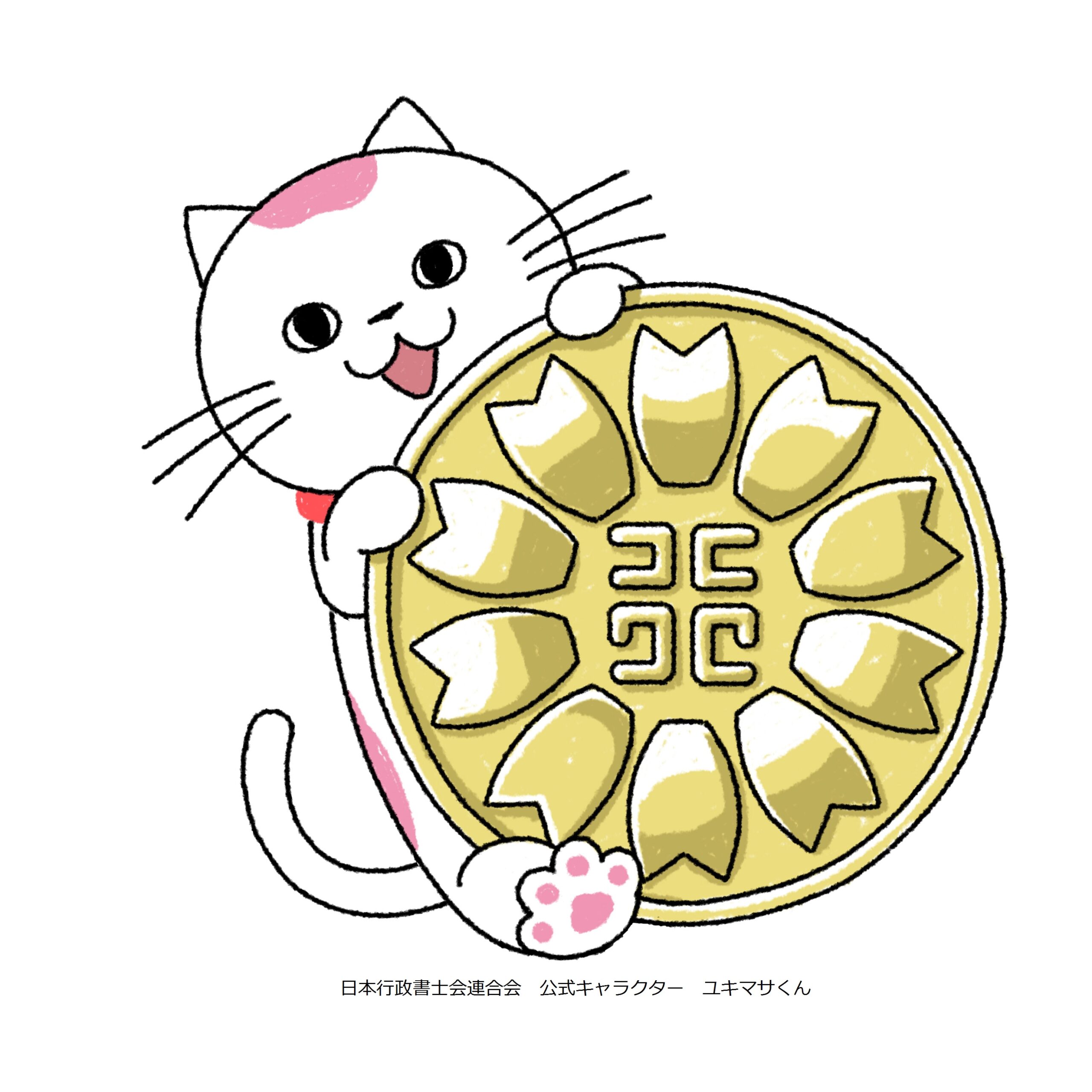
永住許可申請の完全ガイド
永住許可申請とは
永住許可申請とは、外国籍のまま日本に永住することができる「永住者」の在留資格を取得するための手続きです。出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条に基づき、法務大臣が裁量により許可を行います。
「永住者」の在留資格の特徴
1. 在留期間の制限がない
在留期間の更新手続きが不要となり、在留期限を気にすることなく日本に滞在できます。
2. 就労活動の制限がない
職種や業種に制限なく、どのような仕事にも就くことができます。転職の際も入管への届出は不要です。
3. 社会的信用が高まる
住宅ローンの審査や融資を受ける際に有利になります。また、身元保証人としても認められやすくなります。
4. 日本国籍は取得しない
帰化とは異なり、母国の国籍を保持したまま日本に永住できます。母国への帰国や再入国も可能です(再入国許可が必要)。
永住許可と帰化の違い
永住許可と帰化は混同されがちですが、以下のような違いがあります。
| 項目 | 永住許可 | 帰化 |
|---|---|---|
| 国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍を取得 |
| 申請単位 | 個人単位で申請可能 | 原則として家族単位で申請 |
| 申請先 | 出入国在留管理局 | 法務局 |
| 審査期間 | 約4〜12ヶ月 | 約1〜2年 |
| パスポート | 母国のパスポート | 日本のパスポート |
| 選挙権 | なし | あり |
| 再入国 | 再入国許可が必要 | 自由に出入国可能 |
| 退去強制 | 一定の犯罪で退去強制の対象 | 退去強制はない |
永住許可申請のメリット
- 母国の国籍を維持できる
- 家族全員が要件を満たしていなくても個人単位で申請可能
- 帰化より審査期間が短い
- 在留カードの更新手続きが不要(7年ごとの更新のみ)
永住許可申請のデメリット
- 選挙権・被選挙権がない
- 一定の重大犯罪を犯すと退去強制の対象になる
- 再入国許可の手続きが必要(有効期間は最長5年)
- 在留カードの常時携帯義務がある
永住許可の基本要件
出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインでは、以下の要件が示されています。
(1) 素行が善良であること(素行要件)
法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。
具体的な審査ポイント:
- 刑事処分を受けていないこと(罰金刑、科料、執行猶予、実刑など)
- 交通違反の履歴が少ないこと(軽微な違反1〜2回程度は許容される場合あり)
- 税金や年金、健康保険料を適切に納付していること
- 在留状況に問題がないこと(不法就労、資格外活動の違反などがない)
- 入管法上の届出義務(転居届、所属機関の変更届など)を履行していること
注意点: 素行要件は申請者本人だけでなく、配偶者や同居家族の素行も考慮される場合があります。家族に重大な法令違反がある場合、申請者本人の永住許可に影響する可能性があります。
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(生計要件)
日常生活において公共の負担にならず、安定的に生活できる資産または技能を有していることが求められます。
具体的な審査ポイント:
- 安定した収入があること(年収の目安: 300万円以上が望ましい)
- 生活保護を受けていないこと
- 預貯金などの資産があること
- 継続的に就労していること、または十分な資産があること
- 配偶者や子どもなど、世帯全体の収入で判断される場合もある
注意点:
- 生計要件は、申請者本人が満たしていなくても、配偶者など同一生計の家族の収入・資産を合算して判断される場合があります
- 例: 専業主婦の方が永住許可を申請する場合、配偶者の収入で生計要件を満たすことが可能
- 扶養家族が多い場合は、より高い収入が求められる傾向があります
(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)
以下の条件を満たすことが求められます。
① 居住要件(原則)
原則として継続10年以上の在留が必要:
- 継続して10年以上日本に在留していること
- そのうち、就労資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」など)または居住資格(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など)で引き続き5年以上在留していること
「継続して」の意味:
- 単に10年間日本にいればよいわけではなく、中長期在留者として適法に在留していることが必要
- 短期滞在や留学生として在留していた期間も10年にカウントされますが、就労資格・居住資格での5年以上の在留が別途必要
- 長期間の出国(概ね3ヶ月以上)や頻繁な出国は「継続性」が否定される可能性があります
在留資格の例:
- 就労資格: 技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能、企業内転勤、興行、技能実習など
- 居住資格: 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、家族滞在など
② 在留状況が良好であること
最長の在留期間で在留していること:
- 現在の在留資格に規定されている最長の在留期間(通常3年または5年)を有していること
- 例: 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で5年の在留期間が認められている場合、実際に5年の在留期間を持っていることが必要
その他の審査ポイント:
- 在留カードの有効期間内に在留していること
- 入管法上の届出義務(転居届、所属機関の変更届など)を適切に履行していること
- 資格外活動許可を得ずに資格外活動を行っていないこと
③ 公的義務を履行していること
納税義務:
- 所得税、住民税、消費税などの税金を適切に納付していること
- 過去5年分程度の納税証明書の提出が求められます
- 未納や滞納がある場合、永住許可は困難です
公的年金・社会保険:
- 厚生年金、国民年金、健康保険などの公的年金・社会保険に加入し、保険料を適切に納付していること
- 過去2年分程度の年金記録、納付証明書の提出が求められます
- 未加入期間や未納期間がある場合、不許可の理由となります
その他の公的義務:
- 罰金刑や懲役刑などの刑事処分を受けていないこと
- 入管法違反、税法違反などの行政処分を受けていないこと
④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
- 感染症法に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症などに罹患していないこと
- 薬物中毒者でないこと
居住要件の特例(10年要件の緩和)
一定の条件を満たす場合、原則10年の居住要件が短縮されます。
1. 日本人・永住者・特別永住者の配偶者
要件:
- 配偶者として3年以上継続して日本に在留していること
- かつ、現に日本に引き続き1年以上在留していること
または:
- 婚姻後3年を経過していること
- かつ、現に日本に引き続き1年以上在留していること
具体例:
- 日本国内で結婚し、結婚後3年以上経過し、かつ日本に1年以上在留している場合
- 海外で結婚し同居していた期間を含めて婚姻後3年を経過し、かつ日本に1年以上在留している場合
注意点:
- 実体を伴った婚姻関係(同居・生計を一にしている)であることが必要
- 別居している場合、理由によっては不許可となる可能性があります
- 配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)を持っている必要はありませんが、実務上は配偶者ビザでの在留が望ましいです
2. 日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子
要件:
- 引き続き1年以上日本に在留していること
対象となる子:
- 日本人の実子(嫡出子、非嫡出子)
- 永住者の実子
- 特別永住者の実子
- 日本人、永住者、特別永住者の特別養子
注意点:
- 未成年者である必要はありませんが、未成年の場合は親の扶養を受けていることが前提
- 成人している場合は、独立生計要件を満たす必要があります
3. 定住者
要件:
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
対象となる定住者:
- 日系人(日系2世、3世、4世)
- 日本人の配偶者等の離婚・死別後に定住者に変更した者
- 難民認定者の家族
- 中国残留邦人の配偶者など
4. 難民の認定を受けた者
要件:
- 難民認定後、引き続き5年以上日本に在留していること
対象:
- 難民条約に基づき難民認定を受けた者
5. 我が国への貢献があると認められる者(高度人材外国人)
要件:
- 引き続き5年以上日本に在留していること
または:
- 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った結果が70点以上である者で、引き続き3年以上日本に在留していること
または:
- 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った結果が80点以上である者で、引き続き1年以上日本に在留していること
対象となる高度人材:
- 「高度専門職1号」または「高度専門職2号」の在留資格を有する者
- 「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」などの在留資格で、ポイント70点以上または80点以上を満たす者
ポイント計算の項目:
- 学歴(学士、修士、博士など)
- 職歴(実務経験年数)
- 年収(300万円以上)
- 年齢(30歳未満が有利)
- ボーナス項目(日本の大学卒業、日本語能力、成長分野への従事など)
高度人材外国人の優遇措置:
- 永住許可申請時の「最長の在留期間で在留していること」という要件が免除される場合があります
- 配偶者や子どもも同時に永住許可申請が可能になる場合があります
6. 我が国への貢献があると認められる者(その他)
以下のような者も5年以上の在留で永住許可の対象となる場合があります:
- 外交、社会、経済、文化等の分野において日本に顕著な貢献をした者
- 大学教授、研究者として著名な業績がある者
- オリンピックメダリストなど、スポーツ分野で顕著な実績がある者
- 文化勲章、褒章などを受章した者
永住許可申請の流れ
STEP 1: 要件の確認と準備
まず、自分が永住許可の要件を満たしているか確認します。
確認項目:
- 在留期間(原則10年以上、特例の場合は該当する年数)
- 素行要件(犯罪歴、交通違反歴)
- 生計要件(年収、預貯金、資産)
- 納税状況(所得税、住民税の納付状況)
- 年金・保険の加入・納付状況
- 現在の在留期間(最長の在留期間を有しているか)
不安な点がある場合は、専門家(行政書士)に相談することをお勧めします。
STEP 2: 必要書類の収集
永住許可申請には多数の書類が必要です。主な必要書類は以下の通りです。
基本書類(全員必須)
- 永住許可申請書
出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能 - 写真(4cm×3cm)
申請前3ヶ月以内に撮影されたもの - パスポートおよび在留カード
原本を提示(コピーも提出) - 身元保証書
日本人または永住者・特別永住者による身元保証が必要 - 住民税の課税証明書および納税証明書
過去5年分(海外在住期間がある場合はその説明) - 住民税の納付書または領収書のコピー
直近1年分 - 国民年金・厚生年金の保険料納付証明書
過去2年分 - 公的年金の加入期間を証明する資料
ねんきん定期便、年金手帳のコピーなど - 健康保険証のコピー
- 預金通帳のコピー
残高がわかるページ
在留資格・職業別の追加書類
会社員の場合:
- 在職証明書
- 会社の登記事項証明書(勤務先が法人の場合)
- 給与明細書(直近3ヶ月分)
- 源泉徴収票(直近1年分)
経営者・役員の場合:
- 会社の登記事項証明書
- 会社の決算報告書(直近3年分)
- 法人税の納税証明書(直近3年分)
- 事業内容を説明する資料
自営業の場合:
- 確定申告書のコピー(直近3年分)
- 営業許可証など事業を証明する書類
- 事業内容を説明する資料
配偶者ビザの場合:
- 配偶者の住民票
- 配偶者の在職証明書または収入証明書
- 配偶者の納税証明書
- 婚姻届受理証明書または戸籍謄本
家族滞在の場合:
- 扶養者(親)の在職証明書
- 扶養者(親)の納税証明書
- 在学証明書(学生の場合)
その他の書類
- 理由書(永住を希望する理由、日本での生活状況などを記載)
- 履歴書(学歴、職歴、日本での在留歴など)
- 不動産登記事項証明書(不動産を所有している場合)
- 運転免許証のコピー(交通違反歴の確認のため)
注意点:
- 書類は原則として発行から3ヶ月以内のものが必要
- 外国語の書類には日本語訳を添付する必要があります
- 申請内容により追加書類を求められる場合があります
STEP 3: 申請書類の作成
申請書に必要事項を記入します。
記入時の注意点:
- 黒色のボールペンまたは万年筆で記入
- 訂正する場合は二重線を引き、訂正印を押す
- 英語以外の外国語の場合は日本語訳を併記
主な記入項目:
- 氏名、生年月日、国籍
- 現在の在留資格と在留期間
- 住所、電話番号
- 日本での在留歴
- 家族構成
- 職業、勤務先
- 永住を希望する理由
STEP 4: 出入国在留管理局への申請
申請書類が揃ったら、住所地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
熊本県の管轄:
- 福岡出入国在留管理局 熊本出張所
所在地: 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第2合同庁舎
電話: 096-362-3605
受付時間: 平日 9:00〜12:00、13:00〜16:00
申請方法:
- 申請は原則として本人が出頭する必要があります
- 16歳未満の場合は、親権者または法定代理人が代理で申請可能
- 行政書士などの取次者による申請も可能
申請時に持参するもの:
- 申請書類一式
- パスポート原本
- 在留カード原本
- 手数料(永住許可申請時は不要、許可時に8,000円)
STEP 5: 審査
出入国在留管理局で審査が行われます。
審査期間:
- 標準処理期間: 約4ヶ月
- 実際には4ヶ月〜12ヶ月程度かかる場合が多い
- 高度人材外国人の場合は比較的短期間で審査される傾向
審査中の注意点:
- 追加書類の提出を求められる場合があります
- 出入国在留管理局から電話や郵送で連絡が来ることがあります
- 審査期間中に住所や勤務先が変わった場合は、速やかに届出が必要
STEP 6: 結果の通知
審査結果が通知されます。
許可の場合:
- ハガキまたは電話で通知が来ます
- 通知を受けたら、パスポートと在留カードを持参して出入国在留管理局に行きます
- 手数料8,000円を印紙で納付
- 新しい在留カード(在留資格「永住者」)が交付されます
不許可の場合:
- 不許可の理由が書面で通知されます
- 不許可の理由によっては、再度申請することも可能
- 不許可の理由を改善してから再申請することをお勧めします
STEP 7: 永住許可後の手続き
永住許可を取得した後も、いくつかの手続きが必要です。
在留カードの更新:
- 永住者の在留カードは、16歳未満の場合は16歳の誕生日まで、16歳以上の場合は交付日から7年間有効
- 有効期限の2ヶ月前から更新申請が可能
住所変更・転居の届出:
- 永住者であっても、転居した場合は14日以内に市区町村役場に届出が必要
- 在留カードの住所欄を更新してもらいます
再入国許可:
- 日本を出国して再入国する場合は、再入国許可(有効期間最長5年)またはみなし再入国許可(有効期間1年)が必要
- みなし再入国許可は、出国時に在留カードまたはパスポートを提示することで自動的に適用されます
国籍国のパスポート更新:
- 外国籍を保持しているため、母国のパスポートを更新する必要があります
永住許可申請でよくある不許可理由
永住許可申請が不許可になる主な理由は以下の通りです。
1. 納税義務・社会保険料の未納
- 所得税、住民税の未納・滞納
- 国民年金、厚生年金の未加入・未納
- 健康保険料の未納
- 過去に遡って納付しても、未納期間があったことが判明すると不許可になる場合があります
対策:
- 申請前に納税証明書、年金記録を確認し、未納がないことを確認
- 未納がある場合は、完納してから申請する
2. 素行不良
- 刑事処分(罰金刑、懲役刑など)
- 交通違反(特に飲酒運転、無免許運転、スピード違反など重大な違反)
- 入管法違反(資格外活動、不法就労など)
対策:
- 刑事処分を受けた場合は、一定期間(3〜5年程度)経過してから申請
- 交通違反は軽微なもの1〜2回程度は許容される場合もありますが、頻繁な違反や重大な違反は不許可の理由となります
3. 収入不足
- 年収が低すぎる(目安: 300万円未満)
- 生活保護を受けている
- 安定した収入がない(頻繁な転職、無職期間が長いなど)
対策:
- 配偶者など同一生計の家族の収入を合算できる場合は、その旨を説明
- 預貯金など資産がある場合は、その証明を提出
4. 在留期間が短い
- 最長の在留期間を有していない(3年の在留期間しかないなど)
- 継続して10年以上在留していない(中断期間がある、長期間の出国があるなど)
対策:
- まずは在留期間を最長(通常5年)にしてから永住許可申請を行う
- 頻繁な出国や長期間の出国は避ける
5. 申請書類の不備
- 必要書類が不足している
- 申請書の記載内容に虚偽がある、または不正確
- 書類の有効期限が切れている
対策:
- 申請前にチェックリストを作成し、書類の漏れがないか確認
- 専門家(行政書士)に書類チェックを依頼
6. 身元保証人の問題
- 身元保証人の収入が不足している
- 身元保証人自身が納税義務を履行していない
対策:
- 収入が安定している日本人または永住者に身元保証を依頼
- 身元保証人にも納税証明書の提出を求められる場合があります
永住許可申請を成功させるためのポイント
1. 十分な準備期間を確保する
永住許可申請の準備には、最低でも2〜3ヶ月程度の期間が必要です。必要書類の収集、作成に時間がかかるため、余裕を持って準備を始めましょう。
2. 納税・社会保険料の納付状況を事前に確認
申請前に、過去5年分の納税証明書、過去2年分の年金記録を取得し、未納がないことを確認してください。未納がある場合は、完納してから申請することをお勧めします。
3. 最長の在留期間を取得してから申請
現在の在留期間が3年以下の場合は、まず在留期間更新許可申請を行い、最長の在留期間(通常5年)を取得してから永住許可申請を行うことをお勧めします。
4. 交通違反に注意
永住許可申請を考えている場合は、交通違反に特に注意してください。軽微な違反1〜2回程度は許容される場合もありますが、重大な違反や頻繁な違反は不許可の理由となります。
5. 理由書をしっかり作成
永住を希望する理由、日本での生活状況、将来の計画などを詳しく記載した理由書を作成することで、審査官に良い印象を与えることができます。
6. 専門家に相談
永住許可申請は複雑で、必要書類も多岐にわたります。不安な点がある場合は、入管業務に精通した行政書士に相談することをお勧めします。
家族の永住許可申請
配偶者や子どもも永住許可を取得できる?
申請者本人が永住許可を取得した後、配偶者や子どもも永住許可を申請することができます。
配偶者の場合:
- 配偶者は「永住者の配偶者等」の在留資格に変更することも可能
- 「永住者の配偶者等」は就労制限がなく、永住者とほぼ同等の待遇を受けられますが、離婚した場合は在留資格を変更する必要があります
- 永住許可を取得する場合は、配偶者自身が要件を満たす必要があります(居住要件の特例により、婚姻後3年+日本在留1年で申請可能)
子どもの場合:
- 永住者の実子は、居住要件の特例により、引き続き1年以上日本に在留していれば永住許可を申請できます
- 未成年の子どもは、親の扶養を受けている場合、生計要件は親の収入で判断されます
いつでもお声掛けください。096-385-9002
