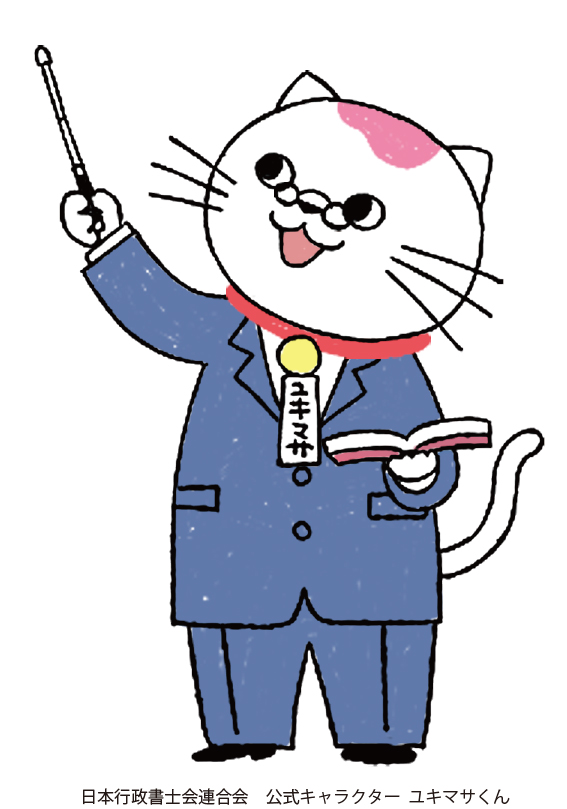
外国人・外国法人による日本法人設立完全ガイド
外為法届出・在留資格取得・会社設立手続きの実務解説
【行政書士法人塩永事務所監修・2025年11月15日時点最新版】
エグゼクティブサマリー
グローバル経済の進展に伴い、日本市場への参入を検討する海外企業家・外国法人が増加しています。日本は世界第5位の経済規模を有し、高齢化社会における医療・介護、デジタルトランスフォーメーション、インバウンド観光など、多様な成長機会を提供しています。
外国人・外国法人による日本法人設立は、会社法上、日本人・日本法人と同等の権利が認められていますが、実務上は以下の特有の要件・手続きが必要となります。
主要な留意点:
- 外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく対内直接投資の届出・報告義務
- 在留資格「経営・管理」の取得要件(2025年10月16日改正施行)
- 非居住者による資本金払込の実務的制約
- 外国語書類の日本語翻訳・公証要件
本ガイドは、行政書士法人塩永事務所の実務経験に基づき、外国人・外国法人が日本で法人を設立する際の全プロセスを、法的根拠・実務的ポイント・よくある誤解を含めて詳細に解説します。
1. 外国人・外国法人による日本法人設立の可否と法的枠組み
1-1. 会社法上の原則
結論: 外国人・外国法人であっても、日本人・日本法人と同等に法人設立が可能です。
会社法は、発起人・株主・役員の国籍・居住地による制限を設けていません(会社法第25条、第26条等)。したがって、以下のケースがすべて適法に可能です。
- 発起人全員が外国人・外国法人
- 株主全員が外国人・外国法人
- 取締役・代表取締役全員が非居住者
- 本店所在地が日本国内にあれば、外国資本100%の法人設立が可能
1-2. 実務上の制約と追加要件
ただし、会社法以外の法令により、以下の追加要件・手続きが必要となります。
(1) 外国為替及び外国貿易法(外為法)の適用
対内直接投資に関する届出・報告義務
非居住者または外国法人が、日本法人の株式等を取得する行為は、外為法第26条第2項および第55条の5第1項に基づく「対内直接投資等」に該当します。
届出・報告の区分:
| 区分 | 対象 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|---|
| 事前届出 | 特定の国・地域の投資家による安全保障関連業種等への投資 | 日本銀行経由で財務大臣・事業所管大臣へ届出 | 投資実行の6ヶ月前〜投資実行予定日の30日前まで |
| 事後報告 | 上記以外の一般的な投資(非居住者の出資比率1%以上) | 日本銀行経由で財務大臣・事業所管大臣へ報告 | 投資実行後45日以内 |
罰則:
- 届出義務違反・虚偽届出: 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科(外為法第70条)
- 行政措置: 株式等の処分命令(外為法第29条)、業務停止命令
実務上の重要ポイント:
- 非居住者の出資比率が1%未満であっても、実質的支配関係がある場合は届出対象となる可能性があります
- 「非居住者」の定義は外為法第6条第1項第6号および施行令第11条に規定されており、原則として日本国内に住所または居所を有しない個人、日本国内に主たる事務所を有しない法人を指します
- 届出・報告漏れが後日判明した場合、遡及的な行政処分の対象となるため、設立時点での適切な対応が不可欠です
(2) 在留資格(ビザ)の取得要件
外国人が日本で会社経営に従事する場合の在留資格
外国人が日本国内で報酬を伴う経営活動を行うためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく適法な在留資格が必要です。
該当する主な在留資格:
- 経営・管理: 事業の経営または管理に従事する活動
- 永住者: 活動制限なし
- 日本人の配偶者等: 活動制限なし
- 永住者の配偶者等: 活動制限なし
- 定住者: 活動制限なし
- 高度専門職1号ハ: 貿易その他の事業の経営等
- 高度専門職2号: 活動制限なし(高度専門職1号からの変更者)
不法就労の罰則:
- 不法就労者: 3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金、またはその併科(入管法第70条)
- 不法就労助長者(雇用主): 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科(入管法第73条の2)
重要な注意点:
- 法人設立登記自体には在留資格は不要ですが、設立後に日本国内で経営活動を行う場合は必須です
- 短期滞在(90日以内の観光・商用ビザ)では、報酬を伴う経営活動は認められません
- 在留資格なしで経営活動を行った場合、不法就労として強制退去・再入国拒否の対象となります
(3) 資本金払込の実務的制約
日本国内の銀行口座への払込が原則
会社法では資本金の払込場所に制限はありませんが、実務上、以下の理由により日本国内の銀行口座への払込が必要となります。
実務上の要請:
- 法務局への登記申請時、払込証明書として日本の金融機関が発行する通帳コピーまたは取引明細書の提出が求められます
- 海外銀行の支店や外国銀行からの送金証明は、一部の法務局で受理されない事例があります
- 在留資格「経営・管理」の申請時、入国管理局は日本国内での資金管理状況を重視します
非居住者が直面する実務的課題:
- 日本の銀行は、原則として非居住者・外国法人の口座開設を制限しています
- 法人設立前は法人名義口座を開設できないため、発起人個人名義の口座または協力者の口座を利用する必要があります
- マネーロンダリング対策(犯罪収益移転防止法)により、外国人の口座開設には、在留カード、マイナンバー、日本国内の住所証明等が求められます
実務的な解決策:
- 日本に居住する協力者(親族・友人・取引先等)の口座を一時的に利用
- 一時的な短期滞在で来日し、銀行口座を開設してから資本金を払込
- 在留資格取得後に正式な法人口座を開設し、資本金を移管
(4) 外国語書類の翻訳・公証要件
登記申請・在留資格申請における翻訳義務
登記申請書および在留資格申請書の添付書類は、原則として日本語で作成する必要があります。外国語で作成された書類には、日本語翻訳文の添付が必須です。
翻訳要件:
- 翻訳者の氏名・住所の記載(翻訳者の資格は不問)
- 翻訳の正確性を担保するため、専門家(行政書士、司法書士、公認翻訳者等)による翻訳を推奨
- 原本との対応関係が明確になるよう、ページ番号等を付記
公証・認証要件:
- 外国で作成された私署証書(印鑑証明書、宣誓供述書等)は、以下のいずれかの認証が必要です
- アポスティーユ認証: ハーグ条約加盟国の場合、発行国の官公署による認証
- 領事認証: ハーグ条約非加盟国の場合、発行国の官公署→外務省→日本大使館・領事館の3段階認証
- 認証済みの書類には、日本語翻訳文を添付
2. 会社形態の選択と発起設立・募集設立の区別
2-1. 主要な会社形態の比較
日本法上の会社形態には、株式会社、合同会社(LLC)、合名会社、合資会社がありますが、外国人・外国法人の設立では株式会社または合同会社が選択されるのが一般的です。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社(LLC) |
|---|---|---|
| 設立費用 | 約25万円〜(登録免許税15万円〜、定款認証費用等) | 約10万円〜(登録免許税6万円〜) |
| 意思決定機関 | 株主総会、取締役会(任意) | 社員(出資者)の過半数決議 |
| 機関設計の柔軟性 | 低い(会社法の規定が詳細) | 高い(定款自治が広範に認められる) |
| 対外的信用力 | 高い(日本企業に広く認知) | 株式会社に比べやや低い |
| 決算公告義務 | あり(官報掲載等) | なし |
| 増資手続き | 比較的複雑(株主総会決議等) | 比較的簡便 |
| 株式譲渡制限 | 定款で自由に設定可能 | 原則として社員全員の承認が必要 |
外国人・外国法人に推奨される形態:
- 株式会社: 日本企業・金融機関との取引信用を重視する場合、将来的な株式公開を視野に入れる場合
- 合同会社: 設立コストを抑えたい場合、少人数での事業運営を想定する場合、機関設計の柔軟性を重視する場合
2-2. 発起設立と募集設立の区別
株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2種類があります。
発起設立(会社法第25条第1項第1号)
定義: 発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法
特徴:
- 設立手続きが簡便(創立総会の開催不要)
- 発起人のみで意思決定が完結
- 小規模・閉鎖的な会社に適する
- 外国人・外国法人の設立では、発起設立が大多数を占める
設立の流れ:
- 発起人による定款作成・認証
- 発起人による設立時発行株式の引受け
- 出資の履行(資本金払込)
- 設立時取締役等の選任
- 設立時取締役等による調査(会社法第46条)
- 設立登記申請
募集設立(会社法第25条第1項第2号)
定義: 発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りを他者から募集する方法
特徴:
- 設立手続きが複雑(創立総会の開催が必要)
- 発起人以外の出資者(設立時募集株式の引受人)の関与
- 大規模な資本調達を想定する会社に適する
- 外国人・外国法人の設立で選択されることは稀
設立の流れ:
- 発起人による定款作成・認証
- 発起人による設立時発行株式の引受け
- 設立時募集株式の募集事項の決定
- 設立時募集株式の申込み・割当て
- 出資の履行
- 創立総会の招集・開催
- 設立時取締役等の選任
- 設立時取締役等による調査
- 設立登記申請
外国人・外国法人への推奨: 手続きの簡便性・コスト・スピードの観点から、発起設立を強く推奨します。募集設立は、大規模な資本調達が確実に見込まれる特殊なケースに限定すべきです。
3. 代表取締役の非居住者と外為法上の対内直接投資
3-1. 法改正の経緯と現行制度
2015年3月会社法改正以前
改正前の会社法では、「株式会社は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。ただし、取締役が1人の場合は、その取締役が代表取締役となる」との規定(旧会社法第349条)と、商業登記規則の運用により、代表取締役のうち最低1名は日本に住所を有する者であることが事実上要求されていました。
この要件は、会社の実体を日本国内に確保し、訴訟等における送達の確実性を担保する趣旨でした。
2015年3月会社法改正以降
平成26年(2014年)改正会社法(平成27年(2015年)3月1日施行)により、この実務上の制約が撤廃されました。現行法では、代表取締役・取締役全員が非居住者であっても、適法に株式会社を設立できます。
改正の背景:
- グローバル化の進展に伴う海外企業の日本進出促進
- 国際的な事業展開における柔軟性の確保
- 日本国内に物理的拠点を有さない海外企業の日本市場参入障壁の除去
3-2. 外為法上の対内直接投資制度
代表取締役全員が非居住者である会社の設立は適法ですが、外為法上の「対内直接投資等」に該当するため、以下の届出・報告義務が発生します。
対内直接投資等の定義(外為法第26条第2項)
以下の行為が「対内直接投資等」に該当します。
- 株式等の取得: 非居住者による日本法人の株式・持分の取得(出資比率1%以上)
- 株式等の保有: 既に株式等を保有する非居住者による追加取得(合計で10%以上となる場合)
- 役員就任: 非居住者が日本法人の役員に就任すること
- 事業譲渡: 非居住者による日本法人の事業の全部または重要な一部の譲受け
外国人・外国法人による会社設立は、上記1「株式等の取得」に該当します。
事前届出が必要なケース
以下の要件をすべて満たす場合、投資実行の30日前までに事前届出が必要です(外為法第27条第1項)。
事前届出対象の3要件:
- 投資家の属性: 特定国・地域の居住者または法人(現在、該当国・地域の指定はなし。ただし、安全保障上の懸念がある国・地域は実質的に審査が厳格化)
- 投資対象業種: 外為法施行令別表に定める指定業種(国の安全、公の秩序、公衆の安全、日本経済の円滑な運営に支障を来すおそれがある業種)
- 具体例: 武器製造、航空機製造、原子力、電気通信、放送、サイバーセキュリティ関連、医薬品製造等
- 出資比率: 1%以上
事前届出の手続き:
- 届出書(「株式取得等に関する届出書」様式第5)3通を日本銀行本店または支店に提出
- 日本銀行経由で財務大臣および事業所管大臣(業種により異なる、例: 経済産業大臣、総務大臣等)へ送付
- 審査期間: 原則30日間(この間、投資実行は禁止)
- 審査の結果、以下のいずれかの措置
- 承認: 投資実行可能
- 条件付き承認: 一定の条件(株式保有比率の制限、役員選任の制限等)を付して承認
- 不承認: 投資実行不可
- 審査期間の延長: 最長5ヶ月まで延長可能
事後報告が必要なケース(標準的なケース)
事前届出対象に該当しない対内直接投資(一般的な業種への投資)は、投資実行後45日以内に事後報告を行います(外為法第55条の5第1項)。
事後報告の手続き:
- 報告書(「株式・持分・議決権取得に関する報告書」様式第9)3通を日本銀行本店または支店に提出
- 日本銀行経由で財務大臣および事業所管大臣へ送付
- 報告受理後、特段の問題がなければ手続き完了
事後報告の期限:
- 株式取得等の実行日(通常、登記申請日または出資の履行日)から45日以内
実務上の重要ポイント:
- 期限を1日でも過ぎると、外為法違反となり、罰則の対象となります
- 報告漏れが判明した場合、遡及的に報告を求められ、行政処分の対象となる可能性があります
- 非居住者の出資比率が1%未満であっても、実質的支配関係がある場合(例: 非居住者が単独で取締役の過半数を選任できる場合)は、報告義務が発生する可能性があります
罰則規定
刑事罰:
- 事前届出義務違反、虚偽届出: 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科(外為法第70条)
- 事後報告義務違反、虚偽報告: 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらの併科(外為法第73条)
行政措置:
- 株式等の処分命令: 財務大臣は、国の安全等を損なうと認める場合、株式等の全部または一部の処分を命じることができます(外為法第29条)
- 業務停止命令: 事業所管大臣は、一定期間の業務停止を命じることができます
- 氏名・名称の公表: 違反事実が公表され、企業の信用が著しく毀損されます
3-3. 非居住者の判定基準
外為法における「非居住者」の定義は、以下の通りです(外為法第6条第1項第6号、外為法施行令第11条)。
個人の場合
非居住者に該当: 日本国内に住所または居所を有しない個人
居住者に該当: 日本国内に住所または居所を有する個人
判定基準:
- 住所: 生活の本拠地。客観的な生活状況(家族の所在、職業、資産の所在等)により判定
- 居所: 相当期間継続して居住する場所。一般に6ヶ月以上の滞在で居所と認定
実務上の留意点:
- 在留資格(ビザ)の有無は、直接的な判定要素ではありません
- 短期滞在(90日以内)で来日している外国人は、原則として非居住者です
- 在留資格「経営・管理」等を取得し、日本国内に生活の本拠を有する外国人は、居住者です
法人の場合
非居住者に該当: 日本国内に主たる事務所を有しない法人
居住者に該当: 日本国内に主たる事務所を有する法人
判定基準:
- 主たる事務所: 法人の実質的な管理・支配が行われている場所
- 登記上の本店所在地だけでなく、実際の業務執行場所を総合的に判断
実務上の留意点:
- 外国法人の日本支店は、外国法人の一部門であるため、非居住者です
- 日本で設立された法人(日本法人)は、原則として居住者です
- ただし、日本法人であっても、実質的な管理・支配が外国で行われている場合(例: 全役員が非居住者、重要な意思決定が海外で行われている等)は、非居住者と判定される可能性があります
4. 外為法に基づく届出・報告の実務
4-1. 日本銀行への届出・報告窓口
外為法に基づく対内直接投資の事前届出・事後報告は、日本銀行の本店または支店に提出します。
提出先:
- 日本銀行本店国際局: 東京都中央区日本橋本石町2-1-1
- 電話: 03-3279-1111(代表)
- 国際局為替管理課
- 日本銀行各支店: 札幌、仙台、新潟、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、松山、福岡など
提出方法:
- 窓口持参または郵送
- 電子申請は現時点では対応していません
提出部数:
- 届出書・報告書: 3通(正本1通、副本2通)
受付時間:
- 平日9:00〜12:00、13:00〜15:00(土日祝日を除く)
4-2. 事前届出の具体的手続き
提出書類
必須書類:
- 株式取得等に関する届出書(外為法施行規則様式第5): 3通
- 届出者(非居住者)の氏名・住所、国籍・地域
- 日本法人の商号・本店所在地、事業内容
- 取得する株式の種類・数、出資比率
- 取得予定日
- 事業内容説明書: 日本法人の詳細な事業計画(事業内容、製品・サービス、取引先、雇用計画等)
- 届出者の本人確認書類: パスポートコピー、法人登記簿謄本等
- 日本法人の定款案: 設立予定の会社の定款
追加書類(審査の過程で求められる場合):
- 技術情報の取扱いに関する説明書
- 取引先・仕入先に関する資料
- 出資者の財務状況に関する資料
- その他、安全保障審査に必要な資料
審査の流れ
- 提出・受理: 日本銀行が形式審査を行い、受理
- 財務大臣・事業所管大臣への送付: 日本銀行が関係省庁へ送付
- 審査: 国の安全、公の秩序、公衆の安全、日本経済の円滑な運営への影響を審査
- 審査期間: 原則30日間(届出受理日の翌日から起算)
- 結果通知: 承認・条件付き承認・不承認・審査期間延長のいずれかを通知
審査期間中の制約:
- 届出に係る対内直接投資等を実行することは禁止されます
- 期間経過前に投資を実行した場合、外為法違反となります
不承認・条件付き承認のケース
不承認となる可能性が高いケース:
- 国の安全を損なう軍事技術の流出リスクがある場合
- 重要インフラ(電気、ガス、通信等)への外国政府の影響力行使が懸念される場合
- サイバーセキュリティ上の重大なリスクがある場合
条件付き承認の例:
- 株式保有比率の上限設定
- 役員選任における事前承認制
- 技術情報へのアクセス制限
- 定期的な事業報告義務
4-3. 事後報告の具体的手続き
提出書類
必須書類:
- 株式・持分・議決権取得に関する報告書(外為法施行規則様式第9): 3通
- 報告者(非居住者)の氏名・住所、国籍・地域
- 日本法人の商号・本店所在地、事業内容
- 取得した株式の種類・数、出資比率
- 取得日(通常、登記申請日)
- 定款の写し: 認証済み定款のコピー
- 登記事項証明書: 設立登記完了後に法務局で取得(履歴事項全部証明書)
- 報告者の本人確認書類: パスポートコピー、法人登記簿謄本等
任意だが提出を推奨する書類:
- 事業計画書: 日本法人の具体的な事業内容を説明
- 株主名簿: 全株主の氏名・住所、保有株式数
いつでもお声掛けください。
