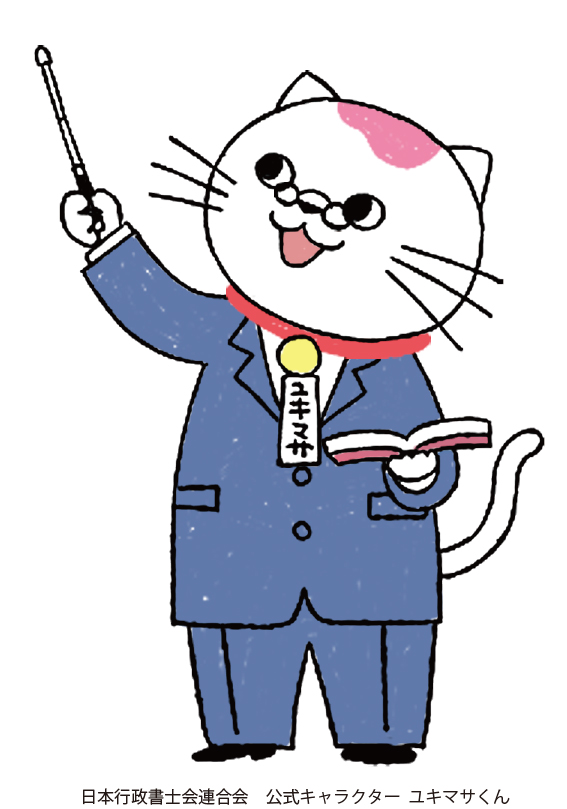
監理団体許可取得の完全ガイド – 行政書士法人塩永事務所
技能実習制度において、監理団体は技能実習生の受入れと適正な実習実施を監理する重要な役割を担っています。行政書士法人塩永事務所では、監理団体許可申請から許可取得までの手続きを専門的にサポートし、確実な許可取得を実現いたします。
監理団体とは
監理団体とは、技能実習生の受入れを希望する企業(実習実施者)を監理し、技能実習の適正な実施を確保するための団体です。2017年11月の技能実習法施行により、従来の「監理団体」から「監理団体許可制」へと移行し、より厳格な要件が課されるようになりました。
監理団体の種類
監理団体には、実施できる技能実習の区分に応じて2つの種類があります。
一般監理事業
- 第1号から第3号までの技能実習を監理可能
- より厳格な許可要件が求められる
- 優良な監理団体のみが許可を受けられる
特定監理事業
- 第1号および第2号技能実習のみ監理可能
- 第3号技能実習は監理できない
- 一般監理事業よりも要件が緩和されている
監理団体になれる組織
監理団体の許可を受けられるのは、営利を目的としない法人に限定されています。
許可対象となる法人
- 事業協同組合、企業組合
- 商工会、商工会議所
- 中小企業団体、職業訓練法人
- 公益社団法人、公益財団法人
- 一般社団法人、一般財団法人
- その他営利を目的としない法人
重要: 株式会社などの営利法人は監理団体になることができません。
監理団体許可の要件
監理団体の許可を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1. 組織要件
営利を目的としない法人であること 株式会社などの営利法人は許可を受けられません。事業協同組合などの非営利法人である必要があります。
適切な事業運営体制があること
- 外部監査を受ける体制が整っていること
- 実習監理を適正に行える人的体制があること
- 財産的基礎が安定していること
2. 事業所要件
適切な事業所が確保されていること
- 事業を的確に遂行できる事務所を有していること
- プライバシーを保護できる相談体制が整っていること
3. 人的要件
監理事業を適正に実施できる役職員がいること
監理責任者の配置
- 監理事業を行う事業所ごとに1名以上配置
- 監理事業の業務を統括管理する者
- 3年以上の実務経験または専門知識を有すること
- 欠格事由に該当しないこと
指定外部役員または外部監査人の選任
- 監理団体の業務の適正な運営を確保するため
- 監理団体の役員または職員以外の者から選任
- 弁護士、公認会計士、中小企業診断士などの資格者が望ましい
4. 財産的基礎要件
事業を適正に運営するに足りる財産的基礎を有すること
- 債務超過状態でないこと
- 一般監理事業の場合、さらに厳格な財産要件あり
5. 優良要件(一般監理事業の場合)
一般監理事業の許可を受けるには、「優良な監理団体」の基準を満たす必要があります。
優良要件の評価項目
- 実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制
- 技能等の修得等に係る実績
- 法令違反・問題の発生状況
- 相談・支援体制
- 地域社会との共生
これらの項目について点数制で評価され、一定以上の点数を獲得する必要があります。
監理団体許可取得までの流れ
ステップ1: 事前準備・要件確認(1〜2ヶ月)
まず、監理団体としての要件を満たしているか確認します。
主な確認事項
- 法人格の有無と種類
- 組織体制の整備状況
- 役職員の適格性
- 財産的基礎の確認
- 事業計画の策定
必要な準備
- 監理責任者の選任
- 指定外部役員または外部監査人の選任
- 事業所の確保
- 規程類の整備(監理団体規程、業務規程など)
ステップ2: 申請書類の作成(1〜2ヶ月)
監理団体許可申請には、膨大な書類の作成・収集が必要です。
主な提出書類
基本書類
- 監理団体許可申請書
- 監理団体許可申請に係る申立書
- 登記事項証明書
- 定款または寄附行為
- 役員名簿
- 監理責任者の履歴書
- 指定外部役員・外部監査人の履歴書と就任承諾書
事業関連書類
- 監理事業を行う事業所の概要
- 事業計画書
- 監理費用の明細書
- 監理団体規程
- 実習監理の実施方法に関する書類
財務関連書類
- 貸借対照表、損益計算書
- 直近2年分の財務諸表
- 監理費用の収支予算書
- 納税証明書
体制関連書類
- 組織図
- 監理責任者の選任に関する書類
- 指定外部役員・外部監査人の選任に関する書類
- 相談体制に関する書類
- プライバシーマーク取得状況(該当する場合)
優良要件関連書類(一般監理事業の場合)
- 優良な監理団体の確認に係る書類
- 技能実習実績証明書
- 優良要件適合申告書
その他
- 誓約書
- 役員の住民票
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 技能実習計画認定申請書(予定)
ステップ3: 事前相談(任意、1〜2週間)
正式申請前に、外国人技能実習機構の地方事務所・支所で事前相談を行うことができます。
事前相談のメリット
- 申請書類の不備を事前に確認できる
- 不明点を直接確認できる
- 申請後の手戻りを防げる
ステップ4: 申請書類の提出(1日)
申請書類が整ったら、外国人技能実習機構の本部事務所または地方事務所・支所に提出します。
提出方法
- 窓口持参
- 郵送(書留郵便等)
提出先 外国人技能実習機構(OTIT)
- 本部事務所: 東京都港区
- 地方事務所・支所: 全国13ヶ所
申請書類は正本1部、副本1部の計2部を提出します。
ステップ5: 審査(2〜4ヶ月)
外国人技能実習機構による審査が行われます。
審査内容
- 書面審査: 提出書類の確認
- 実地調査: 事業所への訪問調査(必要に応じて)
- 財務状況の確認
- 役職員の適格性確認
- 組織体制の確認
審査期間中の対応
- 追加資料の提出依頼への対応
- 照会事項への回答
- 補正指示への対応
この段階で不備や疑義があった場合、追加書類の提出や説明が求められます。迅速かつ適切な対応が重要です。
ステップ6: 許可証の交付(審査終了後1〜2週間)
審査を通過すると、外国人技能実習機構から許可証が交付されます。
許可証の記載事項
- 許可番号
- 許可年月日
- 監理事業の区分(一般/特定)
- 許可の有効期間(3年間または5年間)
- 監理事業を行う事業所の所在地
ステップ7: 許可取得後の手続き
許可取得後も、各種届出や更新手続きが必要です。
必要な届出
- 変更届出: 役員、監理責任者、事業所等に変更があった場合
- 廃止届出: 監理事業を廃止する場合
- 休止・再開届出: 監理事業を休止または再開する場合
定期報告
- 事業報告書の提出(毎年)
- 監理費用の収支決算書の提出(毎年)
更新申請 許可の有効期間満了前に更新申請が必要です。
許可取得後の義務
監理団体は、許可取得後も以下の義務を履行する必要があります。
1. 実習監理の適正実施
実習実施者への監査
- 3ヶ月に1回以上の定期監査
- 技能実習生の労働条件、生活環境の確認
- 技能実習計画の履行状況の確認
技能実習生への訪問指導
- 1ヶ月に1回以上の訪問
- 技能実習の進捗確認
- 相談対応
2. 報告・届出義務
定期報告
- 事業報告書(毎年)
- 監理費用の収支決算書(毎年)
随時報告
- 技能実習計画の認定取消し等があった場合
- 失踪等の問題が発生した場合
3. 帳簿書類の作成・保存
以下の書類を作成し、5年間保存する義務があります。
- 技能実習生の名簿
- 監査・訪問指導の記録
- 相談対応の記録
- 技能実習計画
- 雇用契約書、雇用条件書
4. 外部監査の実施
指定外部役員または外部監査人による外部監査を年1回以上実施する必要があります。
許可の有効期間と更新
有効期間
一般監理事業
- 新規許可: 5年間
- 更新許可: 7年間
特定監理事業
- 新規許可: 3年間
- 更新許可: 5年間
更新申請
有効期間満了の6ヶ月前から3ヶ月前までに更新申請を行う必要があります。更新申請の手続きは、新規申請とほぼ同様です。
よくある不許可事由
監理団体許可が下りないケースとして、以下のような事例があります。
組織要件の不備
- 営利法人である
- 定款に監理事業の記載がない
- 組織運営が不安定
人的要件の不備
- 監理責任者が欠格事由に該当
- 実務経験・専門知識が不足
- 指定外部役員等が選任されていない
財産的基礎の不備
- 債務超過状態
- 事業継続性に疑義
事業計画の不備
- 実現可能性が低い
- 監理体制が不十分
- 監理費用が不適切
優良要件の不達成(一般監理事業)
- 優良要件の点数が基準に達しない
- 過去の実習実績が不十分
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、監理団体許可申請に関する以下の業務を総合的にサポートいたします。
1. 許可取得前の総合コンサルティング
要件診断
- 現在の組織が監理団体の要件を満たしているか診断
- 不足要件の洗い出しと改善提案
- 一般監理事業と特定監理事業のどちらが適切か判断
組織整備支援
- 監理責任者の選任支援
- 指定外部役員・外部監査人の選任支援
- 組織体制の構築アドバイス
規程類の整備
- 監理団体規程の作成
- 業務規程の作成
- 各種マニュアルの整備支援
2. 申請書類の作成代行
膨大な申請書類を専門家が作成
- 監理団体許可申請書の作成
- 事業計画書の作成
- 監理費用の明細書の作成
- 優良要件適合申告書の作成(一般監理事業)
- その他必要書類の作成
添付書類の収集支援
- 必要書類のリストアップ
- 取得方法のアドバイス
- 書類の精査・確認
3. 申請手続きの代行
外国人技能実習機構とのやり取り
- 事前相談の同行
- 申請書類の提出代行
- 補正対応
- 照会事項への回答対応
進捗管理
- 審査状況の確認
- タイムリーな情報提供
- スケジュール管理
4. 許可取得後の継続サポート
変更届出の支援
- 役員変更届
- 監理責任者変更届
- 事業所変更届
- その他各種変更届
定期報告の支援
- 事業報告書の作成支援
- 監理費用収支決算書の作成支援
更新申請の支援
- 更新時期のリマインド
- 更新申請書類の作成
- 更新手続きの代行
日常業務のサポート
- 実習監理に関する相談対応
- 監査・訪問指導のアドバイス
- トラブル発生時の対応支援
- 法令改正情報の提供
5. 関連業務のワンストップサポート
事業協同組合設立支援 監理団体として最も一般的な事業協同組合の設立から支援いたします。
技能実習計画認定申請支援 監理団体許可取得後、実際に技能実習生を受け入れるための技能実習計画認定申請もサポートします。
他士業との連携
- 司法書士: 法人登記関連
- 社会保険労務士: 労務管理、社会保険手続き
- 税理士: 会計・税務処理
- 弁護士: 法的トラブル対応
監理団体許可取得の費用と期間
標準的な所要期間
トータル: 約6〜10ヶ月
- 事前準備: 1〜2ヶ月
- 書類作成: 1〜2ヶ月
- 申請から許可まで: 2〜4ヶ月
- 許可証交付: 1〜2週間
※事業協同組合の新規設立から行う場合は、さらに5〜8ヶ月程度必要です。
主な費用
法定費用
- 審査手数料: 無料(外国人技能実習機構への申請)
専門家報酬
- 行政書士報酬: 案件の規模や複雑さにより異なります
- 特定監理事業: 基本報酬+成功報酬
- 一般監理事業: 基本報酬+成功報酬(特定よりも高額)
その他費用
- 書類取得費用: 登記事項証明書、納税証明書など
- 交通費: 外国人技能実習機構への訪問など
- 事業協同組合設立費用(新規設立の場合)
※具体的な金額については、ご相談時にお見積りいたします。
なぜ専門家のサポートが必要なのか
監理団体許可申請は、技能実習法をはじめとする複雑な法令の理解と、膨大な申請書類の作成が求められる高度な手続きです。
専門家に依頼するメリット
1. 確実な許可取得
- 法令要件を完全に満たした申請書類の作成
- 不許可リスクの最小化
- 補正対応の適切な実施
2. 時間とコストの削減
- 書類作成の大幅な時間短縮
- 不備による手戻りの防止
- 一発での許可取得による時間的・金銭的コスト削減
3. 最新情報への対応
- 頻繁に変更される法令・通達への対応
- 審査傾向の把握と対策
- ベストプラクティスの適用
4. 本業への専念
- 複雑な手続きを専門家に任せられる
- 技能実習生受入れの準備に集中できる
- ストレスフリーな申請プロセス
5. 許可取得後のサポート
- 継続的なコンプライアンス支援
- 制度変更への迅速な対応
- トラブル発生時の的確なアドバイス
よくあるご質問
Q1: 株式会社でも監理団体になれますか? A: いいえ、監理団体は営利を目的としない法人である必要があります。株式会社の場合は、まず事業協同組合などの非営利法人を設立する必要があります。
Q2: 一般監理事業と特定監理事業、どちらを選ぶべきですか? A: 第3号技能実習(4〜5年目)まで監理する予定があるか、優良要件を満たせるかによります。初めての場合は特定監理事業から始め、実績を積んでから一般監理事業への変更を目指すのが一般的です。
Q3: 監理団体許可の審査期間はどのくらいですか? A: 標準処理期間は2〜4ヶ月程度ですが、書類の不備や追加資料の要請があった場合はさらに時間がかかることがあります。
Q4: 許可取得後、すぐに技能実習生を受け入れられますか? A: 監理団体許可取得後、個別の技能実習計画の認定を受ける必要があります。認定申請から認定まで1〜2ヶ月程度かかります。
Q5: 監理団体許可の更新手続きは難しいですか? A: 新規申請とほぼ同様の手続きが必要ですが、これまでの実習実績や監理実績が評価されます。適正に監理事業を行っていれば、更新は比較的スムーズです。
Q6: 監理費用はどのくらいに設定すればよいですか? A: 実費相当額の範囲内で設定する必要があり、不当に高額な監理費用は認められません。適切な金額設定について、当事務所がアドバイスいたします。
Q7: 事業協同組合の設立から依頼できますか? A: はい、当事務所では事業協同組合の設立から監理団体許可取得まで一貫してサポートいたします。
監理団体許可取得のポイント
成功のための重要ポイント
1. 早期の準備開始 許可取得には6〜10ヶ月かかります。技能実習生の受入れ予定時期から逆算して、余裕を持って準備を始めましょう。
2. 組織体制の整備 監理責任者、指定外部役員等の適切な人材確保が重要です。人選には十分な時間をかけましょう。
3. 財産的基盤の確保 債務超過状態では許可されません。財務状況の改善が必要な場合は、早めに対策を講じましょう。
4. 適切な事業計画 実現可能性の高い、具体的な事業計画の策定が重要です。机上の空論では許可されません。
5. 専門家の活用 複雑な手続きは専門家に任せ、確実かつ効率的に許可を取得しましょう。
まずは無料相談から
監理団体許可の取得は、技能実習生の適正な受入れと日本の産業発展に貢献する重要な第一歩です。行政書士法人塩永事務所では、豊富な実績と専門知識を活かし、皆様の監理団体許可取得を全面的にサポートいたします。
無料相談で分かること
- 監理団体許可取得の可能性
- 必要な準備と期間
- 具体的な手続きの流れ
- 費用の概算
- 最適なスケジュール
まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。お電話またはメールにてお問い合わせください。
お問い合わせ 行政書士法人塩永事務所 [連絡先096-385-9002 info@shionagaoffice.jp]
技能実習生の受入れは、適切な監理団体の存在が不可欠です。私たちが確実な許可取得をサポートし、皆様の国際貢献と事業発展をお手伝いいたします。
