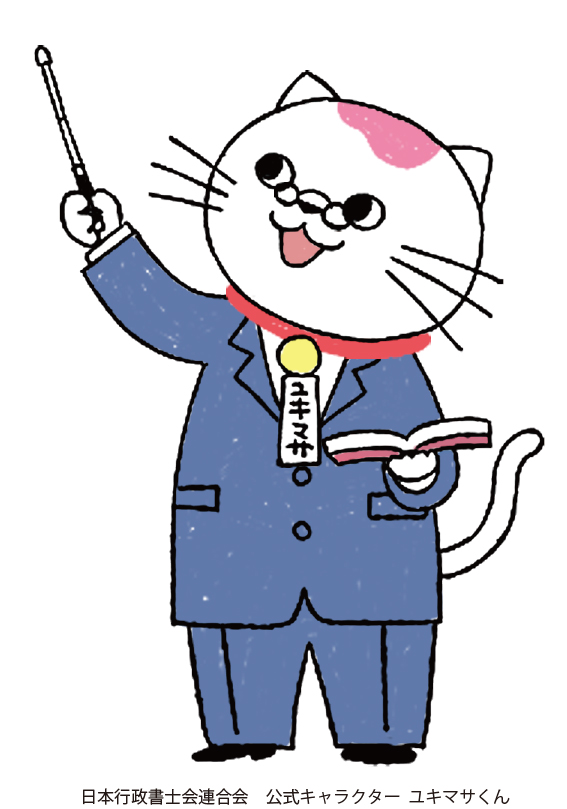
旅行会社の設立:申請手続きから登録までの完全ガイド
行政書士法人塩永事務所 > 許認可ガイド > 旅行会社の設立
はじめに
旅行会社や旅行代理店として事業を営むためには、旅行業法に基づく許認可の取得が必須です。この手続きは「旅行業の登録」と呼ばれ、取り扱う旅行業務の内容によって取得すべき許認可の種類が異なります。
行政書士法人塩永事務所は、旅行業登録手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所として、事業者様の登録申請をサポートいたします。
本ガイドでは、旅行会社設立手続きの詳細についてご説明いたします。
効率的な設立手続きの進め方
以下の順序で進めることをお勧めします。
- 旅行事業に該当するかの検討
- 取得すべき許認可の種類の検討
- 許認可取得条件の検討・調整
- 許認可取得手続きへの着手
この順序で進めることで、手戻りを防ぎ、円滑な手続きが可能となります。
旅行業に該当するかの判断
旅行業の定義
ご相談で最も多いのは、「検討中の事業が旅行業に該当するか」というご質問です。
事業が旅行業に該当するか否かは、以下の3つの条件すべてに該当する場合、旅行業法上の旅行業に該当します。
- 報酬を得ている
- 旅行業法第2条第1号から第9号に記載されている行為を行う
- それを事業として行っている
旅行業法第2条における具体的な行為
旅行業法第2条では、以下の行為が旅行業として定義されています。
第一号:募集型企画旅行の実施
旅行の目的地・日程、運送・宿泊サービスの内容、旅行代金を定めた旅行計画を作成し、必要な運送等サービスの提供に係る契約を自己の計算において締結する行為
第二号:運送等関連サービスの手配
第一号に付随して、運送・宿泊以外の旅行関連サービスの提供に係る契約を自己の計算において締結する行為
第三号:旅行者のための代理・媒介・取次
旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
第四号:サービス提供者のための代理・媒介
運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
第五号:運送機関・宿泊施設を利用したサービス提供
他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
第六号~第八号:付随サービス
前各号に付随する運送等関連サービスの代理・媒介・取次、旅行者の案内、旅券受給のための手続代行その他の便宜サービスの提供
第九号:旅行相談
旅行に関する相談に応ずる行為
登録種別の選択
6つの登録種別
旅行業の登録には、取り扱う旅行業務により、以下の6つの種別があります。
- 第1種旅行業登録
- 第2種旅行業登録
- 第3種旅行業登録
- 地域限定旅行業登録
- 旅行サービス手配業登録
- 旅行業者代理業登録
登録種別ごとの取扱可能業務
| 登録の種別 | 取扱可能な旅行業務 |
|---|---|
| 第1種旅行業 | ・海外・国内の募集型企画旅行<br>・海外・国内の受注型企画旅行<br>・海外・国内の手配旅行<br>・他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結 |
| 第2種旅行業 | ・国内の募集型企画旅行<br>・海外・国内の受注型企画旅行<br>・海外・国内の手配旅行<br>・他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結 |
| 第3種旅行業 | ・営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行<br>・海外・国内の受注型企画旅行<br>・海外・国内の手配旅行<br>・他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結 |
| 地域限定旅行業 | ・営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行<br>・営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の受注型企画旅行<br>・営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の手配旅行<br>・他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結 |
| 旅行サービス手配業 | 旅行業者の依頼を受けて、次のいずれかの手配業務<br>・国内の運送・宿泊<br>・国内の全国通訳案内士・地域通訳案内士以外の有償ガイド<br>・国内の免税店における物品販売<br>※ランドオペレーター業務 |
| 旅行業者代理業 | 旅行業者から委託された業務 |
用語解説
募集型企画旅行
一般にパッケージツアーやパック旅行と呼ばれる旅行商品。旅行会社があらかじめ旅行の目的地・日程、運送・宿泊などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行計画を作成し、パンフレットやインターネットで旅行者を募集して実施する旅行。
受注型企画旅行
フルオーダーメイド型の旅行商品。旅行者からの依頼を受けて、旅行会社が旅行の目的地・日程、運送・宿泊などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行計画を作成・提案し、実施する旅行。
手配旅行
旅行会社が旅行者からの依頼を受けて、旅行者のために運送・宿泊等の旅行サービスの提供を受けることができるよう手配をする旅行。
登録種別の検討方法
顧客が誰かを明確にする
登録種別を検討する際、最初に検討すべきは**「顧客(お客様)が誰であるか」**という点です。
旅行会社が顧客の場合:旅行サービス手配業
顧客を国内・海外の旅行会社と想定し、日本国内の運送・宿泊・ガイド・免税店の手配といったランドオペレーター業務のみを行う場合は、旅行サービス手配業登録をご検討ください。
旅行者(エンドユーザー)が顧客の場合:第1種~第3種、地域限定、旅行業者代理業
顧客を旅行会社に限定せず、旅行者(エンドユーザー)を想定している場合は、第1種、第2種、第3種、地域限定、旅行業者代理業登録をご検討ください。
他社の専属代理店の場合:旅行業者代理業
他の旅行会社の1社専属代理店として旅行事業を行う場合は、旅行業者代理業登録を取得します。
具体的な事業内容による選択
海外パッケージツアーを企画・販売する場合
→ 第1種旅行業登録が必要
国内全域のパッケージツアーを企画・販売する場合
→ 第2種旅行業登録が必要
国内の着地型旅行商品の企画・販売に限定する場合
→ 地域限定旅行業登録をご検討ください
国内・海外の受注型企画旅行や手配旅行を取り扱う場合
→ 第3種旅行業登録が必要
最も登録が多いのは第3種旅行業
日本国内で最も登録が多いのは第3種旅行業です。日本国内には11,107社の旅行会社があり、そのうち5,816社(52.36%)が第3種旅行業登録を取得しています。
第3種旅行業の登録を取得されることが最も多くなっています。第3種旅行業登録取得後、事業規模拡大に合わせて、第2種や第1種へと登録種別を変更される旅行会社様もいらっしゃいます。
地域限定旅行業は登録取得のハードルが低く、他の旅行業登録と比較すると取得しやすい点が魅力ですが、取扱可能な旅行業務の範囲が限定されています。検討中の旅行業務が地域限定旅行業者の取扱可能範囲内に収まっていれば問題ありませんが、実際には範囲を超えているケースが多い印象です。
そのため、これから旅行業へ参入される方は、まず第3種旅行業登録の取得を検討されることをお勧めします。
旅行業登録の条件
登録種別の検討が完了したら、次はその種別の登録条件の確認に進みます。
旅行業の登録を取得するには、法令等で定められた条件を満たす必要があります。この条件は「登録要件」とも呼ばれ、取得する登録種別により異なります。
一般に許認可取得のための条件は、**「人」「モノ」「お金」**の3つの要素に整理すると、条件を漏れなく検討できます。
登録種別ごとの要件
| 登録種別 | 人 | モノ | お金 |
|---|---|---|---|
| 第1種旅行業 | ○ | ○ | ○ |
| 第2種旅行業 | ○ | ○ | ○ |
| 第3種旅行業 | ○ | ○ | ○ |
| 地域限定旅行業 | ○ | ○ | ○ |
| 旅行業者代理業 | ○ | ○ | × |
| 旅行サービス手配業 | ○ | ○ | × |
第1種~地域限定旅行業の登録を取得するには、「人」「モノ」「お金」の3つの要素をクリアしなければなりません。一方、旅行業者代理業と旅行サービス手配業の登録を取得するには、「人」と「モノ」の2つの要素のみをクリアすればよく、お金に関する条件は定められていません。
「人」に関する条件
登録拒否事由に該当しないこと
申請者が旅行業法第6条で定められている登録拒否事由に該当する場合は、申請をしても登録は拒否されます。
旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録は、法人で取得されることが多いですが、制度上は個人事業主でも登録の取得は可能です。
法人の場合
取締役や監査役といった役員が、登録拒否事由に該当していないことが求められます。
個人事業主の場合
当該本人が、登録拒否事由に該当していないことが求められます。
さらに、営業所で選任する旅行業務取扱管理者も、登録拒否事由に該当していないことが求められます。
旅行業法第6条(登録の拒否)の主な事由
- 旅行業若しくは旅行業者代理業の登録、又は旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 暴力団員等
- 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号等のいずれかに該当するもの
- 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
- 必要と認められる財産的基礎を有しないもの
- 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
例えば、旅行業法に違反して旅行業登録を取り消された法人の役員に就任していた方は、取消しの日から5年間は、旅行業登録申請予定の法人の役員や旅行業務取扱管理者になることはできません。また、破産手続開始の決定を受けて復権していない場合も同様です。
旅行業務取扱管理者の選任
旅行業務取扱管理者とは
旅行業務取扱管理者は、顧客との旅行取引に関する責任者です。以前は「旅行業務取扱主任者」と呼ばれていました。
登録を取得するには、1営業所につき1名以上の旅行業務取扱管理者の選任が求められます。旅行業務を取り扱う従業員が10名以上になる営業所では、複数名の管理者の選任義務が生じます。
選任の意味
ここでの「選任」の意味は、常勤雇用を意味します。したがって、旅行業務取扱管理者は役員である必要はなく、使用人(従業員)であれば選任できます。
ただし、勤務実態のない方を選任だけする、いわゆる名義貸しは認められません。他の旅行業者や他の営業所との兼任は原則できませんが、地域限定旅行業者に限り、以下の条件を満たす場合は、一人の旅行業務取扱管理者が自社で運営する複数の営業所の管理者を兼任できます。
- 営業所間の直線距離が40km以下である
- その営業所の取引額の合計が1億円以下の場合
旅行業務取扱管理者が兼任できるのは、地域限定旅行業で上記の条件を満たす場合に限られます。したがって、第1種、第2種、第3種、旅行業者代理業、旅行サービス手配業では、営業所間での兼任はできません。
旅行業務取扱管理者の資格
旅行業務取扱管理者には、誰でも選任できるわけではありません。旅行業務取扱管理者の資格を有する方を常勤雇用することが求められます。
4つの資格
- 総合旅行業務取扱管理者試験合格者
- 国内旅行業務取扱管理者試験合格者
- 地域限定旅行業務取扱管理者試験合格者
- 旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了者
登録種別ごとに選任できる資格者
| 資格 | 第1種・第2種・第3種・旅行業者代理業<br>(海外旅行・国内旅行) | 第1種・第2種・第3種・旅行業者代理業<br>(国内旅行のみ) | 地域限定旅行業 | 旅行サービス手配業 |
|---|---|---|---|---|
| 総合旅行業務取扱管理者試験合格者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 国内旅行業務取扱管理者試験合格者 | × | ○ | ○ | ○ |
| 地域限定旅行業務取扱管理者試験合格者 | × | × | ○ | × |
| 旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了者 | × | × | × | ○ |
第1種、第2種、第3種、旅行業者代理業
選任する営業所での取扱業務が海外・国内の両方なのか、それとも国内旅行のみなのかにより、選任できる合格者の資格が異なります。
- 海外旅行を取り扱う営業所:「総合」の合格者のみ
- 国内旅行のみを取り扱う営業所:「総合」「国内」のいずれかの合格者
「地域限定」の合格者と旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了者は選任できません。
地域限定旅行業
「総合」「国内」「地域限定」の合格者を旅行業務取扱管理者に選任できます。
旅行サービス手配業
「総合」「国内」の合格者もしくは旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了者を旅行業務取扱管理者として選任できます。
それぞれの資格については、資格名をインターネット上で検索すると、資格の取得方法を確認できます。
5年ごとの旅行業務取扱管理者定期研修
「総合」「国内」「地域限定」旅行業務取扱管理者試験合格者を選任する場合、選任する旅行業務取扱管理者は、5年ごとに旅行業務取扱管理者定期研修を受講していることが求められます。
旅行業務取扱管理者定期研修は、旅行業協会が実施する、旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るための研修です。
ただし、選任日から5年以内の試験合格者に限っては、選任に際しての受講義務は免除されます。
登録申請前に受講できない場合の特例
定期研修の受講義務がある方が登録申請前に受講できない場合は特例があります。
選任予定の合格者が5年以内に定期研修を受講していない場合は、旅行業の登録取得後に実施する定期研修を受講し、受講後に観光庁や都道府県に受講証を届け出る旨の誓約書を提出することで、定期研修受講義務のある方であっても、受講前に旅行業務取扱管理者に選任できます。
「モノ」に関する条件
営業所の確保
「モノ」に関する条件のモノは、営業所です。
旅行業務を行う営業所の確保が必要となります。営業所の広さや設備の要件は法令で定められていませんが、旅行会社の実在性が担保できる営業所が必要です。
営業所における掲示・備え置き義務
第1種、第2種、第3種、地域限定及び旅行業者代理業の営業所
- 登録票の掲示
- 取扱料金表の掲示
- 旅行業約款の掲示もしくは備え置き
これらを行わなければならないと法律で定められています。
旅行サービス手配業
登録票や料金表の掲示義務、旅行業約款の掲示もしくは備え置きの義務は課されていませんが、選任した旅行業務取扱管理者が旅行業務を行う場所を確保するという意味でも、実態のある営業所を確保する必要があります。
使用権限を証する書類
手続き上は、観光庁や、北海道、宮城県、愛知県、京都府、大阪府、福岡県が登録行政庁である場合は、使用権限を証する書類の提出は求められていません。
それに対して東京都、神奈川県、埼玉県が登録行政庁の場合は、使用権限を証明する書類として、
- 自社所有物件の場合:建物登記簿謄本
- 賃貸物件の場合:賃貸借契約書の写し
を提出する必要があります。
営業所の注意点
自己所有物件の場合
自己所有物件の場合、オフィスビルの1室を旅行業の営業所として使用する場合は問題になる点はありませんが、所有している分譲マンションの一部屋を旅行会社の営業所として使用する場合は、当該マンションの管理規約違反にならないよう注意が必要です。
一般的なマンションの管理規約は使用目的を住居に限定していますので、旅行業の営業所として使用される区分所有物件が、事務所として使用できるか否かを管理組合に事前に確認する必要があります。
賃貸物件の場合
賃貸物件の場合は、賃借人は旅行業務を行う申請人名義であることが求められます。
旅行業務を法人で行う場合、賃借人が社長個人名義の契約書の写しで登録申請手続きを進めようとする方がいらっしゃいますが、社長個人と法人とは別人格として扱われますので、必ず法人名義での賃貸借契約が必要です。
まとめ
旅行会社の設立には、事業内容の明確化、適切な登録種別の選択、登録要件の充足という段階的なプロセスが必要です。
行政書士法人塩永事務所では、旅行業登録手続きを専門的に取り扱っており、豊富な実績に基づいた的確なアドバイスとサポートを提供しております。
旅行業登録に関するご相談は、お気軽行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。
096-385-9002
行政書士法人塩永事務所
旅行業登録手続き専門行政書士事務所
