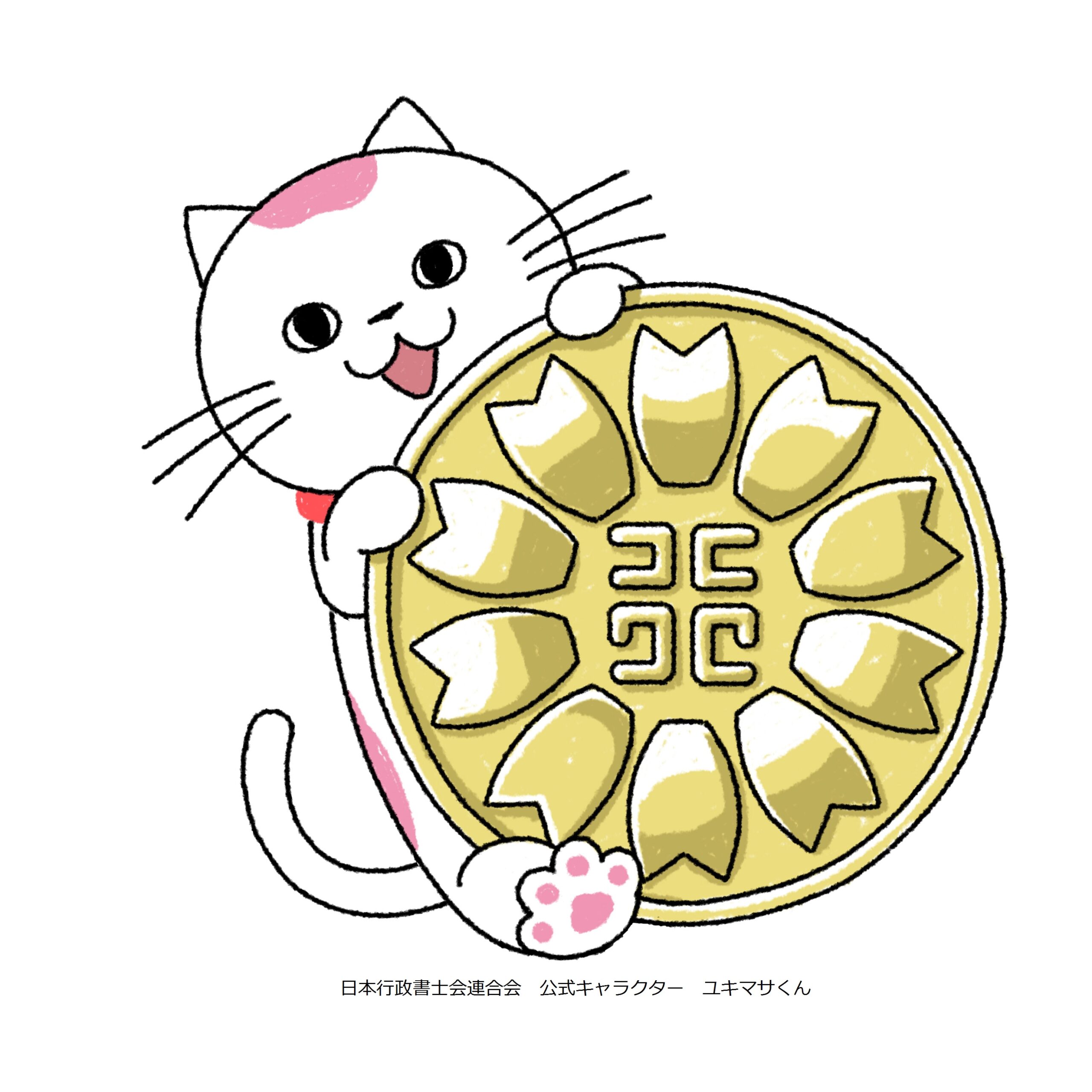
【離婚協議】行政書士法人塩永事務所がサポートする、納得のいく離婚協議書の作成
行政書士法人塩永事務所では、ご相談者様のご希望や状況を丁寧に伺い、法的に有効かつ実用的な離婚協議書の作成を全面的に支援いたします。
協議離婚とは
夫婦が話し合いによって離婚の合意に至り、離婚届を役所に提出することで成立する離婚の形式を「協議離婚」と呼びます。日本では最も一般的かつ手続きが簡易な離婚方法であり、多くの夫婦がこの方法を選択しています。
しかし、協議離婚は手続きが簡単である反面、養育費・財産分与・慰謝料・親権などの重要な取り決めを曖昧なまま離婚してしまうケースも少なくありません。その結果、離婚後にトラブルが発生する可能性があります。
こうした事態を防ぐためには、離婚時に夫婦間で十分に話し合い、合意内容を「離婚協議書」として文書化しておくことが極めて重要です。
離婚の基本的な流れ
- 一方が離婚を提案する
- 離婚条件(財産分与・養育費・親権など)について協議する
- 離婚協議書を作成する
- 離婚届を役所に提出する
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚に際して夫婦間で合意した内容を記載した契約書です。口頭での合意では証拠能力が弱く、後々のトラブルを防ぐためにも、文書として残すことが推奨されます。
特に以下のような事項については、明確に記載しておく必要があります:
- 離婚の合意と協議離婚である旨
- 離婚届の提出日および提出者
- 財産分与の内容(対象財産、支払者・受取者、金額、支払方法、支払期日)
- 年金分割に関する取り決め
- 慰謝料の有無とその詳細(支払者・受取者、金額、支払方法、支払期日)
- 養育費の詳細(支払者・受取者、金額、支払方法、支払期日、支払終了時期、特別支出時の負担割合)
- 未成年の子の親権者・監護者の指定
- 面会交流の頻度・方法・時間帯・子の受け渡し方法
- 強制執行認諾文言付き公正証書の作成に関する合意
- 同一内容の書面を2通作成し、夫婦それぞれが保管する旨
離婚協議書には、夫婦双方の氏名・住所を記載し、署名押印を行います。なお、離婚協議書には法定の様式は存在しないため、当事者間で自由に作成可能です。
離婚協議書作成に必要な書類
状況に応じて必要書類が異なりますが、以下は基本的な必要書類とケース別の追加書類です。
基本書類(すべてのケースに共通)
- 印鑑登録証明書(発行から3か月以内)と実印 ※外国籍または海外在住で日本に住所がない方は「サイン証明書」で代用可能(領事館・大使館で取得)
- 本人確認書類(以下のいずれか) - 運転免許証+認印 - 顔写真付き住民基本台帳カード+認印 - パスポート+認印
- 代理人を立てる場合:代理人の本人確認書類、依頼者の印鑑登録証明書、委任状
ケース別追加書類
未成熟子がいる場合
未成熟子とは、経済的に自立していない子どもを指します。未成年であっても自立していると認定されれば該当しません。
財産分与がある場合
財産の種類に応じて以下の書類が必要です:
| 財産の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 不動産 | 不動産登記簿謄本(3か月以内)、固定資産税評価証明書 |
| 自動車 | 車検証、査定書(資産価値がある場合) |
| 生命保険 | 保険証券、解約返戻金証明書 |
| 有価証券 | 株式等を証明する資料 |
| 年金分割 | 夫婦双方の年金手帳(コピー可)、年金分割のための情報提供通知書 |
離婚協議書作成時の注意点
- 公正証書化の推奨 離婚協議書を公正証書にすることで、相手が約束を守らなかった場合に強制執行(給与差押え・預金口座凍結など)が可能になります。公証役場で公証人の面前で作成するため、法的効力と安心感が得られます。
- DV・モラハラの懸念がある場合は専門家へ相談 離婚を切り出すことで相手が逆上する可能性があるため、人目のある場所で話す、信頼できる第三者を同席させるなどの対策が必要です。
- 子どもの前での話し合いは避ける 夫婦間の争いは子どもに心理的な影響を与える可能性があります。話し合いは子どものいない場所で行いましょう。
- 事前に条件を整理しておく 話し合いの場では感情的になりやすいため、事前に希望する条件を紙に書き出し、「譲れる条件」と「譲れない条件」を明確にしておくとスムーズです。
- 離婚届の不正提出を防ぐための対策 協議離婚は双方の合意が前提ですが、稀に一方が勝手に離婚届を提出するケースがあります。これを防ぐには、事前に「離婚届不受理申出」を役所に提出しておくことが有効です。申出が受理されていれば、相手が勝手に提出しても離婚は成立しません。
ご相談は行政書士法人塩永事務所へ
離婚協議書の作成は、法的知識と文書作成の専門性が求められます。行政書士はその道のプロフェッショナルです。後々のトラブルを未然に防ぐためにも、確実な手続きを行いましょう。
