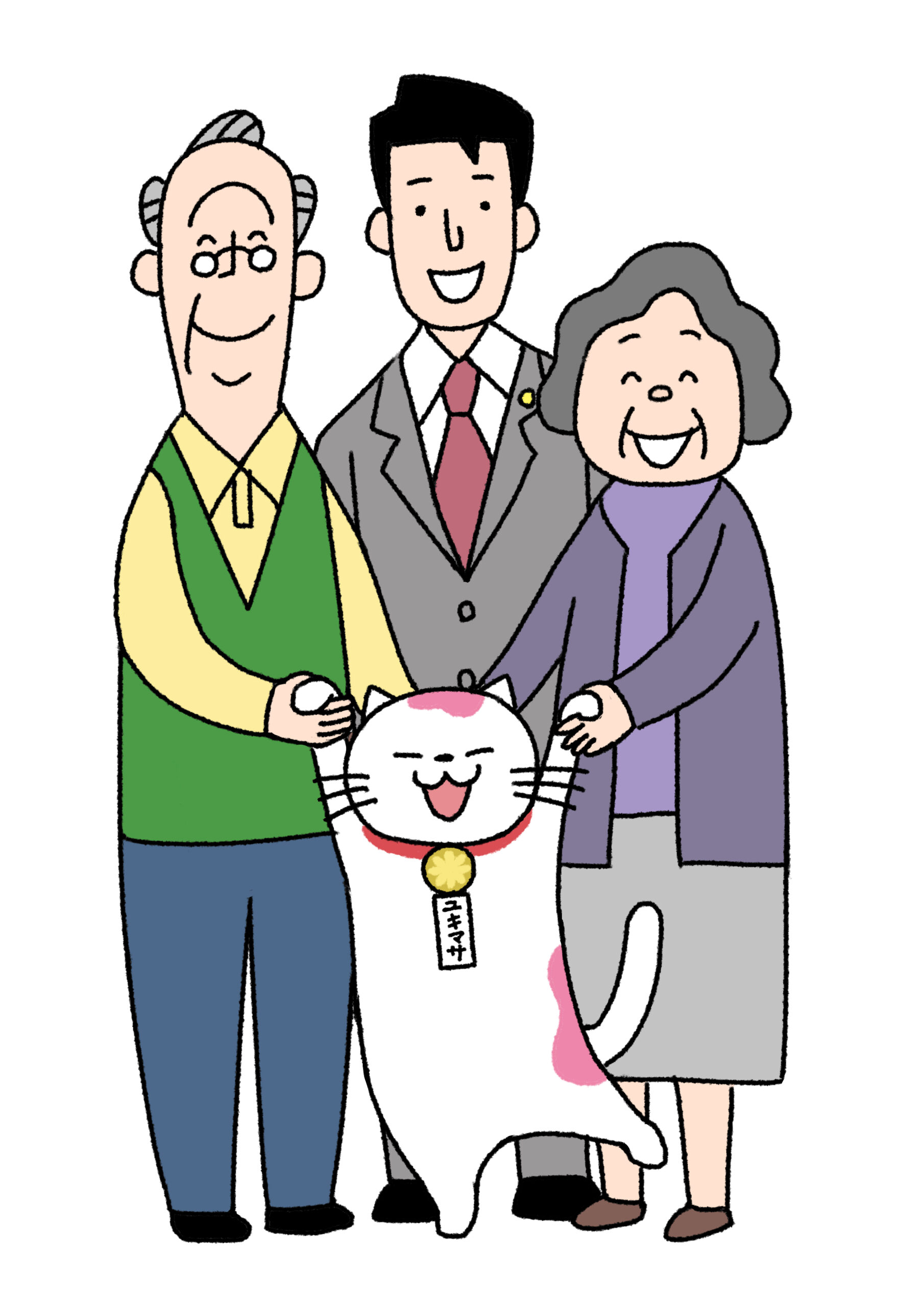
配偶者ビザ(在留資格)の法的要件と手続きの専門的解説
行政書士法人塩永事務所
1. 法的根拠と在留資格の定義
1.1 在留資格の法的位置づけ
配偶者ビザは、出入国管理及び難民認定法(入管法)第2条の2第1項に基づく在留資格であり、正式には以下の2つの在留資格に分類されます:
「日本人の配偶者等」(入管法別表第二の上欄)
- 法的根拠:入管法別表第二の「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」
- 対象者:日本国民の配偶者、日本国民の特別養子、日本国民の子として出生した者
「永住者の配偶者等」(入管法別表第二の下欄)
- 法的根拠:入管法別表第二の「永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」
- 対象者:永住者・特別永住者の配偶者、永住者・特別永住者の子として日本で出生し継続在留している者
1.2 法定要件の構造
入管法第7条第1項第2号に基づき、在留資格該当性と上陸許可基準適合性の双方を満たす必要があります:
- 在留資格該当性:当該外国人の活動が別表記載の活動に該当すること
- 上陸許可基準適合性:法務省令で定める上陸許可基準に適合すること
- その他の要件:素行が不良でないこと等(入管法第7条第1項第4号)
2. 婚姻の適法性に関する法的要件
2.1 準拠法の適用原則
国際私法(法の適用に関する通則法)第24条第1項により、婚姻の成立要件は各当事者の本国法によって判断されます:
日本人配偶者側の要件
- 民法第731条~第737条の婚姻要件(年齢、重婚禁止、近親婚禁止等)
- 戸籍法第74条に基づく婚姻届の提出義務
外国人配偶者側の要件
- 当該外国人の本国法による婚姻成立要件
- 領事婚、宗教婚等の本国における有効な婚姻手続きの完了
2.2 婚姻の方式に関する準拠法
通則法第24条第2項により、婚姻挙行地法または当事者の本国法のいずれかに適合すれば足ります:
創設的届出主義国(日本等)の場合
- 市区町村長への婚姻届提出により婚姻成立
- 戸籍法第25条による受理要件の充足が必要
報告的届出主義国の場合
- 宗教的挙式、民事挙式等の実質的婚姻成立行為が前提
- その後の役所への届出は報告的性質
2.3 重国籍者・無国籍者の特例
重国籍者の場合(通則法第38条第1項)
- 日本国籍を有する場合:日本法を適用
- 日本国籍を有しない場合:最も密接な関係を有する地の法
無国籍者の場合(通則法第38条第3項)
- 常居所地法を適用
3. 在留資格認定証明書交付申請の法的構造
3.1 法的性質と効果
行政処分としての性質
- 入管法第7条の2第1項に基づく要証明行為
- 行政手続法の適用対象(同法第2条第4号)
- 審査基準の公表義務(行政手続法第5条)
証明書の法的効力
- 有効期間:交付日から3か月間(入管法施行規則第6条の2第3項)
- 推定効:上陸許可要件適合の事実上の推定力
- 拘束力:査証発給における事実上の拘束力(外務省査証発給内規)
3.2 審査基準の法的根拠
入管法施行規則第6条の2第2項 申請書、質問書、立証資料等の提出義務
法務省告示(上陸許可基準)
- 日本人配偶者:特段の基準なし(素行・公安要件のみ)
- 永住者配偶者:特段の基準なし(同上)
3.3 代理申請の法的根拠
法定代理人による申請
- 入管法第7条の2第2項:16歳未満の者に係る申請
- 民法上の法定代理権に基づく
任意代理人による申請
- 入管法施行規則第6条の2第6項:弁護士・行政書士等の申請取次者
- 委任契約に基づく代理権の明示が必要
4. 在留資格変更許可申請の法的要件
4.1 法的根拠と要件
入管法第20条第2項 在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可
変更許可の判断基準
- 申請に係る在留資格への該当性
- 上陸許可基準への適合性
- 現在の在留状況の適法性
- 変更の相当性・必要性
4.2 現在の在留活動との関係
在留資格該当活動からの逸脱
- 入管法第22条の4第1項第6号:在留資格取消事由
- ただし、正当な理由がある場合は考慮(同条第2項)
資格外活動許可との関係
- 入管法第19条第2項:原則として許可を要する
- 包括許可(週28時間以内)と個別許可の区別
5. 婚姻の真正性に関する立証責任と証明度
5.1 立証責任の分配
申請人側の立証責任
- 在留資格該当性の立証(民事訴訟法第147条類推適用)
- 真正な婚姻関係存在の主張立証責任
入管当局の立証責任
- 偽装結婚等の消極的事実の立証は困難
- 疑念惹起程度で申請人側に反証責任転換
5.2 証明度と心証形成
民事訴訟における証明度
- 高度の蓋然性(最高裁昭和50年10月24日判決)
- 行政処分における証明度も同等と解される
間接事実による推認
- 交際期間、年齢差、経済格差等の間接事実
- 総合考慮による心証形成(経験則の適用)
6. 身元保証制度の法的性質
6.1 法的根拠と性質
入管法第7条第1項第2号ホ 身元保証人がいること(永住許可の場合)
行政指導としての性質
- 配偶者ビザでは法定要件ではない
- 事実上の審査要件として運用
6.2 保証債務の法的効力
道義的責任説(通説・判例)
- 法的拘束力なし(東京地裁昭和62年3月30日判決)
- 行政指導の一環としての位置づけ
保証内容
- 滞在費の支弁
- 法令遵守の指導
- 出頭要請への協力
7. 経済的要件の法的基準
7.1 生計要件の法的根拠
生活保護法第4条第2項(補足性の原理)
- 「その他あらゆるものを」活用した上での最終手段
- 外国人の生活保護受給権は限定的(最高裁平成26年7月18日判決)
7.2 所得基準の運用
明示的基準の不存在
- 法令上の明文規定なし
- 実務上の目安:生活保護基準×1.5倍程度
総合判断要素
- 継続安定収入の存在
- 資産状況(預貯金、不動産等)
- 扶養家族の状況
- 身元保証人の経済力
8. 審査手続きの法的統制
8.1 行政手続法の適用
申請に対する処分(同法第2条第3号)
- 審査基準の設定・公表義務(第5条)
- 標準処理期間の設定・公表努力義務(第6条)
- 理由提示義務(第8条)
8.2 情報公開・個人情報保護
行政機関情報公開法
- 不開示情報該当性の判断(第5条各号)
- 第三者情報の保護(第5条第2号)
個人情報保護法(行政機関等)
- 利用目的の明示(第61条)
- 第三者提供の制限(第69条)
9. 不許可処分に対する救済手続き
9.1 行政救済
異議申立て(入管法第61条の2の10)
- 法務大臣に対する異議申立て
- 申立期間:処分を知った日から7日以内
再審査請求
- 入管法上の明文規定なし
- 行政不服審査法第18条第1項ただし書きにより排除
9.2 司法救済
取消訴訟(行政事件訴訟法第3条第2項)
- 出訴期間:処分を知った日から6か月以内(第14条)
- 管轄:東京地方裁判所(第12条第4項)
執行停止(同法第25条)
- 回復困難な損害要件
- 公共の福祉への重大な影響考慮
10. 在留資格取消制度との関係
10.1 取消事由(入管法第22条の4第1項)
第7号:偽りその他不正の手段による許可取得
- 虚偽書類提出、重要事実の秘匿等
- 故意・重過失を要件とする解釈が一般的
第6号:正当な理由なき在留資格該当活動の不実施
- 離婚後の配偶者ビザ継続保持
- 「正当な理由」の立証責任は外国人側
10.2 意見聴取手続き(同条第3項)
聴聞手続きの準用
- 行政手続法第3章第2節の準用
- 代理人選任権、証拠書類等の閲覧権
11. 特殊事例における法的考慮
11.1 事実婚・内縁関係
法律婚主義の原則
- 民法第739条:婚姻は届出により効力発生
- 事実婚では在留資格該当性なし
例外的考慮
- 宗教的・文化的制約による場合の人道的配慮
- 特定活動(告示外)での対応可能性
11.2 同性婚
現行法下での取扱い
- 民法第24条第1項「夫婦」概念の解釈
- 現在は在留資格該当性なし
将来的課題
- 憲法第24条第2項の解釈問題
- 国際人権法との整合性
12. 国際法・条約との関係
12.1 市民的及び政治的権利に関する国際規約
第23条第1項:家族の保護
- 「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位」
- 国家の保護義務
12.2 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
第5条(d)(vi):婚姻・家族の権利
- 人種差別撤廃義務
- 間接差別の禁止
12.3 児童の権利に関する条約
第10条第1項:家族再統合
- 家族再統合の申請を人道的・迅速・積極的に取り扱う義務
結論
配偶者ビザの申請は、入管法を中心とした複層的な法的要件の充足を要求する高度に専門的な手続きです。単なる書類の収集・提出にとどまらず、国際私法、民法、行政法等の深い理解に基づく総合的な法的構成が不可欠です。
当事務所では、これらの法的要件を正確に把握し、個別事案に応じた最適な法的戦略を構築いたします。複雑な法的問題についても、豊富な実務経験と専門知識に基づき、確実な許可取得を目指します。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
TEL: 096-385-9002
営業時間: 平日9:00-18:00(土日祝日・夜間も対応可)
