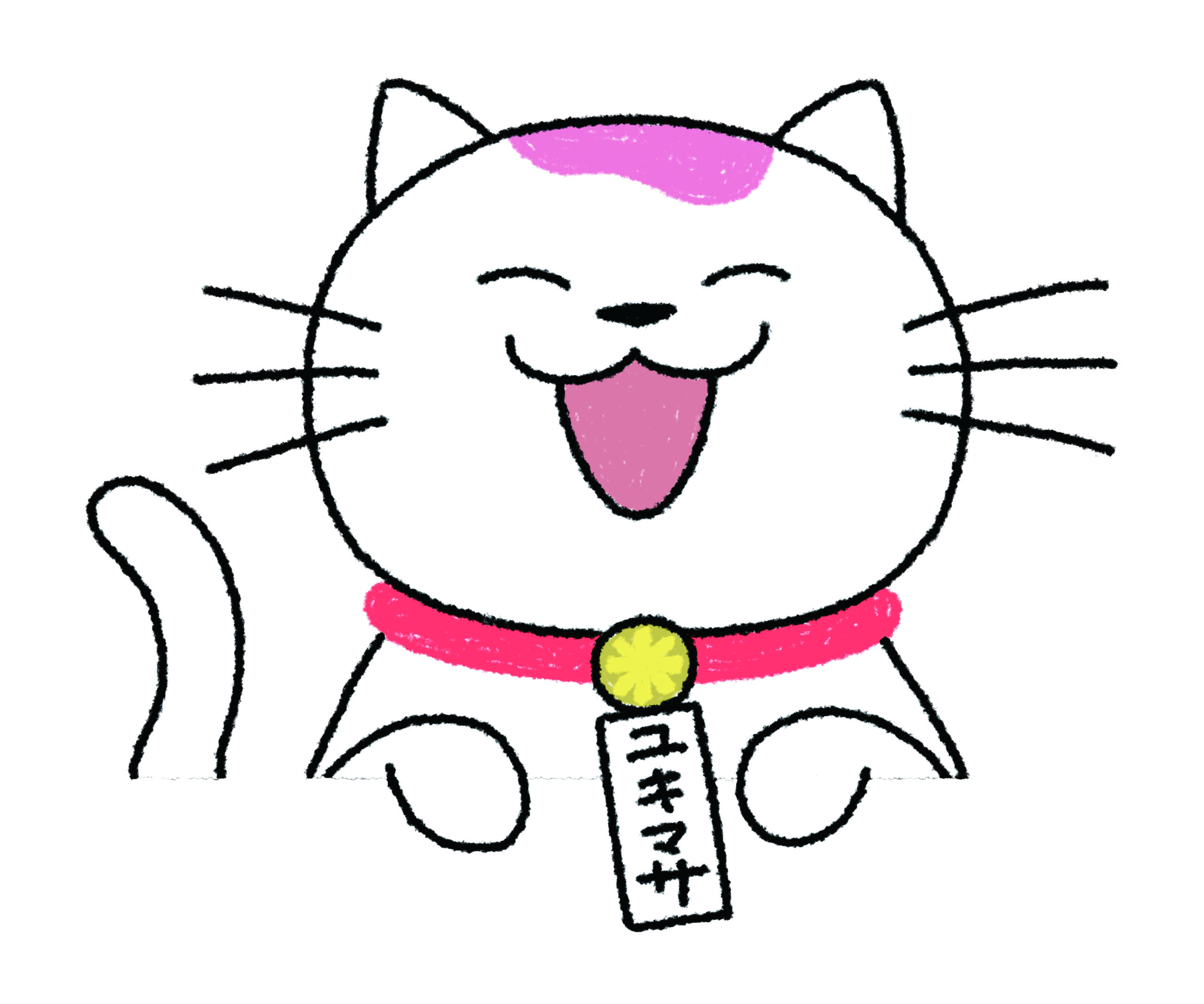
離婚協議書作成サポート — 熊本の行政書士法人塩永事務所におまかせください
行政書士法人塩永事務所は、離婚協議書の作成から公正証書化、必要書類の整理までワンストップで支援します。スピーディーかつ丁寧な対応で、当事者間の合意内容を漏れなく文書化し、離婚後のトラブルを未然に防ぐことを目指します。まずはご相談だけでもお気軽にどうぞ — 相談によってはその場で解決することも少なくありません。
離婚協議書とは(作成の意義)
離婚協議書は法的に作成義務のある書類ではありませんが、離婚後のトラブル防止という点で極めて有用です。主な目的は次の通りです。
-
契約不履行(約束どおりの履行がされないこと)の抑止
-
合意内容の齟齬や解釈の違いを未然に防止
-
金銭や財産の取り扱いについて明確にして後日の争いを回避
離婚協議書に記載すべき主な項目(より詳しく)
下記は実務上、必ず検討・記載することをおすすめする事項です。合意内容は具体的に、可能な限り数値や期日を明記することが重要です。
1. 離婚の合意(離婚届関連)
-
当事者が離婚に合意している旨
-
離婚届の提出日、提出者(どちらが役所へ出すか)、提出先(市区町村)
-
離婚届提出後の手続きに関する役割分担
2. 親権・監護に関する事項
-
未成年の子がいる場合は子の氏名・生年月日・親権者(父/母)
-
監護権や監護の実務(日常の養育に関する取り決め)
-
児童扶養手当・医療保険の加入関係などの取り扱い(必要に応じて)
3. 養育費・教育費・面会交流
-
養育費の支払い有無、金額、支払期間(例:子が自立するまで、○歳まで等)
-
支払方法(毎月の振込、期日)、振込手数料の負担者
-
養育費の見直し条項(収入変動や事情変更時の再協議方法)
-
医療費・教育費(入学金・学費・進学時の費用等)の負担割合と支払い方法
-
面会交流の可否、方法(面会・宿泊交流など)、頻度、日時・場所、実施にあたってのルール
4. 慰謝料・財産分与
-
慰謝料の有無・金額・支払期日・支払方法(振込等)・振込手数料負担者
-
財産分与の対象財産(不動産・預貯金・株式・退職金・保険の解約返戻金等)、評価方法、分与の方法(現金精算・共有名義の解消等)
-
負債(借入金・住宅ローン等)の負担・精算方法
-
税金・名義変更に関する実務(引渡し・登記手続きの負担者、必要書類)
5. 年金分割
-
年金分割の対象は**厚生年金(旧共済年金を含む)**が中心です。国民年金の取り扱い等は個別に確認が必要です。
-
年金分割の合意がある場合は、その方式(合意分割:協議による割合の定め、又は2分の1を上限とする等)や、年金事務所への手続きに関する取り決めを記載します。
6. 清算条項・その他
-
離婚協議書に明記された事項以外の請求を原則として行わない旨(清算条項)を入れるかどうか
-
秘密保持、第三者への通知、将来紛争が生じた場合の紛争解決方法(協議→調停→裁判等の順序)や準拠法の明示
公正証書化(公証役場での作成)のメリットと注意点
離婚協議書を公正証書にすると、養育費や慰謝料などの金銭債務について、原則として裁判手続を経ずに強制執行が可能になるため、実務上の拘束力が高まります(不履行時の回収可能性の向上)。
公正証書作成時に必要となる主な書類(代表例)
行政書士が代理人として公証役場へ出頭する場合にも、次のような書類を整えておく必要があります。案件によって追加書類が求められることがあります。
-
依頼人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
-
委任状(代理出頭する場合)
-
不動産の財産分与がある場合:登記事項証明書(登記簿謄本)・固定資産評価証明書
-
年金分割の合意を行う場合:年金分割用の情報通知書(年金機構が発行する書類)・年金手帳のコピー等
-
金銭債務の公正証書化で印鑑の実印や印鑑証明が必要となる場合があります(公証役場の運用により異なります)
-
その他:戸籍謄本、住民票、預金通帳の写し、給与明細等(必要に応じて)
※ 上記は代表例です。公証役場や個別の合意内容により必要書類は異なりますので、事前に当事務所が確認・準備をサポートします。
当事務所がご提供するサポート内容(実務フロー)
-
初回相談(面談/電話/オンライン) — 現状ヒアリング、主なリスクや解決案の提示
-
協議内容の整理・ドラフト作成 — 合意案を法律用語も踏まえて分かりやすく書面化
-
当事者間の文言調整支援 — 表現の齟齬を減らすための修正提案と交渉サポート(希望があれば立ち合い)
-
公正証書作成支援(必要時) — 公証役場との事前打合せ、必要書類の収集、代理出頭(委任状による)
-
年金分割・関連手続の補助 — 年金機構への申請準備や情報通知書の取得支援(必要に応じ)
-
書類保管・後続手続きの案内 — 名義変更、戸籍謄本の請求、役所手続き等のフォロー
よくあるご質問(FAQ)
Q. 離婚協議書は作れば必ず効力がありますか?
A. 合意内容は当事者間で法的効力を持ちますが、金銭債務の強制執行を想定するなら公正証書化を強くおすすめします。個別の事情で対応方法が変わるため、まずはご相談ください。
Q. 養育費の金額はどう決めればいいですか?
A. 収入、子の人数・年齢、生活費・教育費の見込み等を総合して決めます。将来の変動に備えた見直し条項を入れることも一般的です。
Q. 当事務所は代理で公証役場に行けますか?
A. はい。委任状があれば代理で出頭して手続きを進めることが可能です。事前に必要書類を整理し、当事務所が窓口対応いたします。
対応時間・ご予約について
日曜・祝日・夜間でもご予約いただければ対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。相談だけで解決するケースも多数あります。
行政書士法人 塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
対応エリア
北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/新潟県/富山県/石川県/福井県/山梨県/長野県/岐阜県/静岡県/愛知県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県(全国対応)
