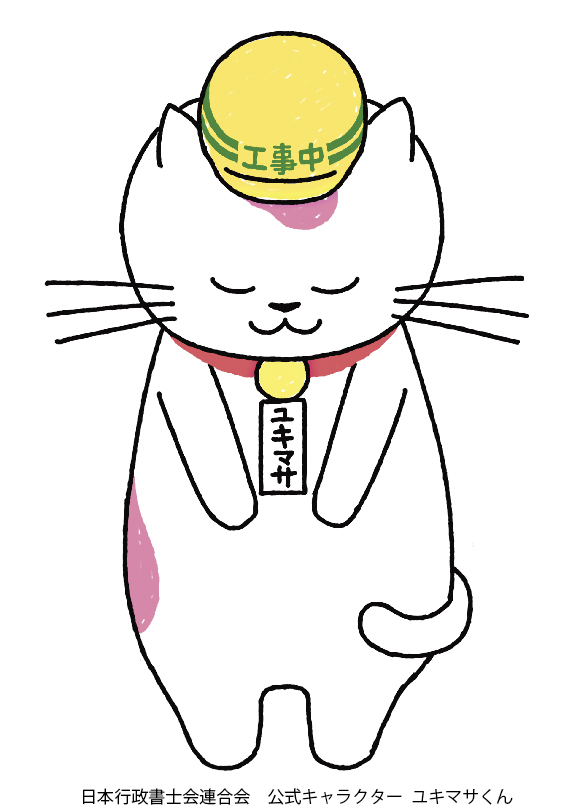
建設業許可申請手続きのすべて~建築・とび・土工等の許可取得を徹底解説~
建設業を営む上で、多くの場合必要となるのが**「建設業許可」**です。特に、建築工事業、とび・土工工事業など、幅広い業種においてこの許可は事業継続の生命線となります。
しかし、建設業許可の申請手続きは複雑で、多くの書類準備や専門知識が求められます。「何から手をつけていいか分からない」「要件を満たしているか不安」といったお悩みをお持ちの事業者様も少なくないでしょう。
行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請のプロフェッショナルとして、数多くの事業者様の許可取得をサポートしてまいりました。この記事では、建設業許可申請の基本から、必要書類、手続きの流れ、そして許可取得後の注意点まで、詳細かつ分かりやすく解説します。
これから建設業許可の取得を目指す方はもちろん、既に許可をお持ちで更新や変更を検討されている方も、ぜひ最後までお読みください。
1. 建設業許可とは?なぜ必要?
建設業許可とは、建設工事を請け負うために必要な許可です。建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者に義務付けられています。
【なぜ建設業許可が必要なのか?】
- 信頼性の向上: 許可を受けていることで、事業者の技術力や経営体制が一定水準以上であることが公的に認められ、取引先や金融機関からの信頼を得やすくなります。
- 請負金額の制限撤廃: 許可がなくても請け負える工事は「1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)」に限定されます。これを超える工事を請け負うためには、建設業許可が必須です。
- 公共工事の受注: 公共工事の入札に参加するためには、建設業許可が前提となります。
- 金融機関からの融資: 融資を受ける際に、建設業許可の有無が審査に影響を与えることがあります。
つまり、建設業許可は、事業の拡大や安定した経営を目指す上で、欠かせない重要なステップなのです。
2. 許可の種類と管轄
建設業許可には、いくつかの種類があり、事業所の所在地や請け負う工事の範囲によって管轄が異なります。
(1) 知事許可と大臣許可
- 知事許可: 営業所が同一の都道府県内のみにある場合に取得する許可です。
- 大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合に取得する許可です。
当事務所は熊本に拠点を置いておりますので、主に熊本県内の知事許可申請を多く扱っておりますが、大臣許可申請についてもサポートが可能です。
(2) 特定建設業許可と一般建設業許可
請け負う工事の規模によって、さらに2つの種類に分けられます。
- 一般建設業許可: 発注者から直接請け負う1件の工事につき、下請契約の合計額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の工事を行う場合に必要です。
- 特定建設業許可: 発注者から直接請け負う1件の工事につき、下請契約の合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる工事を請け負う場合に必要です。特定建設業許可は、下請業者を保護する目的で、より厳しい要件が課せられています。
自社の事業規模や将来の展望に合わせて、どちらの許可が必要かを見極めることが重要です。
(3) 建設工事の種類(業種)
建設業許可は、29種類の工事区分(業種)ごとに取得します。建築工事業、とび・土工工事業は代表的な業種ですが、他にも多岐にわたります。
主な29業種
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事(平成28年6月1日追加)
自社が請け負う(または請け負う予定の)工事がどの業種に該当するかを確認し、必要な業種すべてで許可を取得する必要があります。
3. 建設業許可の取得要件
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。これらの要件のいずれか一つでも欠けている場合、許可は取得できません。
(1) 経営業務の管理責任者としての経験
法人の場合は常勤役員、個人の場合は本人または支配人が、適切な経営経験を有している必要があります。
- 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
- 例:役員として建設業を経営していた期間
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験
- 例:別の建設業種の役員経験
- 経営業務の管理責任者に準ずる地位(補佐する立場)で、7年以上の経験
これらの経験は、原則として「建設業の許可を受けた会社での経験」が求められますが、例外もあります。経験の内容や期間を客観的に証明できる資料(登記事項証明書、確定申告書など)の準備が重要です。
(2) 専任技術者の配置
許可を受けようとする建設業種ごとに、一定の資格や経験を持つ「専任技術者」を営業所ごとに常勤で配置する必要があります。
【専任技術者になるための主な要件】
- 国家資格の保有: 1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士など、建設業法で定められた国家資格を持っている。
- 実務経験: 許可を受けようとする建設業種において、10年以上の実務経験がある。
- 指定学科卒業者は、学歴に応じて実務経験が短縮される場合があります(例:高校・専門学校卒業後5年、大学・高等専門学校卒業後3年)。
専任技術者の実務経験を証明するためには、工事請負契約書、請求書、入金確認書類など、具体的な工事内容が分かる資料が多数必要になります。
(3) 誠実性
申請者、役員、政令で定める使用人(支店長など)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことを指します。具体的には、以下のいずれかに該当しないことが求められます。
- 不正行為(詐欺、脅迫など)や不誠実な行為(工事内容の不履行、著しく不適切な履行など)を行っていないこと
- 法人役員、個人事業主、政令で定める使用人が、過去に建設業法や他の法令(刑法、建築基準法、労働基準法など)に違反し、罰金以上の刑を受けていないこと(期間制限あり)
(4) 財産的基礎・金銭的信用
建設工事を請け負う上で必要な資金力があることを証明する要件です。
- 一般建設業許可の場合:
- 自己資本が500万円以上あること
- または、500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)
- 特定建設業許可の場合: 一般建設業許可よりも厳しく、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上であること
法人の場合は直前の決算書、個人の場合は貸借対照表や預金残高証明書などで証明します。
(5) 欠格要件に該当しないこと
申請者やその役員、法定代理人などが、以下のいずれかの項目に該当しないことが必要です。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 建設業許可を取り消されてから5年が経過していない者
- 営業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法、刑法などの法令に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等
これらの要件をクリアしているかどうかの判断は、非常に専門的です。当事務所では、事前のヒアリングを通じて、お客様がどの要件を満たしているか、また不足している要件をどのようにクリアしていくかを具体的にアドバイスいたします。
4. 建設業許可申請の流れと必要書類
建設業許可の申請手続きは、多岐にわたる書類の収集と作成、そして行政庁との綿密なやり取りが求められます。
(1) 申請の流れ(一般的な例)
- 事前相談・要件確認:
- お客様の事業内容や状況をヒアリングし、どの許可(知事・大臣、一般・特定、業種)が必要か、要件を満たしているかを確認します。
- 特に「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件確認は重要です。
- 必要書類の収集・作成:
- 行政書士がご案内するチェックリストに基づき、各種証明書や契約書などの書類を収集していただきます。
- 申請書本体や添付書類は、行政書士が作成いたします。
- 申請書類の提出:
- 管轄の行政庁(熊本県の場合、県庁の建設業課など)に申請書類を提出します。
- 郵送での申請は原則としてできません。
- 行政庁による審査:
- 提出された書類をもとに、行政庁による厳正な審査が行われます。
- 場合によっては、追加資料の提出や、担当者によるヒアリングが行われることがあります。
- 許可通知:
- 審査に通ると、許可が下りた旨の通知があります。通常、申請から1ヶ月~2ヶ月程度で通知されます。
- 登録免許税・手数料の納付:
- 許可が下りた後、所定の登録免許税(大臣許可)または手数料(知事許可)を納付します。
- 知事許可の場合:新規申請9万円、更新5万円
- 大臣許可の場合:新規申請15万円、更新5万円
- 許可証の交付:
- 登録免許税または手数料の納付後、正式な許可証が交付されます。
(2) 必要書類(主なもの)
建設業許可申請には、非常に多くの書類が必要です。ここでは主な書類を挙げますが、個別の状況によってさらに追加される場合があります。
共通して必要となる書類
- 建設業許可申請書
- 誓約書
- 役員等の一覧表
- 経営業務の管理責任者証明書(略歴書、経験を証明する資料)
- 専任技術者証明書(資格証明書、実務経験を証明する資料)
- 健康保険等の加入状況確認資料
- 財産的基礎に関する調書(直前決算書、預金残高証明書など)
- 納税証明書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 定款(法人の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 住民票(個人の場合)
- 営業所の所在地、写真、案内図
- 使用権原を証明する資料(賃貸借契約書など)
その他、状況に応じて必要となる書類
- 建設業に関する工事経歴書
- 工事請負契約書、注文書・請書(写し)
- 工事の請求書、入金が確認できる資料
- 各種許可証(他業種の許可をお持ちの場合)
- 技術検定合格証明書
- 卒業証明書
- 社会保険加入を証明する書類
- 外国人登録証明書(外国籍の場合)
これらの書類は、行政書士が綿密にチェックし、不足がないか、不備がないかを確認しながら準備を進めます。
5. 許可取得後の注意点
建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。許可を維持し、適切に事業を営むためには、いくつかの注意点があります。
- 有効期間と更新手続き: 建設業許可の有効期間は5年間です。有効期間満了の約3ヶ月前から更新申請が可能になります。更新を忘れてしまうと、許可は失効し、再度新規申請からやり直すことになりますので、計画的な準備が必要です。
- 変更届の提出義務: 許可を受けた内容(商号、所在地、役員、専任技術者、資本金など)に変更があった場合は、30日以内に(一部は2週間以内)行政庁に変更届を提出する義務があります。これを怠ると、罰則の対象となるだけでなく、許可の更新や他の申請に影響が出る可能性があります。
- 決算変更届(事業年度終了届)の提出: 毎事業年度終了後、4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。これは、許可業者の事業状況を行政庁が把握するために必要なものです。
- 各種義務の遵守: 建設業法に定められた各種義務(適切な契約締結、見積もり提示、工事の適正な施工、下請代金の支払いなど)を遵守する必要があります。
これらの手続きや義務の遵守は、専門知識がないと煩雑に感じられるかもしれません。行政書士法人塩永事務所では、許可取得後の各種変更届や更新申請についても継続的にサポートいたします。
6. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
建設業許可申請は、お客様ご自身で行うことも不可能ではありません。しかし、その手間と時間を考えると、専門家である行政書士に依頼することには大きなメリットがあります。
- 複雑な要件確認とアドバイス: 経営業務の管理責任者や専任技術者の要件判断は特に複雑です。当事務所は豊富な経験と実績に基づき、お客様の状況に合わせて最適なアドバイスを提供し、許可取得の可能性を最大限に高めます。
- 膨大な書類作成・収集の代行: 多数の申請書類作成から、必要書類のリストアップ、取得方法のアドバイスまで、お客様の負担を大幅に軽減します。書類の不備による差し戻しを防ぎ、スムーズな申請をサポートします。
- 行政庁との連携: 行政庁との事前の確認や、申請後の問い合わせ対応など、行政書士が窓口となり、お客様に代わって手続きを進めます。
- 迅速かつ確実な手続き: 専門家が手続きを行うことで、申請から許可取得までの時間を短縮し、お客様は本業に集中することができます。
- 許可取得後のサポート: 更新手続きや各種変更届、決算変更届など、許可取得後も継続的にサポートし、お客様の事業運営をバックアップいたします。
まとめ
建設業許可は、貴社の事業をさらに発展させるための重要な礎となります。特に建築工事業やとび・土工工事業など、多岐にわたる工事を請け負う事業者様にとって、許可取得は必須と言えるでしょう。
行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請に関する専門知識と豊富な実績で、お客様の許可取得を強力にサポートいたします。
「ウチの会社は許可が取れるのか?」「どんな書類が必要なのか?」など、少しでも疑問やご不安がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。
私たちは、お客様の事業の健全な発展に貢献できるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
行政書士法人塩永事務所 [096-385-9002]
