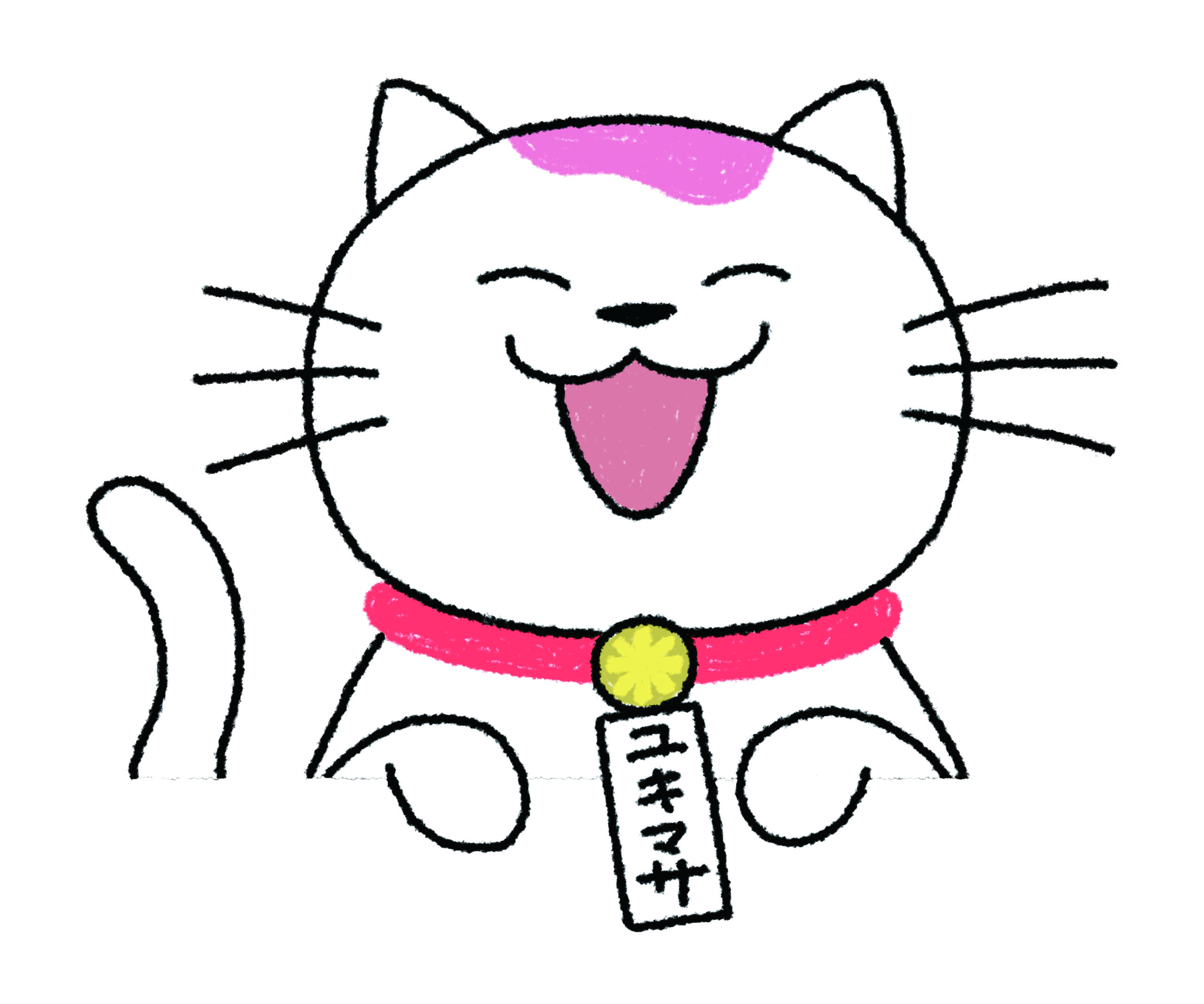
離婚協議書とは?作成のポイント、必要書類、注意点を徹底解説
夫婦間で話し合い、合意の上で離婚することを**「協議離婚」**と呼びます。協議離婚は、夫婦双方が離婚に納得し、役所に離婚届を提出すれば成立するため、最も一般的な離婚方法です。
しかし、協議離婚は手軽に進められる反面、離婚後のトラブルを避けるために取り決めておくべき事項(養育費、財産分与など)が未解決のまま離婚が成立してしまうケースも少なくありません。
離婚後の後悔やトラブルを防ぐためには、これらの重要事項を十分に話し合い、その内容を**「離婚協議書」**として書面に残しておくことが非常に重要です。
本記事では、離婚協議書に記載すべき事項、作成に必要な書類、そして作成時の注意点について詳しく解説します。これから離婚を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
離婚協議書とは?
まずは、一般的な離婚手続きの流れを確認しましょう。
- どちらか一方が離婚を切り出す
- 離婚条件について話し合う
- 離婚協議書を作成する
- 役所に離婚届を提出する
この流れの中で重要な役割を果たすのが「離婚協議書」です。
離婚協議書とは、離婚に際して夫婦間で合意した内容を具体的に記した契約書のことです。離婚時に慰謝料や子どもの親権などについて書面での合意がないと、後になって財産分与や養育費の金額、支払い方法などを巡るトラブルが発生する可能性があります。
離婚後に不必要な問題に直面しないためにも、協議離婚を進める際は、離婚条件をしっかりと話し合い、その内容を離婚協議書として残すようにしましょう。
離婚協議書に記載すべきこと
「離婚協議書に何を記載すれば良いのか分からない」と感じる方も多いかもしれません。ここでは、離婚協議書に盛り込むべき主な内容を具体的に見ていきましょう。
離婚協議書に記載すべき事項は以下の通りです。
- 離婚の合意、および協議離婚である旨
- 離婚届の提出日、および提出者
- 財産分与に関する取り決め
- 分与する財産の種類と具体的な内容
- 支払う側と受け取る側の明確化
- 支払う金額、支払い方法、支払日など
- 年金分割に関する取り決め
- 慰謝料に関する取り決め
- 支払う側と受け取る側の明確化
- 支払う金額、支払い方法、支払日など
- 養育費に関する取り決め
- 支払う側と受け取る側の明確化
- 支払う金額、支払い方法、支払日
- 支払いの終期(例:子どもが20歳になるまで)
- 事故や病気など、特別な出費が必要になった場合の双方の負担割合など
- 未成年の子どもの親権者・監護者
- 面会交流に関する取り決め
- 面会の頻度、時間
- 子どもの受け渡し方法など
- 強制執行認諾文言付き公正証書を作成することへの同意
- 同じ書面を2通作成し、各自1通ずつ保管する旨
これらの項目を詳細に記載した後、夫婦それぞれが氏名と住所を記入し、署名押印します。
なお、離婚協議書には特定の書式が定められていないため、夫婦間で自由に作成することができます。
離婚協議書作成に必要な書類
次に、離婚協議書を作成する際に必要となる書類について見ていきましょう。家庭の状況によっては、原則必要な書類に加えて、いくつか追加で必要になるものがあります。ご自身の状況に合わせて参考にしてください。
原則必要な書類
以下の書類は、原則としてどのような離婚協議書を作成する際にも必要となります。夫婦それぞれで準備しましょう。
- 印鑑登録証明書と実印(発行から3か月以内)
- 外国籍の方や海外在住で日本国内に住所がない方は、印鑑登録証明書の代わりに**「サイン証明書」**でも代用可能です。サイン証明書は、領事館や大使館で発行できます。
- 本人確認書類(以下のうちいずれか一つ)
- 運転免許証と認印
- 顔写真付きの住民基本台帳カードと認印
- パスポートと認印
※代理人に依頼する場合は、代理人に関する上記資料に加え、依頼者本人の印鑑登録証明書と委任状(実印で押印したもの)が必要となります。
未成熟子がいる場合
未成熟子とは、親からの独立した生活が経済的に困難な子どもを指します。ここで注意したいのは、「未成熟子=未成年」ではない点です。未成年であっても、経済的に自立していると判断されれば未成熟子には該当しません。
未成熟子がいる場合は、発行から3か月以内の**「戸籍謄本」**が追加で必要です。
財産分与がある場合
夫婦間で財産分与を行う場合は、以下の書類が追加で必要となります。財産の種類によって必要な書類が異なりますのでご注意ください。
- 不動産の場合
- 不動産登記簿謄本(発行から3か月以内)
- 固定資産税評価証明書
- 自動車の場合
- 車検証
- 査定書(資産価値がある場合のみ)
- 生命保険の場合
- 保険証券
- 解約返戻金証明書
- 株式などの有価証券の場合
- 有価証券を証明できる資料
年金分割の場合
年金分割を行う場合は、以下の書類が追加で必要です。
- 夫婦二人の年金手帳(コピーでも可)
- 年金分割のための情報提供通知書
離婚協議書を作成する上での5つの注意点
離婚協議書を作成する際には、いくつか押さえておくべき注意点があります。主な5つの注意点をご紹介しますので、協議に入る前に確認しておきましょう。
1. 離婚協議書は公正証書にする
離婚協議書を公正証書にすることをおすすめします。公正証書にしておけば、相手が離婚協議書の条件を守らなかった場合に、相手の財産に対して強制執行(例:給与債務や銀行預金口座の差し押さえ)をかけることが可能になります。
公正証書は、全国各地にある公証役場で公証人の面前で作成されるため、その法的効力と信頼性が非常に高いのが特徴です。費用も数万円からと、大きな負担ではないため、可能な限り公正証書にすることをおすすめします。
2. 暴力やモラハラの危険性がある場合は法律家に相談する
相手からの暴力やモラハラがある場合、離婚を切り出した際に相手が逆上する危険性があります。そのような事態を避けるために、人目のある場所で話し合いを行うか、信頼できる第三者(弁護士など)に同席してもらうことを検討しましょう。
暴力やモラハラの危険性が少しでもある場合は、最初から弁護士に相談することをおすすめします。
3. 子どもの前での話し合いは避ける
離婚協議を行う際に特に注意したいのが、子どもの前での話し合いです。離婚協議では、夫婦間で感情的な言い争いになることも少なくありません。両親の激しい言い争いを目にした子どもは、自分を否定されたような気持ちになったり、心に深い傷を負ったりする可能性があります。
子どもにとって、たとえ両親が離婚しても、親であることに変わりはありません。子どもの気持ちを最優先に考え、子どもがいない時間帯に話し合うか、信頼できる親戚などに子どもを預けるなどの配慮をしましょう。
4. 事前に考えを整理しておく
離婚協議で決めなければならないことは多岐にわたります。話し合いの場で、自分の言いたいことがうまく伝えられなかったり、感情論になってしまったりすることもあります。
そうならないために、事前にご自身の希望する離婚条件を具体的に書き出しておくことをおすすめします。さらに、その中で譲れる部分と絶対に譲れない部分を明確に区別しておくと、話し合いがスムーズに進みます。
5. 離婚届を勝手に出される恐れがある場合は離婚不受理申出を提出しておく
協議離婚は、夫婦双方の合意が絶対条件です。しかし残念ながら、一方的な意思で勝手に離婚届を提出してしまうケースも存在します。万が一、片方が勝手に離婚届を提出した場合、裁判所に訴えを起こして取り消すことは可能ですが、訴訟手続きは大変な時間と費用を要します。
もし、離婚届を勝手に提出される恐れがあると感じる場合は、事前に離婚不受理申出を提出しておきましょう。離婚不受理申出は、役所の窓口でシンプルな書類を記入するだけで申請できます。この申出が提出されていれば、相手が勝手に離婚届を提出しても、離婚は受理されません。この効力は、申出をした本人が役所に赴いて取り下げるか、または本人が離婚届を提出するまで継続します。
【まとめ】離婚協議書は専門家への依頼がおすすめ
本記事では、離婚協議書に記載すべき内容、必要書類、そして作成時の注意点について解説しました。
離婚協議書はご自身で作成することも可能ですが、その手続きは複雑であり、内容に不備があると後々のトラブルに発展する可能性が高まります。そのため、専門家への依頼を強くおすすめします。
行政書士は、書類作成の専門家です。将来的なトラブルを避けるためにも、適切な手続きを踏むことが非常に重要です。
離婚協議書のご相談は、ぜひ行政書士法人塩永事務所までお気軽にご連絡ください。
