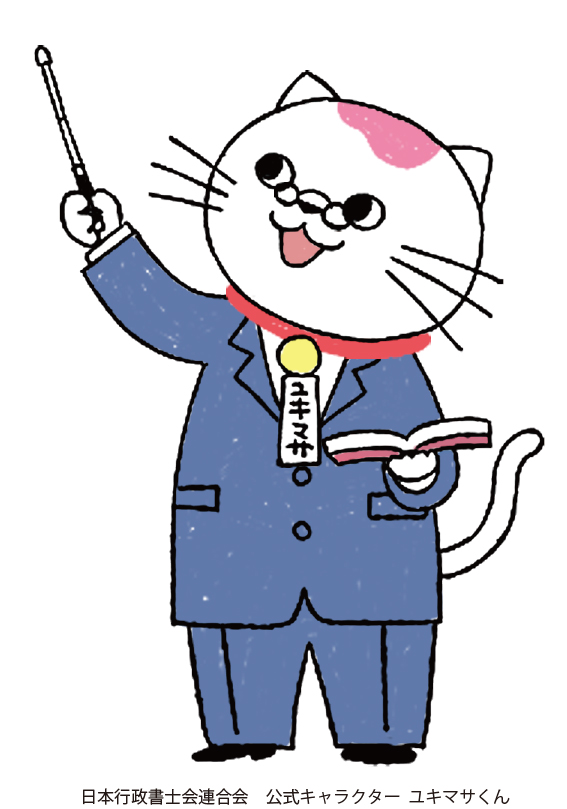
エコアクション21認証手続きの詳細ガイド行政書士法人塩永事務所エコアクション21は、環境省が推進する中小企業向けの環境マネジメントシステム(EMS)であり、環境負荷の低減と経営改善を両立させるための実践的なツールです。ISO14001に比べ導入が容易で、環境への取り組みを「見える化」することで、経費削減、生産性向上、企業イメージの向上を実現します。行政書士法人塩永事務所では、認証取得から継続的な運用まで、専門的なサポートを提供しています。本ガイドでは、認証手続きの詳細をステップごとに解説します。エコアクション21とはエコアクション21は、環境省が1996年に策定した日本独自の環境マネジメントシステムです。PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を基盤とし、環境方針の策定、目標設定、実行、評価、改善を通じて、持続可能な経営を支援します。特に中小企業や地方公共団体向けに設計されており、簡易な運用で環境負荷の低減と経済的メリットを両立できる点が特徴です。認証取得のメリットエコアクション21の認証取得は、経営面と営業面で多くのメリットをもたらします。1. 経営面のメリット
- 経費削減:エネルギー使用量や廃棄物処理費の削減によるコストダウン。
- 生産性向上:業務プロセスの効率化による時間とリソースの最適化。
- 従業員の環境意識向上:環境教育を通じて組織全体の意識改革。
- 企業イメージの向上:環境配慮型企業としてのブランド力強化。
2. 営業面のメリット
- 公共工事での加点:建設業の経営事項審査や自治体の総合評価入札で加点対象。
- 融資優遇:日本政策金融公庫や自治体の低金利融資制度の活用。
- 取引先の信頼向上:環境経営への取り組みが取引先からの評価を高める。
- 新規顧客獲得:環境意識の高い顧客やパートナーとの取引機会拡大。
認証手続きの詳細な流れエコアクション21の認証手続きは、環境省の「エコアクション21ガイドライン2017年版」に基づき、以下の7つのステップで進行します。全体の所要期間は通常6~9ヶ月です。ステップ1:初期準備(1~2ヶ月)認証取得の基盤を構築する段階です。以下のプロセスを進めます。1-1. 全体研修の実施
- 目的:エコアクション21の概要と意義を組織全体で共有。
- 内容:
- 経営者および全従業員向けの研修(オンラインまたは対面)。
- 環境マネジメントシステムの基本概念、PDCAサイクルの説明。
- 認証取得による経済的・社会的メリットの理解促進。
- ポイント:従業員のモチベーション向上のため、具体的な事例(例:同業他社の成功事例)を交えた説明が有効。
1-2. 推進体制の構築
- 環境経営責任者の選任:通常、経営者が担当。組織全体の環境方針を統括。
- 環境経営推進員の選任:実務の中心となる担当者(管理職や環境担当者)。
- 各部門の環境担当者の指名:部門ごとの環境活動を推進するリーダー。
- ポイント:明確な役割分担と責任の文書化が求められる。
1-3. 現状把握
- 環境負荷の洗い出し:
- エネルギー使用量(電気、ガス、燃料など)。
- 水使用量、廃棄物排出量、化学物質使用量(該当する場合)。
- 「環境への負荷の自己チェック表」(ガイドライン付属)を活用。
- データ収集:
- 過去3年分の光熱費、水道代、廃棄物処理費の請求書や領収書を収集。
- 環境関連法規制(例:廃棄物処理法、エネルギー使用の合理化等に関する法律)の遵守状況を確認。
- ポイント:正確なデータ収集が環境経営レポートの基盤となる。
当事務所のサポート:初期診断を行い、環境負荷の特定やデータ収集の効率的な方法を提案。研修プログラムの設計も支援。ステップ2:環境経営システムの構築(2~3ヶ月)ガイドラインに準拠した環境経営システムを構築します。2-1. 環境方針の策定
- 内容:
- 経営者が事業の特性や地域の環境課題を踏まえた環境方針を作成。
- 例:「省エネルギーと廃棄物削減を通じて、地域社会の持続可能性に貢献する」。
- 周知方法:
- 社内:イントラネット、掲示板、朝礼での共有。
- 社外:ウェブサイトやパンフレットでの公表。
- ポイント:方針は具体的かつ簡潔に、全従業員が理解できる内容に。
2-2. 環境目標の設定
- 目標例:
- 「年度内にCO2排出量を5%削減する」。
- 「廃棄物リサイクル率を80%に向上させる」。
- 要件:
- 数値化可能で測定可能な目標。
- 各部門に分解したサブ目標を設定。
- 実施計画:
- 目標達成のための具体的な行動計画(例:LED照明の導入、社用車のエコドライブ)。
- 責任者、スケジュール、予算を明確化。
2-3. 環境活動計画の策定
- 内容:
- 省エネルギー(例:空調の温度設定最適化)。
- 省資源(例:紙の両面印刷推進)。
- 廃棄物削減・リサイクル(例:分別ルールの徹底)。
- グリーン購入(例:環境ラベル製品の優先購入)。
- ポイント:従業員が実行可能な現実的な計画を策定。
当事務所のサポート:環境方針や目標の策定支援、業種別ガイドライン(例:建設業、製造業)に沿った計画の提案。ステップ3:環境活動の実施(3ヶ月以上)環境活動を実際に行い、実績データを蓄積します。3-1. 日常的な環境活動
- 具体例:
- 省エネルギー:照明の消灯徹底、エネルギー監視装置の導入。
- 省資源:電子化による紙使用量の削減。
- 廃棄物削減:分別ルールの徹底、リサイクルボックスの設置。
- グリーン購入:エコ商品の選定基準の導入。
- ポイント:全従業員の参加を促し、取り組みを習慣化。
3-2. 記録・データ管理
- 記録項目:
- 環境負荷データ(CO2排出量、廃棄物量、水使用量など)。
- 活動実績(例:省エネ機器導入の効果)。
- 法規制遵守状況(例:廃棄物処理の委託契約書)。
- 方法:データ管理表(Excelなど)を使用し、月次で更新。
- ポイント:認証申請には最低3ヶ月分のデータが必要。
3-3. 内部コミュニケーション
- 方法:
- 月次会議で進捗報告と課題共有。
- 従業員からの改善提案の収集(例:提案ボックス、イントラネット)。
- ポイント:PDCAサイクルを回すための継続的な情報共有が重要。
当事務所のサポート:データ管理フォーマットの提供、会議運営のアドバイス、従業員向け啓発資料の作成。ステップ4:環境経営レポートの作成(1ヶ月)認証申請の核となる環境経営レポートを作成します。4-1. 環境経営レポートの構成
- 必須項目(ガイドラインに基づく):
- 組織概要:事業内容、従業員数、事業所情報。
- 環境方針:策定した方針の全文。
- 環境目標と実績:目標値と実績値の比較(表やグラフで可視化)。
- 主な環境活動:具体的な取り組み内容と成果。
- 環境負荷の実績:CO2排出量、廃棄物量、水使用量などのデータ。
- 次年度の取り組み:継続的改善の計画。
- 形式:PDF形式で提出(A4サイズ推奨、20~30ページ程度)。
4-2. 数値データの整理
- CO2排出量:電力・燃料使用量を基に、環境省の排出係数を用いて算出。
- 廃棄物発生量:種類別(一般廃棄物、産業廃棄物)の集計。
- 水使用量:水道使用量の請求書データから集計。
- 化学物質:PRTR法対象物質の使用量(該当する場合)。
- ポイント:データの正確性と透明性が審査の鍵。
当事務所のサポート:レポート作成のテンプレート提供、データ集計の支援、ガイドライン適合性の確認。ステップ5:認証申請(1ヶ月)審査機関に申請書類を提出します。5-1. 申請書類の準備
- 必須書類:
- 認証・登録申請書(地域事務局指定の様式)。
- 環境経営レポート(電子データ)。
- 環境経営システムの運用状況を示す書類(例:環境方針、目標、計画)。
- 組織図、事業所配置図、環境関連法規制の遵守証明(必要に応じて)。
- ポイント:書類の不備は審査遅延の原因となるため、事前確認が重要。
5-2. 申請手続き
- 提出先:地域事務局または中央事務局(一般財団法人持続性推進機構)。
- 方法:電子メールでPDFファイルを送付。
- 申請手数料:標準審査工数に基づく(1人日あたり50,000円・税抜)。
- 審査日程:申請後、地域事務局が審査員を選任し、日程を調整。
当事務所のサポート:書類作成・提出代行、審査員との調整、申請手数料の見積もり支援。ステップ6:現地審査(半日~1日)審査員による書類審査と現地審査が行われます。6-1. 審査の流れ
- 書類審査:
- 環境経営レポートや運用書類のガイドライン適合性を確認。
- データの正確性や一貫性を評価。
- 現地審査:
- 事業所訪問(主要事業所を対象、複数事業所の場合は調整)。
- 環境活動の実施状況確認(例:省エネ設備、廃棄物管理状況)。
- 経営者・従業員へのヒアリング(環境方針の理解度、活動の浸透度)。
- 所要時間:事業規模により半日~1日。
6-2. 審査のポイント
- 環境経営システムの構築・運用状況。
- 環境目標の達成度とデータの信頼性。
- 法規制遵守(例:廃棄物処理法、フロン排出抑制法)。
- 継続的改善の仕組み(PDCAサイクルの運用状況)。
当事務所のサポート:現地審査の事前準備(模擬審査、チェックリスト提供)、審査当日の立ち会い、指摘事項への対応支援。ステップ7:認証取得(審査後1~2ヶ月)審査結果に基づき、認証可否が決定されます。7-1. 審査結果の通知
- プロセス:
- 審査員が報告書を作成し、地域事務局の判定委員会に提出。
- 委員会がガイドライン適合性を最終評価。
- 結果:
- 認証適合の場合:認証番号とロゴマークが発行され、登録証が交付。
- 不適合の場合:改善要求事項が通知され、対応後に再審査。
- ポイント:改善要求への迅速な対応が認証取得の鍵。
7-2. 認証後の活動
- 認証マークの活用:名刺、ウェブサイト、パンフレットに使用可能。
- 環境経営レポートの公表:毎年1回、ウェブサイトや地域事務局を通じて公開。
- 更新審査:2年ごとに現地審査を含む更新審査が必要。
- 継続的改善:PDCAサイクルを回し、新たな目標を設定。
当事務所のサポート:認証マークの活用方法の提案、年次レポートの作成支援、更新審査の準備。よくある課題と対策認証取得や運用でよく見られる課題と、その対策を以下にまとめます。課題1:従業員の理解不足
- 原因:環境活動の目的や意義が浸透していない。
- 対策:
- 定期的な研修(例:月1回の環境勉強会)。
- 具体的な目標と成功事例の共有(例:他社のCO2削減事例)。
- インセンティブ制度の導入(例:省エネ提案への報奨金)。
課題2:データ管理の負担
- 原因:環境負荷データの収集・整理に手間がかかる。
- 対策:
- 簡易なデータ管理ツール(Excelテンプレート、専用ソフト)の導入。
- データ収集担当者の明確化と役割分担。
- 自動化ツールの活用(例:スマートメーターによるエネルギー監視)。
課題3:継続的な改善活動
- 原因:PDCAサイクルの運用が形骸化する。
- 対策:
- 定期的な内部監査(例:四半期ごとのチェック)。
- 外部コンサルタントによる客観的評価。
- 新たな環境目標の設定(例:ゼロカーボンに向けた長期計画)。
当事務所のサポート:課題ごとのカスタマイズされた解決策の提案、従業員向け研修の実施、データ管理システムの構築支援。当事務所のサポート内容行政書士法人塩永事務所は、エコアクション21の認証取得から運用まで、以下の一貫したサービスを提供します。1. 認証取得支援
- 初期診断:事業者の環境負荷や運用状況を詳細に分析。
- 導入計画の策定:事業規模や業種に応じたスケジュール作成。
- 環境経営システムの構築:方針、目標、計画の策定支援。
- 環境経営レポートの作成:ガイドライン適合性の確保と効率的な作成。
- 申請書類の作成・提出代行:地域事務局との円滑な連携。
2. 継続支援
- 年次審査の準備:環境経営レポートの更新と提出支援。
- 改善活動の提案:最新の環境技術や事例に基づくアドバイス。
- 法規制対応:環境関連法改正への迅速な対応支援。
- 内部監査支援:PDCAサイクルの効果的な運用をサポート。
3. 費用対効果の最大化
- 補助金・助成金の活用:環境関連補助金の申請サポート(例:省エネ設備導入補助金)。
- 融資制度の情報提供:日本政策金融公庫や自治体の融資制度の案内。
- 公共工事での活用:入札加点の具体的な活用方法を提案。
費用と期間費用:
- 審査費用:1人日あたり50,000円(税抜)+審査員の交通費。事業規模により工数は1~3人日程度。
- コンサルティング費用:当事務所では事業者の規模やニーズに応じた見積もりを提供(例:中小企業で30~50万円)。
- その他:省エネ設備導入やデータ管理ツールの費用(任意)。
期間:
- 準備から認証取得まで6~9ヶ月(事業者の準備状況による)。
- 環境活動の実績データ蓄積に最低3ヶ月必要。
当事務所のサポート:初期相談で詳細な見積もりとスケジュールを提供。補助金活用によるコスト軽減も提案。まとめエコアクション21の認証取得は、環境負荷の低減と経営改善を同時に実現する有効な手段です。適切な準備と継続的な取り組みにより、中小企業でも無理なく認証を取得し、経済的・社会的メリットを享受できます。行政書士法人塩永事務所は、業種や事業規模に応じたオーダーメイドのサポートを提供し、確実な認証取得と持続的な環境経営の実現をお手伝いします。お問い合わせエコアクション21の認証取得をご検討中の事業者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。初回相談は無料で、貴社のニーズに最適なプランをご提案いたします。行政書士法人塩永事務所
住所:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日9:00~18:00
環境経営を通じて、貴社の持続可能な未来を共に築きましょう!
