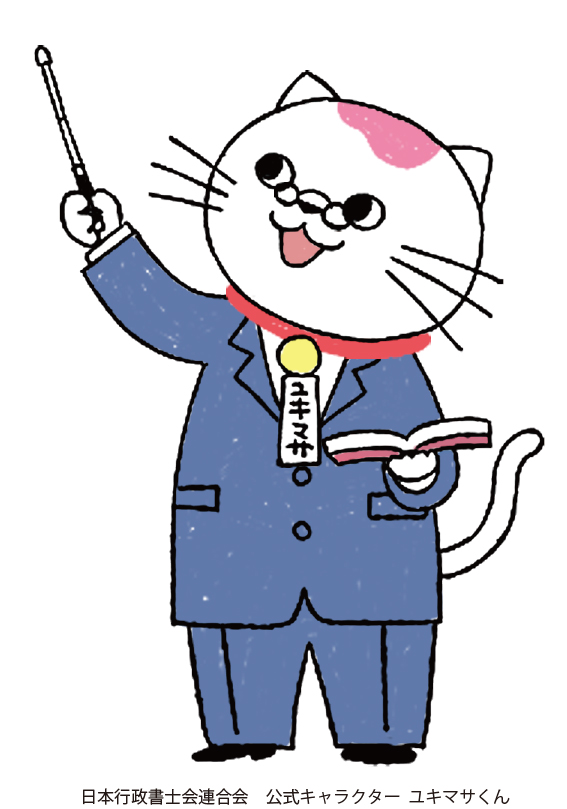
建設業(建築・とび・土工等)の許認可申請を徹底解説! ~行政書士法人塩永事務所~建設業を営む事業者にとって、建設業許可は事業拡大や信頼性向上のために不可欠な資格です。特に、建築工事やとび・土工工事などを行う場合、一定規模以上の工事を受注するには建設業許可が必要です。熊本を拠点に、建設業許可申請のサポートで豊富な実績を持つ行政書士法人塩永事務所が、建設業許可の概要、申請手続き、注意点をわかりやすく解説します。皆様のビジネスをスムーズに進めるお手伝いをいたします!1. 建設業許可とは?建設業許可は、建設業法に基づき、建設工事を行う事業者が国土交通省や都道府県から取得する許可です。建築工事、とび・土工工事、電気工事など、建設業法で定められた28業種(2025年現在)ごとに許可を取得する必要があります。許可を取得することで、以下のようなメリットがあります:
- 大規模工事の受注:500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上)を受注可能。
- 信頼性の向上:発注者や金融機関からの信頼が得られ、融資や入札参加の機会が増える。
- 事業拡大:公共工事や大型民間工事の入札に参加可能。
特に、建築工事(建築一式工事、木造建築工事など)やとび・土工工事(土木工事、舗装工事、解体工事など)は需要が高く、許可取得が事業成長の鍵となります。2. 建設業許可の種類建設業許可には、以下の種類があります:
- 特定建設業許可:元請として4,500万円以上の工事(建築一式は7,000万円以上)を受注する場合に必要。厳格な財務基準や技術者の配置が求められる。
- 一般建設業許可:4,500万円未満の工事(建築一式は7,000万円未満)を受注する場合に必要。特定建設業より要件が緩和されている。
- 大臣許可と知事許可:
- 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を置く場合。
- 都道府県知事許可:1つの都道府県にのみ営業所を置く場合。
また、許可は業種ごと(例:建築工事業、とび・土工工事業)に取得する必要があり、複数の業種を取得することも可能です。3. 建設業許可の取得要件建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を満たす必要があります:(1)経営業務の管理責任者(経管)の配置
- 建設業の経営経験を持つ者が事業所に常勤でいること。
- 例:建設業の役員経験5年以上、または建設業の個人事業主としての経験5年以上。
(2)専任技術者(専技)の配置
- 各業種に応じた資格(例:1級建築士、1級土木施工管理技士など)または実務経験(通常10年以上)を持つ技術者を常勤で配置。
- 例:とび・土工工事業の場合、1級とび技能士や10年以上の実務経験が必要。
(3)請負契約の誠実性
- 事業者や役員が、詐欺、脅迫、許可取消し歴などの不正行為がないこと。
(4)財産的基礎
- 一般建設業:500万円以上の自己資本、または資金調達能力。
- 特定建設業:資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上など。
(5)欠格要件に該当しない
- 破産者、建設業法違反による許可取消しから5年未満の場合などは許可を取得できない。
特に、建築工事業やとび・土工工事業では、専任技術者の資格や実務経験の証明が重要です。例えば、建築工事業では1級・2級建築士、施工管理技士が求められ、とび・土工工事業では土木施工管理技士や実務経験証明がポイントとなります。4. 申請手続きの流れ建設業許可申請は、以下のような流れで進めます:
- 事前準備:
- 必要書類の収集(財務諸表、資格証明書、実務経験証明書など)。
- 経管や専技の要件確認。
- 書類作成:
- 申請書(様式第1号)や添付書類(登記簿謄本、納税証明書、工事実績証明など)を準備。
- 業種ごとの実績や技術者リストを正確に記載。
- 申請窓口への提出:
- 知事許可:都道府県の建設業課。
- 大臣許可:国土交通省地方整備局。
- 審査:
- 書類審査や現地調査が行われ、通常1~2ヶ月で許可が下りる。
- 許可取得:
- 許可通知書を受け取り、営業開始。
注意点
- 実務経験の証明:過去の工事契約書や注文書、請求書などで実績を証明する必要がある。書類が不足していると審査が遅れる。
- 申請期限:許可の有効期間は5年間で、更新手続きは期限の30日前までに行う。
- 電子申請の導入:一部の都道府県では電子申請が導入されており、環境整備が必要。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート建設業許可申請は、書類作成や要件確認が複雑で、初めての方にとってはハードルが高いもの。当事務所では、熊本を拠点に、全国の建設事業者様向けに以下のサポートを提供します:
- 要件診断:経管や専技の要件を無料で診断。
- 書類作成代行:煩雑な書類作成を全て代行し、ミスを防止。
- 実務経験の証明支援:過去の工事実績の整理や証明書類の作成をサポート。
- スピード対応:最短1週間での申請書類作成が可能(知事許可の場合)。
- 更新・業種追加の管理:許可の有効期間や業種追加のタイミングを徹底管理。
例えば、建築工事業の許可を取得したいが実務経験の証明が難しい場合、弊所では元請・下請との契約書類の整理から代替証明方法の提案まで行います。また、とび・土工工事業の許可申請では、解体工事や土木工事の経験を適切に整理し、スムーズな申請を実現します。6. よくある質問Q:建設業許可はどのくらいの期間で取得できますか?
A:書類提出から通常1~2ヶ月ですが、弊所にご依頼いただければ、書類準備を最短1週間で完了させ、早期申請が可能です。Q:実務経験が10年未満でも許可は取得できますか?
A:資格(例:1級建築士、1級土木施工管理技士)を持っていれば、実務経験が短くても許可取得が可能です。詳細はご相談ください。Q:許可取得後の手続きは必要ですか?
A:毎年、事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。また、5年ごとに更新手続きが必要です。7. まとめ建設業許可は、建築工事やとび・土工工事などを行う事業者にとって、事業拡大や信頼性向上の鍵となる重要な資格です。しかし、要件の確認や書類作成には専門知識が必要で、ミスがあると許可取得が遅れるリスクがあります。行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、全国の建設事業者様を対象に、建設業許可申請のトータルサポートを提供します。初回相談は無料で、要件診断から書類作成、申請後のフォローまで一貫して対応。皆様が本業に専念しながら、スムーズに許可を取得できるよう全力でサポートします。お問い合わせ
- 電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
- メール:info@shionagaoffice.jp
- ウェブサイト:shionagaoffice.jp
今すぐご相談いただき、建設業許可を取得して、事業の新たな一歩を踏み出しましょう!
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては最新の法令や都道府県のガイドラインをご確認ください。行政書士法人塩永事務所では、具体的なご相談に基づき、最適なアドバイスを提供いたします。
