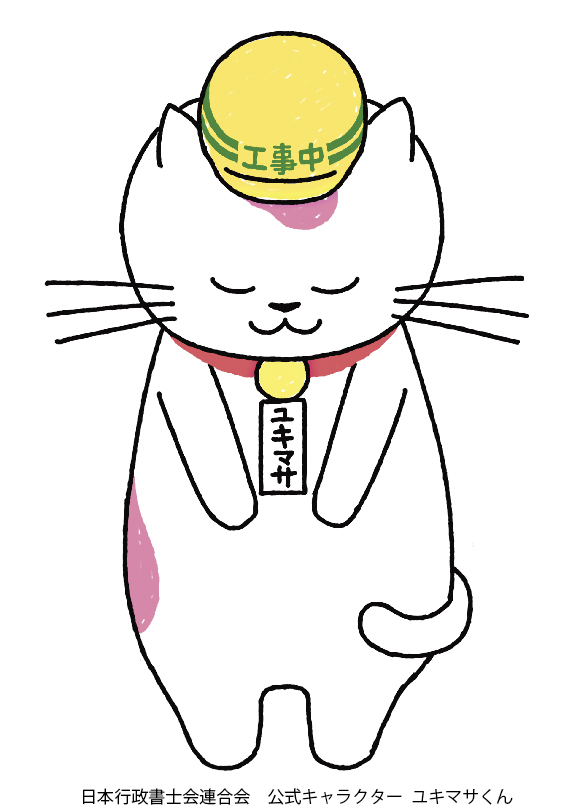
建設業許可・土木工事の申請手続きを徹底解説行政書士法人塩永事務所建設業を営む事業者にとって、一定規模以上の工事を請け負う際には「建設業許可」の取得が不可欠です。特に土木工事(土木一式工事)を請け負う場合、建設業法に基づく許可が必要となります。この記事では、土木工事の建設業許可申請手続きの詳細を、初心者の方にもわかりやすく解説します。行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験を活かし、スムーズな許可取得をサポートします。建設業許可とは?建設業許可は、建設業法に基づき、500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負う際に必要となる許可です。土木工事を含む29の業種ごとに許可を取得する必要があります。許可を取得することで、公共工事の入札参加や大型案件の受注が可能になり、事業の信頼性向上にもつながります。許可には以下の2つの区分があります:
- 知事許可:1つの都道府県内に営業所を置く場合
- 大臣許可:複数の都道府県に営業所を置く場合
また、許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分けられ、元請として4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の下請契約を締結する場合は特定建設業の許可が必要です。
土木工事(土木一式工事)とは?土木一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとに、道路、河川、橋梁、トンネルなどの土木工作物を建設する工事です。主に元請業者が請け負う大規模かつ複雑な工事で、複数の下請業者による施工が含まれます。なお、下請として行う工事は原則として「土木一式工事」に該当しません。例えば、盛土工事や掘削工事は「とび・土工・コンクリート工事」に分類される場合があります。
建設業許可の取得要件建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。土木工事の場合、特に「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件が重要です。1. 経営業務の管理責任者(経管)の設置営業所に常勤する経営業務の管理責任者が必要です。以下のいずれかの条件を満たす者が求められます:
- 土木工事業の会社で役員として5年以上の経験
- 土木工事業の個人事業主として5年以上の経験
- 土木工事業以外の建設業で役員または個人事業主として6年以上の経験
- 建設業許可を持つ事業者の支店長等(建設業法施行令第3条の使用人)として5年以上の経験
証明には、登記簿謄本、工事請負契約書、注文書、請求書、確定申告書等が必要です。
2. 専任技術者(センギ)の設置営業所ごとに常勤の専任技術者を配置する必要があります。土木工事の場合、以下のいずれかの条件を満たす者が必要です:
- 一般建設業:
- 土木工事の実務経験10年以上
- 土木工学等の指定学科を大学で卒業後、3年以上の実務経験
- 高校で指定学科卒業後、5年以上の実務経験
- 技術士(建設・鋼構造及びコンクリート等)、1級土木施工管理技士等の資格保有者
- 特定建設業:
- 1級土木施工管理技士、1級建設機械施工技士、または対応する技術士の資格保有者
- 一般建設業の専任技術者要件を満たし、4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験
実務経験の証明には、建設業許可通知書、工事請負契約書、厚生年金記録等が必要です。
3. 財産的基礎
- 一般建設業:自己資本500万円以上、または資金調達能力500万円以上
- 特定建設業:自己資本4,000万円以上、欠損額が資本金の20%以下、流動比率75%以上等
4. 誠実性法人や役員等が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。過去の詐欺、脅迫、横領等の違法行為がないか調査されます。5. 欠格要件に該当しない以下のいずれかに該当する場合、許可は取得できません:
- 破産手続き中で復権していない
- 建設業許可を取り消されて5年未満
- 禁固以上の刑を受けた場合等
申請手続きの流れ建設業許可の申請は、以下のステップで進めます。1. 要件の確認自社が許可要件を満たしているか確認します。特に経管とセンギの要件はハードルが高いため、事前に書類(契約書、資格証明書等)を整理しましょう。行政書士に相談することで、要件の充足状況を正確に把握できます。2. 必要書類の準備申請には多くの書類が必要です。主な書類は以下の通りです:
- 建設業許可申請書(国土交通省指定様式)
- 登記簿謄本(法人)
- 役員等の身分証明書、登記されていないことの証明書
- 工事経歴書
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)
- 納税証明書
- 専任技術者の資格証明書または実務経験証明書類(契約書、請求書等)
書類は都道府県のウェブサイトからダウンロード可能なひな形を使用し、正確に作成します。
3. 申請先への提出
- 知事許可:営業所所在地の都道府県庁(例:東京都なら都市整備局)
- 大臣許可:関東地方整備局等(直接提出または郵送)
東京都の場合、受付時間は平日9:00~17:00(手数料納入は11:30まで、13:00~16:00)。事前予約が必要な場合や郵送申請の可否は、事前に確認が必要です。
4. 審査申請後、行政庁による審査が行われます。審査期間は約30~45日で、書類に不備があると追加提出を求められる場合があります。
5. 許可通知審査に合格すると、許可通知書が交付されます。これにより、建設業許可番号が発行され、500万円以上の土木工事を請け負うことが可能になります。申請にかかる費用
- 手数料:
- 知事許可:9万円
- 大臣許可:15万円
- 実費:登記簿謄本、住民票等の取得費用(数千円程度)
- 行政書士報酬(代行の場合):10~18万円(要件や証明の複雑さによる)
行政書士に依頼することで、書類作成や提出の負担を軽減でき、法改正にも対応可能です。
土木工事許可取得のポイント
- 元請工事の確認:土木一式工事は元請として請け負う大規模工事が対象。下請工事は別の業種(例:とび・土工工事)に該当する場合があるため、業種選定に注意が必要です。
- 実務経験の証明:実務経験は元請工事かつ500万円未満の工事で証明する必要があります。契約書や請求書を整理し、明確な証拠を準備しましょう。
- 特定建設業の要件:土木工事業は指定7業種の一つで、特定建設業では1級資格が必須です。資格取得を計画的に進めることが重要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート当事務所では、土木工事を含む建設業許可申請を専門に扱い、以下のようなサポートを提供します:
- 要件充足の確認とアドバイス
- 必要書類の収集・作成代行
- 行政庁とのやり取り代行
- 法改正への対応と最新情報の提供
特に、過去の実務経験証明や複雑な書類作成に不安がある場合、専門知識を活かし、スムーズな申請をサポートします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。まとめ土木工事の建設業許可取得は、事業拡大や信頼性向上のために重要です。しかし、要件の確認や書類準備には時間と専門知識が必要です。行政書士法人塩永事務所では、お客様の状況に応じた最適な申請手続きをサポートし、確実な許可取得を目指します。500万円以上の土木工事を請け負いたい、公共工事の入札に参加したいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。お問い合わせ先:
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
