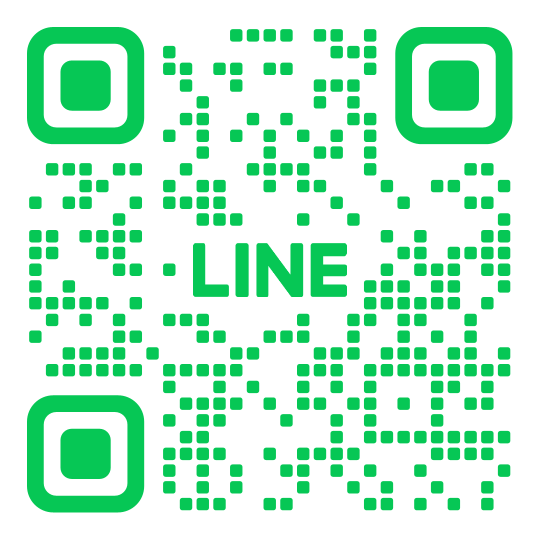
【専門解説】酒類販売業許可申請について
〜種類別の要件・流れ・ポイントを徹底解説〜
行政書士法人塩永事務所(熊本の行政書士法人)
はじめに|「お酒を売る」には許可が必要です
飲食店や小売店、ネットショップ、輸出ビジネスなど、「酒類」を取り扱うビジネスは多岐にわたります。しかし、酒類の販売には原則として『酒類販売業免許(酒販免許)』が必要であり、無許可販売は酒税法違反として重い罰則が科されます。
本記事では、酒類販売業免許の種類、取得要件、申請の流れ、注意点まで、実務に精通した行政書士の視点から詳しく解説します。
1. 酒類販売業免許とは?
「酒類販売業免許」は、国税庁(税務署)によって発行される免許です。
この免許がなければ、酒類の「販売」(有償譲渡)はできません。
▼「酒類」とは?
-
アルコール度数1度以上の飲料(ビール、ワイン、焼酎、リキュール等)
-
自家製梅酒やどぶろくも該当
※無許可での販売は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金(酒税法第56条)
2. 酒類販売業免許の種類
販売形態や対象によって免許の種類が異なります。主なものを整理すると以下の通りです。
| 種類 | 概要 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 店頭で一般消費者に酒を販売 | 酒屋、スーパー、飲食店併設販売 |
| 通信販売酒類小売業免許 | ネット通販やカタログ販売 | ECショップ、農家ワイナリー等 |
| 特定酒類小売業免許 | 酒の種類を限定した販売(例:ビールのみ) | イベント、観光施設等 |
| 酒類卸売業免許 | 販売先が酒類業者(BtoB) | 卸売業者、メーカー、輸入業者 |
| 輸出入酒類販売業免許 | 輸出・輸入目的の販売 | 貿易商社、インバウンド事業者 |
※その他、「特例卸売業免許」や「酒類製造免許」との併用もあり得ます。
3. 許可要件(人的・経済的・場所的)
3-1. 人的要件
申請者(法人代表者含む)が次のような条件を満たしている必要があります。
-
成年者であり、破産や前科歴などの欠格事由がない
-
税務署・警察等からの行政処分歴がない
-
酒類業に関する知識や経験がある(販売管理者設置要)
※法人申請の場合、代表者・役員全員が対象となります。
3-2. 経済的要件
-
営業に必要な資金力・収支見込みがあること
-
赤字決算・債務超過では審査が厳しくなる
提出資料として、資金計画書、貸借対照表、損益計算書等が求められます。
3-3. 場所的要件
-
営業所(事務所)・倉庫が現実に存在すること
-
他の用途と明確に区分されていること
-
通信販売免許の場合はWebページも必要
※レンタルオフィスやバーチャルオフィスは原則不可
4. 通信販売酒類小売業免許の特徴(要注意)
いわゆる「ネットで酒を売る」には、**特別な免許(通販免許)**が必要です。以下の点に注意が必要です。
4-1. 対象となる酒類は限定的
-
地方特産の酒類
-
輸入酒類
-
製造者直販品
※すべての酒が販売できるわけではありません(ビールや一般ワインの一部は不可)
4-2. ホームページやカタログの提出義務
-
通販の実態を示す資料(サイト画面、構成図、価格表)
-
特定商取引法に基づく表示
4-3. 年齢確認義務
-
未成年者への販売防止対策(年齢確認ボタンや本人確認措置)
5. 酒類販売業免許の申請の流れ
申請先は営業所の所在地を管轄する**税務署(酒類指導官)**です。申請から許可までは約2〜3ヶ月を要します。
STEP1|事前相談
-
酒類指導官との面談
-
業種や販売形態、施設の確認
※いきなり申請書を持っていっても受理されないケースがほとんどです
STEP2|必要書類の準備
例:
-
申請書(様式第1号〜第10号等)
-
定款・登記簿謄本
-
履歴事項全部証明書
-
事業計画書・収支見込表
-
営業所の賃貸契約書
-
酒類の仕入れ計画・販路
-
販売管理者設置届
-
販売実績の証拠書類(更新の場合)
STEP3|提出と審査
-
書類提出後、税務署によるヒアリング・実地調査
-
必要に応じて補正・追加資料の提出
STEP4|免許付与
-
免許証の交付(営業開始が可能に)
-
酒類販売管理者の選任・届出義務
-
年次報告義務等も発生
6. 実務上の注意点とよくあるトラブル
■ トラブル①:事務所が要件を満たしていない
→店舗を賃借したが、酒の販売に必要な要件(間仕切り・帳簿・表示)が整っていないと不許可になることがあります。
■ トラブル②:許可を得ずに販売開始
→ECショップやイベント販売で、知らずに酒を販売していたケース。悪質と判断されれば重い処分になります。
■ トラブル③:名義貸しや実態のない法人
→実質的な運営者と申請者が異なる場合、形式だけの申請は通りません。
7. 行政書士法人塩永事務所のサポート体制
私たち行政書士法人塩永事務所は、酒類販売業許可の申請実務に精通した専門チームを有し、熊本県を中心に、九州全域・全国対応も可能です。
◯ 当事務所が選ばれる理由
-
税務署との事前相談も同行可能
-
許可取得実績多数(小売・卸・通販・輸出入すべて対応)
-
経営計画・販売管理体制のアドバイスも実施
-
外国人による申請サポートにも対応(英語・中国語・ヒンズー語など)
◯ サポートメニュー(一例)
| サポート内容 | 概要 |
|---|---|
| 事前調査 | 営業所や業種に応じた要件確認 |
| 書類作成 | 全申請書類の作成代行 |
| 添付資料取得支援 | 法人登記・定款・登記事項証明書等 |
| 管轄税務署対応 | 事前相談同行、質問対応、補正対応 |
| 許可後の支援 | 管理者届出、記帳指導、更新サポート |
8. まとめ|酒類販売は「制度理解」と「計画性」がカギ
酒類の販売ビジネスは成長市場ですが、それだけに法規制・許認可要件が非常に厳格です。
また、インボイス制度や電子帳簿保存法など、会計・税務面での管理も求められます。
酒類販売免許は、単なる「申請書の提出」ではなく、事業実態の整備・販売計画の裏付け・信用力の証明を総合的に求められる手続きです。
ご相談は行政書士法人塩永事務所へ
私たちは、熊本県内における許認可業務のプロフェッショナルです。
これまでに数百件を超える許可申請をサポートし、特に「実地調査に強い」「税務署とのやりとりがスムーズ」と高い評価をいただいております。
「お酒を売りたい。でも何から始めたらいいかわからない…」
そんなときは、私たちにお任せください。
【行政書士法人塩永事務所】
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Instagram / X(旧Twitter):@shionagaoffice
営業時間:平日9:00~18:00(土日祝も予約対応可)
