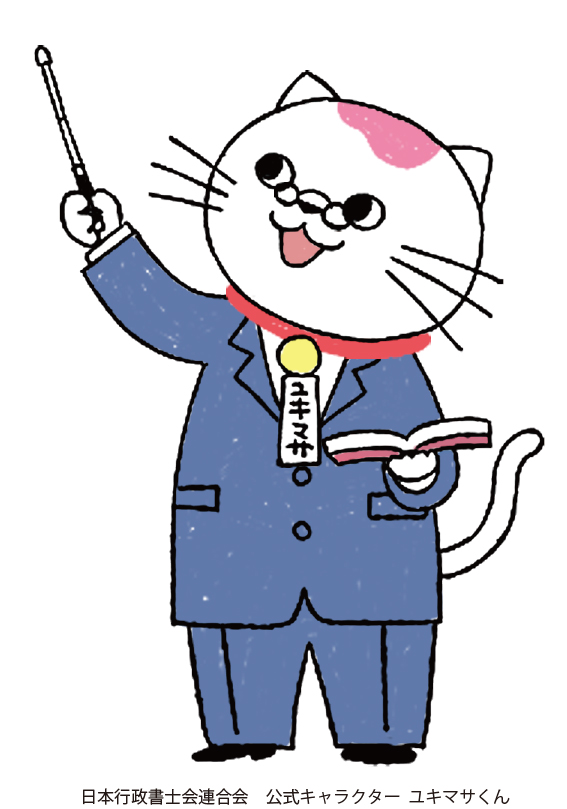
酒類販売業免許は、酒税法に基づき、酒類(アルコール度数1度以上の飲用に供される飲料)を継続的に販売する事業者が取得しなければならない許可です。酒税法第7条および第9条により、販売場所ごとに所轄の税務署から免許を取得する必要があります。無免許で酒類を販売した場合、酒税法第56条に基づき「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があるため、適法な事業運営のためには免許取得が必須です。
-
一般酒類小売業免許:一般消費者や飲食店、菓子製造業者向けに販売する場合。例:コンビニ、スーパー、酒販店。
-
通信販売酒類小売業免許:インターネットやカタログを通じて販売する場合。輸入酒は制限なく販売可能だが、国産酒は特定条件(製造者の年間課税移出数量が3,000キロリットル未満など)を満たす必要がある。
-
酒類卸売業免許:酒類小売業者やコンビニ、スーパーなどの免許取得事業者向けに販売する場合。例:洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許など。
-
酒類販売代理業・媒介業免許:酒類の販売を代理または媒介する事業者向け。コールセンターやオークション形式の販売が該当。
これらの免許は、事業内容に応じて適切なものを選択し、場合によっては複数同時に申請することも可能です。
-
人的要件:申請者(法人または個人)が破産者でないこと、酒類関連の違反歴がないことなど。
-
場所的要件:販売場所が飲食店と明確に区分されていること、賃貸物件の場合は貸主の使用承諾書が必要。
-
経営基礎要件:直近期の貸借対照表で純資産がマイナスでないこと、過去3期連続で資本等の20%を超える損失がないこと。新型コロナの影響で一時的に売上が低下した場合、事業計画書やキャッシュフロー計算書を提出することで申請が可能な場合も。
-
需給調整要件:酒類の販売見込み数量や仕入先・販売先の具体性が求められる。特に卸売業免許では、過去の販売実績や取引先との契約状況が厳しく審査される。
これらの要件は、税務署の酒類指導官による事前相談で確認され、満たさない場合は申請が受理されません。
新型コロナウイルス禍で導入された「料飲店期限付酒類小売業免許」を取得した飲食店が、継続的な酒類販売を目指すケースが増えています。この場合、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許への移行が必要ですが、飲食店は原則として酒類販売が難しいため、専門知識を持った行政書士のサポートが不可欠です。 当事務所は、こうした特殊ケースでも迅速に対応し、期限内に申請を完了させます。
地方の地酒販売から全国展開のコンビニチェーンまで、幅広い業態に対応。複雑な条件の申請にも対応いたします。
急ぎの免許取得には、税務署の酒類指導官との事前相談が鍵となります。当事務所では、申請前の綿密なヒアリングと書類準備により、初回相談から申請まで最短で翌日対応が可能なケースも。過去には、クライアントの事業開始スケジュールに合わせます。
酒類販売業免許の申請は、税務署が公開する資料が少なく、一般の行政書士でも取り扱いが難しい分野です。当事務所は複雑なケースにも対応いたします。
-
飲食店と販売スペースの区分けが必要なケース
-
コロナ影響による経営基礎要件の例外申請
-
輸出入酒類卸売業免許の取得
-
ECサイトでの通信販売免許の要件確認
申請には、登記簿謄本、納税証明書、販売場の図面、事業計画書など、多数の書類が必要です。当事務所では、これらの書類収集や作成を代行し、クライアントの負担を軽減。申請後も、税務署との補正対応や審査担当官との折衝を全て引き受けます。
初回相談は無料で、オンラインや電話での対応も可能。事業内容に応じた最適な免許の提案から、申請後のフォロー(酒類販売管理者の選任、帳簿義務の説明など)まで一貫してサポートします。
-
酒類販売業免許申請書
-
販売場の図面(次葉1・2)
-
事業の概要(次葉3)
-
収支の見込み(次葉4)
-
所要資金の額及び調達方法(次葉5)
-
納税証明書、登記簿謄本、使用承諾書など
専門知識を活かし、正確かつ迅速に申請書類を作成。税務署への提出も代行し、クライアントの時間を節約します。
審査期間(通常1~2か月)中に、税務署から追加書類の提出や現地確認が求められた場合、迅速に対応。審査の進捗を逐一報告し、クライアントの不安を軽減します。
免許交付時には、登録免許税(一般小売業免許:3万円、卸売業免許:9万円)の納付を案内。交付後は、販売管理者の選任や帳簿義務、未成年者飲酒防止の取り組みについてアドバイスを提供。
税務署の酒類指導官との事前相談は、申請の成否を左右します。当事務所では、指導官とのスムーズなコミュニケーションを確保し、要件の確認や補正リスクを最小限に抑えます。
特に卸売業免許や通信販売免許では、販売見込み数量や取引先の具体性が求められます。当事務所は、事業計画書の作成支援を通じて、説得力のある申請をサポートします。
-
登録免許税:一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許:3万円、卸売業免許:9万円
-
当事務所の報酬:小売業免許で18~25万円、卸売業免許で30~40万円が相場。急ぎの対応や複数免許の同時申請の場合、個別に見積もりを提供。
-
EC市場の拡大:コロナ禍以降、オンラインでの酒類販売が急増。通信販売酒類小売業免許の需要が高まっている。
-
地産地消の需要:地域限定の酒類を全国や海外に販売するニーズが増加。輸出免許の取得で国際市場にも進出可能。
-
飲食店の多角化:飲食店がオリジナル酒類の販売で収益源を拡大する動きが活発化。
A1. 通常の審査期間は1~2か月ですが、当事務所の迅速な書類準備と事前相談により、最短1か月での交付が可能なケースもあります。
A2. 飲食スペースと販売スペースの明確な区分など、特定の要件を満たせば取得可能です。当事務所が要件確認から申請までサポートします。
A3. 事業計画書やキャッシュフロー計算書を提出し、税務署と事前交渉を行うことで申請が可能な場合があります。当事務所が交渉を代行します。
-
電話:096-385-9002(毎日9:00~18:00)
-
メール:info@shionagaoffice.jp
