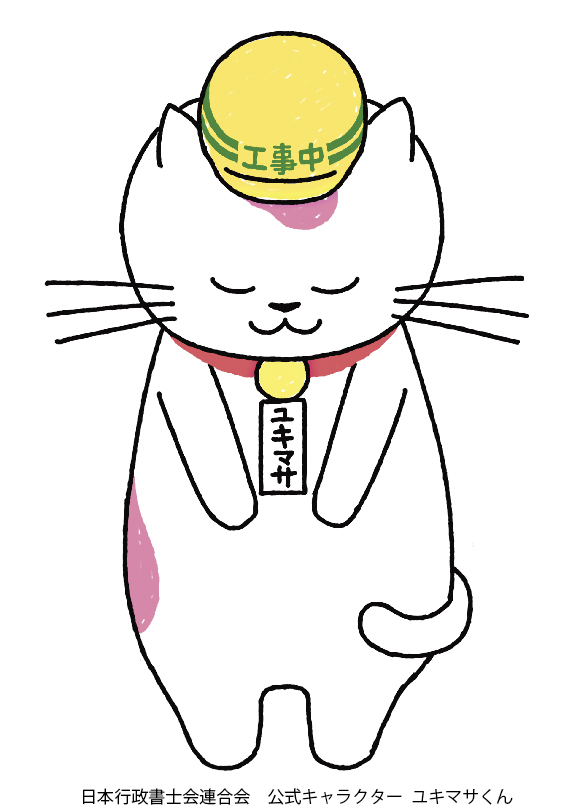
解体業を始めるには?~解体工事業登録・建設業許可の取得手続きについて徹底解説~
こんにちは、行政書士法人塩永事務所です。当事務所は、熊本県内を中心に多くの建設業関連手続きに携わってまいりました。今回は、特にニーズの高まる「解体業」にスポットを当て、解体業の許可・登録に関するポイントを詳細かつ専門的に解説いたします。
1.解体業とは?
解体業の定義
解体業とは、建築物や構築物を取り壊す工事を行う業種を指します。具体的には、建物の構造体そのものを除去する「建築物の解体」、ブロック塀や外構の撤去、内装のスケルトン工事などが含まれます。
近年、空き家問題や都市再開発、老朽化対策の一環として、解体工事のニーズは全国的に増加しており、専門業者としての立場を確立するためにも適切な許可・登録が不可欠です。
2.解体業を行うには登録または許可が必要
解体業を始めるためには、次のいずれかの手続きが必要になります。
(1)解体工事業登録(建設リサイクル法)
解体工事業者として年間500万円未満の軽微な工事のみを請け負う場合には、「解体工事業登録」が必要です。これは建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づく制度で、元請として工事を請け負う場合はこの登録が義務づけられています。
登録のポイント:
-
有効期間は5年間
-
工事現場での建設資材の分別解体、再資源化を適切に行うための体制が必要
-
登録業者名簿に掲載されることで社会的信用が向上
(2)建設業許可(建設業法)
解体工事の請負金額が500万円(税込)以上となる場合には、「建設業許可(解体工事業)」が必要です。2016年6月から、建設業法において「解体工事業」が独立業種として明確に位置づけられるようになりました。
許可業種としての解体工事業
以前は「とび・土工工事業」に含まれていた解体工事が、建設業法改正によって単独業種とされ、許可要件や技術者配置の基準も個別に設けられるようになりました。
3.解体業における建設業許可の取得要件
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
(1)経営業務の管理責任者(経管)の設置
-
解体工事業に関する経営業務の経験が5年以上ある者
-
または、他の建設業種での経営経験でも可(条件あり)
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は本人または支配人が該当する必要があります。
(2)専任技術者の配置
-
解体工事業に関する一定の資格や実務経験を有する技術者が必要です。
-
該当資格例:
-
1級または2級建築施工管理技士(建築)
-
解体工事施工技士
-
実務経験10年以上の者(工事現場管理)
-
(3)誠実性
-
過去に建設業法違反による処分歴がないこと
-
不正または著しく不誠実な行為がないこと
(4)財産的基礎
-
一般建設業許可では自己資本500万円以上、または直前5年以内に500万円以上の工事実績が必要
(5)欠格要件に該当しないこと
-
暴力団関係者や禁固以上の刑に処された者などは不可
4.解体工事業登録と建設業許可の違い
| 項目 | 解体工事業登録 | 建設業許可(解体) |
|---|---|---|
| 必要な工事規模 | 500万円未満 | 500万円以上 |
| 所管法令 | 建設リサイクル法 | 建設業法 |
| 技術者要件 | 原則なし(講習受講推奨) | 必要(専任技術者が必要) |
| 有効期間 | 5年間 | 5年間 |
| 実務経験要件 | 不要 | 必要 |
工事の規模や取引先からの要望によっては、建設業許可の取得が必須となる場面が多くあります。特に元請として公共工事に関与する場合は、許可取得が実質的な前提条件となります。
5.提出書類と申請の流れ
(1)解体工事業登録の流れ
-
登録申請書作成(講習修了証の添付が望ましい)
-
熊本県の建設業課へ提出
-
審査・登録通知(約1〜2ヶ月)
-
登録完了後、名簿掲載・証明書交付
(2)建設業許可の申請の流れ
-
必要要件確認(経管・技術者・財産など)
-
申請書作成・添付書類準備
-
熊本県(または国土交通省地方整備局)へ提出
-
審査(約1〜2ヶ月)
-
許可証交付
6.行政書士法人塩永事務所のサポート体制
当事務所では、以下のような総合的なサポートをご提供しています。
(1)書類作成・添付書類収集の代行
解体業関連の申請には、法人登記簿、納税証明書、資格証明書、財務諸表など多数の書類が必要です。弊所ではこれらの収集・作成を一括して代行します。
(2)技術者要件・経管要件の精査
実務経験や資格の証明が難しいケースについても、個別にヒアリングを行い、どのような実績が使えるかを丁寧に確認いたします。
(3)解体工事業登録から建設業許可へのステップアップ支援
初期段階で解体工事業登録を行い、一定の事業実績を積んだ後に建設業許可への切替を目指す方法についてもご提案可能です。
(4)建設リサイクル法に基づく報告義務への対応支援
解体工事を請け負った後は、一定規模以上の工事について「分別解体等の計画書」や「再資源化等の報告書」を自治体へ提出する必要があります。これらの書類作成も支援可能です。
7.まとめ
解体業は、高齢化や空き家対策、都市再生の動きとともに今後ますます需要が高まる分野です。しかし、法制度上の要件を満たさないまま営業を続けた場合、行政処分や信用失墜につながるおそれがあります。
許可取得を円滑に進め、安心して事業展開を行うためにも、解体工事業登録や建設業許可の申請は、専門家のサポートを受けることを強くおすすめいたします。
【ご相談・お問合せは行政書士法人塩永事務所まで】
建設業界に精通した行政書士が、貴社の現状を丁寧にヒアリングし、最適な許可取得の道筋をご提案いたします。熊本県内はもちろん、周辺地域の事業者様もお気軽にご相談ください。
