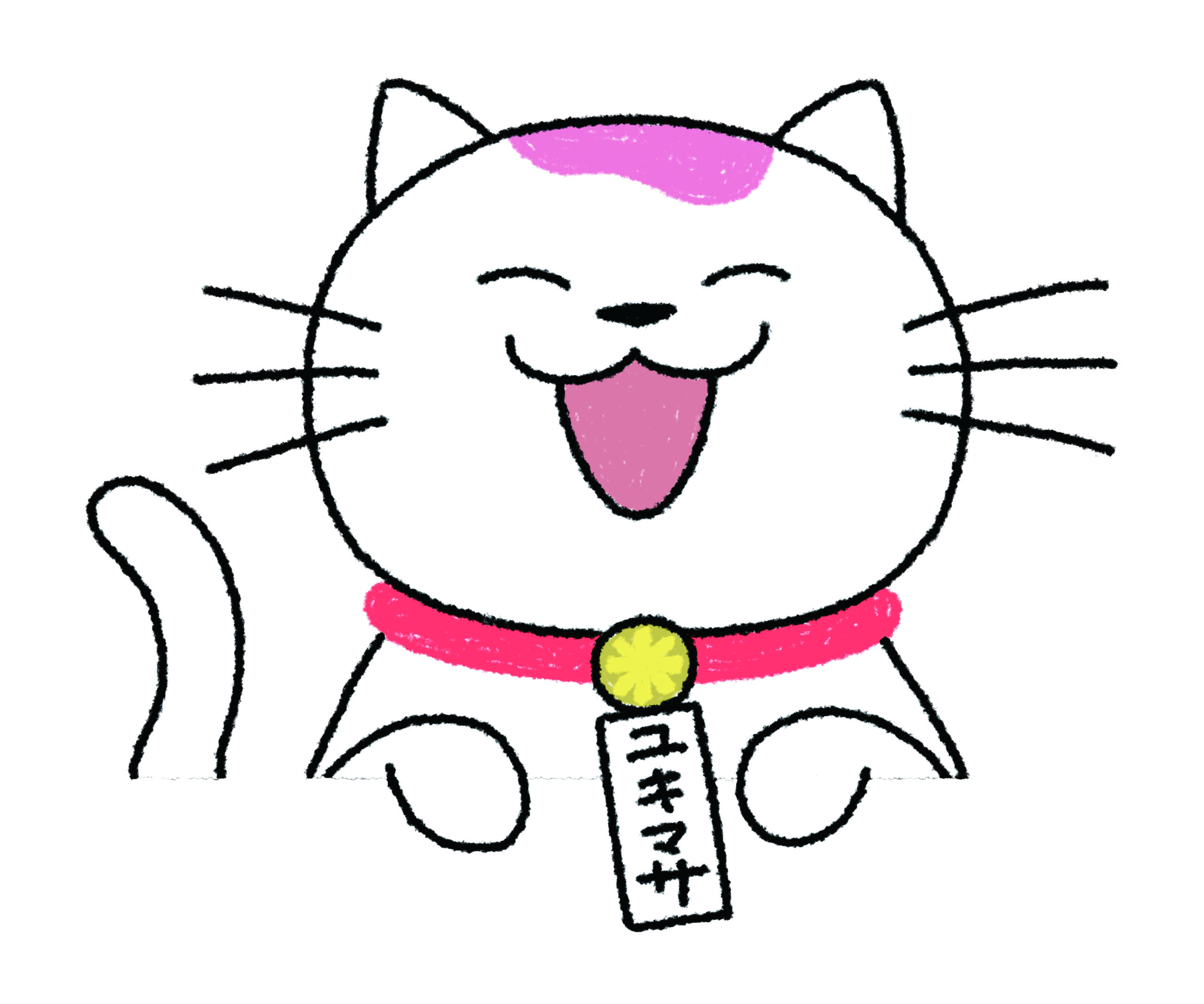
離婚協議書は、夫婦が協議離婚の際に話し合いで決めた条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など)を書面にまとめた契約書です。一方、公正証書は、公証役場で公証人(法務大臣が任命する公務員)が作成する公文書で、離婚協議書の内容を基に作成されます。主な違いは以下の通りです
-
法的効力:離婚協議書は契約書として有効ですが、相手が約束を守らない場合、裁判を経て判決(債務名義)を得る必要があります。公正証書は「強制執行認諾文言」を付けることで、裁判を経ずとも養育費や慰謝料の不払い時に強制執行が可能
-
証拠能力:公正証書は公証人が双方の意思を確認し作成するため、証拠能力が高く、内容の真実性が保証されます
-
保管:公正証書の原本は公証役場に20年間保管され、紛失や改ざんの心配がありません
離婚協議書を公正証書にするメリットは多岐にわたります
-
強制執行が可能:養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、裁判なしで給与や預金口座の差し押さえが可能です。例:「甲は養育費の支払いを遅延した場合、直ちに強制執行に服する」と記載
-
心理的プレッシャー:公正証書は公文書であり、支払い義務者に「約束を守らなければならない」という意識を促し、不払いを抑止します()。
-
トラブル防止:明確な合意内容が公的に記録されるため、「言った・言わない」の争いを防ぎます。
-
高い信頼性:公証人が中立な立場で作成するため、第三者に対する証明力も強いです。
デメリットとしては、作成に手数料(数千円~数万円)と時間(2~4週間程度)が必要な点が挙げられますが、長期的な安心を考慮するとメリットが上回ると考えられます。
3. 公正証書に記載する主な内容
離婚協議書の公正証書には、以下のような項目を記載します(,)
-
親権:子どもの親権者を指定(例:「長女の親権者を乙とする」)。
-
養育費:支払い金額、期間、振込先(例:「甲は乙に対し、月額4万円を長女が20歳になるまで支払う」)。
-
面会交流:子どもとの面会の日時や方法(例:「甲は長女と月1回、乙の同意のもと面会する」)。
-
財産分与:不動産や預貯金の分割方法。不動産の場合は、登記簿謄本や評価額証明書が必要()
-
慰謝料:金額と支払い方法(例:「甲は乙に対し、慰謝料200万円を一括で支払う」)。
-
年金分割:厚生年金の分割割合(上限50%)を合意()。
-
清算条項:協議書に記載された事項以外で追加の請求をしないことを確認(例:「甲と乙は、本協議書に定めるほか、何らの債権債務がないことを確認する」)。
記載内容は、法的に無効な内容(公序良俗に反するものなど)を除き、夫婦の合意に基づき自由に設定可能です()。ただし、将来の事情変更(例:収入の増減)に応じて、養育費などは家庭裁判所の調停で変更可能な場合があります()。
公正証書の作成手順は以下の通りです
-
夫婦間での協議:親権、養育費、財産分与などの条件を話し合い、合意内容を離婚協議書にまとめる。
-
公証役場への相談:最寄りの公証役場に電話やウェブで予約し、離婚協議書案を提出。公証人が内容をチェック。
-
必要書類の準備:
-
戸籍謄本(離婚前は家族全員分、離婚後は各人の分)
-
印鑑証明書
-
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
-
不動産関連書類(財産分与する場合)
-
年金番号がわかる資料(年金分割する場合)(,)
-
-
公正証書の作成日:予約日に夫婦(または代理人)が公証役場を訪問。公証人が案文を読み上げ、内容を確認後、署名・捺印。
-
手数料支払いと受領:公証人手数料を支払い、公正証書を受け取る。手続き全体で約2~4週間かかる
代理人対応:夫婦の一方または双方が公証役場に行けない場合、行政書士や弁護士を代理人に指定可能。ただし、公証人の許可と委任状(印鑑証明書付き)が必要()。
公正証書作成にかかる費用は以下の通りです(,):
-
公証人手数料:公証人手数料令に基づき、契約金額(養育費や慰謝料の総額)に応じて決定。例:
-
慰謝料100万円:5,000円
-
養育費月3万円×10年(360万円):11,000円
-
書面4枚を超える場合、1枚250円追加
-
-
書類取得費用:戸籍謄本や印鑑証明書などで1,000~2,000円程度。
-
行政書士報酬:当事務所では、離婚協議書作成と公正証書原案作成を合わせて3万円~8万円(税別)で提供。フルサポート(公証役場との調整含む)は10万円~15万円(税別)()。
夫婦で手数料を折半する場合が多いですが、協議で負担者を決められます
-
丁寧なヒアリング:離婚条件を詳細に確認し、チェックシート(全13ページ63項目)を活用して漏れのない協議書を作成()。
-
全国対応:メール、電話、LINEで全国の公証役場に対応。遠方の夫婦も安心()。
-
迅速かつ正確:公証役場との調整を代行し、最短2週間で原案完成。
-
アフターフォロー:離婚後の公正証書変更や養育費の調停相談も対応。
事例:当事務所でサポートしたA様(大阪府)は、養育費と財産分与を公正証書化。住宅ローンの残債問題を公証人と調整し、仮登記による解決策を提案。スムーズに離婚を成立させ、感謝の声をいただきました()。
-
離婚届のタイミング:公正証書作成後、離婚届を提出することで契約が確定。公正証書だけでは離婚の効力は生じません()。
-
内容の慎重な確認:公正証書は法的拘束力が高く、作成後の変更には双方の合意が必要。安易な作成は避け、専門家に相談を()。
-
行政書士の役割:行政書士は書類作成の専門家であり、代理交渉はできません。交渉が必要な場合は弁護士への相談を推奨()。
安心の離婚手続きを、確かな専門知識でサポートします。
