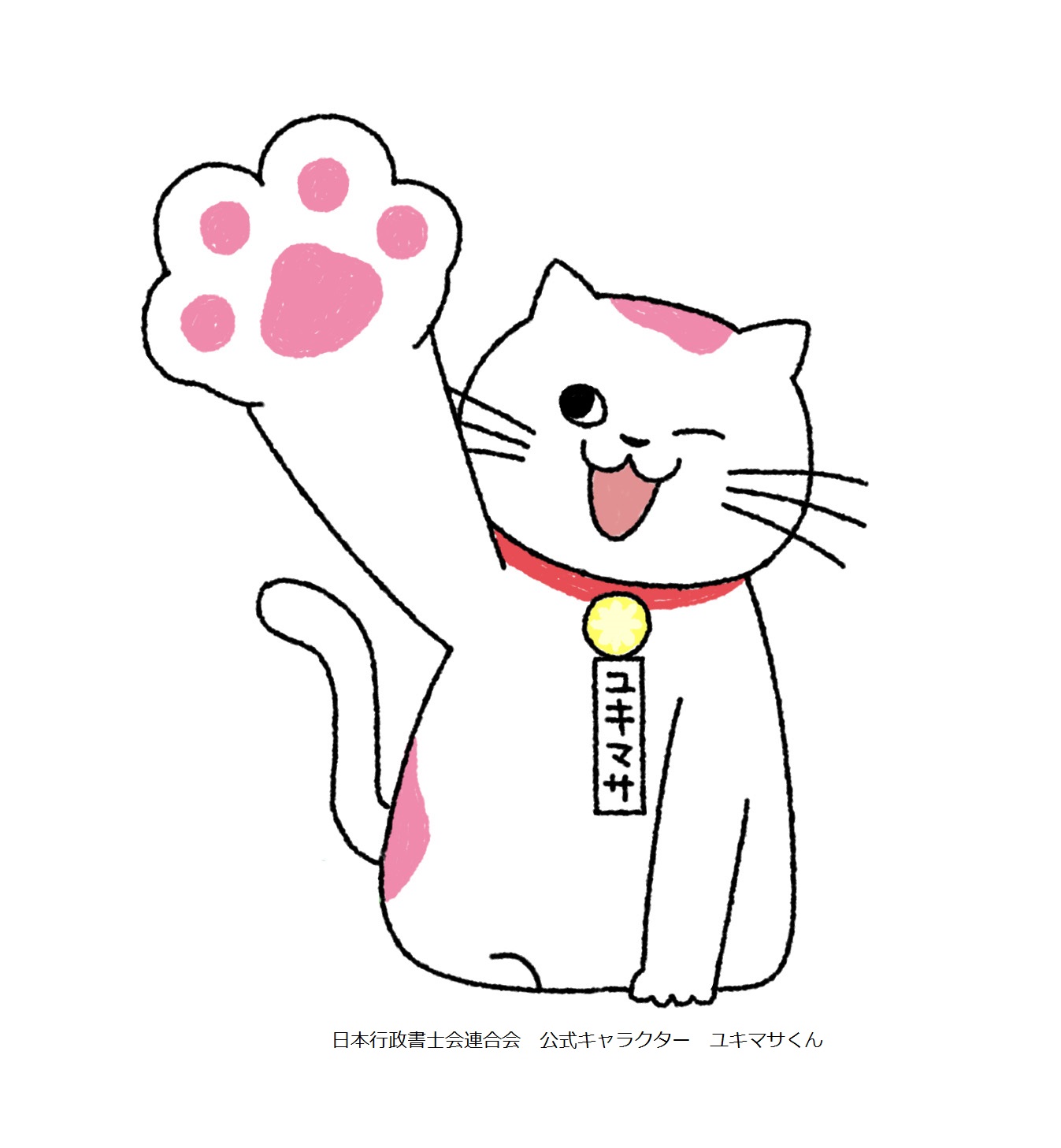
育成就労制度「監理支援機関」の新規許可申請ガイド:許可要件・書類・外部監査人・スケジュール・手数料を徹底解説
2024年6月の改正出入国管理法により、外国人技能実習制度を廃止し、2027年に新たな在留資格「育成就労」を導入する「育成就労制度」が始動します。この制度の中核を担う「監理支援機関」の新規許可申請について、許可要件、必要書類、外部監査人の役割、申請スケジュール、申請手数料をわかりやすく解説します。これから申請を検討する方に向けて、ポイントを簡潔にまとめました。
1. 監理支援機関の役割とは?
監理支援機関は、育成就労制度において、外国人労働者(育成就労外国人)と受入機関(育成就労実施者)を橋渡しし、適正な就労環境を確保する非営利法人です。主な業務は以下の2つ:
-
雇用あっせん:育成就労外国人との雇用契約の成立を支援。
-
監理支援:受入機関の育成就労実施状況を監査・指導。
旧技能実習制度の「監理団体」に相当しますが、より厳格な基準が設けられ、特定技能制度の「登録支援機関」とは異なる役割を持つため、注意が必要です。
2. 許可要件:監理支援機関になるための条件
監理支援機関として許可を受けるには、「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)第25条に定める以下の条件を満たす必要があります:
-
非営利法人
営利を目的としない法人(例:NPO法人、社団法人など)であること。 -
事業遂行能力
監理支援事業を適切に運営できる体制や能力を有すること。 -
財務基盤
事業の継続性を担保する十分な財産的基礎があること。 -
情報管理体制
個人情報や秘密の保護に関する適切な措置を講じていること。 -
外部監査人の設置
受入機関と独立した立場で、公正な監査が可能な知識・経験を持つ外部監査人を設置すること。 -
送出機関との契約
外国送出機関から求職申込みの取次ぎを行う場合、契約を締結していること。 -
総合的な適性
監理支援事業を適正に遂行できる能力を有すること。
ポイント:外部監査人の設置は必須で、旧制度のような「外部役員」での代替は認められません。
3. 外部監査人の役割と選任基準
外部監査人の役割
外部監査人は、監理支援機関の役員が職務を適正に執行しているかをチェックする重要なポジションです。監理支援機関の中立性・透明性を保証するため、以下の要件が求められます:
-
独立性:受入機関と密接な関係がないこと。
-
専門性:育成就労制度や入管法に関する知識・経験を持ち、公正な監査が可能なこと。
-
適格性:欠格事由(法令違反など)に該当しないこと。
適任者とは?
特定の資格は不要ですが、以下の人物が適しているとされています:
-
行政書士・弁護士:申請取次資格を持ち、在留資格手続きに精通。
-
社会保険労務士・税理士:外国人雇用や企業運営に詳しい。
-
実務経験者:受入機関や監理団体での勤務経験者。
おすすめ:個人事務所より、複数資格者が在籍する士業法人を選ぶと、監査体制の安定性が向上します。
報酬の目安 個別にお見積もりいたします。月3万円から
報酬は監査対象の規模や条件で異なりますが、以下の要因が影響します:
-
監査人の専門性。
-
監理する育成就労外国人の人数や国籍。
-
事業所の所在地や対応言語の要件。
4. 必要書類:申請に必要なものは?
監理支援機関の許可申請には、育成就労法第23条に基づく以下の書類を準備します:
-
申請書
-
法人名、住所、代表者情報。
-
役員および監理支援責任者の氏名・住所。
-
事業所の名称・所在地。
-
外国送出機関との契約情報(該当する場合)。
-
-
添付書類
-
事業計画書:監理対象の受入機関や育成就労外国人の見込数、事業概要。
-
証明書類:非営利法人証明、財務状況、個人情報管理体制、外部監査人の選任状況など。
-
主務省令で定める追加書類。
-
注意:主務省令は2024年9月時点で未公表。詳細は今後発表されます。
5. 申請スケジュール:いつから準備すべき?
-
開始時期:育成就労制度は2027年施行予定(改正法公布日:2024年6月21日から3年以内)。申請受付開始は主務省令公表後。
-
申請の流れ:
-
要件チェック:外部監査人の選任や財務状況の確認。
-
書類準備:必要書類を収集・作成。
-
申請書作成:主務省令に基づくフォーマットで提出書類を整える。
-
申請提出:主務大臣(出入国在留管理庁など)に提出。
-
許可取得:審査通過後、許可証を受領。
-
最新情報:施行日や申請開始時期は、法務省の公式サイトで確認してください。
6. 申請手数料:いくらかかる?
申請手数料は実費を基に主務省令で定められますが、2024年9月時点で具体的な金額は未公表です。申請時に納付が必要なため、予算計画に含めておきましょう。
7. 申請先:どこに提出する?
申請は主務大臣(出入国在留管理庁や関連省庁)が指定する窓口に提出します。地方出入国在留管理局が受付窓口となる可能性が高いですが、詳細は主務省令公表後に判明します。
8. 成功のポイントと注意事項
-
厳格な審査:監理支援機関は、技能実習制度より厳しい監督下に置かれます。許可要件を満たす体制を早めに構築しましょう。
-
外部監査人の選定:制度開始前に、育成就労制度や入管法に精通した外部監査人を確保することが重要。
-
専門家への相談:申請取次資格を持つ行政書士や弁護士に依頼すると、書類作成や手続きがスムーズに進みます。特に、行政書士法人塩永事務所のような専門事務所は、全国対応で信頼性が高い選択肢です。
9. まとめ:準備を今から始めよう!
育成就労制度の監理支援機関は、外国人労働者の適正な受け入れを支える重要な役割を担います。許可申請には、非営利法人としての資格、財務基盤、外部監査人の設置など、複数の要件をクリアする必要があります。2027年の制度開始に備え、主務省令の公表を待ちつつ、外部監査人の選任や書類準備を進めることが成功の鍵です。
申請に不安がある方は、申請取次資格を持つ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。監理責任者等講習修了者在籍で、外国人雇用に関する豊富なノウハウを提供します!
参考情報
-
法務省(出入国在留管理庁):制度詳細や最新情報
-
行政書士法人塩永事務所:許可申請代行・外部監査人就任サービス
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
※全国対応、初回相談無料。
行政書士法人塩永事務所
※全国対応、初回相談無料。
